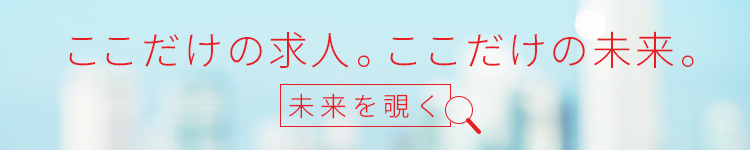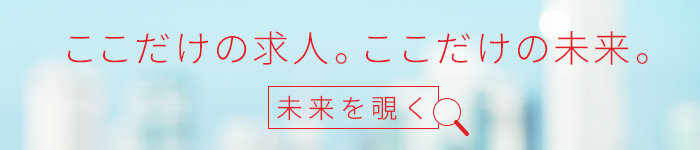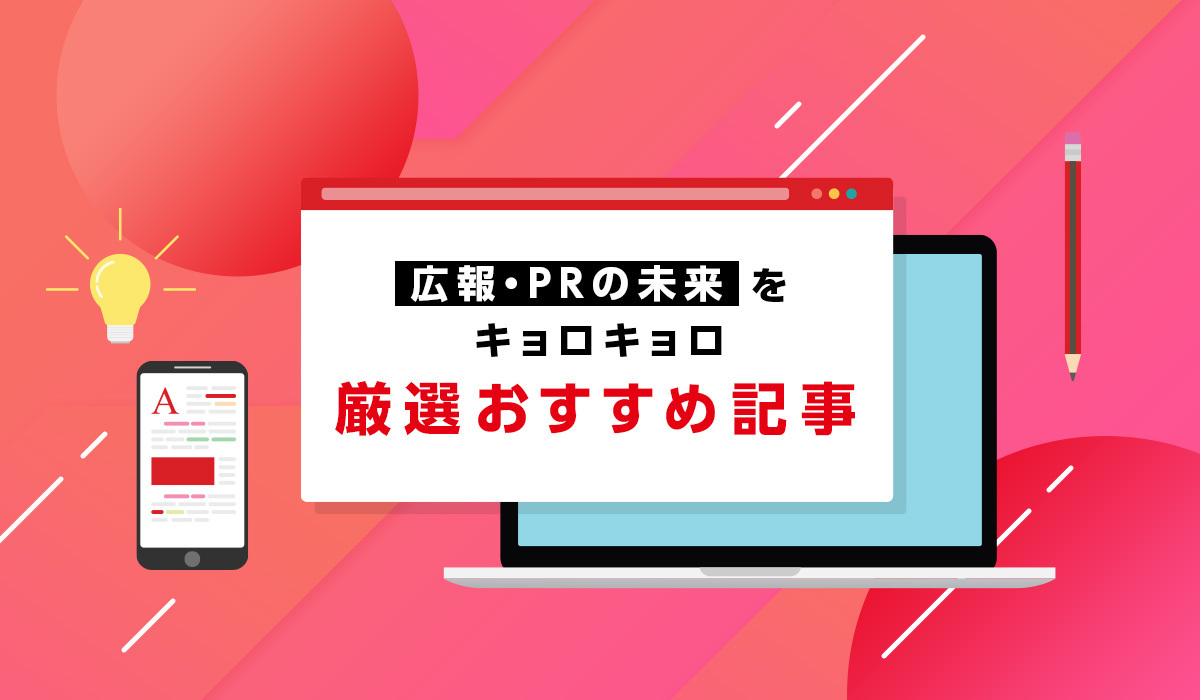選は創作なり──AIを優秀なアシスタントにするためには人間のクリエイティビティがいる 【第62回宣伝会議賞 協賛企業賞】博報堂 マーケットデザイン事業ユニット クリエイティブ局 江口チーム チームリーダー クリエイティブディレクター 江口貴博さん

第62回宣伝会議賞にて、マスメディアンの課題「職種に関係なく、チャレンジマインドで新しい価値を提案し、次のアクションやコミュニケーションを生む人材のキャッチフレーズ」で協賛企業賞を受賞した江口貴博(えぐちたかひろ)さん。受賞作は「アイデアが生まれる場所に、人は集まる。」。今までどんなキャリアを歩まれてきたのか、どんな視点でキャッチコピーを書いたのか、日頃、どんな思いで広告クリエイティブをしているのか、そしてどんな未来を描こうとしているのか。後編ではAIを活用したクリエイティブ制作の実態や、「AI×クリエイティブ」の未来について、元博報堂・クリエイティブディレクターの黒澤晃がお聞きします。
この記事は前後編です:前編はこちら
「インタレストドリブン。興味を持ったものには正直でありたいと思う」
──僕もChatGPTにコピーを考えてもらうことがありますが、全然いいものが出てこない印象があります。プロンプトとかを含めたやり方の問題ですか。
仕込むにはそれなりのアイデアと時間が必要で、そのままChatGPTにコピーを出させたら、いいものはほぼ出てこないのが現状だと思います。
僕は宣伝会議賞用にGPTsを仕込んで、商品名と特徴とターゲットを入れると、ぴったりなコピーを出すようにしました。
──どんな仕込み方をしているんですか。
そこらへんは具体的に公開できないんですが、宣伝会議賞受賞作品の傾向の本質を抽出してGPTsに学ばせるんです。広告づくりにおける「デコンストラクション」のような形で。例えば、宣伝会議賞のコピーは「1度読んだだけでは理解できない深みのあるコピー」「距離感のある言葉を組み合わせたコピー」……とかとかですかね。
ただ、いいものが出ないのは、こちら側の分析や気づきが足りないということかもしれません。そういう意味では、使う側の能力はちゃんと要求されているのだと感じます。
──瞬時にたくさんコピーが出てくる感じですか。
そうですね。僕の場合、20個ずつ出力していますが、いいなと思うのは60個に1、2個あるかどうか。良かった1、2個を選択して、それを基にまた選択肢を変えて出させるみたいな繰り返しの作業です。
──現業でコピーを書くと変数が多くて、いくつもの防波堤を乗り越えなきゃいけない。そういう意味で、一番純粋にコピーの力が出ているのは宣伝会議賞という話もあります。言葉のみでビジュアルがない賞でもありますし。
仰る通りですね。ChatGPTと一緒にやってみようと思ったのはそれが理由です。宣伝会議賞は、コピーの良し悪しを決めるレトリックの最高峰だと僕は感じていて、GPTsの磨き上げの場としては最適なんじゃないかと思いました。 実は若手の頃にも、宣伝会議賞に挑戦したことがあって、今回は20年ぶりの挑戦だったんです。当時は、ペンや紙の手書きでしたが、今回はAIをアシスタントにして戻ってきたということになります。
実は若手の頃にも、宣伝会議賞に挑戦したことがあって、今回は20年ぶりの挑戦だったんです。当時は、ペンや紙の手書きでしたが、今回はAIをアシスタントにして戻ってきたということになります。
──それは面白い話ですね。一方で、クリエイティブをAIで生成していくことに対する賛同もあるけれど、批判もかなりあります。そこらへんはどう捉えていますか。
博報堂という会社はクリエイティブの力が強みでもあるので、特にデリケートに捉えています。
僕は今、2月からスタートした「HCAI」という組織に兼務していますが、何の略かと言うと「Human Centered AI Institute」です。ヒューマンセンタード、つまり、人間や人間の能力が中心、というのが部署名にも表れていますよね。AIは人間の仕事を駆逐するものではなく、人間の能力や可能性を拡張させるもので、人間はAIにより空いた時間を有意義に使うという考え方です。それが博報堂のスタンスだし、僕ももちろんそれに同意して、AIとのクリエイティブ制作には取り組んでいます。
HCAIは、社内の超AI好きが集まった濃いチームです。これから広告やコピーだけでなく、小説や漫才などさまざまなジャンルに寄与できる可能性を探っていこうとしています。
──今回の応募の作業で、AIによる能力の拡張を感じたことはありました?
「アイデアが生まれる場所に、人は集まる。」――マスメディアンさんがこのコピーをチョイスしたのは、仕事や企業を探している転職希望者や就活生と、求人募集する側の企業という、2つのターゲットのことを考えられたコピーだったからじゃないかと思うんです。
本当は両方のターゲットがいるけど、宣伝会議賞にコピーを応募する人って転職する側で書きたくなるんですよ。なぜなら、書いている自分も転職する側だし。きっと僕でもそうなると思います。想像だけど、ターゲットのスタンスは99対1ぐらいだったんじゃないかなと思います。
でも、転職希望者は実はターゲットの1つでしかない。AIは複数のターゲットがいれば、それらをフラットに判断するので募集企業側もターゲットだと判断して、今回のコピーが生まれたんです。
──AIは、偏りがなくフラットというのが面白いですね。
だからアイデアを生む人に企業からの希望が集まるのと同じように、募集企業側もアイデアフルに頑張ることでどんどん人が集まるんだ。だから頑張ろう、生き生きとした企業に見せようよ、と鼓舞するコピーになっているんですよね。
それが、たくさんある応募コピーの中から選んでいただいた理由かなと自分で勝手に思っているんです。言葉の上手い下手もあるけど、実はそういう冷静な視点、人間だと見逃しがちな視点が取れたのも、AIによって生まれた大きな価値だったなと個人的には思いました。
──ただ、雑多にあるAIの一次発想に、光る宝物のような意味を見出したのは、やっぱり江口さんのクリエイティビティだという気がします。センスがなければ、そのコピーをそもそも応募してない(笑)。
その流れで言うと、「選ぶ能力」っていうのはすごく重要ですよね。さらに、「指針やビジョンを示す」「選ぶ」「オーガナイズ」みたいな、いわゆるクリエイティブディレクターが必要としている能力、それが実はAIツールと向き合う時にめちゃくちゃ活きています。
GPTsに仕込むのは「指針やビジョンを示す」だし、GPTsの回答から意味を見出すのは「選ぶ」だし、出た回答を組み合わせるのは「オーガナイズ」。それらのプロセスは、クリエイティブ1年目の人にはできないかもしれないですよね。
──そこも「AI×クリエイティブ」の、1つのポイントだと感じます。結局、たくさん自分の頭で考えた経験がないと、ビジョン、チョイス、オーガナイズのパーソナルな能力はつかないので。
僕もそう思います。だから、チームの若いメンバーには「アイデア出しにAIを使いなさい」とは言ってなくて、むしろ自分で考えることを推奨しています。社内でのAI導入セミナーなども僕が担当しているのですが、会社としても、全クリエイティブ員に対するAIの使用は強制ではなく、クリエイティブや企画書の作成などに使いたい人は使ってもいいかも、ぐらいのスタンスですね。なので、実際はあんまり使いたくないって人も多いです。自分で書いた方が早いという優秀な人もいっぱいおられるんで。 「選は創作なり」という高浜虚子の言葉があります。僕もその言葉をいつも大切にしていて、たとえばCM制作の中でも、たくさんのコピーから1つ選びとった案がその時点では何でもないものに見えるのに、映像と音と…と組み合わさっていくと、素晴らしい作品に仕上がって驚くことってありませんか。「選ぶ」というのは立派な創作だと僕は思うんです。
「選は創作なり」という高浜虚子の言葉があります。僕もその言葉をいつも大切にしていて、たとえばCM制作の中でも、たくさんのコピーから1つ選びとった案がその時点では何でもないものに見えるのに、映像と音と…と組み合わさっていくと、素晴らしい作品に仕上がって驚くことってありませんか。「選ぶ」というのは立派な創作だと僕は思うんです。
AI×クリエイティブ領域でも「選べる人になれるかどうか」が極めて重要なポイントで、その能力は経験を積んだクリエイティブディレクターの能力に近いと思います。その意味で、よりいいクリエイティブディレクターになれるようにこれからも頑張りたいと思います。
──「選は創作なり」。高浜虚子の言葉で、多くの句作(自分と他者)の中から、「本当に光るもの」を選び取ること、それは作句と同じくらいクリエイティビティが必要だという意味だと思う。AIに書かせると楽だという発想とは今回、まるで違うと感じた。むしろ、江口さんのように仕込みのアイデアに時間をかけ、鋭いチョイスの視点を磨くことで初めて、AIは本当に優秀なクリエイティブアシスタントになりうるのだと感じた。

「インタレストドリブン。興味を持ったものには正直でありたいと思う」
──僕もChatGPTにコピーを考えてもらうことがありますが、全然いいものが出てこない印象があります。プロンプトとかを含めたやり方の問題ですか。
仕込むにはそれなりのアイデアと時間が必要で、そのままChatGPTにコピーを出させたら、いいものはほぼ出てこないのが現状だと思います。
僕は宣伝会議賞用にGPTsを仕込んで、商品名と特徴とターゲットを入れると、ぴったりなコピーを出すようにしました。
──どんな仕込み方をしているんですか。
そこらへんは具体的に公開できないんですが、宣伝会議賞受賞作品の傾向の本質を抽出してGPTsに学ばせるんです。広告づくりにおける「デコンストラクション」のような形で。例えば、宣伝会議賞のコピーは「1度読んだだけでは理解できない深みのあるコピー」「距離感のある言葉を組み合わせたコピー」……とかとかですかね。
ただ、いいものが出ないのは、こちら側の分析や気づきが足りないということかもしれません。そういう意味では、使う側の能力はちゃんと要求されているのだと感じます。
──瞬時にたくさんコピーが出てくる感じですか。
そうですね。僕の場合、20個ずつ出力していますが、いいなと思うのは60個に1、2個あるかどうか。良かった1、2個を選択して、それを基にまた選択肢を変えて出させるみたいな繰り返しの作業です。
──現業でコピーを書くと変数が多くて、いくつもの防波堤を乗り越えなきゃいけない。そういう意味で、一番純粋にコピーの力が出ているのは宣伝会議賞という話もあります。言葉のみでビジュアルがない賞でもありますし。
仰る通りですね。ChatGPTと一緒にやってみようと思ったのはそれが理由です。宣伝会議賞は、コピーの良し悪しを決めるレトリックの最高峰だと僕は感じていて、GPTsの磨き上げの場としては最適なんじゃないかと思いました。

──それは面白い話ですね。一方で、クリエイティブをAIで生成していくことに対する賛同もあるけれど、批判もかなりあります。そこらへんはどう捉えていますか。
博報堂という会社はクリエイティブの力が強みでもあるので、特にデリケートに捉えています。
僕は今、2月からスタートした「HCAI」という組織に兼務していますが、何の略かと言うと「Human Centered AI Institute」です。ヒューマンセンタード、つまり、人間や人間の能力が中心、というのが部署名にも表れていますよね。AIは人間の仕事を駆逐するものではなく、人間の能力や可能性を拡張させるもので、人間はAIにより空いた時間を有意義に使うという考え方です。それが博報堂のスタンスだし、僕ももちろんそれに同意して、AIとのクリエイティブ制作には取り組んでいます。
HCAIは、社内の超AI好きが集まった濃いチームです。これから広告やコピーだけでなく、小説や漫才などさまざまなジャンルに寄与できる可能性を探っていこうとしています。
──今回の応募の作業で、AIによる能力の拡張を感じたことはありました?
「アイデアが生まれる場所に、人は集まる。」――マスメディアンさんがこのコピーをチョイスしたのは、仕事や企業を探している転職希望者や就活生と、求人募集する側の企業という、2つのターゲットのことを考えられたコピーだったからじゃないかと思うんです。
本当は両方のターゲットがいるけど、宣伝会議賞にコピーを応募する人って転職する側で書きたくなるんですよ。なぜなら、書いている自分も転職する側だし。きっと僕でもそうなると思います。想像だけど、ターゲットのスタンスは99対1ぐらいだったんじゃないかなと思います。
でも、転職希望者は実はターゲットの1つでしかない。AIは複数のターゲットがいれば、それらをフラットに判断するので募集企業側もターゲットだと判断して、今回のコピーが生まれたんです。
──AIは、偏りがなくフラットというのが面白いですね。
だからアイデアを生む人に企業からの希望が集まるのと同じように、募集企業側もアイデアフルに頑張ることでどんどん人が集まるんだ。だから頑張ろう、生き生きとした企業に見せようよ、と鼓舞するコピーになっているんですよね。
それが、たくさんある応募コピーの中から選んでいただいた理由かなと自分で勝手に思っているんです。言葉の上手い下手もあるけど、実はそういう冷静な視点、人間だと見逃しがちな視点が取れたのも、AIによって生まれた大きな価値だったなと個人的には思いました。
──ただ、雑多にあるAIの一次発想に、光る宝物のような意味を見出したのは、やっぱり江口さんのクリエイティビティだという気がします。センスがなければ、そのコピーをそもそも応募してない(笑)。
その流れで言うと、「選ぶ能力」っていうのはすごく重要ですよね。さらに、「指針やビジョンを示す」「選ぶ」「オーガナイズ」みたいな、いわゆるクリエイティブディレクターが必要としている能力、それが実はAIツールと向き合う時にめちゃくちゃ活きています。
GPTsに仕込むのは「指針やビジョンを示す」だし、GPTsの回答から意味を見出すのは「選ぶ」だし、出た回答を組み合わせるのは「オーガナイズ」。それらのプロセスは、クリエイティブ1年目の人にはできないかもしれないですよね。
──そこも「AI×クリエイティブ」の、1つのポイントだと感じます。結局、たくさん自分の頭で考えた経験がないと、ビジョン、チョイス、オーガナイズのパーソナルな能力はつかないので。
僕もそう思います。だから、チームの若いメンバーには「アイデア出しにAIを使いなさい」とは言ってなくて、むしろ自分で考えることを推奨しています。社内でのAI導入セミナーなども僕が担当しているのですが、会社としても、全クリエイティブ員に対するAIの使用は強制ではなく、クリエイティブや企画書の作成などに使いたい人は使ってもいいかも、ぐらいのスタンスですね。なので、実際はあんまり使いたくないって人も多いです。自分で書いた方が早いという優秀な人もいっぱいおられるんで。

AI×クリエイティブ領域でも「選べる人になれるかどうか」が極めて重要なポイントで、その能力は経験を積んだクリエイティブディレクターの能力に近いと思います。その意味で、よりいいクリエイティブディレクターになれるようにこれからも頑張りたいと思います。
──「選は創作なり」。高浜虚子の言葉で、多くの句作(自分と他者)の中から、「本当に光るもの」を選び取ること、それは作句と同じくらいクリエイティビティが必要だという意味だと思う。AIに書かせると楽だという発想とは今回、まるで違うと感じた。むしろ、江口さんのように仕込みのアイデアに時間をかけ、鋭いチョイスの視点を磨くことで初めて、AIは本当に優秀なクリエイティブアシスタントになりうるのだと感じた。