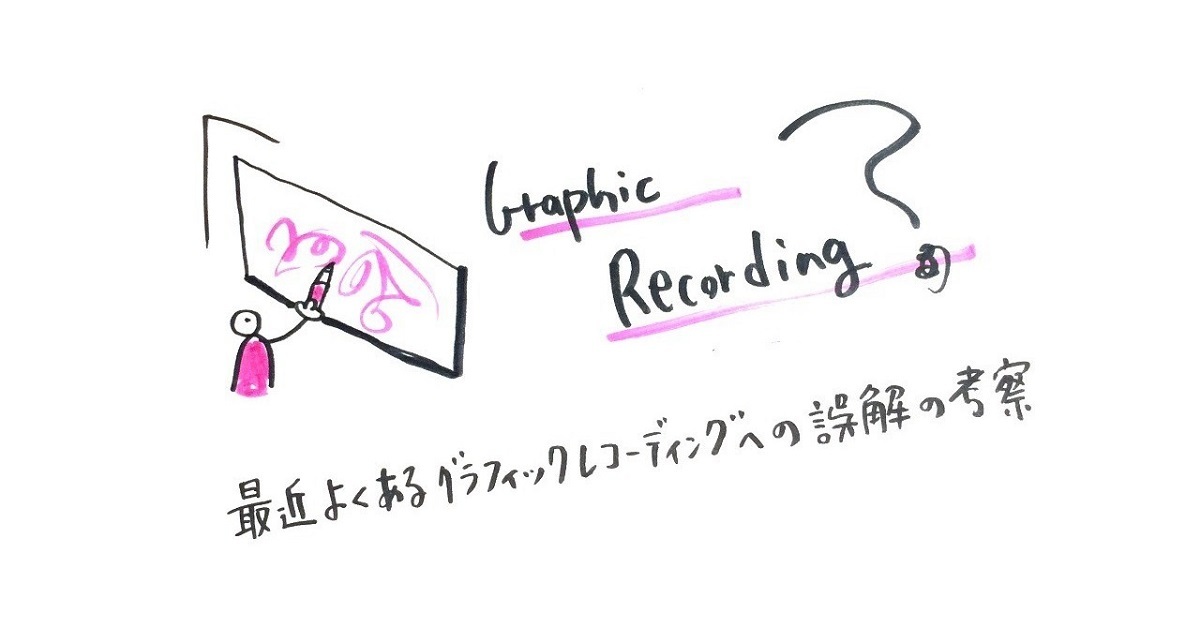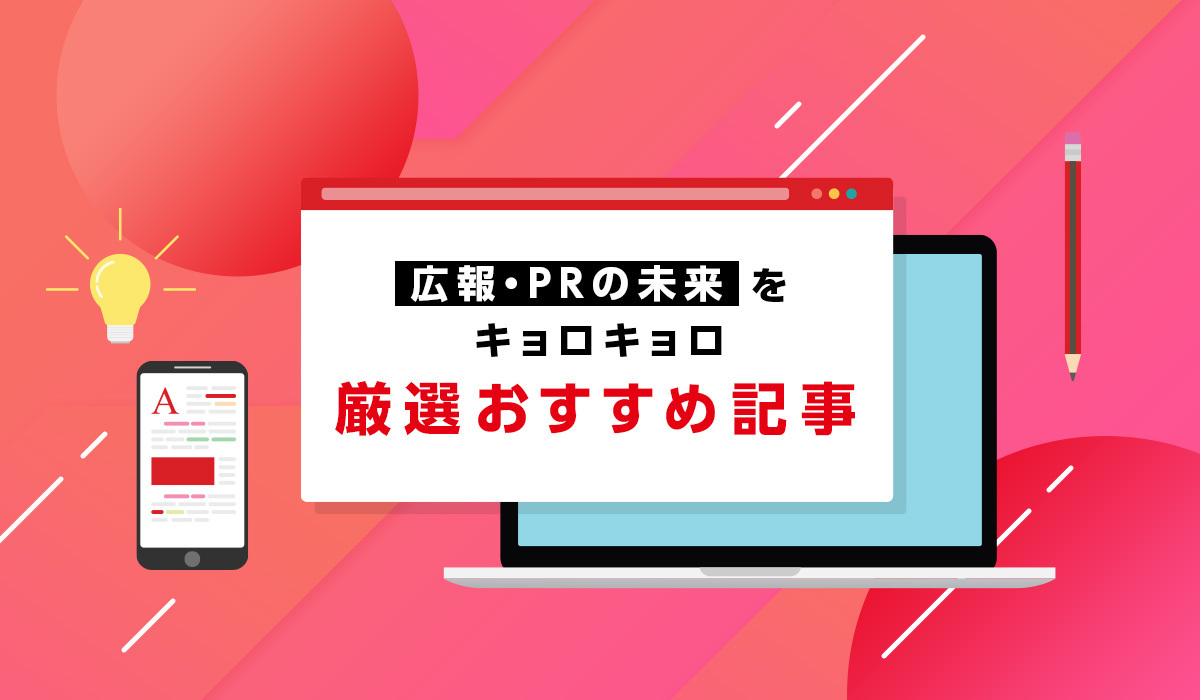雨降って地固まる。批評は文化の発展に必要 #クリエイターの生存戦略 〈後編〉 多摩美術大学 情報デザイン学科 専任講師/グラフィックレコーダー 清水淳子さん

Yahoo! JAPANのデザイナーを退職し、現在はフリーランスのメディアアーティストとして活動する市原えつこさんが、さまざまな分野のクリエイターや専門家に話を伺い、クリエイターの生存戦略のヒントとノウハウを探す本連載。第一線で活躍するクリエイターがどのようにキャリア構築をしてきたのか、今後はどのように歩みを進めようとしているのか、対談形式でインタビューしていきます。
第6回は、対話や議論をビジュアライズする「グラフィックレコーディング」の研究・実践をする清水淳子さん。いまでこそ浸透してきたグラフィックレコーディングですが、清水さんがTokyo Graphic Recorderの活動を通して、さまざまな失敗と成功を繰り返して、その価値を発見し普及してきました。現在は、母校の多摩美術大学 情報デザイン学科で専任講師として教鞭を執りつつ、「視覚言語とデザインの関係を再発明する」をテーマに、対話の場と議論の可視化について研究しています。そんな清水さんに、これまでの軌跡や新たな職種の確立について、前編・後編にわたってお聞きしました(マスメディアン編集部)。
第6回は、対話や議論をビジュアライズする「グラフィックレコーディング」の研究・実践をする清水淳子さん。いまでこそ浸透してきたグラフィックレコーディングですが、清水さんがTokyo Graphic Recorderの活動を通して、さまざまな失敗と成功を繰り返して、その価値を発見し普及してきました。現在は、母校の多摩美術大学 情報デザイン学科で専任講師として教鞭を執りつつ、「視覚言語とデザインの関係を再発明する」をテーマに、対話の場と議論の可視化について研究しています。そんな清水さんに、これまでの軌跡や新たな職種の確立について、前編・後編にわたってお聞きしました(マスメディアン編集部)。
大人の手書きグラフィックは「恥ずかしい行為」だと思っていた
市原:清水さんがもともと個人的なメモとして始めた落描きが面白がられ、「グラフィックレコーディング」というメソッドに昇華されていったんですよね。ただ、欲深いフリーランスとしてはグラフィックレコーディングを清水さんの専売特許にした方が儲かるのでは……とも思うのですが、本を出して手法をオープンにし、誰でも習得できるようにしていった理由はなぜでしょうか?清水:そもそも私自身がグラフィックレコーディングにチャレンジし始めた2012年頃、その活動を「知性」として考えておらず、「こんな落書きに近いメモを社会人になって描いているのは、大人として幼稚な行為」だと思っていたのです。というのも、ちゃんとした文字ではなく絵で議論を残すことは、文字を理解できない原始人の壁画みたいなものだと感じていたから。私はあくまでデザイナーが本職で、こういったものは自分の特技を活かした一種の余興にすぎないと考えていました。
でも、依頼してまでグラレコを使いたいと言ってくれる人たちが、どうやらギャグではなく真剣に役に立つと思っているようだと気が付いて。特に2013年の朝日新聞さんの開催するシンポジウムでのお仕事が大きかったですね。「これだけしっかり原稿を書ける人がいる会社なのに、なんでこんなに真剣にグラフィックレコーディングを求めているんだろう?」と。
市原:清水さんの中ではあくまで「文章>情報を含んだ落書き」という考えだったんですね。
清水:グラフィックデザインなど完成度の高い確立した分野に対してはリスペクトしていました。ただ、グラフィックレコーディングはそのような類のものではないと考えていました。考えが変わった大きなきっかけは、2013年のTWDWでの出来事です。誰かが「清水さんの描いたグラフィックレコーディングを天井から吊るして飾ろうよ!」と言い出したのです。私としては「なんでこんな雑で汚い未完成のメモをわざわざ吊るそうと思うのか…?」と疑問だったんです。



『Graphic Recorder ―議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』(ビー・エヌ・エヌ新社)
ライセンス化で見えなくなるもの
市原:面白いですね、まさか清水さんご自身がそんなに半信半疑だったとは思っていませんでした。その時点では、これを専売特許にする発想がそもそもなかったと。清水:そうですね。それにそもそも専売特許にするものじゃないと思っていて。いつか昔に「デザイン思考」という言葉をどこかの会社が特許化してすごく叩かれているのを見て、思考やツールはどこかの会社が独占するものではないなと思いました。例えばイラストレーターという職業を「うちが考えました」と特許をとったらおかしいし、「アーティスト」って言葉の商標をとられたら「なんだこいつ」って話じゃないですか。そういうものなんだろうという意識はずっとありました。職業だしツールだし、グラフィックレコーダーは、イラストレーターやアーティストのような技術職になるのだろうなと。
市原:書籍の刊行後、多くのグラフィックレコーダーが生まれましたよね。私が最近登壇するイベントでもグラフィックレコーダーの方がいらっしゃることがとても多いです。本当にめちゃくちゃ流行っていますが、これだけ広まったことで良かったことは何でしょうか?
清水:広まって良かったのは、「大人が会議でグラフィックを用いて記録すること」が市民権を得たことですね。手書きのグラフィックは、幼稚な落書きではなく、コミュニケーション言語の一つなのだと、たくさんの人が気付き始めたことが何より嬉しかったです。描くのが私1人しかいないと、さすがに1億人には伝わらないから。だから今後は、いろんな地域で、いろんな人に実践してほしいですね。
市原:確かに、清水さんが単独で完成度の高いグラフィックレコーディングをどんどん実践するのもいいけど、それでは波及しないような層にまでリーチして、裾野が広がった感じはありますね。最近「グラフィックレコーダー」「グラフィックカタリスト」という肩書の載った名刺を頂くことがすごく増えました。それも結構な大企業に所属している方が名乗っていて。すごい職業をつくられたなと思います。でも「名乗ったらライセンスフィー2000円」みたいなことはやらないのですね?
清水:やらないやらない(笑)。私以外で資格ビジネスをする人が出てくるかもしれないけど。私がなぜグラフィックで情報を描くかというと、自分の頭で考えて組み立てるプロセスが楽しいから。もし資格になって、みんなが「グラフィックレコーダー検定3級」みたいな参考書を買って、手法・文法を覚えはじめたら、暗記テストみたいにクリアする競技になってしまう。基礎的な部分の習得には良いかもしれませんが、柔軟に自分の頭の中で情報を組み立てるプロセスを経ないと、結局は死んだ知識になるので。

清水:でも、例えばアーティスト検定とかあったらどう思いますか? 試験内容は「この便器を見て感想を述べよ」とか。一応正しい答えはあるじゃないですか。これはマルセル・デュシャンの泉で……とか。それはある程度の知識の有無の確認にはなるかもしれないけれど、合格すればアーティストと名乗っていいかといえばそうではない。それに、そのテストって本当にアーティストに向いている変な人は受けなさそうですよね。医者や弁護士など現段階で明確な正解があるものは資格が必要だけど、さまざまな意味があるもの、考え続けることで新たな正解が生まれるものの場合は、自由に発展する部分が潰されるのはもったいないなと。今後、もしかしたら誰かが検定化するかもしれませんが、そうなったら私はブラックジャックのように検定はとらずに、闇グラフィックレコーダーとして活動します。
英語検定とかはアリなんですけどね。グラフィックは、言語と表現の間だから難しいのだと思います。漫画に近いのかもしれません。「検定にしてナレッジを言語化して」という声はもちろんいただきます。絵を描くなど表現をするのが苦手な人にとってはそのほうが良いかもしれない。検定で測れる部分と、測れない部分があって、測れない部分が本質的には重要と認識したうえで検定はつくらないといけないですね。私はつくる気はないのですが。
炎上から発展する
市原:そういった違和感に真摯に向き合っているのはさすがですね。最近だとムーンショット会議のグラフィックレコーディングがプチ炎上し、あれはグラレコで踏んだらいけない地雷ポイントを踏みまくっていると清水さんのTwitterやnoteでも指摘されていましたが、広く一般に普及することによる闇の部分もあるのではと思っておりました。巷でのグラフィックレコーディングにまつわるさまざまな誤解・誤用についてコントロールが難しいのではないでしょうか?ムーンショットのグラフィックレコーディングについて。
— 清水淳子 / shimizu junko (@4mimimizu) April 27, 2019
私は関与してないので、誰がどんな想いで受けたお仕事なのかわからない。けど、普段自分が仕事を受ける時に、誤解を生まないように気をつけている地雷ポイントを全部踏んでしまってる案件に見える。。。複雑なので、あとでnoteに書きます。 https://t.co/UsnThxZoKb
清水:そうですね。でもやっぱり、私は揉め事はたくさんあっていいと思っている派なんです。アートの歴史も、事故や事件、社会問題がふんだんにあるじゃないですか。印象派の初期の話が私は大好きで。その時まで西洋美術は写実的な絵ばかりだったけど、写真が発明されて以降、印象派の人たちは「実物そっくりに描く必要はない!」とボヤッとした絵をたくさん展示し、当然批難されるわけです。「この未完成の、描きかけの絵を飾って何が楽しいんだ!」と過去の人から散々言われる。
そういう揉め事で発展する部分って絶対にあるんです。大事なのが、描いた人がちゃんと揉め事を引き受けることなのかなと。市原さんもそうでしたが、何かがワーーーッと炎上した時に、それをつくった本人が一旦は引き受けて、何か自分の考えを発言するのは大事だと思っていて。いまはSNSで誰でも発信できるけど、バズったら自分の成果で、炎上したら閉じちゃう傾向がある。場合によっては逃げることも大事ですが、新しい分野の発展にはどうなんだろうと思っています。新しいことに事故や事件はつきものだから「ダメだった」で終わらず、カオスの中でも考え続ける姿勢を私は大事にしたい。
市原:何かを発信したら自分の子どもなんだから、自分でケツを拭けということですね。私も作品が炎上した際、不完全ながら発言してさらに叩かれたりしました。その悔しさや「あの時なんでこれが問題になったのか」という疑問や考察が、「次に何をやりたいか」につながっていきました。やはり必要なプロセスかもしれないですね。それにしても肝が座ってらっしゃいますね。さっきから話を聞いていると発言が格闘家っぽいなと……。これぐらい気概のある人が、先駆者になるのだなとしみじみ思いました。

各国に適したグラレコとは
市原:ちなみに最近は海外でのご活動に興味をお持ちのようですが、どういった背景があるのでしょうか?清水:自然発生的に生まれた自分のグラフィックレコーディングスタイルでしたが、やっていくうちにもともと北欧やアメリカで近しい潮流や雛形があったことを知ったんです。その歴史を参照しながら日本のグラフィックレコーディングやビジュアリゼーションのあり方を考えています。海外のメソッドをそのまま借りるのではなく、日本の国民性や会議のあり方にフィットする描き方が気になっています。例えば、海外だと喋りすぎる人を制御するために描くことが多いけれども、日本だと喋らない人を喋らせるために描くことが多い。やっていることの本質は一緒でも探求するポイントが全然違うんです。日本という島国のウェッティな国民性から鑑みると、海外では有用なメソッドでもみんなが萎縮しちゃうこともある。だからローカライズはすごく重要視していますね。
東京藝術大学の修士で研究していたのも、実際に私がこのウェッティな文化を持つ日本に生まれ落ち、一体どういうプロセスでこの活動を始めたのかが起点になっています。日本という環境で、どのような部分に効果があり、価値を感じてもらえてきたか、実践ベースで考えながら意味を導き出す研究をしていました。
市原:それは、このタイミングで本当に必要な研究ですね。日本に合わせたメソッドを体系化できたら、あとは実践でどんどん広げていくのみ。清水さんからは求道者的な芯の強さを感じとれて、ひとつの分野を切り開いていく人の強さに触れ、励まされました。ありがとうございました!