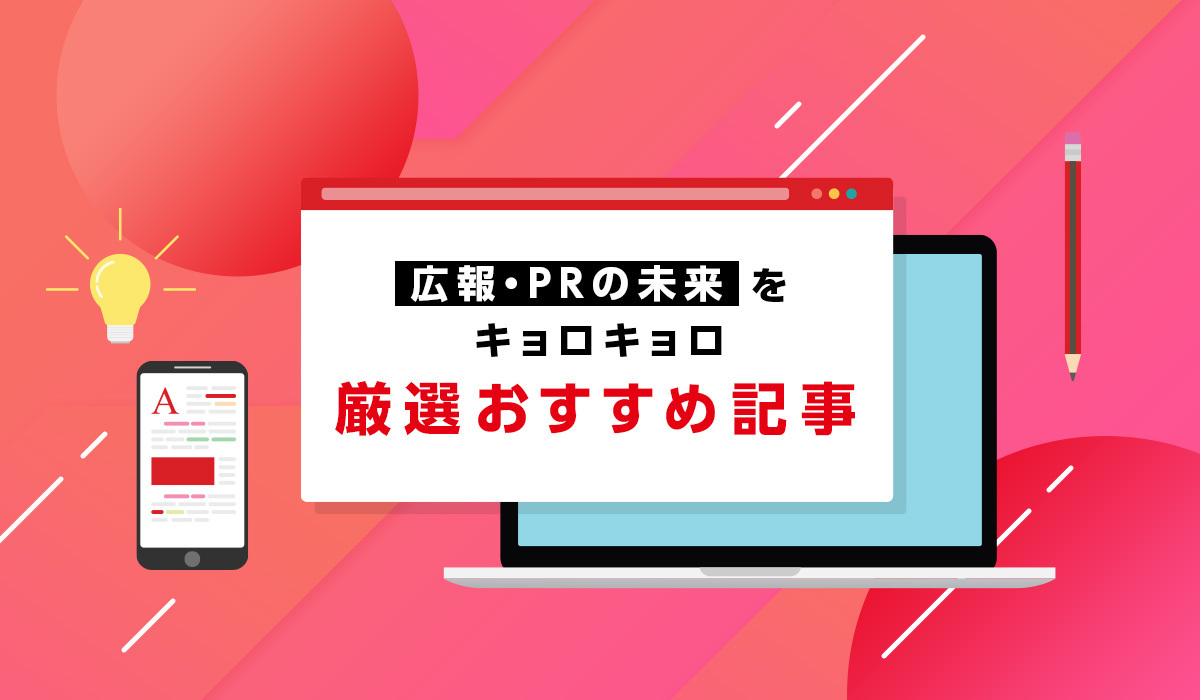コンピューターの手癖をなくしてグラフィックに定着させるには ライゾマティクス 木村浩康さん、田中陽さん

ライゾマティクスといえばアートや音楽などのカルチャーから広告まで幅広く手がける日本を代表するクリエイティブ集団です。とくに創業メンバーである真鍋大度氏、千葉秀憲氏、齋藤精一氏は数々のメディアで取り上げられ、動向が注目されています。今回、advanced by massmedianでは、代表する面々ではなく、現場でライゾマティクスの表現をリードしているデザイナーの木村浩康(きむらひろやす)さんとプログラマーの田中陽(たなかよう)さんの2名にお話を伺いました。ライゾマティクスと聞くとテクノロジーファーストで無機質なイメージを持ちますが、そうではなく、いかに人の温かみを表現できるかに挑戦している姿が見えてきました。
──本日はお忙しい中ありがとうございます。さっそくですが、お二人の簡単な自己紹介。所属部門や業務についてお聞きしていいですか。
木村:所属はそれぞれ、私が“DESIGN”で、田中くんが “RESEARCH”になるのですが、縦割りできれいに分かれているわけではなく、プロジェクトベースでそれぞれの職能が適している人をピックアップして進めていくということが多いです。
田中:“RESEARCH”のアウトプットは、基本的にプログラミングベースやテクノロジーベースの案件が多いため、プログラマーが主に携わっています。“DESIGN”は言わずもがなデザイナーに偏っています。
──田中さんは “デザインエンジニア”という肩書で活動されているようですが、どういう立ち位置なのでしょうか?
田中:どのWebプロダクションもそうだと思うのですが、分業制でデザインチームとエンジニアチームが分断されています。ただ自分自身、AdobeのFlashなどを使ってデザインしていたので、プログラミングとデザインを一緒に捉えていました。PhotoshopやIllustratorだけでなく、プログラミングで絵をつくることをしていたので、デザイナーorエンジニアと分けられるのが好きではありませんでした。だから“デザインエンジニア”と名乗っていました。でもライゾマに入社してからは、もっと自由にできる環境になったため、“ビジュアルアーティスト”と肩書を変えています。 ──前職の会社も、かなりエッジの効いたWeb制作会社だと思うのですが、分断されていたのでしょうか?
──前職の会社も、かなりエッジの効いたWeb制作会社だと思うのですが、分断されていたのでしょうか?
田中:そうです。どこも基本はそうです。デザイナーとエンジニアは分業していないと効率が悪いからです。規模が大きくなればなるほど、職域はしっかり分けられる。でも規模が小さくなればなるほど、そこが曖昧になっていく。だから企業規模を小さくしていくキャリアを積みたいなと大学生の頃から思っていました。
──大学生のときから!? なぜでしょう?
田中:大学の研究室での制作手法が全部1人で行うというやり方だったんです。けど仕事の進め方とか何もわからなかったので、まず大きな会社に入って、業界や社会人の基礎を学ぼうと思って、大手のデジタルエージェンシーに入りました。生意気ですが、お金貰いながら大学院に行くみたいな感覚でしたね。ディレクターとして入社したのですが、デザインとエンジニアリング両方を横断できる気がしなくて、やっぱり少数精鋭の会社じゃないとダメだと思ったんです。それで2社目がWeb制作会社を数社転職し経験を積み、その後ライゾマにといった流れです。
──最初はディレクターだったんですか?
田中:もともとはデザイナー職で入社試験を受けていたのですが、「大規模なプロダクションはデザイナーで入るとデザインしかできないよ。色々やりたいならディレクターの方がいいよ」と言われて、ディレクターで入社しました。
──そういうことだったんですね。では次に木村さん。木村さんは大学でプロダクトデザインを専攻されていたとのことですが、今の仕事とはだいぶ違いますが、どのようにしてWebデザインに行き着いたのでしょうか?
木村:実はプロダクトデザインに特段興味があったわけではないんです(笑)。とにかく美大に入りたくて、受かったのがたまたまプロダクトデザイン科だったんです (笑)。 木村:それよりも大学時代にパソコンを自分でつくるのが好きで。プロダクトデザインよりも、パソコンばかりでした。時代もFlash全盛期で、やっぱりこういうデザインをしたいと思い、ライゾマの前にWeb制作会社に入りました。その会社ではデザインから実装まで全部やっていました。その後個人の仕事もするようになり、ライゾマともいくつか仕事をしていました。1年ぐらいフリーランスとしてライゾマと関わっていたのですが、ある日千葉秀憲から「デザイナーいないし、ウチ来てよ」と誘われて、入社することになりました。フリーランス時代もデザインからプログラミングまですべてやっていたのですが、ライゾマの案件だけはデザインのみでした。彼らから「デザインだけをやって」と言われて。たまに気を利かせてコードを書くと、「勝手に書くんじゃねぇ!」と怒られて。けど、確かに自分でやるよりもアウトプットは良いものができるんです。分業で、その道のプロに任せた方が圧倒的に良い。だったら、自分で全部やることを辞めようと思って。エンジニアのプロがいるならデザイナーに専念して良い作品とつくろうと思い、ライゾマに入りました。
木村:それよりも大学時代にパソコンを自分でつくるのが好きで。プロダクトデザインよりも、パソコンばかりでした。時代もFlash全盛期で、やっぱりこういうデザインをしたいと思い、ライゾマの前にWeb制作会社に入りました。その会社ではデザインから実装まで全部やっていました。その後個人の仕事もするようになり、ライゾマともいくつか仕事をしていました。1年ぐらいフリーランスとしてライゾマと関わっていたのですが、ある日千葉秀憲から「デザイナーいないし、ウチ来てよ」と誘われて、入社することになりました。フリーランス時代もデザインからプログラミングまですべてやっていたのですが、ライゾマの案件だけはデザインのみでした。彼らから「デザインだけをやって」と言われて。たまに気を利かせてコードを書くと、「勝手に書くんじゃねぇ!」と怒られて。けど、確かに自分でやるよりもアウトプットは良いものができるんです。分業で、その道のプロに任せた方が圧倒的に良い。だったら、自分で全部やることを辞めようと思って。エンジニアのプロがいるならデザイナーに専念して良い作品とつくろうと思い、ライゾマに入りました。
──分業か兼業か。田中さんと対照的ですね。
田中:木村さんがコードを書くのを辞めたのって何歳のときですか?
木村:28歳のとき。自分が1週間かかるものをたった1日で仕上げるのを見て。それでもライゾマに入ったばかりのときは、「Flash以外触りたくない」って人しかいなくて。htmlは書いていましたけどね。
田中:いましたね。俺の仕事じゃないって、拒否するプログラマー(笑)。
田中:最近わかってきたのですが、相手の頭の中にすでに完成像があるものを形にするのが、劇的に下手くそなんです。
木村:ただ、言うことを聞きたくないだけじゃない?(笑)
田中:なんとか言うことを聞こうとして、きっとこう考えているんだろうなと推測して、実装するんですけど、そうすると劇的にダサくなる。
木村:気持ちが乗っていないだけでは?(笑)
田中:いやいや、違いますって(笑)。ちなみに木村さんから依頼されるときは気持ちよくやらせてもらっています。「ここのページ空けておいたからよろしく」と言われるだけなので。キャンパスと絵の具だけ用意されて「あとどうぞ」みたいな感じで。
木村:田中くんみたいなアーティスト志向の強いプログラマーもいますし、そうではなく解決することが得意なデザイン志向のプログラマーもいるので、仕事をする前にタイプを見極めなければいけません。 ──どうやって見分けるんですか?
──どうやって見分けるんですか?
田中:普通の会社ってこういうつくり方をしないので、過去のポートフォリオで見極めるのは難しいですね。できるとしたら、個人で遊びとしてつくったものを見るくらいしかなさそう。
──デザイナーもタイプ分けされますか?
木村:グラフィックデザインを積み上げたアート性の強いタイプとシステマチックに考え抜かれた合理性の強いタイプの2つがあります。僕はグラフィックに注視してしまうので、ボタンがどうのこうのといった議論がすごく嫌いで。
──貴社は前者が多いのでしょうか? ちなみに同僚の皆さんはどういう方々が多いのでしょうか? 木村さんも田中さんもWeb制作会社出身ですが。
田中:前者が多いですね。制作会社出身は少ないですね。ウチは本当にバラバラで、建築事務所の出身の人やメーカーでプロダクトデザインやっていた人、それから大学の教授だった人まで、多種多様です。
木村:ライゾマ自体ハードウェアもソフトウェアも幅広く手がけるので、そのアウトプットを見て、自分にも何かできるんじゃないかと感じ取って、入社してくる人が多いですね。だからより一層アウトプットがユニークになるというか、一辺倒でなく幅が広がります。
木村:共通のゴールが見えることですかね。ライゾマで言うと、テクノロジードリブンやデータドリブンで、アウトプットにこのテクノロジーを使いたい、あのデータを使いたいみたいな会話がされて、共通言語となっています。
田中:ライゾマは、すごく綿密に話し合って皆で足並み揃えてプロジェクトを進める感じではないんです。ひとりで全部完結できちゃうような人たちが、でも1つのプロジェクトに思い思いに集まるような感じです。
木村:だからこそ、一本串を刺しているのが、テクノロジードリブンやデータドリブン。共通言語やデータがあるからブレない。勝手に進めたけど、使っているデータが一緒だから、矛盾せずにつながるようなことが多々あります。
田中:テクノロジーやデータを大事にするのがライゾマティクスのカルチャーですが、実はちゃんと言語化はされていないんです。社内で説明もないし。けど、各々がそのカルチャーを勝手に感じ取って、勝手にグルーブを感じて、勝手に集まっている。基本的にみんなフリーランスの集まりみたいなものなんです。
木村:真鍋大度曰く「野良猫の集まり」。勝手に来て、いつの間にかいなくなるみたいな(笑)。会社というよりかは集団感が強いです。
田中:真鍋ほかトップ陣が、自分たちの好きなモノをわかっていて、それに共感しているからこそ、集団として成り立っていますね。
木村:私は共感できますね。イラストや写真、コピーをキレイに配置する王道のグラフィックデザインではなく、テクノロジーやデータを駆使したグラフィックデザインならうまく差別化して勝てるかもしれないという感覚があるからです。この道はまだ多くの人が掘り下げていない分野だからこそ面白い。たとえばデータをグラフィックデザインに定着させる決まり手がまだ見つけられてない。どうしても「コンピューターの手癖」が出てしまうんです。それを払拭できないかを模索しているところです。
──「コンピューターの手癖」ですか? どういうことでしょうか?
木村:プログラミングされた感というか。コンピューターの手癖があると、たとえ最先端な取り組みだとしても既視感が出てしまう気がします。だから、なんとか消して、グラフィックに定着させたいんです。最終的には、コンピューターの手癖がまるで感じられないデザインに仕上がったら最高ですね。
──ライゾマティクスの創立10周年を記念した展覧会「Rhizomatiks 10」のサイトが、遠目で見ると「10」に見える。けど近くで見ると「コード」に見える。この作品もそういった意図でしょうか?
木村:そうです、そうです! トライしてみました。ただ単にコードが並んでいたらコンピューターの手癖が出るけど、そこを星空で「10」と浮かび上がるギミックを入れることで、グラフィックデザインに定着させていく試みです。 田中:木村さんがやりたいのは、いかにコードの手癖、プログラムの手癖を消すか。それって、ジェネレーティブアート(編集部注:コンピュータソフトウェアのアルゴリズムなどを駆使して生成・合成・構築される芸術作品)の歴史そのものだなと思います。僕はプログラマーなのでアプローチは違うけど、やりたいのは多分一緒なんだと思います。
田中:木村さんがやりたいのは、いかにコードの手癖、プログラムの手癖を消すか。それって、ジェネレーティブアート(編集部注:コンピュータソフトウェアのアルゴリズムなどを駆使して生成・合成・構築される芸術作品)の歴史そのものだなと思います。僕はプログラマーなのでアプローチは違うけど、やりたいのは多分一緒なんだと思います。
木村:自分はマウスやペンでアプローチして、田中くんはコードでアプローチしているだけ。あんまり違いはないんだよね。
──目指す先の表現したいクリエイティブは一緒なんですね。最後に、今後のデジタルクリエイターに求められる資質などあれば教えてほしいです。
木村:とある案件で、TOPページで間を持たせるためのデザインを考えていたんですが、社内のプログラマーから「デザインでどうにかしようとするのやめていいよ。プログラミングでどうにかするから」と言われちゃって。
田中:かっこいいですよね。デザイナーが間を持たせようとしたら、プログラマーから「そこはいらない。キャンバスを開けてくれ」と。
木村:実際、それで充分間が持ったんです。そこで思ったのが「誰よりもプログラマーの気持ちを理解できるデザイナー」になりたいなと。それで、さきほどお話しました、「アーティスト志向の強いプログラマー」と「デザイン志向の強いプログラマー」みたいな意識をするようになり、プログラマーのやりやすい環境を整えることに注力しました。今後、デジタル領域のアートディレクターやデザイナーがより増えていくと思います。そういう人たちはコードを書ける必要はないと思いますが、書ける人たちの気持ちがわからないといけないんじゃないかなと。
田中:でもコードを書かないと理解できないんじゃ…。
木村:たしかにね。本気でコード書く志があった上で、折れた人のほうがプログラマーへのリスペクトも生まれるよね。
──田中さんはどうでしょう?
田中:いまのデザイナーはコンピューターを使ってデザインするじゃないですか。でもコンピューターに内側について知らない人が多いですよね。だから我々はコンピューターでどこまでつくれるのか、創作の範囲・限界を一度は調べておかないとダメな気がします。コンピューターにしかできない表現、コンピューターでは表現できない限界を把握しておく必要がある。自分はいま道具として何を使っているのかを意識的に考えたほうが良いです。
木村:そうだね。デザインアプリの限界がコンピューターの限界じゃないからね。
田中:コンピューターってどういうことができるんだろう?っていうのを深く調べておいたほうがデザインの幅が広がると思うんです。絵の具だったら、絵の具の種類を調べたり、重ね塗りなどの技法を調べたりするじゃないですか。それと一緒で、コンピューターでも種類や技法を調べるのは、当たり前のことだと思います。
──デザイナーは表現の幅をどんどん拡張するためには、道具の限界を知らないといけないということですね。
木村:締切が迫っている中で、たとえば1万本の線を引いてグラフィックデザインに落とし込む案があったとして、紙とペンじゃ絶対間に合わない、PCとAdobe Illustratorでも間に合わない。となったとしても、そこにプログラマーがいれば、頼んだらすぐに実現してくれる。さらに1万本の線がランダムで切り替わって、バランスの良いものをその中から抽出できるプログラムをつくってくれたりする。これによって、作業時間の短縮ができて、表現に費やせる時間が増えるわけです。つまり、現在使っている道具の限界を知った上で、それとは別次元のアプローチがないかを探し続けることで、これまでにない表現を生み出す可能性があるということです。そういうことを知っといたほうが良いですね。
──デザイナー・プログラマーという職能の違いだけでなく、これまで両者が歩んできた道が違うからこそ、面白い発見がありましたね。本日はお話ありがとうございました!

木村:所属はそれぞれ、私が“DESIGN”で、田中くんが “RESEARCH”になるのですが、縦割りできれいに分かれているわけではなく、プロジェクトベースでそれぞれの職能が適している人をピックアップして進めていくということが多いです。
田中:“RESEARCH”のアウトプットは、基本的にプログラミングベースやテクノロジーベースの案件が多いため、プログラマーが主に携わっています。“DESIGN”は言わずもがなデザイナーに偏っています。
──田中さんは “デザインエンジニア”という肩書で活動されているようですが、どういう立ち位置なのでしょうか?
田中:どのWebプロダクションもそうだと思うのですが、分業制でデザインチームとエンジニアチームが分断されています。ただ自分自身、AdobeのFlashなどを使ってデザインしていたので、プログラミングとデザインを一緒に捉えていました。PhotoshopやIllustratorだけでなく、プログラミングで絵をつくることをしていたので、デザイナーorエンジニアと分けられるのが好きではありませんでした。だから“デザインエンジニア”と名乗っていました。でもライゾマに入社してからは、もっと自由にできる環境になったため、“ビジュアルアーティスト”と肩書を変えています。

田中:そうです。どこも基本はそうです。デザイナーとエンジニアは分業していないと効率が悪いからです。規模が大きくなればなるほど、職域はしっかり分けられる。でも規模が小さくなればなるほど、そこが曖昧になっていく。だから企業規模を小さくしていくキャリアを積みたいなと大学生の頃から思っていました。
──大学生のときから!? なぜでしょう?
田中:大学の研究室での制作手法が全部1人で行うというやり方だったんです。けど仕事の進め方とか何もわからなかったので、まず大きな会社に入って、業界や社会人の基礎を学ぼうと思って、大手のデジタルエージェンシーに入りました。生意気ですが、お金貰いながら大学院に行くみたいな感覚でしたね。ディレクターとして入社したのですが、デザインとエンジニアリング両方を横断できる気がしなくて、やっぱり少数精鋭の会社じゃないとダメだと思ったんです。それで2社目がWeb制作会社を数社転職し経験を積み、その後ライゾマにといった流れです。
──最初はディレクターだったんですか?
田中:もともとはデザイナー職で入社試験を受けていたのですが、「大規模なプロダクションはデザイナーで入るとデザインしかできないよ。色々やりたいならディレクターの方がいいよ」と言われて、ディレクターで入社しました。
──そういうことだったんですね。では次に木村さん。木村さんは大学でプロダクトデザインを専攻されていたとのことですが、今の仕事とはだいぶ違いますが、どのようにしてWebデザインに行き着いたのでしょうか?
木村:実はプロダクトデザインに特段興味があったわけではないんです(笑)。とにかく美大に入りたくて、受かったのがたまたまプロダクトデザイン科だったんです (笑)。

──分業か兼業か。田中さんと対照的ですね。
田中:木村さんがコードを書くのを辞めたのって何歳のときですか?
木村:28歳のとき。自分が1週間かかるものをたった1日で仕上げるのを見て。それでもライゾマに入ったばかりのときは、「Flash以外触りたくない」って人しかいなくて。htmlは書いていましたけどね。
田中:いましたね。俺の仕事じゃないって、拒否するプログラマー(笑)。
デザイン志向とアーティスト志向
木村:プログラマーって一括りに見られていますが、実際は「デザイン志向が強い人」と「アーティスト志向が強い人」という2つに分けることができます。デザイン志向が強い人は問題を解決するのが得意で、決め込んだ仕様に対して的確に答えることができる人。もうひとつのアーティスト志向の強いタイプは田中くんみたいな人。こっちは白紙のパレットを渡すと、のびのびと描ける人で、そういうタイプは仕様をガチッと固めて縛り付けちゃうと窮屈に感じちゃう。作業になって表現じゃなくなるから。田中:最近わかってきたのですが、相手の頭の中にすでに完成像があるものを形にするのが、劇的に下手くそなんです。
木村:ただ、言うことを聞きたくないだけじゃない?(笑)
田中:なんとか言うことを聞こうとして、きっとこう考えているんだろうなと推測して、実装するんですけど、そうすると劇的にダサくなる。
木村:気持ちが乗っていないだけでは?(笑)
田中:いやいや、違いますって(笑)。ちなみに木村さんから依頼されるときは気持ちよくやらせてもらっています。「ここのページ空けておいたからよろしく」と言われるだけなので。キャンパスと絵の具だけ用意されて「あとどうぞ」みたいな感じで。
木村:田中くんみたいなアーティスト志向の強いプログラマーもいますし、そうではなく解決することが得意なデザイン志向のプログラマーもいるので、仕事をする前にタイプを見極めなければいけません。

田中:普通の会社ってこういうつくり方をしないので、過去のポートフォリオで見極めるのは難しいですね。できるとしたら、個人で遊びとしてつくったものを見るくらいしかなさそう。
──デザイナーもタイプ分けされますか?
木村:グラフィックデザインを積み上げたアート性の強いタイプとシステマチックに考え抜かれた合理性の強いタイプの2つがあります。僕はグラフィックに注視してしまうので、ボタンがどうのこうのといった議論がすごく嫌いで。
──貴社は前者が多いのでしょうか? ちなみに同僚の皆さんはどういう方々が多いのでしょうか? 木村さんも田中さんもWeb制作会社出身ですが。
田中:前者が多いですね。制作会社出身は少ないですね。ウチは本当にバラバラで、建築事務所の出身の人やメーカーでプロダクトデザインやっていた人、それから大学の教授だった人まで、多種多様です。
木村:ライゾマ自体ハードウェアもソフトウェアも幅広く手がけるので、そのアウトプットを見て、自分にも何かできるんじゃないかと感じ取って、入社してくる人が多いですね。だからより一層アウトプットがユニークになるというか、一辺倒でなく幅が広がります。
多様な集団には共通言語が必要
──では次に、木村さん・田中さんのようなデジタル系のクリエイターの人は、そういった異業種の人たちとどのように協業できると思いますか? 最近、オープンイノベーションなど共創が増えており、そういった取り組みの参考になる気がしました。木村:共通のゴールが見えることですかね。ライゾマで言うと、テクノロジードリブンやデータドリブンで、アウトプットにこのテクノロジーを使いたい、あのデータを使いたいみたいな会話がされて、共通言語となっています。
田中:ライゾマは、すごく綿密に話し合って皆で足並み揃えてプロジェクトを進める感じではないんです。ひとりで全部完結できちゃうような人たちが、でも1つのプロジェクトに思い思いに集まるような感じです。
木村:だからこそ、一本串を刺しているのが、テクノロジードリブンやデータドリブン。共通言語やデータがあるからブレない。勝手に進めたけど、使っているデータが一緒だから、矛盾せずにつながるようなことが多々あります。
田中:テクノロジーやデータを大事にするのがライゾマティクスのカルチャーですが、実はちゃんと言語化はされていないんです。社内で説明もないし。けど、各々がそのカルチャーを勝手に感じ取って、勝手にグルーブを感じて、勝手に集まっている。基本的にみんなフリーランスの集まりみたいなものなんです。
木村:真鍋大度曰く「野良猫の集まり」。勝手に来て、いつの間にかいなくなるみたいな(笑)。会社というよりかは集団感が強いです。
田中:真鍋ほかトップ陣が、自分たちの好きなモノをわかっていて、それに共感しているからこそ、集団として成り立っていますね。
テクノロジーやデータとグラフィックデザインは融合する
──テクノロジーやデータを最重要視することをプログラマーが共感する感覚は理解できるのですが、デザイナーはどうなんでしょうか?木村:私は共感できますね。イラストや写真、コピーをキレイに配置する王道のグラフィックデザインではなく、テクノロジーやデータを駆使したグラフィックデザインならうまく差別化して勝てるかもしれないという感覚があるからです。この道はまだ多くの人が掘り下げていない分野だからこそ面白い。たとえばデータをグラフィックデザインに定着させる決まり手がまだ見つけられてない。どうしても「コンピューターの手癖」が出てしまうんです。それを払拭できないかを模索しているところです。
──「コンピューターの手癖」ですか? どういうことでしょうか?
木村:プログラミングされた感というか。コンピューターの手癖があると、たとえ最先端な取り組みだとしても既視感が出てしまう気がします。だから、なんとか消して、グラフィックに定着させたいんです。最終的には、コンピューターの手癖がまるで感じられないデザインに仕上がったら最高ですね。
──ライゾマティクスの創立10周年を記念した展覧会「Rhizomatiks 10」のサイトが、遠目で見ると「10」に見える。けど近くで見ると「コード」に見える。この作品もそういった意図でしょうか?
木村:そうです、そうです! トライしてみました。ただ単にコードが並んでいたらコンピューターの手癖が出るけど、そこを星空で「10」と浮かび上がるギミックを入れることで、グラフィックデザインに定着させていく試みです。

木村:自分はマウスやペンでアプローチして、田中くんはコードでアプローチしているだけ。あんまり違いはないんだよね。
──目指す先の表現したいクリエイティブは一緒なんですね。最後に、今後のデジタルクリエイターに求められる資質などあれば教えてほしいです。
木村:とある案件で、TOPページで間を持たせるためのデザインを考えていたんですが、社内のプログラマーから「デザインでどうにかしようとするのやめていいよ。プログラミングでどうにかするから」と言われちゃって。
田中:かっこいいですよね。デザイナーが間を持たせようとしたら、プログラマーから「そこはいらない。キャンバスを開けてくれ」と。
木村:実際、それで充分間が持ったんです。そこで思ったのが「誰よりもプログラマーの気持ちを理解できるデザイナー」になりたいなと。それで、さきほどお話しました、「アーティスト志向の強いプログラマー」と「デザイン志向の強いプログラマー」みたいな意識をするようになり、プログラマーのやりやすい環境を整えることに注力しました。今後、デジタル領域のアートディレクターやデザイナーがより増えていくと思います。そういう人たちはコードを書ける必要はないと思いますが、書ける人たちの気持ちがわからないといけないんじゃないかなと。
田中:でもコードを書かないと理解できないんじゃ…。
木村:たしかにね。本気でコード書く志があった上で、折れた人のほうがプログラマーへのリスペクトも生まれるよね。
──田中さんはどうでしょう?
田中:いまのデザイナーはコンピューターを使ってデザインするじゃないですか。でもコンピューターに内側について知らない人が多いですよね。だから我々はコンピューターでどこまでつくれるのか、創作の範囲・限界を一度は調べておかないとダメな気がします。コンピューターにしかできない表現、コンピューターでは表現できない限界を把握しておく必要がある。自分はいま道具として何を使っているのかを意識的に考えたほうが良いです。
木村:そうだね。デザインアプリの限界がコンピューターの限界じゃないからね。
田中:コンピューターってどういうことができるんだろう?っていうのを深く調べておいたほうがデザインの幅が広がると思うんです。絵の具だったら、絵の具の種類を調べたり、重ね塗りなどの技法を調べたりするじゃないですか。それと一緒で、コンピューターでも種類や技法を調べるのは、当たり前のことだと思います。
──デザイナーは表現の幅をどんどん拡張するためには、道具の限界を知らないといけないということですね。
木村:締切が迫っている中で、たとえば1万本の線を引いてグラフィックデザインに落とし込む案があったとして、紙とペンじゃ絶対間に合わない、PCとAdobe Illustratorでも間に合わない。となったとしても、そこにプログラマーがいれば、頼んだらすぐに実現してくれる。さらに1万本の線がランダムで切り替わって、バランスの良いものをその中から抽出できるプログラムをつくってくれたりする。これによって、作業時間の短縮ができて、表現に費やせる時間が増えるわけです。つまり、現在使っている道具の限界を知った上で、それとは別次元のアプローチがないかを探し続けることで、これまでにない表現を生み出す可能性があるということです。そういうことを知っといたほうが良いですね。
──デザイナー・プログラマーという職能の違いだけでなく、これまで両者が歩んできた道が違うからこそ、面白い発見がありましたね。本日はお話ありがとうございました!