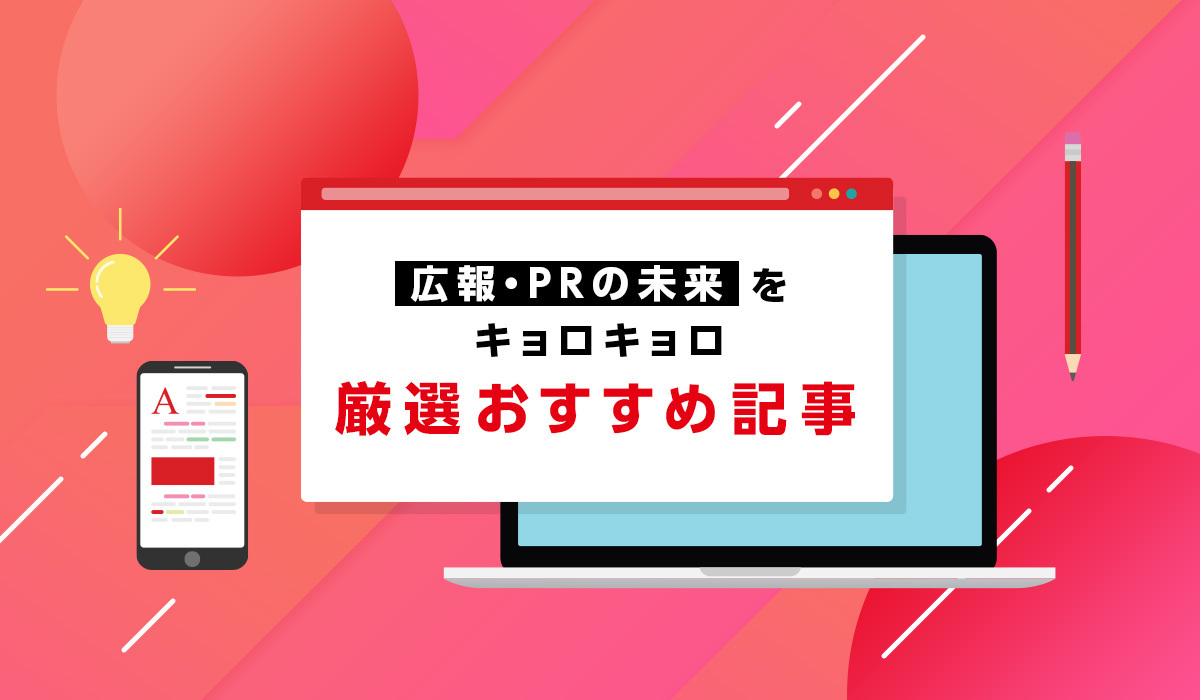XRを真のエンタメへ!ストーリーテリングが鍵となる Supership XR戦略企画室 XRコンテンツプロデューサー 待場勝利さん

XRは、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)、複合現実(MR)などの現実世界と仮想世界を融合させる技術です。今後ますます市場の拡大が見込まれるXR領域において、コンテンツとしての可能性はどこにあるのでしょうか? KDDI傘下のデジタルトランスフォーメーション事業を手掛けるSupershipでXRコンテンツプロデューサーを務める待場勝利(まちばかつとし)さんに、ご自身のキャリアからXR市場の展望と課題までお聞きしました。
フレームを超えた映像の世界に可能性を感じて
──テレビの製作畑からどのような経緯でVRの道へ進まれたのでしょうか。大学卒業後、映画製作の夢を諦めきれずにアメリカへ留学しました。帰国後は、テレビ報道番組のアシスタントディレクターからキャリアをスタートし、叩き上げでディレクターにまでなりました。その後、20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン(以下、フォックスジャパン)で海外ドラマの日本語版プロデューサーを約10年経験した後、サムスン電子ジャパン(以下、サムスン)に転職しました。当時、日本で流通しているサムスン製品は携帯電話のみ。ハードを売るのではなく、付随するコンテンツを強化するという経営方針のもと、映像と音楽のサービスを立ち上げるべく奮闘していました。そして1年が経ったころ、サムスンからVR用ヘッドセット「Gear VR」が発売されたのです。それまでVRの存在自体も知らなかった私ですが、初めてVRを体験し、どっぷりVRにはまっていきました。
──VRに興味を持ってサムスンに入ったのではなく、サムスンでVRに出会ってのめり込んでいったのですね。VRに転換したきっかけはありましたか?
2016年はVR元年といわれていますが、そのタイミングでGear VRが発売されました。サムスンとしてもVRに力を入れようとしていましたが、日本のなかではVRのことがわかる社員がいませんでした。そこで、映像や音楽のコンテンツ製作の経験があった私が、ゼロベースでVRを勉強することになりました。

──もやもやしていたときの運命の出会いだったのですね。
“もやもや”が続いているなかで、なんとなくヒントが見えてきた感じです。
それには、サムスンでの経験が大きいです。海外や日本のVR業界の方と話をする機会に恵まれました。いろいろな方と話をしていくうちに、VRで重要なのはコンテンツで、もっとたくさんコンテンツをつくらないとVR市場は発展しないと気づきました。特に、手応えを感じたのは、ハリウッドへの出張のときです。アメリカではすでにVRの研究が始まっており、VRもストーリーテリングが重要だといわれていました。VRというとゲームを一番に思い浮かべる方も多いと思いますし、当時からゲームでの応用が先進的でしたが、私はゲームの経験がありません。しかし、ストーリーテリングとVRがつながった瞬間、映像畑の私でもやれると確信を持ったのです。それからは、ストーリーテリングにこだわって活動をしています。
ストーリーテリングでXRの可能性を
──VRでのストーリーテリングの醍醐味を教えてください。いまのVR映像は、映画の黎明期に似ていると思います。映像作家クリス・ミルクがTED2016でスピーチをした内容の引用になりますが、スクリーンに映像が投影できる技術が開発されたころ、リュミエール兄弟が公開した『ラ・シオタ駅への列車の到着』という映画があります。駅のプラットフォームに汽車が到着するだけの映画なのですが、この映画が劇場の大きなスクリーンで上映されたとき、初めてその映像を観た観客は汽車にひかれると錯覚し、思わず劇場から逃げ出したという逸話が残っています。クリス・ミルクは、TEDで同じことを再現します。VRデバイスを配り、自分に向かってくる汽車の映像をVRで流しました。観客は、汽車が自分にぶつかろうとした瞬間に、ヘッドマウントディスプレイを外したのです。映画も情景を描写する映像から、物語を語る映画に進化し、いまでは多種多様なクリエイティブの表現が存在しています。VRもまさに同じ出発点にいると思います。
──VRでストーリーテリングを表現することへの可能性を感じ、本格的にVRのコンテンツづくりに集中していったのですね。いまはどのようなお仕事をされているのでしょうか。
2019年からSupershipのXR戦略企画室に所属しています。以前はVR戦略企画室という名称だったのですが、VRにとどまらず、ARやMRなど新しい技術を取り入れたコンテンツ製作に力を入れています。
事業は、自社事業と受託事業の2つの軸があります。自社事業であるXRstadiumは、XR映像を配信するプラットフォームです。XRはまだまだ発展途上の領域で、会社にとって投資事業の位置づけです。しかし、きちんと利益を還元できる事業にしていかなければならないと思い、受託でXRコンテンツの製作を請け負う事業も立ち上げました。私の立ち位置は、プロデューサーとしてコンテンツを製作しながら、XRでなにをしたいのか、なにが実現できるのかをクライアントに提案するコンサルタントのような役割も担っています。
最近の手掛けたコンテンツとしては、内閣府と海洋研究開発機構(JAMSTEC)の共同主催によるイベント「Society 5.0科学博」で、有人潜水調査船「しんかい6500」のライブ中継をVRで行いました。本来は、スカイツリーと沼津でライブビューイングを実施し、子どもたちに生中継で観てもらう予定でした。それはコロナ感染拡大により叶いませんでしたが、ライブ配信自体は行いました。深海にいるサメがやってきたりして、深海という未知の世界をリアルタイムに360度の映像として中継できました。フレーム映像とは違った視聴体験を提供できたと思います。
──個人活動も行っていると伺いました。
Supershipに入社する前から、VR映画を製作する活動も行っています。どのようにVRでストーリーテリングしていくのか、新しい映画の表現方法を試みています。例えば、伊東ケイスケ監督が手掛けたVRアニメーションにプロデューサーとして関わっています。これまで、「Feather」、「Beat」、「Clap」という作品を製作しました。3年連続で、ヴェネチア国際映画祭へ参加し、「Beat」、「Clap」についてはヴェネチア国際映画祭バーチャルリアリティ部門「Venice VR Expanded」にノミネートされました。
個人活動は直接Supershipに関係ありませんが、この活動を通してXR産業が盛り上がっていくことで、巡り巡ってSupershipにも還元できると思い、続けています。

VRアニメーション「Clap」
XRのこれから
──いままさにXRは流行の波に乗ろうとしているところなのでしょうか。XRのあるべき姿が見えてくるまでには、もう少し時間がかかると思っています。いまが最終形ではなく、最終形に向かうまでの途中過程。それに向けていろいろ試している段階です。
その最終形が見えるひとつのきっかけとして、私は大阪で行われる2025年日本国際博覧会をターゲットにしています。万博はその時代の先の未来を見せるもの。2025年にXRコンテンツのその先のビジョンを見せるべきだと思っています。
──そのためにはなにが足りないのでしょうか。
技術もインフラも含めて、なにもかも足りていないですが、私が課題に感じていることの一つに、圧倒的にユーザーが少ないことがあります。どんなに素晴らしい作品をつくったとしても、たくさんの方に体験してもらわないと、ビジネスとして成り立ちません。XRが産業として残っていくためにはビジネスとしての成功も勝ち取らないといけません。そのためには、VRデバイスが一人一台、最低でも一家に一台まで普及していく必要があります。
そして、そのユーザーのVRリテラシーも上げていかなければなりません。未だにVRのイベントを開催すると、「360度見渡してください」と伝えないと、ヘッドマウントディスプレイをかぶったまま、まっすぐじっとしている方が多いです。映像はまっすぐ向いて観るものという固定観念があるからでしょうが、VR映像は映画やテレビのように前に座っていれば、物語が始まるわけではありません。例えば、昨年ヴェネチア国際映画祭でVR作品賞を受賞した『The Hangman at Home: An Immersive Single User Experience』という作品は、マッチが目の前に置いてある場面から始まります。ユーザーがそのマッチを手に取り、蓋を開け、マッチを擦って、火が灯ると、物語が始まる仕掛けが施されています。ということは、マッチを擦らないと物語は始まらないのです。VRはユーザーが能動的に動いて楽しむものです。このようなリテラシーがライトユーザーまで浸透していかないと、VR映像は進化していかないでしょう。ユーザーの目が肥えることで、作品が淘汰され、つくり手の表現も成熟されていきますから。
さらには、XRの世界に日常的に行くきっかけづくりも重要だと考えています。いろいろな都市をデジタル化したとしても、そこになにがあるのか。実在の渋谷のように若者が毎日足を運びたくなるような仕掛けをつくる必要がある。人気ゲームの「フォートナイト」上で米津玄師さんらがライブを開いたことが話題になりましたが、ゲームや音楽、映画などといった複数ジャンルのエンタメをオンライン上で融合するという発展はありだと思いました。私としてはその一つの答えとして、ストーリーテリングを打ち出しています。ライトユーザーも楽しめる新しい形のエンターテイメントまで昇華していければ、ユーザーもついてくるはずです。
──そのために、待場さんは未開の領域で奮闘しているのですね。
2020年2月に、日本初のXRに特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」を発足したのもその一環です。そのほかにもXRについて講演したり、WebマガジンでVR映画を紹介するコーナーを毎週連載したり、日々普及活動に邁進しています。
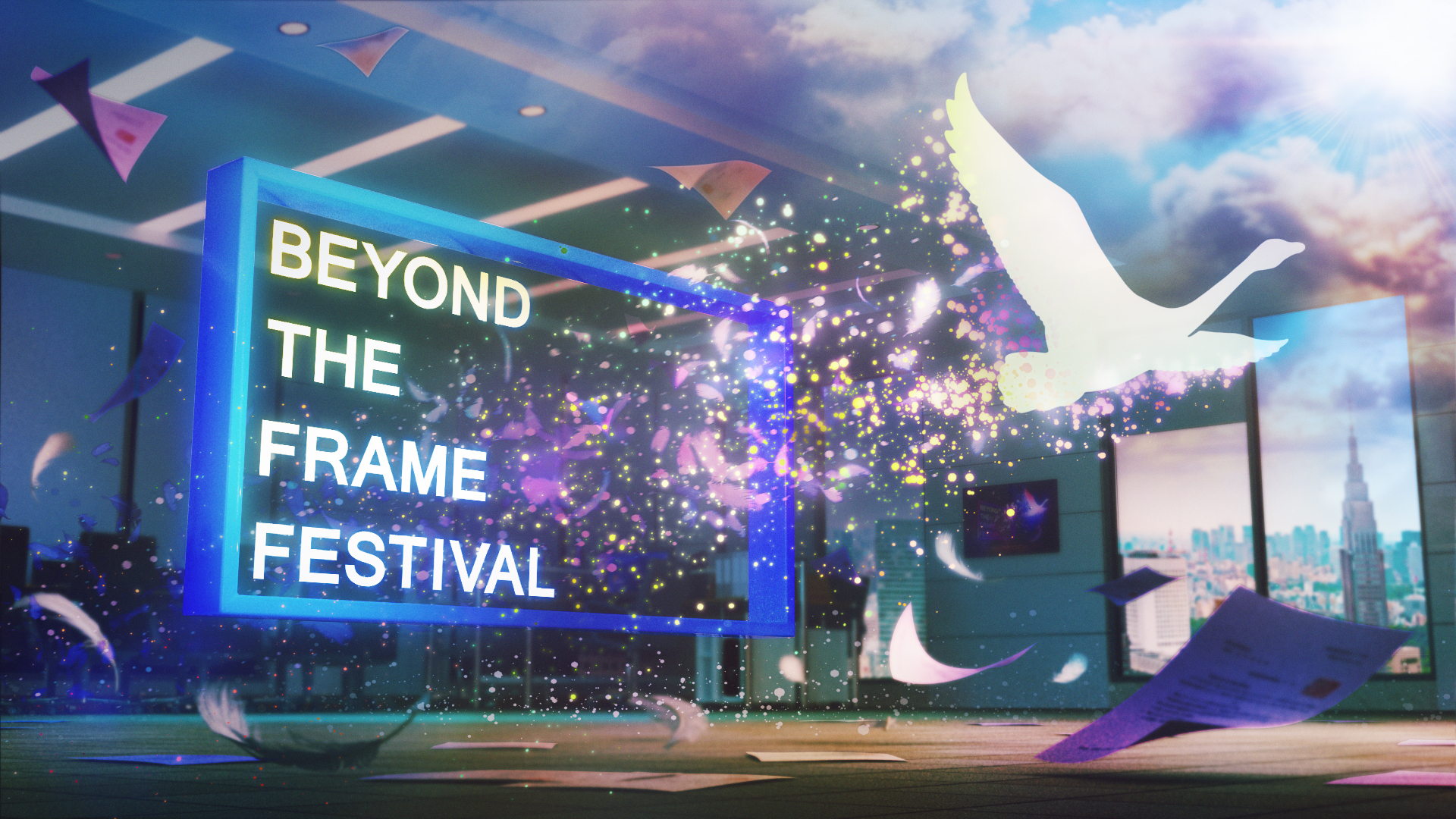
日本初のXRに特化した国際映画祭「Beyond the Frame Festival」
SupershipのXR戦略企画室をVRにこだわらず先端技術を取り入れたコンテンツづくりの専門集団にしていきたいです。もちろん技術開発も重要ですが、ユーザーが体験して楽しいと思うことは普遍的なことだと思います。その軸はぶらさず、まだテスト的なところもありますし、技術的に実現できないところもありますが、AR、MRなど先端技術を使って、楽しいと思ってもらえるコンテンツをつくっていきたいです。そして私のバックグラウンドには映画があるので、XRで新しい映画の形もつくりたいです。2025年に向けて、いろいろなプロジェクトにトライしていきます。