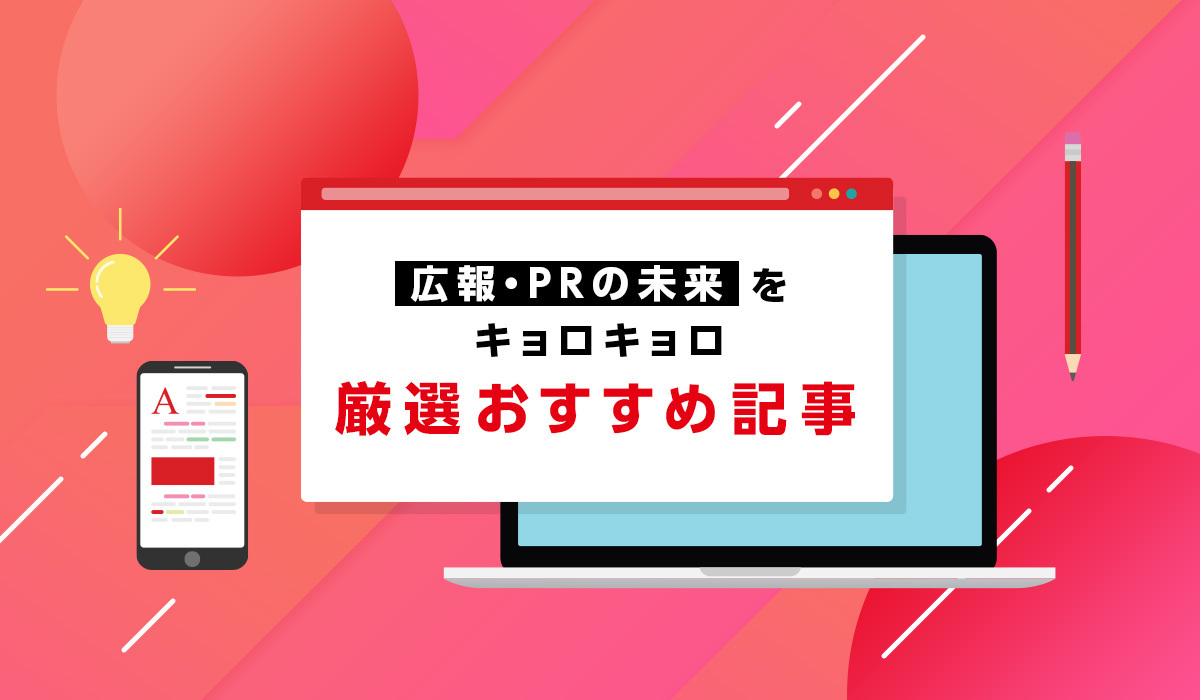広告クリエイターはAIとどう向き合うべきか 電通デジタル アドバンストクリエイティブセンター AIクリエイティブ事業部 AIクリエイティブ・エンジニア/プランナー 石川隆一さん

「クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞」は、その年、広告コミュニケーションにおいて優れたクリエイティブワークを行った個人を表彰する、広告クリエイター憧れの賞です。今年発表された2021年の受賞者も、個性あふれるクリエイティブディレクターやアートディレクターが名前を連ねました。
そんななか、ひときわ異彩を放ったのが電通デジタルの石川隆一(いしかわりゅういち)さんです。その仕事は、AIクリエイティブ・エンジニアでありプランナーでもあります。AIの知見を活かしたデジタル広告作品を次々と生み出したことが、歴史ある広告賞で評価されたことは、広告界の新しい時代の幕開けを予感させるニュースとなりました。石川さんが広告の世界に飛び込んだのは、ほんの4年前。新参のクリエイターは、広告クリエイティブの今後になにをもたらそうとしているのでしょうか。
そんななか、ひときわ異彩を放ったのが電通デジタルの石川隆一(いしかわりゅういち)さんです。その仕事は、AIクリエイティブ・エンジニアでありプランナーでもあります。AIの知見を活かしたデジタル広告作品を次々と生み出したことが、歴史ある広告賞で評価されたことは、広告界の新しい時代の幕開けを予感させるニュースとなりました。石川さんが広告の世界に飛び込んだのは、ほんの4年前。新参のクリエイターは、広告クリエイティブの今後になにをもたらそうとしているのでしょうか。
「AIがプロ棋士に勝った」というニュースに心奪われて
──いきなりですが、石川さんがどんなお仕事をされているのか、ちょっとわかりづらくて……。そうでしょうね(笑)。一般的に広告というと、有名なクリエイターがつくる従来型のマス広告やデジタル広告をイメージされる方が多いと思います。でも、僕が所属する電通デジタルの「アドバンストクリエイティブセンター(ACRC)」はほかにもさまざまなことにチャレンジしています。AI(人工知能)やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)などのデジタル技術とデータを融合して、新しい広告表現を生み出すことに挑戦しているクリエイティブ組織です。
そのなかでも、僕はAIを専門に扱うグループに入っています。クライアントの課題を聞いて企画を考え、それを実現するためのAI開発やディレクションするのが仕事です。
──音楽大学卒業というご経歴といまのお仕事にギャップがあって、すごく面白いです。
実はミュージシャンを夢見る少年だったんですよ。かつては音大といえばクラシックでしたが、僕が大学進学を考えるころにはジャズやポップスを教えるところも増えていて。ギターをやっていたので、ロックとか、はやっている音楽を勉強したくて音大に進みました。

はい。レコード会社にお世話になっておりました。でも全然売れなかった。プロの道は厳しかったですね。断念して、ほかの所属アーティストのマネージャーになりました。
──それでも、音楽にかかわることができていたんですね。AIに興味を持つ出来事があったのですか?
日本の音楽業界は、CDを売るというビジネスモデルが難しくなり始めた状況でした。音楽が好きな気持ちに変わりはなかったものの、自分の仕事として冷静に将来を考え、なにか新しいことを始めないといけないと思ったんです。
身の振り方を探っていたとき、ふと「AIが現役のプロ棋士に勝った」というニュースを目にして、一瞬で心を奪われました。「AIが世の中を変えるかもしれない」と。すごく未来がある分野に感じて、「この技術を使ったクリエイティブな活動をしてみたい」と思いました。
そういうことをやっている会社はどこなんだろうと調べたら、広告会社の電通グループのなかに、新しいデジタル技術を使った表現に挑戦するチームであるACRCができたことを知りました。すごく面白そうだと思いました。そこから、AIづくりの基礎を教わるために専門学校に通い始めたんです。Python(パイソン)という言語を使ったプログラミングやディープラーニング(AIの学習手法の1つ)の仕組みなど、3カ月間みっちり学びましたね。自分に向いていたのか、勉強はそんなに苦労しなかったです(笑)。在学中に国際的なAIコンペティションプラットフォーム「Kaggle(カグル)」で入賞して、「AIをつくれる」という実績ができた。それで、電通デジタルの採用面接を受けて、卒業とともに入社することになったのです。
──音楽の世界で生きてきたくらいですから、根っこからクリエイターなんでしょうね。だからAIに興味を持っても、グーグルやアップルではなく、広告会社の電通デジタルを選んだ。
AIエンジニアになりたかったのなら、もっとなんどもKaggleのコンペに出て、金メダルの常連として有名になるくらいの高みを目指したと思います。僕はAIをつくる人ではなく、AIを使った表現を追求する、クリエイターになりたかったんです。
僕ら人間が得られる情報って、自分の視界に入ってくるものくらいですよね。匂いとか味もありますが、ほとんどは目で見たことです。AIを使うと、目だけでは感知できなかった関連データを得ることができるようになります。言わば人間の「見る」機能を拡張する。これって、すごく価値があることだと思います。広告表現に取り入れることができたら面白いことになると考えていました。
僕はAIエンジニアではなく「クリエイター」
──転身から約4年。期待していた活動ができていますか。
入社したとき、電通デジタルは設立2周年を迎えたばかり。AIをつくれる人はごくわずかでした。広告の電通グループがAIをつくったと発表しても、「どうせAIもどきでしょ」と冷ややかに見られていました。
だから、最初の1年間は「AIを使った表現をやりたい」という気持ちをぐっと抑え、研究職というスタンスで働いていました。バナー広告の大量自動生成ツールにAIを組み込んで、表現の違いによってクリック率がどのくらい変わるかを予測したり、アートディレクターがデザインのよしあしを判定する感性をAIでモデル化できないか検討したり、論文を学会で発表したりするなど、AIの研究に努めていました。
──その後、どのようにクリエイターとして活動していくことになったのでしょうか?
2年目からは徐々に、AIを表現に取り入れたプロジェクトが形になっていきました。電通には、マス広告をやってきた優秀なプランナーがたくさんいます。彼らが「AIのスペシャリストが来た!」と面白がってくれた。「こんなことできない?」と相談されることが増えていったんです。
最近の例では、横浜八景島主催の「“名画になった”海 展」がその1つ。プラスチックごみによる海洋汚染問題をアートで表現した展示会です。例えば、ごみであふれた未来の海を葛飾北斎が描いたらどんな絵になるか。そんなことをAI技術で再現しました。
──AIに絵画の巨匠のタッチを学ばせたわけですね。1回きりのイベントで終わってしまうのがもったいない。ソリューション化して広くクライアントに提供するわけにはいかないのでしょうか。
もちろん可能です。ただ、僕自身は「自分がつくったAIをソリューションとして残したい」という思いがなくて。会社としてそうした方がいいものは、「このままあげる!」って、ほかの人に渡して開発してもらっています(笑)。
僕が興味あるのは、AIをつくってなにかのサービスの一部分に入れることではありません。AIを使って表現することなんです。自分のAIを使ったプロジェクトが世の中に広がって、皆さんに見てもらったり、体験してもらったりすることに魅力を感じています。
広告やプロモーションの領域で、AIを使う事例は増えています。でも、「はやりの技術を使ってみた」というものが少なくありません。ふたを開けたら、ちっとも面白くない。僕はそういうのがすごくイヤ。AIって本当に素晴らしい技術なんです。これをクリエイティブで昇華させたいという思いを強く持っています。
──「クリエイティブで昇華させる」というのは、どういうイメージですか?
AIという技術で、面白い表現をするということです。
例えば、先ほどの「“名画になった”海 展」なら、絵のタッチを転写できるAIを、どうすれば面白く使えるかを考える。そこに「葛飾北斎が未来の海の絵を描く」というアイデアを組み合わせる。
「老化するAI」というのもあります。これをどう使えば面白いか。警察庁と協力して、過去の指名手配被疑者の写真から年をとった現在の姿を予測し、特設サイトで情報提供を呼びかけるキャンペーンをやりました。

誰でもAIをつくれる。プロは市場価値をキープする努力が必要だ
──そういったAIを使ったアイデアは、いつ湧いてくるのですか?寝ている間ですね。僕は明晰夢(めいせきむ)を見ることができるんです。「これは夢だ」とわかっていながら見る夢なのですが、そのなかで企画を考えることが多い気がします。いいアイデアが出たときは、起きてすぐにメモしておきますよ。
──やはり、そういう特別な能力を持っている人でないと、AIをつくるのは難しそうですね……。
いや、そんなことはありません(笑)。たとえ文系出身でも、努力すればなれると思います。ただ、プログラミング言語、特にPythonには数学の知識が必要です。英語はできなくても大丈夫ですが、数学が致命的に苦手だと無理かもしれません。

いまはAIバブルですから、AIエンジニアの市場価値がすごく高い。でも、誰でもスマホでつくれる時代に変わりつつあります。正直なところ、中途半端な知識やスキルでは市場価値を維持できないだろうと考えています。僕は継続的にKaggleのコンペに参加して自分の技術力を確認したり、論文を毎日読んで新しい情報を得たりすることを意識的にやっています。
クリエイティブにとって「最適化」を競うより大切なこと
──AIを使ったクリエイティブとして、いま実現したいことはありますか。ちょっと考えているのが、レコメンドエンジンを使った新しい表現です。
レコメンドエンジンは、購入履歴や閲覧履歴などのデータをもとに、ユーザーの好みに合うコンテンツを表示するシステム。ユーザーがWeb上の膨大な情報におぼれることなく、必要とするコンテンツにたどり着きやすくなっているのは、システムのなかでAIが好みを学習して、どんどん最適化していっているからです。
僕はお酒を飲みながらYouTubeを見ていると、最後は必ず玉置浩二にたどり着きます(笑)。いつも同じ動画を見て泣く(笑)。それが夜のルーティンになっています。
あるとき、ふと思ったんです。「あれ、なんだか視野が狭くなってしまったんじゃないか?」って。セレンディピティ(予想外の幸運)が起きにくくなっている。「思いがけない遭遇」を体験することが、デジタルの世界になって減ってしまったなと思いました。
──確かに、最適化と視野が狭くなることは表裏一体ですね。
だから、レコメンドエンジンを使って、あえてユーザーの興味の外にあるものをお勧めするのはどうだろうと。昔、レンタルビデオ店でふと目についた作品を借りていましたよね。本屋でなにげなく手に取って買っていました。そういった体験をデジタル上で表現できないかなと考えています。距離があるものと出会って、人生の視野を広げる。そういうキャンペーンをやってみたいです。

広告制作のプロセスにAIを活用すれば、クリエイティブはもっと創造性あるものができるということです。
でもAIが得意なのはやっぱり最適化することです。AIをクリエイティブに取り入れようとしている人たちの多くは、創造性を高めるというより、過去のデータを学習させて、より効果が出る表現にしたいと考えています。
それがクリエイティブにとって正しいことなのかというと、僕はそうではないと思う。レコメンドエンジンが視野を狭めるのと同じで、最適化され過ぎるとクリエイティブの幅が狭くなっていきます。クライアントの課題解決に向けた広告会社のプレゼンも、「AIがこう言っているので、こうすれば改善されます」なんてことをやり始めると、どこも同じ解になる。新しい広告表現がどんどん生まれづらくなっていきます。
そうならないために、最適化され過ぎる危険性を理解した上でAIを活用しなければなりません。僕はあえて、最適化とは逆の方向にAIを使って、創造性を高めることにチャレンジしてみたいと思っています。
──それはぜひ実現させてほしいです。
デジタルの世界って、発展途上の領域だからこそ、まだまだできることはたくさんあると思っています。まだ生み出されていない面白いクリエイティブ表現をつくりだす。そのことを考えるとドキドキしますし、世の中をワクワクさせたいと思っているんです。
──いま、あらゆる側面で最適化や効率化が進んでいます。その流れにはあらがえません。クリエイティブの領域にそれが取り入れられることを想像すると、怖い気もします。一方で、広告プロセスにおいてAIがうまく使われれば、表現の幅が広がるのではないかという期待感もあります。これからの時代を行くクリエイターの皆さんには、新しい技術をまさしくクリエイティブに使って、心が動かされるような広告、世の中を突き動かすプロジェクトをぜひしかけていただきたいと思っています。楽しみにしています。本日はありがとうございました。