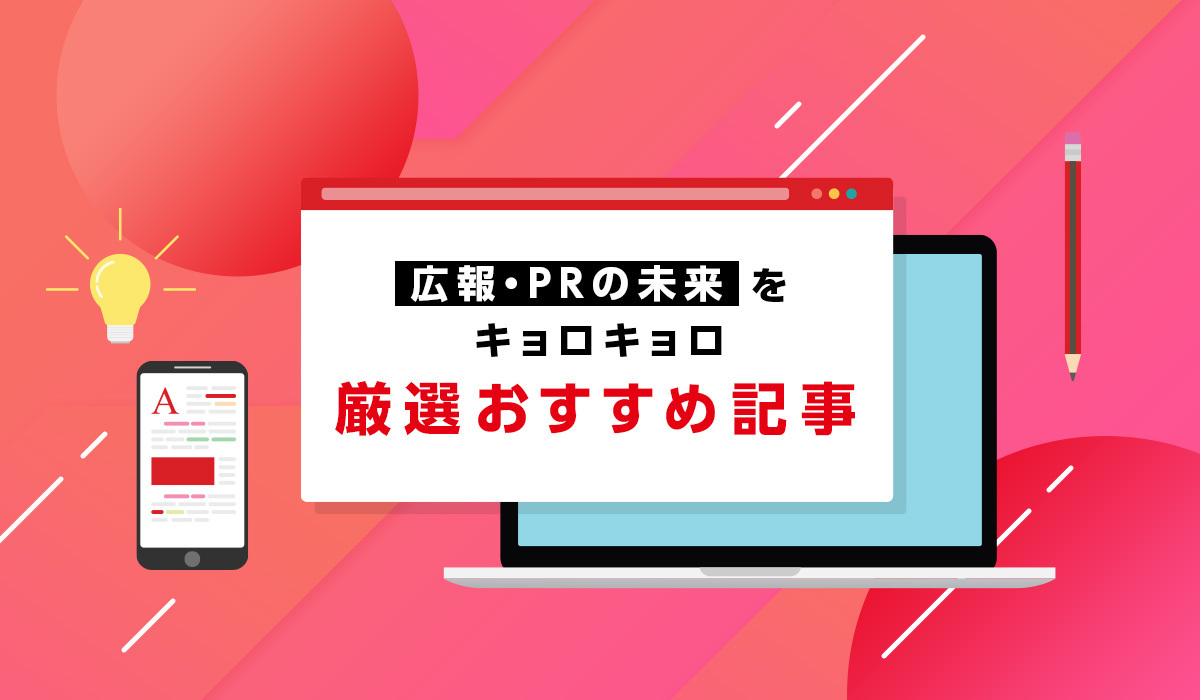嘘や無理を少しずつ潰していって、残っていた輝きが「自分らしさ」だと思う 【2022 CREATOR OF THE YEAR】電通 栗田雅俊さん

10年分のコピー年鑑を読み込んだ新人時代
──クリエイター・オブ・ザ・イヤー、おめでとうございます。今日はいろいろお聞きしたいことがありますが、まずは新人の頃のお話をお願いします。
僕が入った頃の電通は、入るとみんな営業・マーケティングなど別の部署に配属されて、1年目の終わりにクリエーティブ局への転局試験がありました。で、その結果、コピーライターになったんです。希望していたので、ホッとしたのを覚えています。しかし、配属されてしばらくして、自分の力のなさに気がついて、どうしたらいいものかと悩み、『コピー年鑑』(編集:東京コピーライターズクラブ、出版:宣伝会議)を10年分、えい!と買いました。
──え、あの高価な本を買ったんですか。資料室で借りるのでなく。
たしか1冊1万5000円くらいで、15万円くらいしたと思うんですけど、バッ!って買いました。それはある種の覚悟だったんです。資料室に置いてあってもコピー年鑑をたぶん深くは読まない。買って徹底的に読もうと覚悟を決めた。当時全然お金がなくて痛かったのですが、自分の中でリスクを背負った。そうすると、元を取りたくてもう舐めるように読み込むんですね(笑)。あ、このコピーとこのコピー似ているな、そういうことにも気づいて。もしかしたら、これってルールがあるんじゃないかと感じました。そして、自分で観察して、分析して、法則を発明して、書きためて、自分の中で腑に落ちるようにコピー表現を構造化していった。
いざ仕事が来た時に、そのリストを照らし合わせると、コピーが量産できた。僕はコピーが本当に書けなくて、下手くそだったんですけど、そういうふうに、一度自分の手に取れるサイズにしたのが、地力につながっていった感じがして。あそこで10年分買ってなかったら、間違いなく今の自分はなかったなって思うんです。
──振り返れば、10年分一括購入は安かったかもしれません。
10年分読むと、いつの年鑑の何ページぐらいにこういう作品があるというアーカイブができます。自分の脳内に百科事典がある気分になってくる。参照スピードもすごく上がるし、今、置かれている広告界の流れもわかってくる。若い頃、先輩から教えられたこともためになったけど、自力でコピー年鑑に取り組んだのが大きかったかもしれないです。
──そんな中、自分の視点やスキルが上がったと感じたのはいつ頃でしたか。いい仕事の打席に巡り合ったのか、技術が習熟したのか、やり方を変えたのか。どうでしょうか。
「僕が僕っぽい感じになれた時」があったのは覚えているんです。それはラジオCMの仕事でした。当時、若手はラジオCMを任されるみたいな時代で。僕はラジオCMをつくっていたとはいえ、全然うまくなくて、コピー年鑑に載ってるようなものとはすごい距離があった。
僕には才能がないんだなぁ、なんでできないんだろう。ちょっと悲しい気持ちになったりしてたんですけど、でも、頑張らなきゃと思って、ギリギリまで追い込まれながら考えてたんです。商品がこうだから必要なストーリーはこうだとか、どういうキャラクターつくってどういうセリフをしゃべらせるとか、設定はこうして、商品の内容をこう言っていこうとか、もうほんとにいろんなことを考えていました。で、ふと、その時、もう疲れていたせいか、そういうの全部やめよう…と思ったんです。
そこで書いたのが、2人の地味な男がただしゃべってるだけというCMです。この2人が誰なんだとか、ストーリー設定とか、まったくなくて、この男たちがしゃべっていることがちょっと面白いということを目指した。で、それを書いてた時に、「抜けた感じ」があったんです。つまり、僕、無理してない。今、無理してないぞ、っていう感じ。
──僕が僕っぽい感じになれた時。すごく興味深いです! 具体的に聞かせてください。
それは、とある男性向けニオイケア商品のラジオCMでした。だから、ニオイが気になるシチュエーションとか、ニオイすぎるストーリーとか、ニオイにまつわる面白い企画構造を考えていました。でも、夜までやってもいい案が思いつかない。それでフラフラの頭で書いたのが、あんまりテンションの高くないモテなさそうな僕みたいな男が2人いて、ただ会話をするというもの。
1人が「あのさ、『くさい』って言葉あるだろ、あれ人を傷つけちゃう言葉だから良くない。だから俺、『くさい』を『すばらしい』って言い換えたらいいと思うんだ」と言い出す。するともう1人が「なるほど! いい考えだ」と褒める。すると男が「ありがとう。ところで、君、最近わりとすばらしいよね」と言い始めて「いやちょっと待って」となる。その後も「さっきあまりのすばらしさに、エレベーターで近づけなかった」みたいに2人で話し続けるというラジオCMです。
ある言葉をある言葉に言い換えて、会話をずっと続けていくだけなんですが、好評でシリーズ化もできたんです。髪が抜けることを「宝くじ当たった」って言い換えるとか。こういうのは、僕が普段、友達と冗談で話しているような内容で、それをCMにした。そうすると、全然無理してない。場所やタレントさんの設定や、ストーリーづくりに無理に持っていかなくても、普通に今僕がしゃべっているのに近い感覚で企画ってできるんだと思ったんです。面白いことってそんなに無理してつくらなくてもいいんだ。自分の中にある、「自分が面白いと思ってることをいかに傷つけずにそのまま出せるか」ということが、クリエイティブなのかもしれない、と思ったんです。

自分に嘘をついていない状態での広告づくりが一番強い
──まさにブレークスルー、神が降りてきた感じもあります。映画監督のマーティン・スコセッシが、「最も個人的なことが、最もクリエイティブなこと」と言っていた。自分丸出しみたいなことをした方が、逆に効率的で、効果的に面白さが出せるかもしれないと思いました。それが初めてできて、初めて褒められた。
一生懸命勉強して、すごく構造を考えていたけど、やっぱり無理しているところもありました。構造から入ろうとする思い込みがまず間違ってたんだ。今、僕、無理してないな、嘘ついてないなっていう時が1番強いんだ、と初めて感じられ、それが僕の指針になったんです。
──うまくいかなかった経験があったからこそ、その指針にたどり着いたんですね。
結局、自分という人間がどんな武器を持ってるかは、自分ではわからなくて、いろいろ使ってみて、「槍下手だな」「弓はダメだ」という経験の後で、「俺、ハンマーが得意だった」みたいなことが見つかる。たぶん、そういう順番な気がする。だから、なかなか効率的に直線的にはいかない。世の中についてもそうで、水に石をポイッと投げて、水紋の形がどこまで広がるかで、あ、世の中ってこういう形をしてるんだってわかる。その石をいくら見てても何もわからない。投げて試行錯誤して初めてわかる。
──ちょっと時間がかかるけど、確かな方法かもしれません。
そうですね。だから、表現をする人たちは1人前と言われるまで、やはり10年ぐらいかかる気がします。デジタル社会は早く結果が出る社会ですから、今の時代においては長いと思われるんでしょうけど。しかし、10年やって確かなものを見つけたら、あとは、だいぶ楽ができるし、ずっといい結果が出やすくなると思っています。
──わかります。そこまで行くのが大変だけど、そこまでいくと見える風景が違ってきます。
「仁が出る」ということがすごく僕は重要だと思っています。「仁」は簡単に言うと個性みたいなこと。もともと歌舞伎の世界で用いられる言葉で、その人固有の雰囲気や「らしさ」を指します。落語の世界でも「仁が出る」は重要とされているそうで、その噺の面白さと、語る人の人となりが合ってないと、同じ話でも面白くならない。広告づくりも同じだと思っていて、その人らしさ、その人しか持ってない属性をうまく掛け合わせないと、企画の面白さがうまく出せない。だから、自分の「仁」が何なのか、を確かめるのが大事。つまり、自分に対して嘘をつかない、嘘をつくと苦しくなるということ。それは何回も、散々経験したからこそわかった。そして、自分が嘘をつかずにいられる環境をどうつくるかということも大事なことだと思っています。
──人は、一番自分のことをわかっているつもりだけど、なかなかわからない。わかるまで時間がかかるということですね。
そう、いい企画も自分で選べなかったりしますよね。やはり、人に見つけてもらったりして経験を積んでいく必要がある。階段式で何かが積み上がっていくこともあるけど、どちらかというと、最初から持ってるものをいかに「あ、ここに原石があるんだ!」と自分で見つけて、採掘するか。そういう意味で、時間が必要という感じがする。やっていく中で、嘘や無理を少しずつ潰していって、残っていた輝きを見つける。そんな感じが、意外と本質なのかもしれないなと思っています。
──とても意味深いですね、ものづくりに関わる方はもちろん、そうでない方にも参考になると思いました。ちょっと今の話と関係あるかもしれませんが、アイデアはどういう時に出てきますか、また秘訣はありますか。
アイデアの出し方…難しいですね。昔、僕が一番思いついてたのは、打ち合わせに向かう電車の中でした。何も思いついてなくて、ここで思いつかなかったらやばい!と危機を感じた時に出てくることがすごく多かったです。最近リモートワークになって、電車の中での危機感がないんです。思いつかないのは、僕のせいじゃなくて、社会のせいだと思ってたりします(笑)。そういう追い込まれた時に脳は頑張って働く。だから、脳が頑張れるような環境にしておきたいですね。最近は、脳の状態がいい朝に思いつくとことが多いので、睡眠も大事だと感じています。夜、思いつかなかったら、さっさと寝ちゃうとか、そこは割と意識するようになったかもしれないです。
──数学の有名な発見とかは、すごく脳をオンにしまくって、オフにした瞬間にポッと出てくると聞いたことがあります。
オフのことで言うと、寝てる間に脳が考えてくれるんじゃないかという気がちょっとします。寝ている間でも脳は情報処理しているという話もあります。
実は昔、通っていたCMの塾で1等賞を頂いたことがあるんですが、その時のコンテが、前日に夢で見たものだったんです。課題は長持ち乾電池のCMで、どんなシチュエーションで使われていたら面白いだろう、といろいろ考えていたけどいいのが思いつかなかった。仕方なく寝たら、夢を見ました。「時限爆弾を仕掛けた犯人が立てこもっている。爆弾を脅しにして警察といろいろ交渉をしている。そんな時、急に爆弾の電源が切れてしまい、脅しが効力を失って逮捕されてしまう。すぐ切れたのは爆弾に長持ち乾電池を使ってなかったから」そんな映像がハリウッド映画みたいな感じで流れたんです。え、何これ?と思ったけど、起きてそれをそのままコンテにしました。で、講評でいろいろ考えたねと褒められて、脳が寝てる間に勝手に考えてくれたのかなぁって思いました。
──すごいですね。それは、ちょっと便利な方法です(笑)。
またそういうことないかなと思っていつも寝てるんですけど、なかなか再現されません(笑)。でも、そういう企画が夢の中で出てくるのは、ずっと考え続けていて脳に負荷をかけていたからじゃないかと思います。それがオフになって整理されて出てくる。睡眠もすごく重要なんだろうなという気はしています。

はい、そういう時もあります。みんなでコンテを見て、会議室でいろいろしゃべる中で、ああだこうだと沸騰していると思いつく。僕の感じでは、3回ぐらい飛ぶと、いい企画になります。このアイデアからこっち行って、そのアイデアからこっち行って、また次のアイデアに飛んでいく。そうすると、ちょっと論理を越えたものになっていく。3回くらい飛べた時は、これはいいな!という、確信が持てる瞬間ですね。大喜利合戦みたいにみんなで話し合って、生み出していくことも好きです。
──それは日を変えてということですか。
いえ、その日の打ち合わせの中で、が多いです。みんなでアイデアを出し合うと、いろんな幅も出てきて、それをラリーしながら掛け算していく。その掛け算が、うまく2回か3回続けば、まず間違いない。もう他の人には単純には思いつかないものになっている。そうすると企画に強度が生まれる。やっぱり1人だとなかなかそこまではいかないです。みんながちょっと興奮状態になってアイデアを考える時間はとても好きです。
──なるほど。それは会議室からいいアイデアが生まれる栗田流のコツですね。
さらに言うと、そのやり方は、参加者の中にアイデアを考えてない人がいるとやりにくいことがあります。しゃべりやすい空気がちょっと失われる。みんなが考えてきていると話は弾みやすくなる。それもコツですね。できるだけ真剣に取り組んでいる人同士の波が共鳴する状態をいかにつくるかということ。だから、リモートワークはそこが難しいところだと思うんです。ちょっと耳だけ参加しときますみたいな人、割と出てきちゃうじゃないですか。
──いますね。傍観者A、Bみたいな(笑)。
いろんな事情があるのでしょうがないんですが、そういう状況で企画を出すのって公開発表になっちゃうんですよね。アイデアを見せるのって恥をかくのと同義なんで、その恥ずかしさを共有してない人たちの前では、発表者が体裁を整えようとしてしまって、どろっとした混ざり合いが起きない。そういう時には、アイデアを考えるメンバーだけに「もう一回少人数でやろう」と声をかけることもあります。ちっちゃいところで、ぎゅっ、とやるために。
一番大事なのは、アイデアのジャンプ台をどうつくるかということではないでしょうか。どんな環境でもアイデア自体は出ると思いますが、自分に無理のないいいアイデアを出すには、ポンとジャンプできる環境が必要です。いいダンサーも、ダンスフロアが狭いと踊れない。場所を広げて、跳びやすくしてあげる環境づくりが、いい結果につながる。最近、そっちに時間をかけた方がいいのかもしれないとも思います。
──それはまさにクリエイティブディレクションの仕事の1つですね。
そうですね。なかなか僕も全部うまくできているわけじゃないのですが、そう思います。僕の場合は、みんなでやる時だけでなく、1人でやる時もかなりあるし、コピーも書くしCMもつくるしで、クリエイティブづくりの型みたいなものも決まってない。でも、基本的には、ジャンプできそうな台ができたら、もうあんまり心配しないです。今、そういう環境づくりをする重要性は増している気がします。
──サントリーの飲食店キャンペーンは自分でコピーを書くスタイルでしたか。
書きました。さらにクリエーティブ・ディレクターの田中直基さんにコピーを見てもらいつつ、2人で話してつくりあげていった感じです。あのキャンペーンは、コピーうんぬんではなく、サントリーさんの飲食店を応援する気持ちとそれをコロナ禍の中にやるんだという意思と勇気、その設定がもう素晴らしかったということだと思います。広告の形をつくっていったのは、主従でいうと従ですね。そういう意味で、オリエンが、すでにアイデアだったといえます。
──「人生には、飲食店がいる。」はいいな!と思いました。そうだよなぁ、いろんな人生の節目節目に僕自身も飲食店があったなぁ。そう思って、飲食店を応援する気持ちに素直に入れました。共感コピーの強さですね。
僕は日頃、嘘をつかずにやることと、愛らしくやること、その2つが企画において大切だと思っていて、このキャンペーンも愛らしくできないかなとは思っていました。それで、当初は「サントリーが飲食店を応援する」というオリエンだったものを、飲食店を愛しているお客さんにも喜んでもらいたい、この輪に入ってもらいたいと考えて、あのコピーが出てきたような気がします。縦軸はぶらさずに横幅を広げた感じでしょうか。
それと、「人生」という言葉は、お酒や飲食を文化と捉えて、人間に興味や関心を持ち続けているサントリーさんだから使える言葉だな、背負える言葉だなとも感じていました。普通はなかなか使いづらい言葉ですよね。
──確かに、その企業だから使える言葉というのはあります。
リー・クロウという、海外の有名なクリエイティブディレクターが、「偉大なブランドは、自分のことではなく、自分が愛するものについて語る」という名言を残しています。後からそうかもと思ったところなんですが、今回も、飲食店への愛を語ったことでサントリーさんのブランド好意度にも貢献できたのかもしれません。一種の代弁なんですが、代弁ってすごい愛を生む構造かもしれないな。そんな発見も自分の中ではありました。
──代弁は愛を生む。
だから、推しとか、愛するものについて語ってる○○芸人さんとか、誰かについて心を入れて語っているのは意外と好ましく見えますよね。人間ってそういうものなんだなって思ったりします。

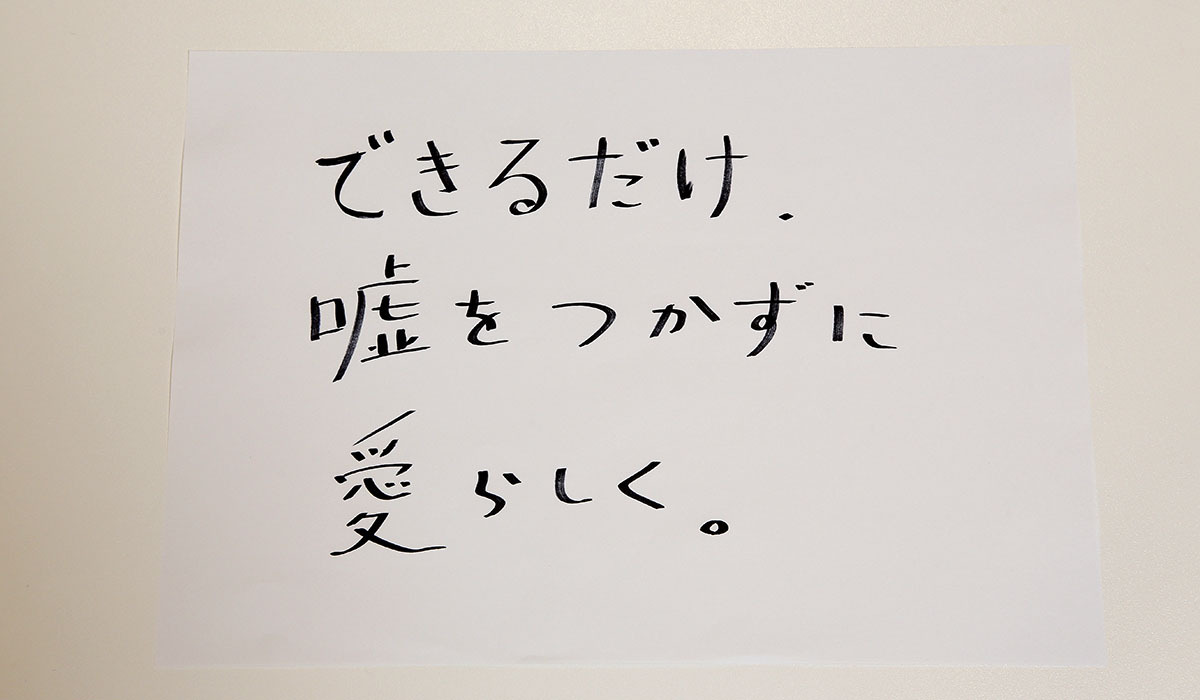
希望的であるということが、広告のいいところ
──クリエイターとして、広告の仕事の変化を、この10年ぐらいで感じていますか。また若い世代の広告離れが進んでいると言われています。どう思われているか、お聞きしたいです。
メディア環境が大きく変わって、僕も、デジタルどうする、SNSどうする、リアルどうする、とか、そんなふうに取り組むことが当たり前になっています。選択肢が増えたのはいいことです。もしかしたら20年ほど前までのマス広告に圧倒的な力があった時代はむしろ特殊な状態だったのかもしれない。テレビCMが強すぎた、しかし、今はフラットな状態になったということで、それはしょうがないのかなという気はします。ただ、その流れは止められないですが、僕はマス広告がすごく大事なものだとも言いたいですね。
東日本大震災の時に思ったんです。あの時、ACジャパンのCMばかりになったじゃないですか。それは仕方がないことだけど、普通のCMが流れてないことに落ち込んで暗くなった。あいつ、いつもはうるさいけどいなくなると寂しいなぁ、そんな感じ。その時に、CMって、いつも新発売だよとか、おいしくなったよとか、いろいろ言うなと思ってたけど、これ実はめちゃくちゃポジティブな情報ばかりだったんだと思った。この世界は確実に前進していますよ、また新しいものが生まれていますよ、そんなポジティブな波動のようなものを無意識に僕らは受け取ってたんじゃないか。だから、なくなるとこの世界が止まっちゃったみたいな気がしたんだなと。ポジティブというのは、ある種の希望です。すごく希望的であるっていうことが、広告のとてもいいところなんじゃないかなと思ったんです。
──広告はポジティブな感情を社会につくっている。さらに言えば、いい広告ほどそうかもしれません。
商品を売るとか、企業をイメージアップさせるとかの前に、広告は存在していること自体に意味があるのかもしれない。広告離れは進んでいるかもしれませんが、そういう観点でいうと、なくなっちゃうとかなり寂しいだろうという気がする。社会的な視点で役割もあるのではと。僕は広告が好きなので、できるだけ担う人を増やしたくて、今、若い人向けに研修とかをはじめたりもしてるんです。
デジタルの登場で、広告界はちょっと偏りがちだったかもと思っています。ターゲティング広告とか、獲得広告の方向にだいぶ意識がいっちゃったところがあって、広告の社会的使命や価値みたいなことは、あまり考えなくなりましたよね。数字を上げることが命題になりがちで。実は広告にはいろんな役割があるのに、一部がものすごく肥大化しちゃったような感じもあって。
──広告が一面的な機能のものになっている感じはすごくします。
僕ら広告をつくる側にも責任があって、広告にそういう価値があるものだとあまり言ってこなかった。アピールはせず黒子に徹して一心不乱につくるのがいいんだ、そんな職人みたいな気分もありました。広告づくりが面白いと発信してる人もとても少ない。でもそれってマスメディア全盛時の、言わなくても人が集まっていた時代の習性かもしれなくて。それだとSNSで初めて広告業界に触れるような世代には、なかなか届かないかもしれないなと。これからは、もうちょっとアピールして広告に魅かれる人を増やすのも大切な仕事かもと思っているんです。
──2つの問いが忘れがたく残った。1つは、自分らしさを見つけることこそ、クリエイティブ(創造性)の本質ではないか、という問い。無理せず、嘘をつかない自分に至り着く。それは一朝一夕ではできないとも話していた。もう1つは、広告と社会の関係を捉え直すべきではないかという問い。栗田さんは、広告はポジティブな波動みたいなものだと言った。広告をつくる側がもっとアピールしていき、広告づくりの面白さを伝えていく。そこに新しい意見が加えられて、きっと新しい広告の価値が世の中に提示されていくのだろうと思った。