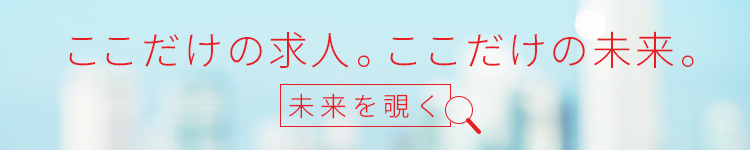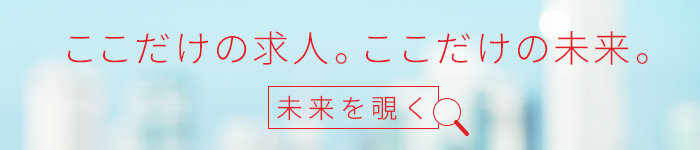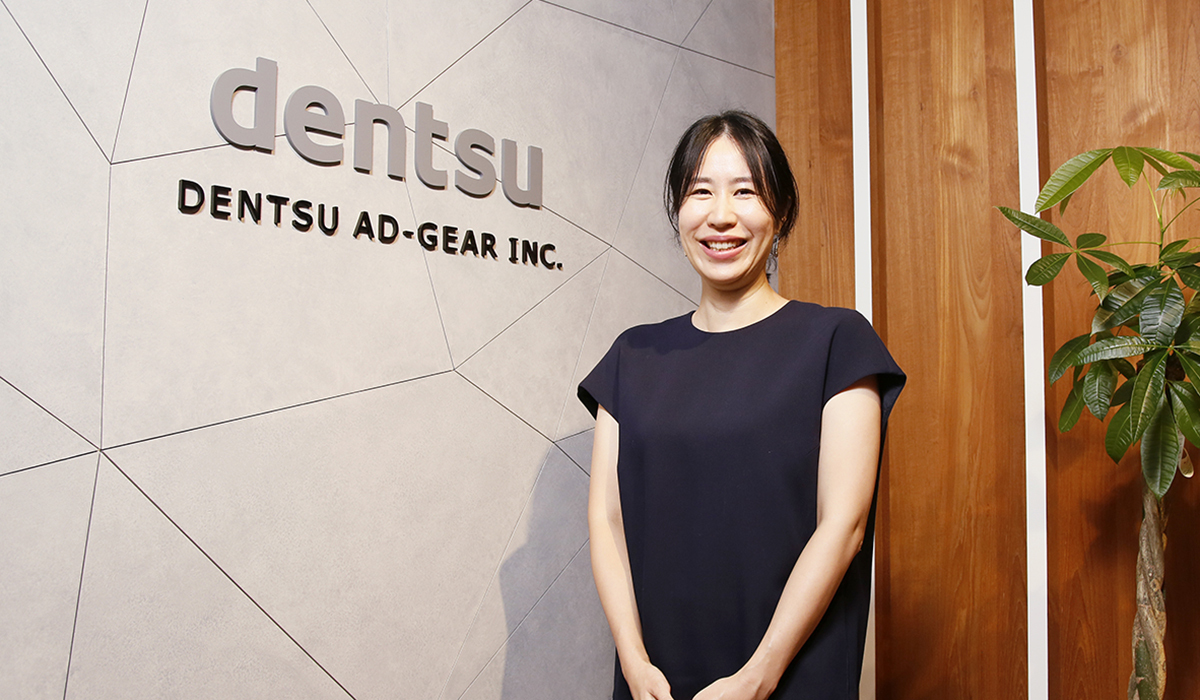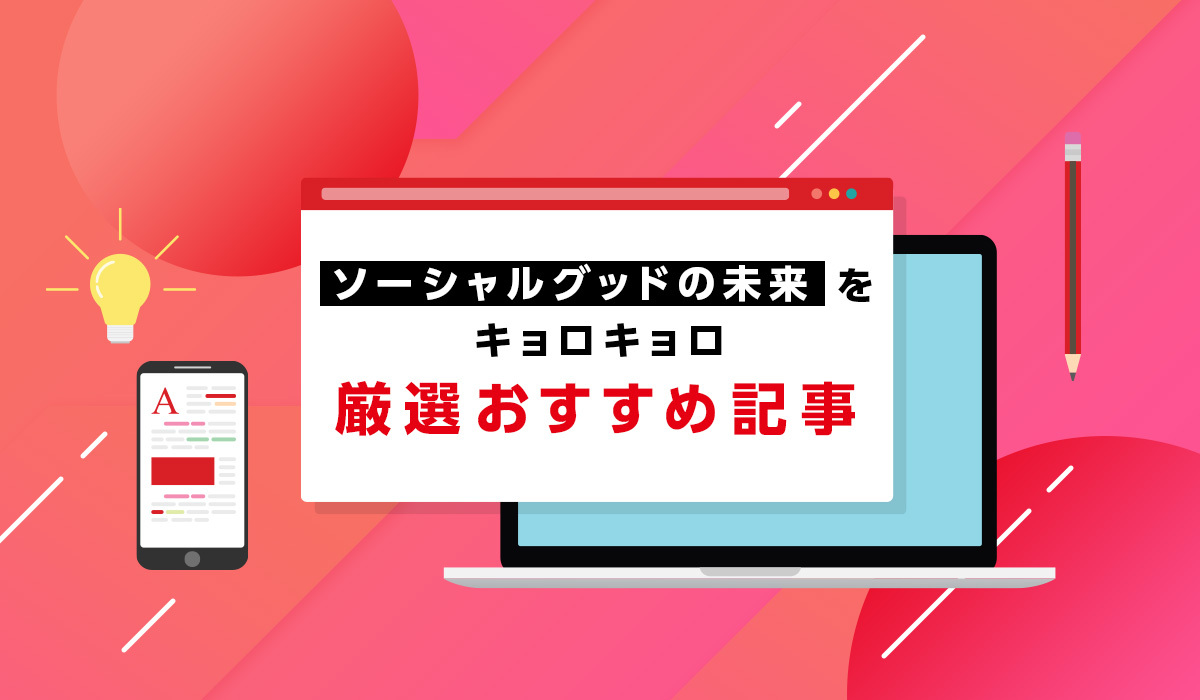答えの出ないモヤモヤが私のキャリアをつくる 多様性を発想の源に変えるインクルーシブデザインの考え方 一般社団法人シブヤフォント アートディレクター ライラ・カセムさん

シブヤフォントでアートディレクターを務める、ライラ・カセムさん。障がい者支援事業所の利用者・支援員と共にインクルーシブデザインでの制作活動を続け、取り組みの輪を広げています。常にマイノリティの方に視線を向け働きかけ続けるライラさんは、どのようにしてインクルーシブデザインと出会ったのでしょうか? 後編ではデザイナーを志した経緯をはじめ、ライラさんの今までをお伺いします。
この記事は前後編です:前編はこちら
「街に出かけてきた障がいのある人とない人が、真ん中で出会える場所になりたい」
インクルーシブデザインに出会うまでの「モヤモヤ」
──ライラさんはいつごろデザイナーを志すようになったのでしょうか?私の母はイギリス出身で、日本で働いていました。インクルーシブデザインのパイオニアのひとりと言われている、元新聞記者兼美術記者です。日本では外国籍であり、脳性麻痺のある私を娘に持つ、少数者である母の“世の中とクリエイティブにバトる”姿をいつも見ていたんです。
母は、自ら障がいのある人のための美術鑑賞プログラム「心で見る美術館」を主催したり、障がいとアートの領域で活動する団体「エイブル・アート・ジャパン」や「たんぽぽの家」の活動に参加していて。私はそんな母の姿を見ていたり、週末には手伝いに行ったりして、自然と障がい福祉の現場とつながりがありました。
クリエイティブの力で物事はもっといい方向に導けるという英才教育を、自分でも気付かないうちに受けていたのかもしれません。
私自身は日本で育ち、中学3年生の時にイギリスへ移住。イギリスの高校でアートとプロダクトデザインを専攻しました。そこで昔からコラージュや写真、家族に贈る誕生日カードとか、平面のデザインが好きなことに気付き、エジンバラ芸術大学でグラフィックデザインを専攻しました。
エジンバラ芸術大学は、14人だけの小規模クラス。グループで課題を制作したり、単独の制作でもお互いに相談し合ったりと、デザイン事務所のスタジオカルチャーを学ぶことができました。制作物だけでなく、制作のためのスケッチブックなどのリサーチも評価されるのですが、私はその点数が高かったんです。リサーチが好きな私には、すごく合っていました。
また、デザイン科の先生がガーナ系のスコットランド人で、歩行困難で杖をついている方だったんです。私も人種的マイノリティの環境で育ち、足に脳性麻痺による障がいがあります。自分と似た境遇の方に出会うのは初めてでした。
親は子どものころから何でも挑戦させてくれたので、自分が障がい者だということを意識することはあまりありませんでした。ただ、大人になりつつある時期に、自分ひとりで世の中の目線にどう立ち向かえばいいのか、その先生とフランクに話し合えたのはいい経験になりました。
──大学卒業後は、そのままグラフィックデザイナーの道へ進んだのでしょうか?
卒業後はデザイン事務所で、インターンシップやアルバイトとしてアシスタント業務をしました。ただ、50社近く応募して、選考を通過したのは数カ所。働き出してからも、車椅子で出勤するだけですごく気を使われてしまい……。こんな苦労をするのは自分の実力不足なのか、障がいがあるからなのかわからず、すごくモヤモヤを抱えていました。加えて、女性ということもあり、グラフィックデザイナーとして独り立ちするには、人の2倍も3倍も努力しないといけないのではと思い、心身共に疲れてしまっていました。
さらに、デザイン作業は楽しいですが、商品が世の中に出れば終わり。また次の商品、というサイクルにも疑問がありました。私は、リサーチやクライアントへのヒアリングをして、何が一番欲しいのかを考え、それをビジュアライズしたアイデアを出すという、コミュニケーションの段階が一番好きだったんです。そうしたコミュニケーションのデザイン化にグラフィックデザインの力を活かしたい、また、どうしてその力が社会貢献に活用されていないんだろうと、「モヤモヤ」が「問い」へと育っていったんです。

大学卒業後、デザイン事務所での仕事に悩んでいたころ、母にインクルーシブデザインのワークショップに誘われたことがきっかけです。目の見えない人や手のない人と絆創膏をつくったり、ボスニアの耳に障がいのある作業員たちの印刷工房で活動をしたりしました。
ボスニアの活動で気になったのが、素晴らしいスキルを持った作業員たちがみんな、自信がないこと。大学でデザインを学んだ私を見て、「私も美大に行きたかったけど、自分にはその資格がないと思った」と言う人までいて。そこでハッとしたんです。社会が障がいをどう捉えるかも大事だけど、障がいのある人自身が自分をどう捉えるかもすごく大事。本人が育った環境や経験で自分の可能性を狭めたままだと、障がいのある人の社会進出は成り立たないんだって思ったんです。
実際に障がい者支援事業所(以降、事業所)での活動を見ていると、体に障がいのある人や精神障がいのある人が、自由で面白い絵を描いていて、「これってめちゃくちゃいいデザイン素材じゃん! 世の中にこれをもっと出したい!」と、インクルーシブデザインの世界に没頭するようになりました。
「あなたのやりたいことは大きすぎる」悩みながらもとにかく活動を続けた日々
──そこから実際にインクルーシブデザインの活動をしていくために、どうされましたか?もう一度大学に戻ろうと考えました。デザイン事務所での仕事を続けるのはつらくて。消去法でしたが、博士課程まで修了すれば、よそで就職先を見つけなくても、大学で働けるだろうと思ったんです。
個人で活動し苦労してきた母に「どこかに所属した方が、活動するにも信頼を得やすいよ」とのアドバイスも受けて、日本に戻るタイミングで、東京藝術大学大学院のデザイン科に入学しました。日本で一番有名な東京藝大の学生なら、スムーズに活動できるだろうと思って。
修士課程ではグラフィックデザイン制作を学び直し、博士過程では知的障がいのある方の事業所でのグラフィックデザインの活用法を研究していました。「障害者総合支援法」などで障がい者の社会参加や賃金向上が叫ばれるようになったものの、なかなか進まない日本の現状を見て、アート活動での新しい収入のつくり方や、社会とのつながり方などを調べていたんです。
日本でも「エイブル・アート・ジャパン」や「ヘラルボニー」など障がいがある人のアート作品を世の中につなげる団体はありますが、扱われている作家さんは全体のほんの一握り。日本には約3万の事業所(1万5000以上の就労継続支援B型事業所と1万以上の生活介護事業所)がありますが、ほとんどがアート活動とあまり関わりがありません。また、最初は事業所に協力をお願いしても「あなたのやりたいことは大きすぎる」と門前払いをされたことも。
そんな中で、綾瀬ひまわり園が協力してくれることになり、障がいがある人のアートの商品化の活動を始めました。綾瀬ひまわり園では、アート活動に参加はするものの、隅で何もせず体を揺らしている利用者の方が気になりました。彼も活動に入れれば面白いものができるのでは、と事業所の支援員にも協力してもらい、彼の性格、好きな動きやテクスチャ―を教えてもらうことから始まり、利用者のみんながその人らしく参加できる方法を考えながら、2年間取り組みました。
活動の結果、利用者の気分がよくなったり、自分を傷つけてしまう行動が落ち着いたりと、福祉的な効果も多く見られ、それらを博士論文にまとめました。修了後は東京大学の特任研究員として、事業所での造形活動の支援や、福祉支援員への支援方法や商品開発を教えるワークショップを続けていました。
──その後、シブヤフォントへ参画するようになった経緯を教えてください。
そのうちに、論文などの研究発表は教育業界の人には届くけど、福祉の現場には届かないと気付きました。以来、「アンタントプロジェクト」と呼んで、インクルーシブデザインをテーマにしたアワードへの参加や展示など、なんとか活動の場を広げようとしていました。
2016年に、障がいのある人との協同による仕事や働き方を表彰するアワード「Good Job! Award」に入賞し、同じく入賞していた、代表の磯村さんにシブヤフォントに誘われました。「やりたい!」と即答しましたね。今でもシブヤフォントの活動は、私の天職だと思っています。

教育や研究にも身を置くのは自分の活動を俯瞰できるから
──ライラさんは教育や研究の活動もされていますよね。デザイン制作だけでなく、活動の場を多く持つのはなぜですか?元々は教育者や研究者になる気はなかったんです。子どものころから「なんで?」とよく口にしていたせいか、大学院でも「博士課程を目指すの?」とよく聞かれましたけど。
ただ、いろいろな大学や学校から特別講師を依頼されるようになり、シブヤフォントの活動を伝えていくうち、デザイン業界や自分たちの活動をうまく俯瞰できることに気付いたんです。学生のアイデアが刺激になることもあり、実践だけでなく教育も大切だと日々実感しています。
また、企業プロジェクトでは成功に固執してしまいますが、大学では学生と気軽にプロジェクトを試せます。そして、大学でのプロジェクトで気付いたことを、またシブヤフォントに活かすことができる。去年、初めて奈良女子大学の工学部で研究室も持って、共創デザインを教えています。まさにシブヤフォントのような活動ができないかと、奈良教育大学との共同授業を立ち上げていて、事業所とコラボした授業などを今年の秋から実施する予定です。
私の授業を通して、インクルーシブデザインに興味を持つ学生が増えてくれればうれしいです。
答えは出さなくてもいいから、考えつづけることが大事
──ライラさん個人での制作活動は今行っていますか?クライアントワークはリサーチやコミュニケーションにそこまで時間をかけられないので、もうやりたくない(笑)。基本は友達からの依頼のみにしていて、最近だと「幻聴妄想かるた」という、精神障がいのある方の幻聴や幻覚を描いたカードゲームのデザインを頼まれて、シブヤフォントでの制作手法も取り入れながら、制作をしました。
──今後、ライラさんがやりたいことはありますか?
シブヤフォントでは、ご当地フォントプロジェクトの活動をしている地方16カ所にも、このシブヤフォントラボのようなラボをつくりたいですね。
また、アジアやアフリカなど、海外の事業所とのコラボをすごくやりたくて。私やシブヤフォントの参加事業所の職員が一緒にアドバイザーと訪れ、学んできたことを教え合えるような活動がしたいです。障がいのある方だけでなく、活躍の場が少ないと感じている女性にも向けて、インクルーシブデザインの活動を通して「世界は狭くないよ」と伝えたいです。
あとは、自分の人生をまとめた本を書いてみたいです。今までは人に勧められても全く興味はなかったんですけど、40歳手前でキャリアを積んできた今だからこそ、落ち着いて振り返ることで、今後やりたいことが明らかになりそうだなって。
──最後に、若手デザイナー、インクルーシブデザインに興味を持つデザイナーへのアドバイスをお願いします。
デザインだけに真面目になりすぎず、いろいろなことを楽しむのが大事です。私は音楽のライブが大好きで、月1回は必ず行きます。刺激を受けるものをたくさん用意することで、結局仕事につながることもあるんですよね。
あとは、学業以外の自分の専門と異なる活動も、積極的にやることが大事だと思います。私も学生時代は、「TEDx」というトークイベントのボランティアをやっていました。学生時代から、どうして知的障がいのある人は就職ができないんだろう、とたくさんの「モヤモヤ」という名の「問い」を増やしながら、追求しながら歩んできたことで、現在の私のキャリアもあるのだと思います。
自分が疑問に思ったことを、答えは探さなくてもいいから、ずっと考え続けていく。そのうちに仕事やキャリアのヒントになるような、面白い発見があると思います。

シブヤフォントラボにて