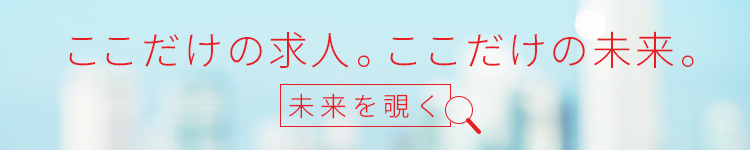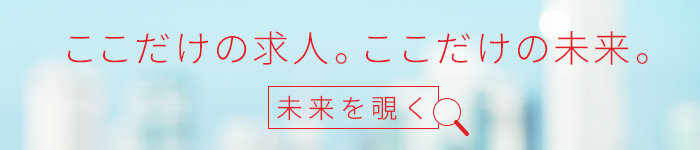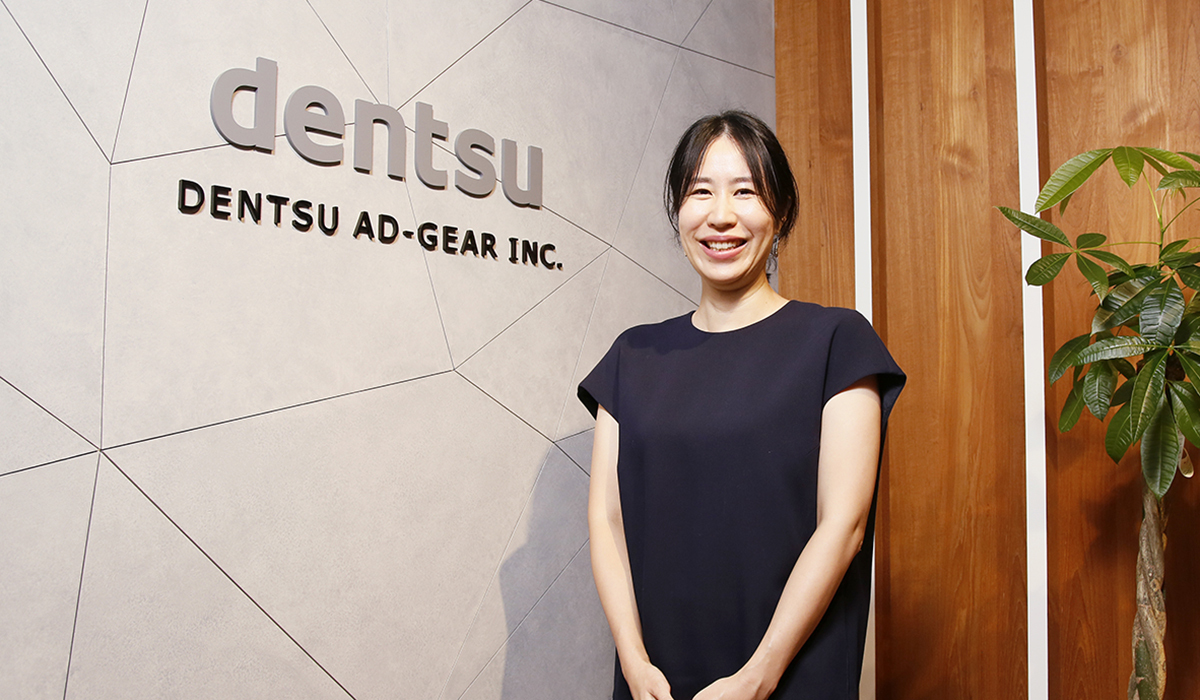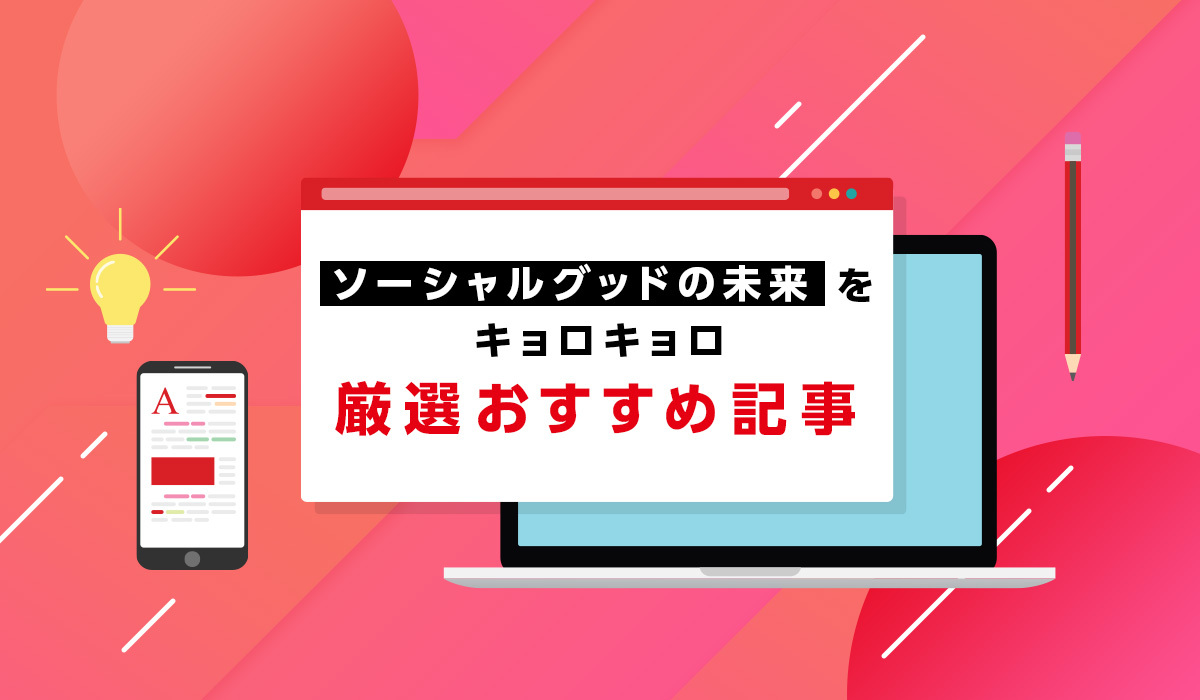街に出かけてきた障がいのある人とない人が、真ん中で出会える場所になりたい 一般社団法人シブヤフォント アートディレクター ライラ・カセムさん

皆さんは「インクルーシブデザイン」という制作方法を知っていますか? 従来のターゲットユーザーから排除されてきた障がい者、外国人、性的少数者、高齢者などのマイノリティの人々がデザインプロセスに参加し、その声を聞きながら、一人ひとりの個性に合わせたデザインを共創する手法のことです。この手法で障がいのある人とデザインの共創を行い、活躍と交流の場を生みだしてきたシブヤフォントは、この春、多様性との新たな出会いの場として「シブヤフォントラボ」を原宿に立ち上げました。立ち上げ人のひとりで、シブヤフォントでアートディレクターを務めるライラ・カセムさんにお話を伺ったので、前後編でご紹介します。
「障がい」を特別視しないでほしい
──まずは、シブヤフォントラボのオープン、おめでとうございます! こちらはどのような施設なのでしょうか?
シブヤフォントラボは、私たち「シブヤフォント」が7年間活動してきたノウハウを活かして、障がいのある人や障がい者支援事業所(以降、事業所)が新たな交流を生みだすための“実験的出会いの場”です。「障がい」という固定観念を取り除き、多様な個性や解釈を受け入れてもらうことで、障がいへの理解や障がいのある人の自信につながればと思っています。街に出かけてきた、障がいのある人とない人、さまざまな人生背景を持つ人が、真ん中で出会えるような場所になりたいんです。

最初は、2016年に「渋谷みやげ開発プロジェクト」として始まりました。渋谷区の障がい福祉課から、現在のシブヤフォントの共同代表・磯村さんが「渋谷の新しいお土産をつくりたい」と依頼を受けたんです。区内の事業所の自主製品を新しいお土産にすることで、渋谷区のシビックプライドにもなり、事業所の工賃向上にもつなげることを目指しました。
実際にどんなお土産にするかを考えるときには、磯村さんが当時講師を務めていた桑沢デザイン研究所の学生と共に数カ所の事業所を訪ねました。プロのデザイナーよりも、学生の方が新鮮なアイデアが出せるのではないかと考えたそうです。そこで、事業所の障がいのある利用者(以降、利用者)が書く文字が面白いという学生の意見から、フォント化していろいろなグッズに利用しよう、というアイデアが生まれたんです。
私が東京藝術大学の大学院を修了して1年経ったころ、「学生のアイデア出しの補助や、デザインパートナー(障がい者など、インクルーシブデザインに参加する少数者のこと)の制作活動のディレクションをしてほしい」と相談を受け、事業所をデザイナーをつなぐ制作のディレクターとして参加することになりました。
活動の初期は、磯村さんの会社が渋谷区から業務委託を受けていたのですが、2021年には事業所と連携した新たな法人を設立しました。現在は主にライセンス事業として展開していて、フォント73種、パターン515種を企業や団体に提供しています。活動メンバーは、事業所の利用者と支援員、デザインを学ぶ学生、行政、私のようなクリエイターです。毎年、フォントとパターン合わせて50~70種をラインナップに加えています。
──現在ではフォントよりパターンの方が多く制作されているんですね。それでも「シブヤフォント」という名前で活動を続けられているのはなぜなのでしょうか?
フォント、つまり文字って世界共通で誰でも使うものだから、シブヤフォントを知らない人も名前で「ん?」と気に留めてくれるかなと思って、あえてシブヤグラフィックでなくシブヤフォントのままにしています。
──利用例を教えてください。
渋谷区との連携事業なので、やはり渋谷区の利用は多いですね。職員の名刺や区が発行する刊行物、そして渋谷区役所新庁舎内は、サインやインテリアなど建物じゅうにシブヤフォントのデザインが使用されています。
一般企業では、ユニクロやしまむら、JUN、ビームスなどのアパレルブランドが多いです。特に、しまむらグループの子ども服は人気で、数千万円以上売り上げたそうです。また、Googleにはフォント3点を買い取っていただき、Google Fontsという世界的なフォントプラットフォームに登録されました。

奥に見えるのは、しまむらグループのベビー・子供用品ブランド「バースデイ」とコラボした子ども服
デザインの力を活用できるのは、商業デザインだけじゃない
──出来上がった商品を見た、デザインパートナーの方々の反応はいかがでしたか?自分が制作したものが実際に店頭で販売されているのは、やっぱりすごくうれしいみたいです。本人だけでなく、親御さんにとっても「うちの子がこんなものつくったの」と、大きな喜びや自信、本人理解(障がいなどの特性を含む、個人の性質を知ること)につながっているようです。
──シブヤフォントでは、ご当地フォントプロジェクトなどの地域活性化事業も行われているのだとか。
はい。渋谷以外の地域にも活動を広げたいと思って。2022年にスタートした「ご当地フォントプロジェクト」では、各地のデザイナーと事業所が組んだチームの制作活動を、私たちがアドバイザーとしてサポートしています。現在、全国16カ所のデータを、シブヤフォントで運営する「ご当地フォント」公式Webサイトに登録しています。
また、イベントプロジェクト「アートコネクト」は、シブヤフォントに参加する事業所が主催する、展示やモノづくりワークショップを通じて区内で暮らし、働く方と交流するイベントです。イベントを始めたきっかけは、シブヤフォントに参加する事業所の方から、「有名な企業や団体に使われるのはとってもうれしいんだけど、さらに地元の方々にも私たちの存在を知ってほしい」と言われたことでした。現在もこのイベントは、事業所のメンバーが事業所から街へ出る、そして人と交流する大事な機会になっています。
他には、コンサルティングの依頼も多くあります。各地・各社で行われるインクルーシブデザインのワークショップやプロジェクトにアドバイザーとして参加することも増えています。
──ライラさんは現在シブヤフォントでは、アートディレクターを務められていますね。普段は主にどのような業務を担当していますか?
パターンとフォントのアートディレクションや、プロジェクトの拡大に努めています。また最近では、パターンを利用したい企業と、希望のパターンを描けるデザインパートナーのマッチングも行うようになりました。
──シブヤフォントの活動は、2022年に桑沢デザイン研究所で授業化もされていますね。学校ではなかなか学べない内容だと思いますが、実際に参加する学生たちにはどういう話をしているんでしょうか?
実は、学生にはデザインパートナーの具体的な障がいについては話さないんです。デザイナーを目指す彼らと同じクリエイターとして、デザインパートナーにも接してほしいからです。人によって描く素材は力強かったり、繊細だったりといろいろです。彼ら彼女らのつくり出す素材をよく見て、どうしたらその人の良さをもっと引き出し拡張できるのか、自分の意見をきちんと言う。そうやって、コミュニケーションを取りながら一緒につくり上げる経験をしてほしいですし、実際学生たちもそれを楽しんでいるみたいです。
学生の中には、シブヤフォントでの活動がきっかけで、フォント制作に目覚めた子もいて。それはうれしかったですね。また、海外、特に中国の学生が多いのですが、自分たちの国ではまずこういった活動がないと驚いていました。彼らにとっては、デザインを通して、言語を超えたコミュニケーションができるので心地いいみたいです。
学生には、将来は事業所と関わらなくてもいいけど、こういう世界があると知っておいてほしいんです。商業だけでなく、社会貢献にもデザインの力は活用できると知っておくだけで、世界の視野は広がると今後も教えていけたらなと思います。
多様性に出会える場所をつくりたい
──さまざまなメンバーと7年間続けてこられたライラさんたちの活動の成果が、今のシブヤフォントをつくっているんですね。4月にオープンしたシブヤフォントラボは、どのような場所にしたいですか?ギャラリーとしての展示、イベントスペースとしてトークイベントやデザインのワークショップを行ったり、そして事業所のメンバーが日々の手仕事やアートワークを実演し、その製品の販売をしたりもしています。ラボを訪れたいろいろな方が、シブヤフォントの活動を知り、シブヤフォントのメンバーと一緒に手を動かしながら、交流ができる場所にしたいと思っています。
オープン前、メンバーには実現したいプロジェクトの妄想を書いた未来新聞を書いてもらいました。そのアイデアの中から、5月5日には原宿でファッションショーを行いました。ラボを訪れた人だけが聞ける、公開ラジオなどもやってみたいですね。

この記事は前後編です:後編はこちら
「答えの出ないモヤモヤが私のキャリアをつくる 多様性を発想の源に変えるインクルーシブデザインの考え方」