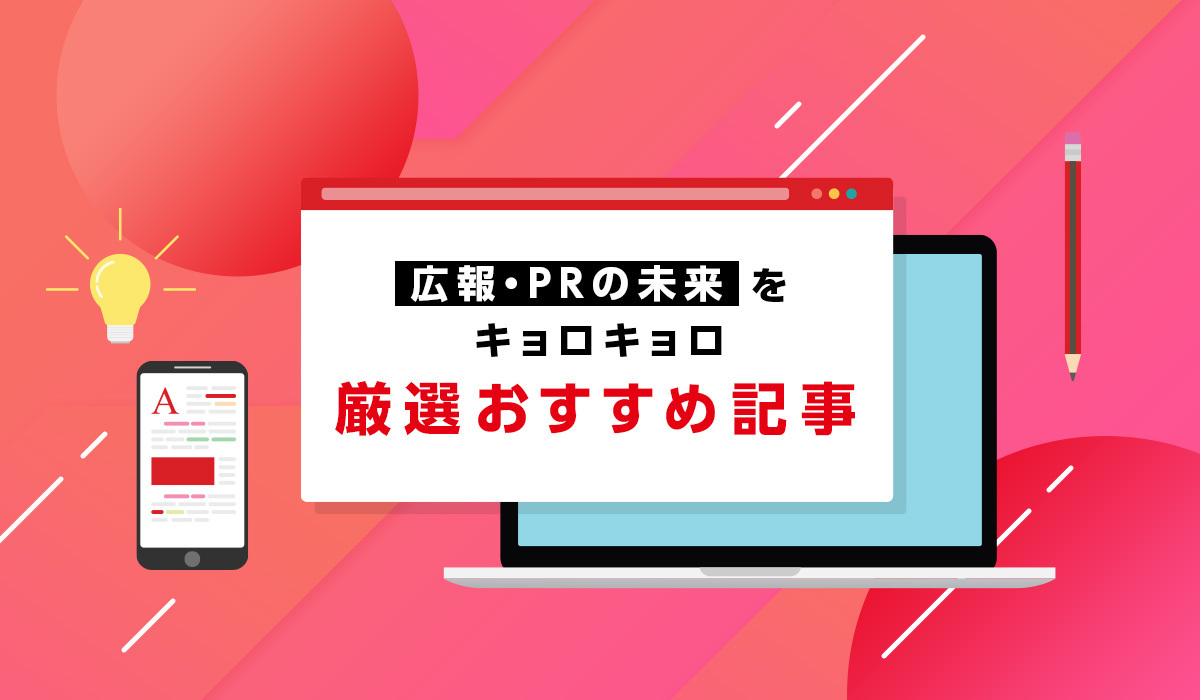アートとビジネスを融合させてヒットを生み出す。八谷和彦の仕事術 #クリエイターの生存戦略 〈前編〉 メディアアーティスト/東京芸術大学 准教授 八谷和彦さん

Yahoo! JAPANのデザイナーを退職し、現在はフリーランスのメディアアーティストとして活動する市原えつこさんが、さまざまな分野のクリエイターや専門家に話を伺い、クリエイターの生存戦略のヒントとノウハウを探す本連載。第一線で活躍するクリエイターがどのようにキャリア構築をしてきたのか、今後はどのように歩みを進めようとしているのか、対談形式でインタビューしていきます。
第7回は、メディアアーティストの第一人者である八谷和彦(はちやかずひこ)さん。愛玩メールソフト「PostPet」の生みの親であり、近年は『風の谷のナウシカ』の劇中に出てくる架空の航空機「メーヴェ」をオマージュした飛行装置の開発プロジェクト「OpenSky」で衆目を集めます。そんな八谷さんですが、市原さんがデビューする前からアドバイスをしていたようで、市原さん曰く「八谷さんは恩師」という間柄。普段から金言を賜っているようですが、今回は特別にadvanced by massmedian独占インタビューをさせていただきました(マスメディアン編集部)。
第7回は、メディアアーティストの第一人者である八谷和彦(はちやかずひこ)さん。愛玩メールソフト「PostPet」の生みの親であり、近年は『風の谷のナウシカ』の劇中に出てくる架空の航空機「メーヴェ」をオマージュした飛行装置の開発プロジェクト「OpenSky」で衆目を集めます。そんな八谷さんですが、市原さんがデビューする前からアドバイスをしていたようで、市原さん曰く「八谷さんは恩師」という間柄。普段から金言を賜っているようですが、今回は特別にadvanced by massmedian独占インタビューをさせていただきました(マスメディアン編集部)。
「会社員経験」はいま振り返ると必要だった
市原:私の心の中には「八谷和彦名言集」があるくらい、八谷さんの言葉に励まされてきました。私が学生の時に進路で悩んでいたら、「作家にはいつでもなれるけど、ビジネスパーソンになるのは人生の途中からだと難しい。だから、まずは社会に出てみた方がいいよ。結局アーティストになっても企業とコラボレーションする時に役立つから」 と八谷さんはおっしゃっていて、その言葉が今でも心に残っています。八谷:いまでも僕は「一度就職できるのだったらしておいたほうがいいよ」と学生には言います。社会人経験はあったほうがいろいろと便利で、見積書や請求書の書き方は、学校ではなかなか教えられないので。見積もりで本当に難しいのは、値段をいくらにするかという価格設定や、もらった見積もりが適正かどうかを判断することじゃないですか。会社だと日常的に相見積もりを取ったりするから、一度会社に入ってしまえば日本の会社の暗黙のビジネスマナーがわかる。けれども、学生生活だけだとわからない。例えば、僕はミスミ(FA・金型部品、工具・消耗品などの通販サイト)を愛用してますが、法人じゃないと使えないため、個人制作の人はミスミを知らない人も多い。法人のアドバンテージに触れる機会があるのも会社勤めのメリットだと思います。
市原:その話を伺った時は、自分がアーティストになるとは一切思っていなかったのですが、いま振り返るとありがたい助言だったなと……。実際に会社員経験の有無によって、企業への折衝やトラブルシューティングが全然違うなと思いました。ある程度相手の内情がわかるので対処しやすいですよね。
八谷:僕自身も市原さんと一緒で、大学生の頃はアーティストになるとはこれっぽっちも思っていなかったです。大学は九州芸術工科大学で、僕が勉強していたのはグラフィックデザイン。卒業後は上京して、CI(コーポレート・アイデンティティ)をコンサルティングする会社に就職しました。ちょうどMacが出たばかりで、デザインの現場も写植・版下作業からDTPへどんどん移り変わる時代でした。
市原:アナログからデジタルへの転換期に立ち会われたのですね。
八谷:あと当時、ほとんどの現代美術は美術館で展示されていませんでした。1989年に僕は上京したのですが、その6年後の1995年に東京都現代美術館が開館しました。このような状況だったので、本当に一部でしか現代美術は展示されておらず、レントゲン藝術研究所などに足しげく通って、趣味としてサブカル的に現代美術を楽しんでいました。

八谷:今は東京藝術大学の同僚でもある小沢剛さんをはじめとした展示作家たちの年齢が近くて、同世代の問題意識や創作の動機に共感できたんです。それで彼らにインタビューしたり交流したりしているうちに、「八谷さんもなにかやらないの?」と誘われて、始めました。
市原:アーティストとの交流がきっかけだったのですね。最初は会社員とアーティストの二足のわらじで活動し、いつぐらいにアーティスト1本になったのでしょうか?
八谷:会社には7年くらい在籍していました。91年に作品をつくりはじめて95年に会社をやめたので、二足のわらじ期間はだいたい4~5年。27歳だった93年に「視聴覚交換マシン(編集部注、お互いの見ているものを交換する装置。 他人の視点でしかものが見えなくなってしまい、 相手の立場に強制的に立たされてしまう。 アイデンティティの境界を曖昧にすることを目的として制作された作品)」をつくって、レントゲン藝術研究所で展覧会を開きました。「今が売り時だ」みたいな気持ちで、賞にも意図的に応募しました。自分自身を売り込みたい気持ちはあまりないのですが、作品を売り込みたい気持ちは今も昔も変わらずあります。プロデューサー気質があるというか、自分はプロデューサーだから黒子となって、面白い作品ができたから、「この新人アイドルどうですか?」みたいな感じで売り込んでいました。

視聴覚交換マシン photo:Kurokawa Mikio
八谷:二足のわらじだったにも関わらず、視聴覚交換マシンなど自分にとってターニングポイントになる作品を立て続けにつくっていました。むしろ今のほうが少ないかもしれない。
市原:私も会社員時代の方が多作でした。不思議ですね。
八谷:それは、仕事がつまらなかったからじゃないですかね(笑)。仕事はもちろん尊いのですが、あくまでクライアントのためにやるものなので。多少なりともストレスはありますよね。
アーティストは自分がクライアント
市原:それもすごく伺いたかったことで。今考えると失礼極まりなくて当時の自分をぶん殴りたいのですが、私は会社員のころ八谷さんに「仕事にやりがいを見出だせない」と人生相談に乗っていただいたことがありました。私からすると八谷さんは超楽しそうに仕事をしているように見えていたのですが、「仕事はつまらなくて当たり前。人から頼まれたものだから。作品制作が面白いのは、自分がクライアントだからだよ」と八谷さんがおっしゃっていて、すごくいい言葉だなと印象に残っています。この 「アーティストは自分がクライアント説」について詳しく伺いたいです。八谷:僕が会社員時代にいろいろ作品をつくっていたのも、やっぱり「仕事がつまんない」という動機も多分にあったからだと思うんです。「これをこうすればもっと面白いのにな」という抑圧から創作意欲が生まれた気がする。クライアントワークはあくまで顧客の価値を最大化するためなので、滅私奉公な部分はある。独立してからのアーティストとしてのクライアントワークは楽しいですね。自分の意見をある程度通せるから。
市原:私も独立してわかったのですが、クライアントワークの中でもかなりグラデーションがないですか? 例えば、アーティストとして自分の作品に対するタイアップ案件と、完全に名前を出さずに下請け的につくる案件は結構違うように感じます。
八谷:そうですね、ソネットエンタテインメントと一緒に開発した電子メールソフト「PostPet」は、もともと自分の作品として始めたんです。これはものすごく楽しかった。クライアントワークとはいえ、ソネットの人とどうやったら面白くなるかを話しながら開発していたし、大きい会社と一緒の仕事だからレバレッジが効く。テレビCMを打ったり、着ぐるみを何体もつくったりするなんて、個人の作家だと到底できないから。
その時には初回の打ち合わせで、単にソネットの下請けとして仕事するのではなく「自分の名前も出させてください、顔が見える開発をしましょう」という交渉をしました。開発者が表に出ることは当時まだ一般的ではなかったのですが、ゲームの世界はそういう流れができつつあった。「誰がこのゲームをつくったのか」をみんな知りたいから、ファミ通などで特集されて、開発者のファンができるカルチャーがあった。
そのほかにPostPetプロジェクトの功績として、ゲーム・エンタメ領域にβ版という概念を取り入れたことがあります。サービス自体はメールソフトなので、メール未送信・未受信はありえないから検証作業は絶対に必要。でも外部の業者に任せると費用がかさむから、β版にしてリリースしたんです。僕は『スーパーマリオシリーズ』の生みの親であり、任天堂社長の宮本茂さんの「アイデアとは一石三鳥を狙うもの」という言葉が好きで。コストダウンさせつつ、ユーザーの認知も高めつつ、コアファンも増やす、という一石三鳥を狙いました。

八谷:そうですね、地道な事務作業に対して、アーティストは「それは自分の仕事じゃない」「そんなのできない」と考えてしまいそうですが、僕は「他の人にもできるなら、自分にもできるはずだ」と思って取り組んでいます。特にOpenSkyは航空法を調べて国土交通省などに許可を取るなど地味な根回しがめちゃくちゃ多い。僕の場合はそういう事務処理から、実機の制作、そして飛行機のテストパイロットまですべててやってるから大変ですね。
ハプニングこそが、利便性を超えた差別化ポイントになる
市原:八谷さんは、PostPetという大型プロジェクトに着手するまではずっと一点物のデバイスアート作品を制作していたんですよね。一点物から一事業の規模までスケールさせるのは大変そうですが、それまでにご経験されていたのでしょうか?八谷:会社員だったころに大手企業のブランド開発に関わったりしたので、新商品の立ち上げにはある程度触れていたんです。会社員として取り組んでいた商品開発を、改めてアーティストの目線で挑戦してみたかった気はありました。マーケティング用語には、顧客のニーズに合わせて開発する「マーケットイン」と、提供者の都合に合わせて開発する「プロダクトアウト」という考え方がありますよね。プロダクトアウトは往々にして悪い例だと言われますが、作家がやる場合はこちらで「俺はこれをつくりたいんだ!」という情熱が、うまく顧客まで届いた場合はマーケットインよりも化けます。
市原:私も会社員のころにマーケットリサーチやユーザーリサーチをしてから開発をする手順でしたが、自分はその手法と相性が悪くて……。
八谷:相性悪いのにマーケットイン発想で無理にやってるとストレスが溜まりますよね(笑)。プロダクトアウト思考の人を豪速球ピッチャーと例えると、マーケットイン思考の人は変化球ピッチャー。それぞれに合った投球法を探すことが大事ですよね。あとバッターとしてヒットの打ち方も少しわかってきた。お客さんがOKと思えば、不自由さがあってもいいんだと。別に便利さを追求する必要はないんです。言い換えるとディスコミュニケーションをつくったほうがコミュニケーションが活性化することがあるんです。視聴覚交換マシンも、体験者同士で視聴覚を交換することは嬉しいというよりもすごく困るわけですが、それゆえにものすごく一体感が生まれるんですよね。PostPetも、ペットを送り出して相手に素敵なことをしてほしいと思ったのに、相手の家で自分のペットがウンチをしちゃったりするわけです。あえて想定外のパラメータを入れてバグを誘発させることはアートの分野ではよくやる手法ですが、便利なものを多くの人に売ろうとするマーケティングの分野だとなかなか出てこない。便利さの競争って価格競争に似ていてベクトルが一つだから、大手企業が参入すると途端にひっくり返っちゃうんですよね。パワー勝負ではなく、お客さんの予想や期待を裏切るアートやエンタメの原理は、自分に合っていたなと思います。
市原:コモディティ化を迎えるマーケットのレッドオーシャンぶりは会社員時代に私もよく感じていました。単なる利便性を超えた尺度を自分の中に持っておくのはすごく大事なことですね。後編も引き続き「クリエイターが長生きする方法」や「クリエイターの必須スキル」についてご相談させてください。
※後編は後日公開予定です。Twitterで案内しますのでぜひフォローしてください。