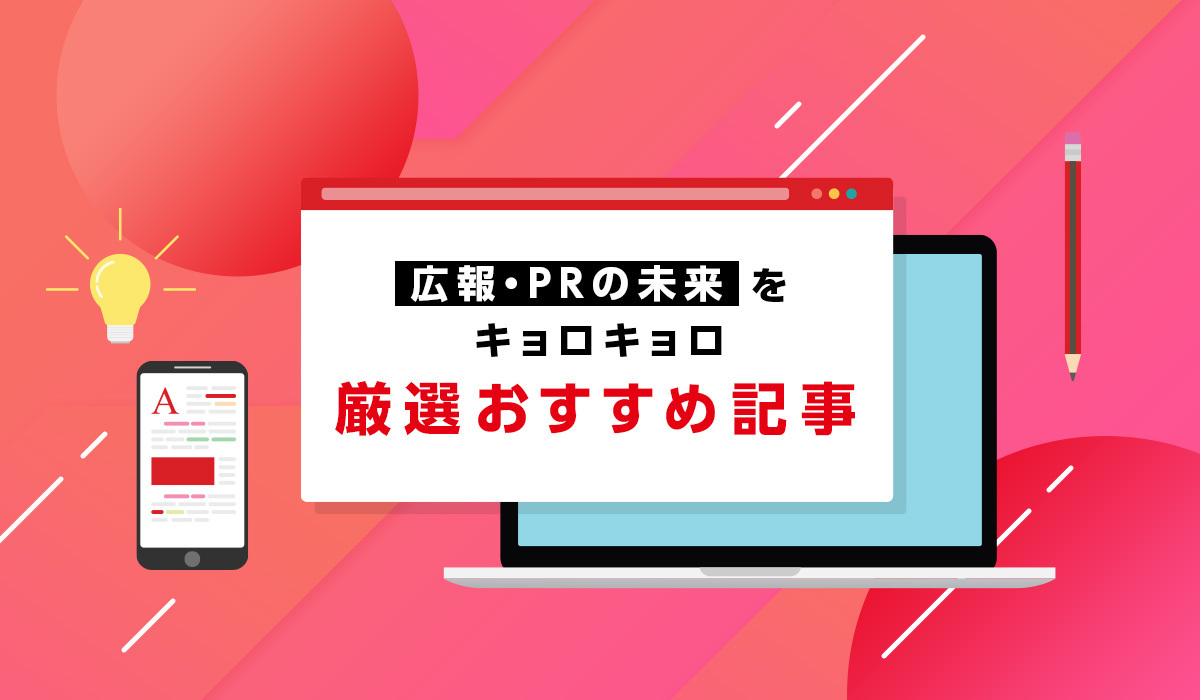テクノロジーで愛に手は届くのか? アイテムクリエイターが鳴らす未来への警鐘 アイテムクリエイター・美術家 懸谷直弓さん

銀行員だったからこそ開けたアートへの道
──懸谷さんは現在のご活動を始められる前は、銀行に勤めていたという珍しい経歴をお持ちなんですよね。その後に東京藝術大学に入学し、芸術の道を志したと。懸谷さんのこれまでのキャリアについて教えていただけますか?もともと絵を描くのは好きだったのですが、「自分は天才ではない」とアートの道を一度諦めてしまった過去があります。その理由は主に2つあって、1つは高校で美術部に所属していたときに、自分より絵の上手い子がたくさんいることを知ってしまったこと。もう1つは、同じく高校生のときの英語の教科書に、ルネ・マグリットという画家の伝記が載っていたんです。その中で彼が、「ジョルジョ・デ・キリコという画家の『愛の歌』を見て涙を流した」というエピソードが載っていたのですが、私はその絵を見ても涙を流せませんでした。そこで、「私にはアートのセンスがないんだな」と悟ってしまったんです。この1つの経験から、「自分が天才でないのであれば、アートの道に進むのは辛いだけ」そう思い、そこでアートの道は一度諦めました。それで大学は文学部に進学して、新卒で銀行に入行しました。

──もう一度アートの道に進もうと思ったのはなぜですか?
常に仕事のことを考えて過ごす生活に疑問を感じるようになったからです。銀行員のころは、仕事に支障をきたさないように早く寝たり、自己啓発本を進んで読んでみたりと、常に仕事のことを考えて過ごす生活を過ごしていたんです。そんな生活を2年近く続けて、やっと慣れてきたときに、私はこの会社で一生働けると思ったんです。一生働けるとわかって、次に考えたことは「自分が死んだらなにを後悔するか」ということ。そこで思い浮かんだのが、高校生のころの漠然とした思い、「アートの世界でやっていくなら東京藝術大学に行きたい」ということでした。
別に銀行を辞めたかったというわけではないんです。たださきほども話したとおりすべてを仕事に捧げていたので、もともと小さいころから好きだったアニメやゲームに一切触れない生活をしていました。「アニメや物語など人間の空想は、仕事と関係がないからやっちゃいけない」「ゲームの中でどれだけキャラクターを育てても自分のレベルアップにはつながらない」そんなふうに思ってしまって。でもそれはやはりもったいないなと。自分のなかに新しい趣味や楽しみをつくりたいと思ったときに、突破口になると思ったのがアートだったんです。
──銀行員だったからこそ、再びアートへの道を志すことにつながっていったんですね。
そうなんです。私のいまの活動は銀行員の経験があったからこそたどり着いた結果なんです。こんな経験を持つ人は多くないと思うので、それを活かした活動をしていきたいと考えました。それがいま私の掲げている、「アート&ファクトリー構想」です。

芸術と工場
──「アート&ファクトリー構想」について、詳しく教えていただけますか?この構想ではアーティストと工場のつながりをつくることを目的としています。アーティストは工場とつながりを持つことで、アトリエとして工場を使うことできます。それによって、よりダイナミックな作品をつくれます。一方工場側は、アーティストが身近にいることでアートやデザインの相談ができるようになったり、工事のデッドストックやデッドスペースを活かしたりすることができます。もしかしたらそのアーティストが工場の跡取りになるかもしれません。もし工場の跡継ぎがいなくなれば、その素晴らしい技術は失われます。継承者問題など年々工場を取り巻く環境は厳しいものになっています。この構想を実現することで工場を守っていくこともできると私は考えています。
──アーティストと工場がつながりを持つことは双方にメリットがあるというわけですね。この構想に至ったのには、どのような経緯があったのでしょうか?
転機になったのは、芸大時代の卒業制作でした。私は『2.5次元の触覚』という作品の制作をしました。全長4メートルほどの大きな作品で、工場の方たちに図面の作成や溶接、運搬など多くの面でご協力いただき、その「脳みそ」や「筋肉」をお借りしました。この作品の制作中に工場の職人の方たちとお話した際に、「アートは自分と関係ない、縁遠い」と思っている方がとても多かったんです。その際に、私がもともと銀行員だったことを伝えると、決して遠くない存在だと共感してもらえたんです。

──「アート&ファクトリー構想」では、今後目指していく展望はどのようなものなのでしょうか?
ゴールは、この構想が日本の文化として根付いていくことです。私一人だけで取り組むのではなく、もっと多くの人を巻き込んで、この考えが50年後、100年後に日本の新しい伝統になっていれば嬉しいです。
以前に、漆芸の人間国宝作家の方と「伝統文化」についてお話をする機会がありました。その方が「伝統とは、いまあるものを残すという思考ではなく、生き方である」とおっしゃっていたのが、すごく印象に残っているんです。伝統というと、いまあるものを絶えないよう残し、伝えていく。このようなイメージを持つ方が多いと思います。しかし本質はそうではなく、伝統とは「環境の変化や人間の想像力の連鎖の中で進化していくものであり、生き方とともに新しくなっていかなければいけない」とお話いただきました。この考えは未来への期待の一つになると思います。だから、「アート&ファクトリー構想」が誰かの期待となれるような、新しい伝統文化にしていくためにも、この先も精力的に取り組んでいきたいです。

手触り感がある未来
──懸谷さんは、東京藝術大学では先端芸術表現科に入学し、新しいテクノロジーを用いたアート作品をつくろうとしていたとお聞きしました。以前advanced by massmedianでも取材させていただいたメディアアーティストの八谷和彦さんのゼミ生だったとか。そうなんです。学生時代は八谷先生のもとで多くのことを教わりました。ですが、いまはどちらかというとその真逆、テクノロジーを用いたメディアアートではなく、現実の「手触り感」のあるものをテーマに扱っています。
──手触り感のあるもの、ですか。それはどうしてなのでしょうか?
現代ではAIやロボットなど、人間の脳みそや筋肉よりも賢くて使えるテクノロジーが台頭してきて、人間の仕事を効率化してくれるようになりました。一方で、テクノロジーを用いても、人が感じる「手触り感」や「痛み」を表現するのは難しくて、再現できているものも少ないですよね。テクノロジーが発展しても、取り残されているものがあると私は思ったんです。

そうです。愛情や友情、縁、心などは誰も触ったことがないし、見たことがないと思います。でも誰もがそれらは存在すると信じていて、それに触れる手段を探しているし、触れられたと思えれば人は満たされていきます。そのような人間の想像力で築かれた領域は、テクノロジーが追いつけない領域なのではないかと思うんです。いくら画質の高いホログラムをつくろうと、精巧な人型のロボットをつくろうと、テクノロジーでは満たすことができない。ロジカルではない、人間の想像力や感情に訴えかけるもの。それらを一番感じられるのが触覚だと私は考えています。だから、人間の想像力を感じられる「手触り感」を追求したいんです。
また、VRやARなどの○○現実(xR)と呼ばれるものは技術が進み、ものすごく現実(リアル)に近づいていると思います。でも、たくさんデバイスを身につけてまでリアルを求める必要があるのかとも思うんです。テクノロジーを介さずに、人間がダイレクトに現実を変えていく方が良いのではないかと。

──わざわざテクノロジーに置き換える必要がない領域があるということですね。
その一つが触覚や手触り感なのではないかと思います。それに、もしxRを発展させていった先が、結局現実には及ばないとわかってしまったときには、再び元の現実と向き合うことになります。その際に、現実で通用するノウハウや蓄積された文化がないと、みんなすごく弱くなってしまう。そうなれば誰も救うことができないですよ。だから私はアートを通して、手触り感があるものたちの文化を育てていきたいと思っています。そのために、私は「アイテムクリエイター」という肩書を名乗っています。
──「アイテムクリエイター」とはどのような意味合いが込められているのでしょうか? 手触り感とアイテムについてもう少しお話いただけますか。
もともとアニメやゲームなど空想の世界が好きだったので、それらの世界に憧れがあるんです。その世界にはさまざまなことを可能にするアイテムが存在しています。体力を回復させたり、敵を倒したりすることのできるアイテム。それをデータの世界ではなく、実際に触れられる現実に生み出していきたい。そんな思いからアイテムクリエイターを名乗っています。
現代はコンテンツがどんどん生まれていますが、反面に消費されるスピードも速く、自分がやってきたことが2~3年の短いスパンで消費されるなんてこともあります。でもそれってちょっと切ないじゃないですか。これは私だけが抱えている問題ではなく、みなさんそれぞれも直面する問題だと思います。だからみんなが自分のいる場所で、試行錯誤を重ねて、それらを守っていかなければいけない。私はアートと手触り感を用いて、それらを守れるアイテムをこれからつくっていきたいと思います。

<撮影協力>株式会社戸塚重量