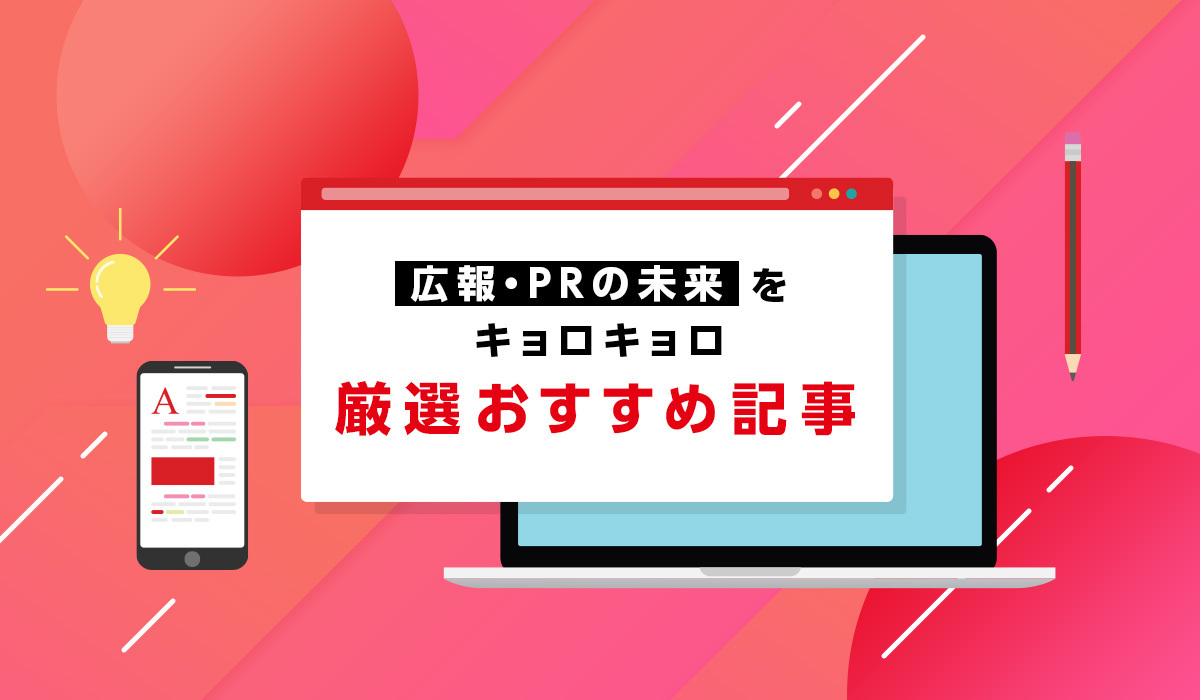誰でもアイデアをカタチに。Webサイトを直感的に制作できるSTUDIOの描く未来 STUDIO 代表取締役CEO 石井穣さん

Webサイトのデザイン・公開・運用までをコーディングなしで完結できる、次世代のデザインツール「STUDIO」。STUDIO株式会社で代表を務める石井穣(いしいゆたか)さんは、Web制作会社や旅行系のスタートアップ「Travee」の立ち上げを経験した後に、このSTUDIOを開発しました。デザイナー、エンジニアとしての経験を持つ石井さんに、STUDIOの目指す世界、そしてWebデザインの未来について、お話を伺いました。
デザイナー・エンジニアにどのような影響が
──STUDIOを開発しようと思ったきっかけを教えてください。私はこれまでデザイナー兼エンジニアとして多くのWebサイトをつくってきたのですが、両方をやるからこそ感じる非効率さがあり、その課題を解決したいという思いがありました。Webサイトをつくる場合、デザイナーがIllustratorやPhotoshop、Sketchなどで絵を描いて、コーディングのフローでエンジニアが1からコードを組み直します。つくっているものは同じなのに、フォーマットが違うことで変換作業が必要になり、二度手間になっていたんです。私自身がデザイナー寄りの思考だったので、コーディングを自動化することで、よりデザインに集中したいという思いから、「STUDIO」をつくりました。
デザイナーは、ただ絵を描くだけの人ではありません。情報をきちんと整理し、新しい価値を生み出せる人こそが真のデザイナーだと思っています。それができる限り、デザイン作業が自動化されていくなかでも、デザイナーという職業はずっとなくならないでしょうね。
──では逆に、コーディングが自動化されていくと、エンジニアの職はどのように変わっていくのでしょうか?
単純作業がなくなる分、より難しいアルゴリズムや、人類が一歩前に進めるような新しいプログラムを書く時間に充てられます。例えば、自動車の自動運転技術のように、いままでになかったもの、人間の生活をよりよくするイノベーティブなものに注力できる世界になるのではないでしょうか。

リリースから半年後の2018年10月には約1万人、2019年1月時点で約3万人、現在は約5万5千人で、そのうち、海外のユーザーが約40%を占めています。
──短期間でそんなに増えたのですね! これまで同様のサービスはなかったのでしょうか?
似たようなサービスはありましたが、コーディングが必須なものや、テンプレートのデザインしかつくれないものばかりでした。「STUDIO」は、自由にデザインを組むことができて、かつ本当にそれだけでWebサイトを構築できる。使いやすさとカスタマイズ性を兼ね備えたデザインツールという意味で、ほかにはないと思います。
実際に、クライアントワークや自身のポートフォリオサイト、スタートアップ企業のLP作成など、さまざまな場面で活用いただいています。自分自身の経験からプレイヤー目線でつくったので、同じような課題を感じていたデザイナーの方に好評で、そこから全社での導入に至ったケースもあり、徐々に広がっていきました。
デザイン業界の巨匠も注目
──デザイン業界の雄である日本デザインセンターからの出資や共同プロジェクトも、「STUDIO」の広まりに寄与しているのではないでしょうか。Webサイト制作用のツールというイメージが強いのですが、なぜグラフィックデザインにルーツを持つ日本デザインセンターとタッグを組むことになったのですか?たしかに、これまでWebデザイナーの方に多く使っていただきましたが、今後はグラフィックデザイナーの方にも広めていきたいという狙いがあります。実は、「STUDIO」はグラフィックデザイナーとも非常に相性が良いんですよ。紙のデザインをしている方がWeb領域に踏み入れる際、コーディングに苦手意識を持つことは少なくありません。しかし、「STUDIO」では、グラフィックデザインのソフトと同じようにデザインすれば、コードに一切触れることなく、一人でWebサイトを構築することができます。コーディング作業を外注してもなかなか思い通りのWebサイトにならなかったり、細かい手直しを依頼するのも面倒だったりするので、自分で簡単に調整できるのは便利ですよね。日本デザインセンターさんにも、これこそが将来のWebデザインの形かもしれない、と賛同いただいています。
──とはいえ、Webならではの表現がグラフィックデザイナーの方にも可能なのかと懸念を抱いてしまいます…。
アウトプットする先が紙かWebかの違いだけなので、大きな問題はないと思います。グラフィックデザイナーの方も、ポスターだけでなく、チラシや冊子など、幅広く手がけていますよね。良いデザイナーは、情報をいかに整理して、どのように見せれば良いのかを構想する能力が高いので、グラフィックデザイナーだからWebはつくれないということはないと思います。もちろん、Webならではのレスポンシブやデバイスの特性など、考慮すべき点はありますが、情報を整理するという点においては根幹の部分は同じです。

「アイデアを誰でもカタチに」というコンセプトをもっと追求していきたいです。現状、「STUDIO」で作成できるのは、静的なサイトのみなので、動的なWebサイトを作成したい場合は、エンジニアに依頼しなければなりません。今後はCMSやEC決済などの機能も備えて、ゆくゆくは、「Webサイトをつくるなら『STUDIO』」というように、プラットフォームのような存在になれたら良いなと思います。基本的にWebサービスは、データの出し入れとデザインのレイアウトによって構成されているので、それぞれをつなぐことで、あらゆるタイプのWebサイトをつくることができる。いままさにCMS機能は開発を進めている最中で、テスト環境で検証中なので、リリースできる日はそう遠くないですね。
──グローバル展開についてはいかがでしょうか? 日本デザインセンターに加え、THE GUILDやPARTY、さらにはCAMPFIREの家入さんやBasecampの坪田さんからも出資を受けていますよね。日本のWeb・デザイン業界の精鋭がまるでアベンジャーズのように集結して世界に切り込んでいくようで、ワクワクします!
もちろんグローバル展開は見据えていますよ。現段階はプロダクトの開発フェーズなので、来年の4月までにSTUDIO3.0をリリース予定です。そこでプロダクトを一気に強化したあとは、完全にグローバル展開に注力していきます。そのための事前調査として、サンフランシスコに赴いて、競合他社のイベントを視察したり、現地のユーザーに会ったりする予定で、市場感を見ながら合わせていきます。Webは基本的に世界共通で構造や作成方法は同じなので、境界線がないんです。世界中で同じような問題を抱えているので、STUDIOというプロダクトもグローバルで通用すると思っています。

2019年7月、プレシリーズAラウンドとして約1.3億円の資金を調達。出資者には、Founder Foundry 1号投資事業有限責任組合(代表取締役 家入一真氏)、D4V 1号投資事業有限責任組合(代表組合員 伊藤健吾氏)、日本デザインセンター(代表取締役 原研哉氏)、THE GUILD(代表取締役 深津貴之氏)、PARTY(代表取締役 伊藤直樹氏)、マネックスベンチャーズ(代表取締役 和田誠一郎氏)、坪田朋氏(Basecamp 代表取締役)、中村洋基氏(PARTY 取締役)、杉山全功氏らが連ねる。
STUDIOの未来を妄想
──今後が楽しみですね! 最後に、STUDIOの遠い未来、こんなSTUDIOがあったら面白いな、という妄想を聞かせていただけますか。アドビ社が「Adobe Sensei」を開発して、デザイン作業の自動化を進めていますが、私たちはそのWeb版として、「STUDIO Senpai」みたいなものをつくっていきたいです。「Adobe Sensei」ではPhotoshopなどの画像データが蓄積され、レタッチ処理が自動化されます。「STUDIO」にもWebサイトの構造を理解したデータが大量に集まっています。将来的には、そのデータを分析して、好みや目的に合わせた提案や、コンバージョンを高める提案などもしていきたいですね。
デザイナーにとっては、「STUDIO」がアシスタント的な存在となり、さらにはメンターにもなりうるので、そういう意味でもSenpai(先輩)になってくれたら嬉しいですね。
──仕事を手助けしてくれるだけではなく、相談にも乗ってくれる「先輩」の存在は非常に心強いですね。STUDIOのグローバル展開も期待大ですね。貴重なお話をありがとうございました!