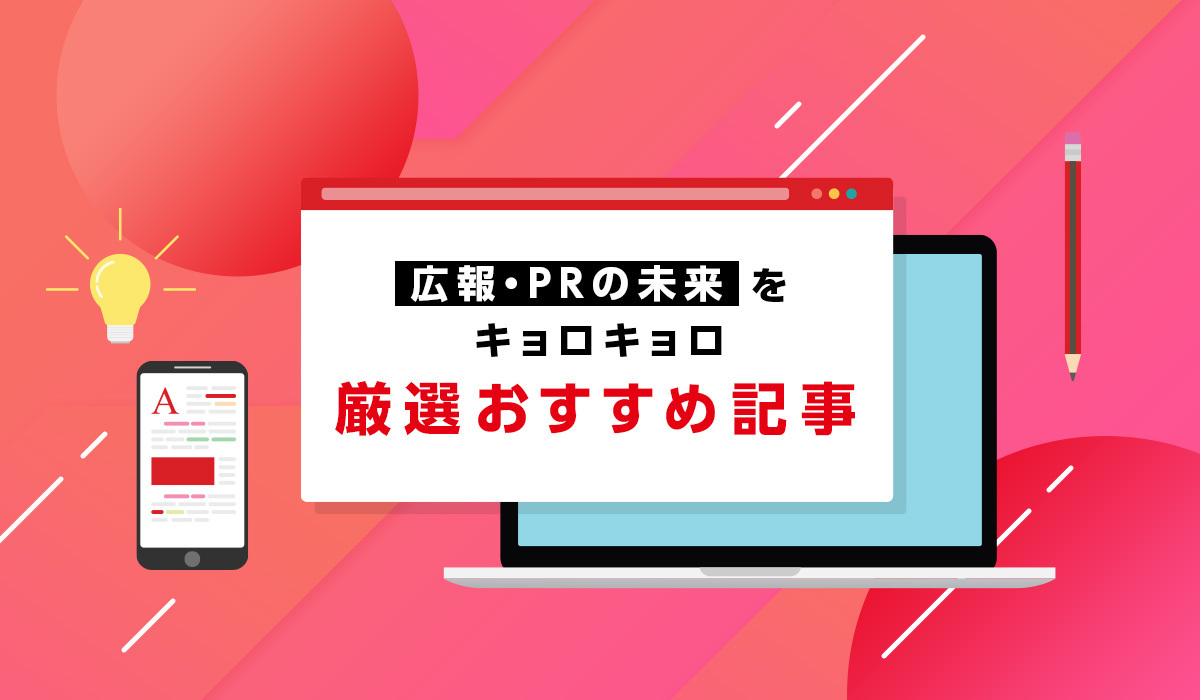入場料のある本屋「文喫」から見る本屋の本質とは スマイルズ 取締役 クリエイティブ本部 本部長 野崎亙さん

食べるスープの専門店の「Soup Stock Tokyo」や、ネクタイブランドの「giraffe」、セレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」など多種多彩な自社事業を展開するスマイルズ。同社は、近年自社事業だけでなく外部のブランド開発や事業開発を進めています。2018年12月には、出版物の取次会社である日本出版販売(日販)が六本木の青山ブックセンター跡地に開業させた本屋「文喫」をプロデュースしました。この本屋の特徴的なところは、入場料があること。本の価値は? 本屋の価値は? これらの本質を改めて見つめ直し、入場料を取るという結論に行き着いたそうです。同プロジェクトを取り仕切ったスマイルズの取締役野崎亙(のざきわたる)さんに、文喫の立ち上げエピソードを伺いました。
──まずどのようにして文喫プロジェクトはスタートしたのでしょうか?
前編でもお話したとおり、当社のクリエイティブチームは内部のクリエイティブディレクションだけでなく、外部の仕事を推奨している環境があります。ある時、日販さんから「新しい本屋をつくりたい」というご相談があり、いろいろと議論をしている中で青山ブックセンター六本木店の閉店情報があり、具体的に動き始めました。





初期段階から、入場料を頂くことを考えていました。ただ最初は1時間500円と設定していました。お客さまにとっての気軽さや既視感を意識していたからです。つまり1500円ではなく500円のほうが足しげく通ってもらえるのでは? これまでになかったサービスではとっつきにくいので漫画喫茶のビジネスをトレースしたほうがよいのでは? といった考えにとらわれていました。
──何をきっかけに1日1500円と決めたのでしょうか?
改めて本屋の本質的価値を考え、本屋とは何者なのかを突き詰めて、真摯に向き合いました。目的買いであれば便利なアマゾンを利用すればいいと思いますが、本屋で何気なく偶然手に取ったものが心に残ったりする。ひょんな出会いが自分の人生に影響を与えてくれることがあったりする。そんな原体験を誰もが持っていて、そこに本屋の価値があるのではと考えました。よく私はn=1と例えるのですが、自分自身の本との接点を思い返して、それを拡張すればひとつの答えになると考えています。

平凡×平凡=ユニーク
──n=1についてもう少し詳しくお話しいただけますか。マーケティングという概念が当社内にはありません。マーケティングはマクロ的視点でロジカルに解を導こうとするアプローチですが、当社はミクロに端を発し解をとらえようとしています。自然科学と自然哲学の関係性のように、目的は一緒でもアプローチの違いがあるわけです。このためn=100(サンプル数100件)などの大人数へのマーケティングリサーチをしません。代わりに担当者の一つの原体験をもとにしたアイデアを大事にしています。実はこのアイデア、単なる思い付きではなくて、その裏側にはその担当者が経験してきた人生があります。この人生の中には、平凡な事象が無数にあります。一つひとつの経験は平凡かもしれませんが、平凡×平凡とかけ合わせると、ユニークな担当者の人生になるわけです。これを逆から捉えると、ユニークなアイデアを因数分解してみると一つひとつは平凡で、誰もが経験したことのある事象だったりします。それをn=1としています。そのn=1の事象に共感を得ることで、n=2,n=3,n=4……と特定多数の人に響くものになるわけです。

──野崎さんの原体験(n=1)は誰もが経験していることで、それは価値があることだとひも解き、事業化したということですね。それの最終的な形が「本と出会うための本屋」というコンセプトなのしょうか?
そうです。これが本質をとらえていて、皆さまにすごくご理解いただけました。そして本と出会うモチベーションで来店いただけるので利用者の満足度が高いです。ある意味、1500円という値段設定によって、「良い本に出会うんだ!」という覚悟をしていらっしゃるからかもしれません。実際に購入することもできるのですが、売れる本はベストセラー本ではなく一般の書店では絶対売れないような変な本ばかりで(笑)。レコード屋でレコードをディグる感覚なのかもしれません。もしくは、京都の料亭で食べる薄い精進料理に旨さを感じようとする感覚にも近いかもしれません。覚悟によってモードが切り替わって、感度が上がっているからではないでしょうか。
最近感じるのが、音楽や映画へのアクセスが簡単になったからといって、必ずしもよく聴いたり観たりするわけでもないなと。イージーなことが人の満足度やモチベーションを喚起してくれるとは限らないというのを自分の実体験から学びました。だから文喫でも入りやすいように500円に設定するのではなく、逆に本に出会う覚悟料として1500円に設定したのは良かったのかなと感じています。
二者択一ではない
──ちゃんと出会えるように細かく店舗内を設計されているのでしょうか?もちろん細かく設計しています。例えば、雑貨は扱わず、本のみを置くとか。書棚と客席をしっかり分けて、出会う時と読む時でモードが切り替わるようにするとか。いろいろと、店内でお客さまの行動は細かく想定しているのですが、あまりサジェストはしないようにしています。どちらかというとノンバーバルで、お客さま自身が使い方を発見できる、新しい文脈を紡げるようにしています。なぜかというと、本との関係性っていろいろあると思っていて、人によっては、本とコーヒーの人もいれば、本と仕事の人もいる。同じケースでも、仕事の役に立つ本の場合もあれば、仕事の息抜きの本の場合もある。つまり一義性ではなく、多義性があると思っています。エントランスのサインのYes and Noに通じる話なのですが、二者択一ではなく、どっちもあるよねということを伝えたいんです。それを単純に多様性という言葉で片付けたくはないし、すべての可能性をシミュレーションした上で、お客さまに強要するものでもないと思っています。

──顧客が紡ぐ文脈からしか事業を起こさないということですね。そしてその顧客の感じる価値は、自身のn=1を振り返る必要があるということでした。前編・後編にわたってありがとうございました。