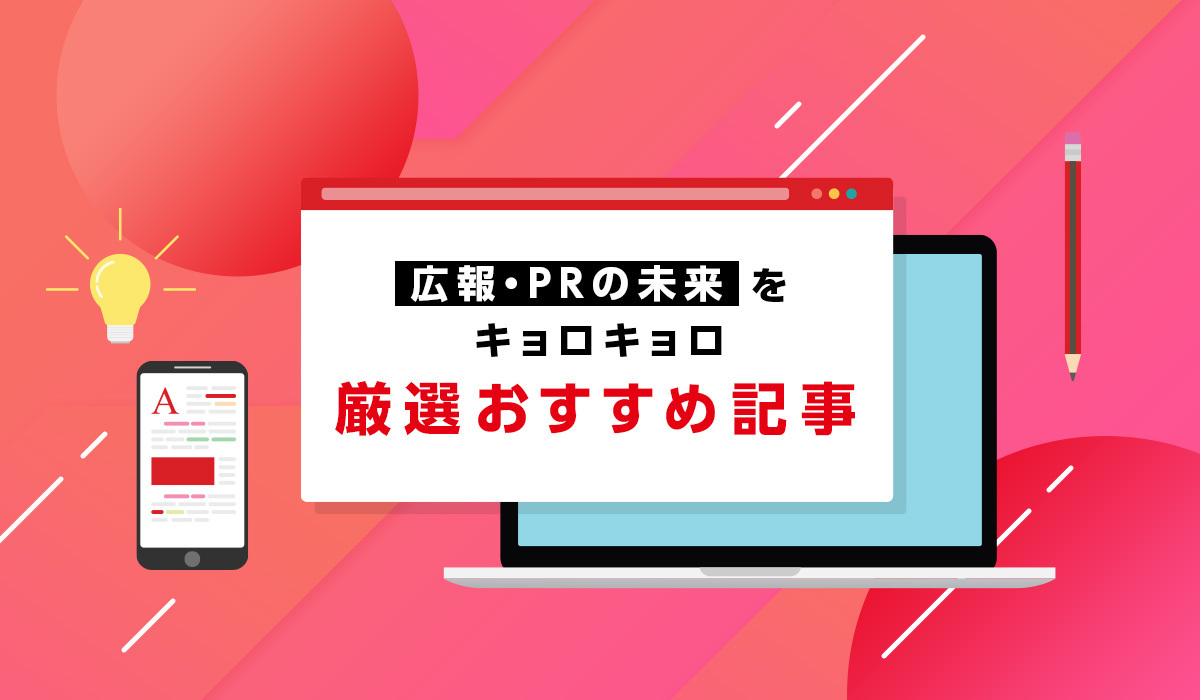「インタラクション」の専門性を武器に、どんな分野でも変化球を投げ続ける #クリエイターの生存戦略 インタラクションデザイナー 奥田透也さん

Yahoo! JAPANのデザイナーを退職し、現在はフリーランスのメディアアーティストとして活動する市原えつこさんが、さまざまな分野のクリエイターや専門家に話を伺い、クリエイターの生存戦略のヒントとノウハウを探す本連載。第一線で活躍するクリエイター達がどのようにキャリア構築をしてきたのか、今後はどのように歩を進めようとしているのか、対談形式でインタビューしていきます。
第3回は、自身の会社の経営者/THE GUILDのボードメンバー/多摩美術大学の講師と三足のわらじを履く奥田透也(おくだゆきや)さん。フレキシブルな働き方で、スマートフォンアプリのUI/UXデザインからインスタレーション作品に至るまでさまざまな制作物を世に送り出しています。そんな奥田さんに、「バランス感覚」や「強みの活かし方」を伺ってきました(マスメディアン編集部)。
第3回は、自身の会社の経営者/THE GUILDのボードメンバー/多摩美術大学の講師と三足のわらじを履く奥田透也(おくだゆきや)さん。フレキシブルな働き方で、スマートフォンアプリのUI/UXデザインからインスタレーション作品に至るまでさまざまな制作物を世に送り出しています。そんな奥田さんに、「バランス感覚」や「強みの活かし方」を伺ってきました(マスメディアン編集部)。
市原:奥田さんの働き方はすごくバランスが良いと感じます。特定組織の仕事に縛られず、複数の職能を持ちながら器用貧乏にならず。さらにその上で専門性もお持ちで。自分の専門分野を活かしながら、作家活動などを通して積み上げたブランドを、うまくご自分の会社である昭和機電へ還元している印象があります。
私も独立して数年経ちますが、ビジネスと創作の整理がまだまだできていなくて……。奥田さんはどうやってこのような働き方やポジションを築いていったのか気になり、今回お話を伺わせていただきました。
奥田:バランスは大事にしています。僕の現在の属性は、自分で経営している「昭和機電」と、フリーランスや会社経営者の集合体「THE GUILDの運営メンバー」、あとは「多摩美術大学統合デザイン学科の非常勤講師」と3つの役割で構成されています。それらの3つの属性をオーバーラップさせることで、その場所やそのレイヤーでしか出会えない人と、いろんな仕事をしています。
比重としては、個別の案件の対応だけでなくコミュニティの運営にも携わっているのでTHE GUILDが最も大きいですね。大学講師は週1なので割合としては小さいです。けれども、現場で働いていると見えない、業界の将来の先行きといった大局的な観点が得られるのは貴重な場ですね。あとは昭和機電。今春から人を雇用してミニマムながら組織になります。一人では受けきれない案件や、やりたくても断らざるを得ない案件が多かったので、組織として対応できるようにしていきます。
市原:このような組織をまたいだ働き方をしているのはなぜでしょうか?
奥田:完全にめぐり合わせですね。もしかしたらずっと一人でやってたかもしれないし。すごく良いタイミングでいろんな方に声をかけていただいて、その時にちゃんと頑張ることを続けていた結果かもしれません。個人事業主としてフラフラしているときに、ご縁のあった深津貴之さんから「THE GUILDに遊びにこないか」とお誘いいただいて、そこから仕事を手伝うようになりました。その流れで、せっかくだからガッツリやろうと思い、ボードメンバーとして運営に回るようになりました。今のところは組織をまたいで仕事をするのがちょうどいいし、現在の働き方は肌にあっていますね。いろんなスタンスをとれることは大事だなと思います。 市原:THE GUILDはすごく面白い組織ですよね。会社に「雇用される」立場だと、その会社の就業規則やルールにガチガチに絡め取られてしまいますが、THE GUILDはあくまで独立した事業主の集合体で、THE GUILDにきた仕事をそれぞれの事業主にアサインしていく形態だと伺いました。
市原:THE GUILDはすごく面白い組織ですよね。会社に「雇用される」立場だと、その会社の就業規則やルールにガチガチに絡め取られてしまいますが、THE GUILDはあくまで独立した事業主の集合体で、THE GUILDにきた仕事をそれぞれの事業主にアサインしていく形態だと伺いました。
奥田:そうです。「THE GUILDという器に自分のポートフォリオを共有することで、より良い仕事がくるといいよね」というスタンスで各メンバーは所属しています。
市原:フリーランスだと規模の大きい仕事を受けることが難しいので、羨ましい体制です。
奥田:フリーランスでもチームをつくれば対応できなくもないですが、チーム体制を整えるにも信頼関係が必要だし、難しいですよね。でも、信頼できる人たちが集まっている場があれば、ドラクエのルイーダの酒場のようにパーティーを組んで、ボス戦にも突撃していける。THE GUILDにいるメンバーは基本的にすごく職人気質で、パーティーに欠かせません。フリーランスのデメリットを解消しつつ、やりたいことができる集合体でありたいです。
奥田:THE GUILDはUI/UXに特化した会社であり、コミュニティです。前職のtha ltd.も恵まれた環境でしたが、自分次第でなんでも着手してよいTHE GUILDは本当に心地が良いです。ただ、手広くしすぎると「単なる便利な人」になってしまうので加減は気をつけています。なんでも手を出すけど、その分野のてっぺんのことはちゃんと勉強する。そうしないと「全部がイマイチな人」になっちゃうから。
市原:フリーランスが陥りがちな問題ですよね。いろんな分野の仕事ができるけど、専門性が曖昧という。自分も耳が痛いのですが……。 奥田:陥らないために必要なことがあって。常に勉強の余地を残しながら仕事をすることと、自分の強みを自覚することです。僕の場合は「プログラムで絵を描く」ことしかできない状態で、この業界に入ったので、「これを極めるしかない、そうしないと死ぬ!」みたいな崖っぷち状態からスタートしました。僕にとっての柱は「プログラムで絵を描く」なので、その特性をうまく抽象化して考え方を適用していけば、どんな領域でも最終的に価値を発揮できると思っています。
奥田:陥らないために必要なことがあって。常に勉強の余地を残しながら仕事をすることと、自分の強みを自覚することです。僕の場合は「プログラムで絵を描く」ことしかできない状態で、この業界に入ったので、「これを極めるしかない、そうしないと死ぬ!」みたいな崖っぷち状態からスタートしました。僕にとっての柱は「プログラムで絵を描く」なので、その特性をうまく抽象化して考え方を適用していけば、どんな領域でも最終的に価値を発揮できると思っています。
名刺やお店の看板など、専門ではないグラフィックデザインの仕事もまれに対応するのですが、単純にグラフィックをつくるだけでは絶対にその分野の専門家には敵いません。だから「インタラクションという概念をグラフィックデザインに注ぎ込むとどうなるか」という実験をします。
例えば中目黒のイタリアンレストランがオープンする時に、お店の看板・ショップカード・ロゴなどのグラフィック一式をご依頼いただきました。お店のネーミングも一緒に考えたのですが、店と人、料理と人、人と人が巡り合う場であることをコンセプトに「Megriva(メグリヴァ)」という名前にしました。さらにオーナーシェフの下の名前が「勝明」さんだったので、それになぞらえて日(太陽)と月を象形文字のように表すアイデアを思いついて。お店とお客さんにもそれぞれの巡り合いやつながりがあるから、太陽と月のロゴを2つに分けてハンコをつくり、ショップカードは未完成の状態で渡して、シェフとお客さんが片方ずつ押して新しいロゴがその都度生まれ続けるという、超アナログながらジェネレーティブデザインの発想をショップカードに入れ込みました。これってグラフィックデザインですが、ある意味インタラクションデザインですよね。 市原:面白いです、美大の教材になりそうな事例ですね。
市原:面白いです、美大の教材になりそうな事例ですね。
奥田:お店の看板も同じ考えに基づいてデザインしています。レイヤー構造にすることで、お店に近づくにつれ、太陽と月の関係性が変わるようにしました。インタラクションデザインを用いて、より良いデザインがつくれたらいいなと思っています。 こういったアプローチで、どうにかいろんな仕事に取り組んでいます。トンチに近いので毎回苦しいんですけどね……。「やっぱり本職の人がいいよね」となってしまわないように、何かしらの挑戦をし続けています。
こういったアプローチで、どうにかいろんな仕事に取り組んでいます。トンチに近いので毎回苦しいんですけどね……。「やっぱり本職の人がいいよね」となってしまわないように、何かしらの挑戦をし続けています。
市原:それは非常に参考になる考え方です……。自分の主戦場ではない案件でも、そうやって自分の専門性を反映させていけば、自分ならではの付加価値が付くわけですね。
奥田:スキルアップって山登りみたいなものじゃないですか。これまで一つの分野でスキルを上げてきて、新しいことをやる時にまたゼロから登るのって大変。だから、ここまで登ってきたその勢いで別の山の頂上に移動できないかを考えたんです。その一つの解として、登った山の頂上から別の山に橋をかけられるのではないか、と思いました。別の山をコツコツ登ってきた王道は尊敬しつつ、別のアプローチで山頂に登れたらいいね、という戦い方です。王道でやろうとしても豪腕ピッチャーがそれぞれの山にいるじゃないですか。その人と豪腕勝負しても勝ち目はない。でもいろいろやりたい質だから、謎に変化球のキレがいい人を目指しています。
市原:いいですね。そのやり方で戦っていけば、どの分野にいっても「何をやっているかわからない人」ではなく「何をやっても面白い切り口で返してくれる人」になれそうです。
奥田:基本的には「面白そうかどうか」で決めています。それに加え、あるひとつの専門分野をやったらカウンター的に別の領域に取り組み、なるべく自分の幅が広がるようしています。完全に専門外の場合は、その分野の信頼できる人と一緒にやることで、僕のインタラクションの専門性を企画に組み込んでいきます。極端な例ですけど「曲をつくってくれ」と頼まれたら、おそらく作曲家さんとタッグを組み、曲のコンセプトからインタラクションの視点を持って考えるんじゃないでしょうか。
市原:収益性ではなく、面白さや専門領域を広げる案件を優先するのですね。
奥田:仕事の選び方としては「お金が良い」だけで引き受けることはあまりないですね。仕事を終えた後、お金、人脈、スキルなどが自分の中に蓄積されます。そういった対価が、割いた時間や労力に見合えばやって良いのではと思いますね。
ただ、「にわとりとたまご」なんですよね。実績がないと良い仕事が来ない、良い仕事が来ないと実績ができない……みたいな。だから、つくれる人は自分で発信して、実績化しちゃうのが一番良い戦略だと思います。そういう意味で、僕もグループ展など自分発信の活動はちゃんと続けていきたいです。
市原:それで今、奥田さんのTwitterアカウントが「ツク郎くん」という名前になっているんですね。
奥田:「つくろう」と思ったんです(笑)。
私が独立1年目に「受託のクライアントワークと作品制作のバランスをとるのが難しい」という悩みをSNSにポストしたら、奥田さんが非常にためになる回答をくださったのが印象に残っています。「下手に作品自体で稼ごうとするよりも、ピュアに自分のやりたいことをつぎ込んで作品をつくり、それをどう次の仕事につなげていくか、そして新たな仕事で得た資本を次の作品に注ぎ込むか……という数珠つなぎのイメージでやっている」とアドバイスしていただき、「なるほど!」と思いました。 奥田:そこまで綺麗に回ることはないですが、今も基本的にはそのスタンスです。ただ、僕はアーティスト気質ではなく、デザイナー精神で作品をつくっています。前提が何もない状態でゼロからつくるときも、課題を勝手に設定してスタートしますね。制作中に判断に迷ったとき、「これが課題を解決しているかどうか」という基準があると進めやすいんです。無の状態で作品と向き合って「自分が本当に良いと思うかどうか」で考えるのは、あまり自信がありません。
奥田:そこまで綺麗に回ることはないですが、今も基本的にはそのスタンスです。ただ、僕はアーティスト気質ではなく、デザイナー精神で作品をつくっています。前提が何もない状態でゼロからつくるときも、課題を勝手に設定してスタートしますね。制作中に判断に迷ったとき、「これが課題を解決しているかどうか」という基準があると進めやすいんです。無の状態で作品と向き合って「自分が本当に良いと思うかどうか」で考えるのは、あまり自信がありません。
展覧会に出品したときも、まず展覧会のテーマがあり、その中のひとつのピースに僕の作品がはめこまれるイメージで創作しています。来場者の人はどういう順番で僕の作品に来て、何を伝えればその展覧会は深いものになるのかを考えて、そこから逆算して作品をつくっています。だから純粋な自己表現というよりデザインの一種なんですよね。
市原:なるほど、完全にUXデザインの観点で作品をつくられていたのですね……。21_21 DESIGN SIGHTの「アスリート展」に出品された作品「ゴールへの道筋」も同じような考え方でつくられたのでしょうか? 奥田:アスリート展は「来場者みんなが実は持っているアスリート性を見つける」ことが目的のひとつでした。その中で、僕の作品は展覧会の最後に設置されていたため、「これはアスリートだけではなくてみんなの話でもあったんですよ」と展示の終わりに気付いてほしくて、あの作品をつくりました。
奥田:アスリート展は「来場者みんなが実は持っているアスリート性を見つける」ことが目的のひとつでした。その中で、僕の作品は展覧会の最後に設置されていたため、「これはアスリートだけではなくてみんなの話でもあったんですよ」と展示の終わりに気付いてほしくて、あの作品をつくりました。
「デザインあ展」という展覧会にも、大日本タイポ組合さん・宇野由希子さんと作品制作して出品したのですが、その時も「どうやったらプログラミングによって作品テーマが面白く伝わるよう実装できるか」という狙いで制作しましたね。
奥田:それは関係ないです(笑)。単純に美味しいご飯が好きだから、幸せになれるじゃないですか。最近は脂が多いものはつらいので赤身肉や馬肉がいいんですけど……。仕事になればいいとは思っているけど、単純な趣味ですね。酒と飯は。 市原:ただ、奥田さんは五感を大事にされている印象がとても強くあります。
市原:ただ、奥田さんは五感を大事にされている印象がとても強くあります。
奥田:五感……言われてみれば確かにそうかもしれないですね。身体的なものをすごく大事にしています。僕の原体験として、幼い頃から自然界のルールやしくみがすごく好きで、水が流れたり、投げられた石が放物線を描いたりする様に美しさを感じていました。自然の摂理をちゃんと踏襲して、自分の作品に宿らせられるかを気にするようにはしています。
市原:こちらの作品も、そういった美しさを再現したものでしょうか? 奥田:この作品は物理演算したものですが、例えばWebページでボタンを押した時の反応や、画面が切り替わる遷移のトランジションは気持ちがいいものとそうでないものがあります。気持ちよさのルールはなにか? それは世の中に当たり前にあるものの中にヒントが含まれています。だから、五感に訴えることは大事にしています。
奥田:この作品は物理演算したものですが、例えばWebページでボタンを押した時の反応や、画面が切り替わる遷移のトランジションは気持ちがいいものとそうでないものがあります。気持ちよさのルールはなにか? それは世の中に当たり前にあるものの中にヒントが含まれています。だから、五感に訴えることは大事にしています。
実は大学の時に合気道をやっていたのですが、合気道の動きってすごく自然に流れるんですよ。力と力がぶつからないように、いなしたり、曲げたり、投げたりして、決して止めない。そうして力の方向を変えながら弱めたり強めたりする身体感覚は、インターフェースやインタラクションを考える上ですごく役に立っています。
市原:インタラクションに対する変態性は幼い頃からずっとあったのですね。この連載で最初にインタビューしたアーティストの草野絵美さんも近いお話をされていて、子どもの頃から偏執狂的に追いかけてきたものは枯れない泉のようなもので、そこを供給源にしていくべきというお話をおっしゃっていました。
奥田:枯れない供給源みたいなものはよくわかります。モチベーションの話にもつながりますが、やっぱり初期衝動が最終的には大事で、それをどう昇華するかなんですよね。初期衝動をアーティストとして作品にする方法もありますし、受託案件にうまく当てはめて昇華する方法もあります。自分なりのやり方を見つけるのがいいのかなと思います。
市原:最後に、 奥田さんが今後やってみたいことは何でしょうか?
奥田:僕は一貫していて、引き続き「インタラクション」を駆使して、誰も挑戦したことのない領域でどんどん変化球を投げていきたいです。そのために改めて「インタラクションとは?」に立ち返ってみようと思っています。概念の探求は、それこそ大学という研究機関とうまく一緒にやっていけそうですね。是非そこに挑戦したいです。
市原:ご自分の専門性をさらに研ぎ澄ませていくわけですね。「インタラクションの専門家」から「インタラクションの化身」のような存在に進化していきそうな予感に武者震いします。奥田さんが繰り出す変化球をこれからも楽しみにしております!

私も独立して数年経ちますが、ビジネスと創作の整理がまだまだできていなくて……。奥田さんはどうやってこのような働き方やポジションを築いていったのか気になり、今回お話を伺わせていただきました。
奥田:バランスは大事にしています。僕の現在の属性は、自分で経営している「昭和機電」と、フリーランスや会社経営者の集合体「THE GUILDの運営メンバー」、あとは「多摩美術大学統合デザイン学科の非常勤講師」と3つの役割で構成されています。それらの3つの属性をオーバーラップさせることで、その場所やそのレイヤーでしか出会えない人と、いろんな仕事をしています。
比重としては、個別の案件の対応だけでなくコミュニティの運営にも携わっているのでTHE GUILDが最も大きいですね。大学講師は週1なので割合としては小さいです。けれども、現場で働いていると見えない、業界の将来の先行きといった大局的な観点が得られるのは貴重な場ですね。あとは昭和機電。今春から人を雇用してミニマムながら組織になります。一人では受けきれない案件や、やりたくても断らざるを得ない案件が多かったので、組織として対応できるようにしていきます。
市原:このような組織をまたいだ働き方をしているのはなぜでしょうか?
奥田:完全にめぐり合わせですね。もしかしたらずっと一人でやってたかもしれないし。すごく良いタイミングでいろんな方に声をかけていただいて、その時にちゃんと頑張ることを続けていた結果かもしれません。個人事業主としてフラフラしているときに、ご縁のあった深津貴之さんから「THE GUILDに遊びにこないか」とお誘いいただいて、そこから仕事を手伝うようになりました。その流れで、せっかくだからガッツリやろうと思い、ボードメンバーとして運営に回るようになりました。今のところは組織をまたいで仕事をするのがちょうどいいし、現在の働き方は肌にあっていますね。いろんなスタンスをとれることは大事だなと思います。

奥田:そうです。「THE GUILDという器に自分のポートフォリオを共有することで、より良い仕事がくるといいよね」というスタンスで各メンバーは所属しています。
市原:フリーランスだと規模の大きい仕事を受けることが難しいので、羨ましい体制です。
奥田:フリーランスでもチームをつくれば対応できなくもないですが、チーム体制を整えるにも信頼関係が必要だし、難しいですよね。でも、信頼できる人たちが集まっている場があれば、ドラクエのルイーダの酒場のようにパーティーを組んで、ボス戦にも突撃していける。THE GUILDにいるメンバーは基本的にすごく職人気質で、パーティーに欠かせません。フリーランスのデメリットを解消しつつ、やりたいことができる集合体でありたいです。
「インタラクション」の専門性を応用し、他領域に挑戦していく
市原:THE GUILDの制作物は非常に真摯な印象がありますが、どういった領域に特化しているのでしょうか?奥田:THE GUILDはUI/UXに特化した会社であり、コミュニティです。前職のtha ltd.も恵まれた環境でしたが、自分次第でなんでも着手してよいTHE GUILDは本当に心地が良いです。ただ、手広くしすぎると「単なる便利な人」になってしまうので加減は気をつけています。なんでも手を出すけど、その分野のてっぺんのことはちゃんと勉強する。そうしないと「全部がイマイチな人」になっちゃうから。
市原:フリーランスが陥りがちな問題ですよね。いろんな分野の仕事ができるけど、専門性が曖昧という。自分も耳が痛いのですが……。

名刺やお店の看板など、専門ではないグラフィックデザインの仕事もまれに対応するのですが、単純にグラフィックをつくるだけでは絶対にその分野の専門家には敵いません。だから「インタラクションという概念をグラフィックデザインに注ぎ込むとどうなるか」という実験をします。
例えば中目黒のイタリアンレストランがオープンする時に、お店の看板・ショップカード・ロゴなどのグラフィック一式をご依頼いただきました。お店のネーミングも一緒に考えたのですが、店と人、料理と人、人と人が巡り合う場であることをコンセプトに「Megriva(メグリヴァ)」という名前にしました。さらにオーナーシェフの下の名前が「勝明」さんだったので、それになぞらえて日(太陽)と月を象形文字のように表すアイデアを思いついて。お店とお客さんにもそれぞれの巡り合いやつながりがあるから、太陽と月のロゴを2つに分けてハンコをつくり、ショップカードは未完成の状態で渡して、シェフとお客さんが片方ずつ押して新しいロゴがその都度生まれ続けるという、超アナログながらジェネレーティブデザインの発想をショップカードに入れ込みました。これってグラフィックデザインですが、ある意味インタラクションデザインですよね。

奥田:お店の看板も同じ考えに基づいてデザインしています。レイヤー構造にすることで、お店に近づくにつれ、太陽と月の関係性が変わるようにしました。インタラクションデザインを用いて、より良いデザインがつくれたらいいなと思っています。

市原:それは非常に参考になる考え方です……。自分の主戦場ではない案件でも、そうやって自分の専門性を反映させていけば、自分ならではの付加価値が付くわけですね。
奥田:スキルアップって山登りみたいなものじゃないですか。これまで一つの分野でスキルを上げてきて、新しいことをやる時にまたゼロから登るのって大変。だから、ここまで登ってきたその勢いで別の山の頂上に移動できないかを考えたんです。その一つの解として、登った山の頂上から別の山に橋をかけられるのではないか、と思いました。別の山をコツコツ登ってきた王道は尊敬しつつ、別のアプローチで山頂に登れたらいいね、という戦い方です。王道でやろうとしても豪腕ピッチャーがそれぞれの山にいるじゃないですか。その人と豪腕勝負しても勝ち目はない。でもいろいろやりたい質だから、謎に変化球のキレがいい人を目指しています。
市原:いいですね。そのやり方で戦っていけば、どの分野にいっても「何をやっているかわからない人」ではなく「何をやっても面白い切り口で返してくれる人」になれそうです。
自分の可能性を拡張する仕事を戦略的に選ぶ
市原:フリーランスで働いていると本当に多様なお仕事の依頼が来ますよね。その中にはそれまでの職域とはまったく違うものもあったのではと思いますが、どういうスタンスで取り組んでいったのでしょうか? 収益性や楽しさ、適性など優先ポイントがあるのですか?奥田:基本的には「面白そうかどうか」で決めています。それに加え、あるひとつの専門分野をやったらカウンター的に別の領域に取り組み、なるべく自分の幅が広がるようしています。完全に専門外の場合は、その分野の信頼できる人と一緒にやることで、僕のインタラクションの専門性を企画に組み込んでいきます。極端な例ですけど「曲をつくってくれ」と頼まれたら、おそらく作曲家さんとタッグを組み、曲のコンセプトからインタラクションの視点を持って考えるんじゃないでしょうか。
市原:収益性ではなく、面白さや専門領域を広げる案件を優先するのですね。
奥田:仕事の選び方としては「お金が良い」だけで引き受けることはあまりないですね。仕事を終えた後、お金、人脈、スキルなどが自分の中に蓄積されます。そういった対価が、割いた時間や労力に見合えばやって良いのではと思いますね。
ただ、「にわとりとたまご」なんですよね。実績がないと良い仕事が来ない、良い仕事が来ないと実績ができない……みたいな。だから、つくれる人は自分で発信して、実績化しちゃうのが一番良い戦略だと思います。そういう意味で、僕もグループ展など自分発信の活動はちゃんと続けていきたいです。
市原:それで今、奥田さんのTwitterアカウントが「ツク郎くん」という名前になっているんですね。
奥田:「つくろう」と思ったんです(笑)。

UXデザイナー的な観点で作品をつくる、独特の制作プロセス
市原:確かに自分で勝手に作品をつくって発信している人は、多方面から仕事が舞い込んでくることもありますよね。奥田さんが個人の作品制作とクライアントワークをどのように位置づけ、相乗効果を狙っているかを伺いたいです。私が独立1年目に「受託のクライアントワークと作品制作のバランスをとるのが難しい」という悩みをSNSにポストしたら、奥田さんが非常にためになる回答をくださったのが印象に残っています。「下手に作品自体で稼ごうとするよりも、ピュアに自分のやりたいことをつぎ込んで作品をつくり、それをどう次の仕事につなげていくか、そして新たな仕事で得た資本を次の作品に注ぎ込むか……という数珠つなぎのイメージでやっている」とアドバイスしていただき、「なるほど!」と思いました。

展覧会に出品したときも、まず展覧会のテーマがあり、その中のひとつのピースに僕の作品がはめこまれるイメージで創作しています。来場者の人はどういう順番で僕の作品に来て、何を伝えればその展覧会は深いものになるのかを考えて、そこから逆算して作品をつくっています。だから純粋な自己表現というよりデザインの一種なんですよね。
市原:なるほど、完全にUXデザインの観点で作品をつくられていたのですね……。21_21 DESIGN SIGHTの「アスリート展」に出品された作品「ゴールへの道筋」も同じような考え方でつくられたのでしょうか?

「ゴールへの道筋」奥田透也, created for Exhibition “ATHLETE” at 21_21 DESIGN SIGHT,2017, Photo: Keizo Kioku
アスリートは人生のあらゆる分岐点で目標に向かって選択し続けている、というコンセプトを可視化した作品。
アスリートは人生のあらゆる分岐点で目標に向かって選択し続けている、というコンセプトを可視化した作品。
「デザインあ展」という展覧会にも、大日本タイポ組合さん・宇野由希子さんと作品制作して出品したのですが、その時も「どうやったらプログラミングによって作品テーマが面白く伝わるよう実装できるか」という狙いで制作しましたね。
幼少期からの偏愛を昇華し、枯れないモチベーションを生み出す
市原:最後は人生相談になってしまい恐縮ですが、個人事業主だと自分を叱咤激励してくれる人がいなくて困っています。仕事のモチベーションを高く保つためのコツはなんでしょうか? 奥田さんは非常にグルメな印象があり、よく美味しそうなものを食べに行かれていますが、あれも芸の肥やしなのでしょうか?奥田:それは関係ないです(笑)。単純に美味しいご飯が好きだから、幸せになれるじゃないですか。最近は脂が多いものはつらいので赤身肉や馬肉がいいんですけど……。仕事になればいいとは思っているけど、単純な趣味ですね。酒と飯は。

奥田:五感……言われてみれば確かにそうかもしれないですね。身体的なものをすごく大事にしています。僕の原体験として、幼い頃から自然界のルールやしくみがすごく好きで、水が流れたり、投げられた石が放物線を描いたりする様に美しさを感じていました。自然の摂理をちゃんと踏襲して、自分の作品に宿らせられるかを気にするようにはしています。
市原:こちらの作品も、そういった美しさを再現したものでしょうか?

実は大学の時に合気道をやっていたのですが、合気道の動きってすごく自然に流れるんですよ。力と力がぶつからないように、いなしたり、曲げたり、投げたりして、決して止めない。そうして力の方向を変えながら弱めたり強めたりする身体感覚は、インターフェースやインタラクションを考える上ですごく役に立っています。
市原:インタラクションに対する変態性は幼い頃からずっとあったのですね。この連載で最初にインタビューしたアーティストの草野絵美さんも近いお話をされていて、子どもの頃から偏執狂的に追いかけてきたものは枯れない泉のようなもので、そこを供給源にしていくべきというお話をおっしゃっていました。
奥田:枯れない供給源みたいなものはよくわかります。モチベーションの話にもつながりますが、やっぱり初期衝動が最終的には大事で、それをどう昇華するかなんですよね。初期衝動をアーティストとして作品にする方法もありますし、受託案件にうまく当てはめて昇華する方法もあります。自分なりのやり方を見つけるのがいいのかなと思います。
市原:最後に、 奥田さんが今後やってみたいことは何でしょうか?
奥田:僕は一貫していて、引き続き「インタラクション」を駆使して、誰も挑戦したことのない領域でどんどん変化球を投げていきたいです。そのために改めて「インタラクションとは?」に立ち返ってみようと思っています。概念の探求は、それこそ大学という研究機関とうまく一緒にやっていけそうですね。是非そこに挑戦したいです。
市原:ご自分の専門性をさらに研ぎ澄ませていくわけですね。「インタラクションの専門家」から「インタラクションの化身」のような存在に進化していきそうな予感に武者震いします。奥田さんが繰り出す変化球をこれからも楽しみにしております!