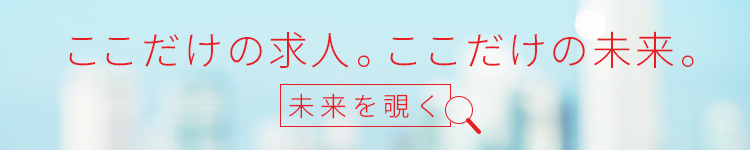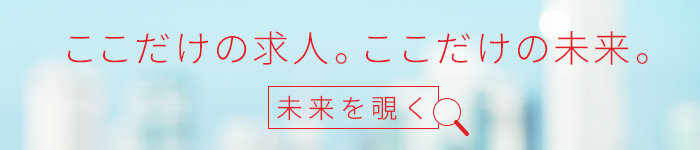ゲームセンターで釣った魚が家に届く? ユーザー視点からはじまるゲームづくりとは ゲームプロデューサー 小山順一朗さん

ゲームセンターで釣った魚が自宅に届く? そんな驚きのキャンペーンを展開しているのがアーケードゲーム『釣りスピリッツ』。このキャンペーンの仕掛け人である小山順一朗(こやまじゅんいちろう)さんは、『機動戦士ガンダム 戦場の絆』『アイドルマスター』『太鼓の達人』など数多くのゲーム開発を手掛けてきた売れっ子ゲームクリエイター。このキャンペーンの裏側にはなにがあるのか、そこには小山さんのこれまでのマーケティング視点がありました。
ゲームセンターから食卓まで
──「釣りスピリッツぱくぱくキャンペーン」について教えてください。アーケードゲーム『釣りスピリッツ』で実施したキャンペーンで、ゲームセンターで釣れる魚が実際に家に届く、というものです。Twitterで応募すると、実際に離島で取れたクエやハタなど、普段は目にすることの少ない魚たちが自宅に届き、家で実際に触れて、捌いて味わうことができます。
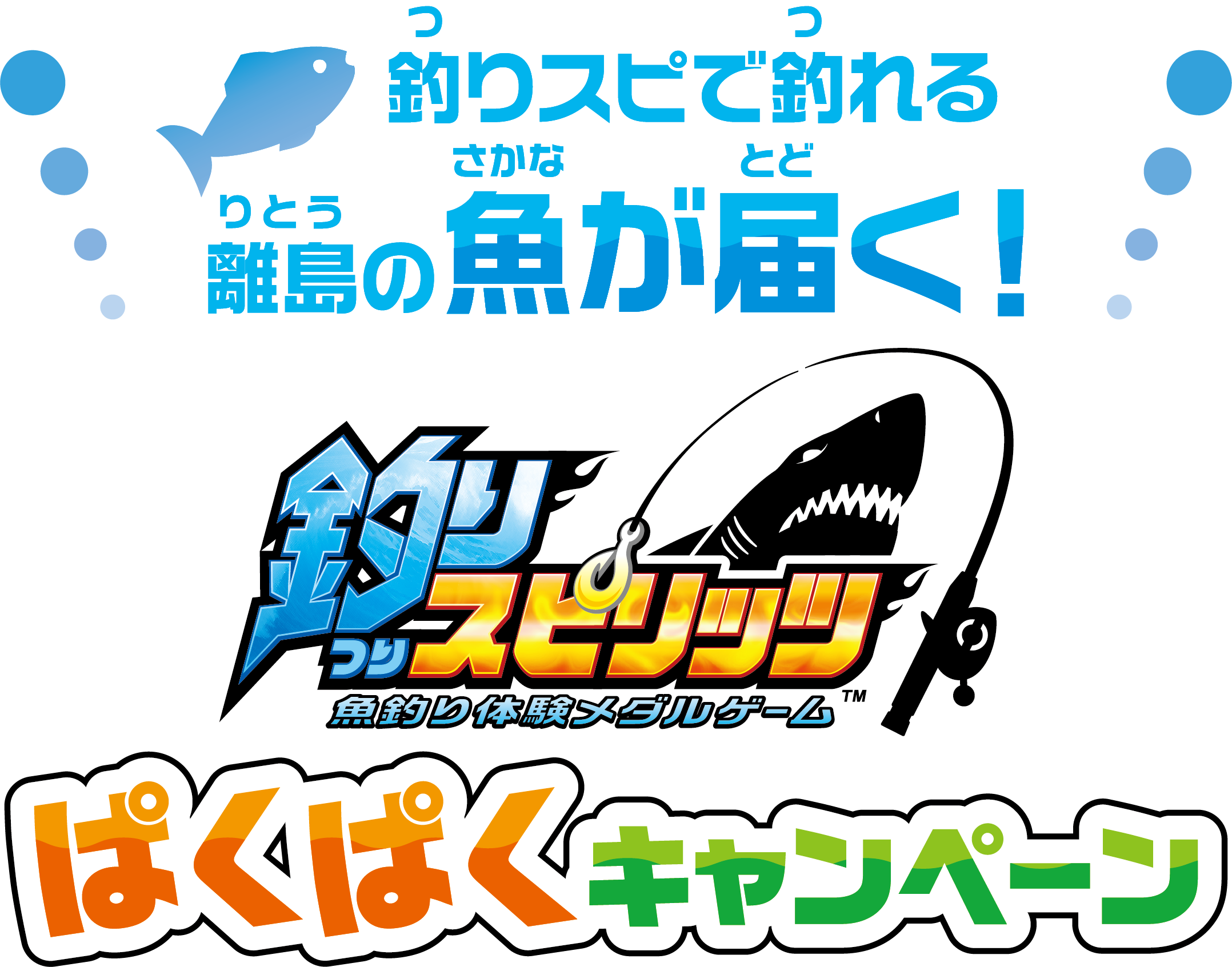
──ゲームセンターで遊ぶところから実際に食べるところまでつながるのは驚きました。なぜこのキャンペーンを始めたのでしょうか。
実際の釣りでできて、釣りスピリッツでできない最も大きな課題に「釣った魚を手に入れて食べること」があります。そのできないことを解消するために、ずっと魚を届けたいと思っていましたが、解決策を見出すことができずにいました。魚をゲームセンターで渡すわけにもいかないですし、直送するにもどういったルートがあるのかわかりませんでした。
そんなとき、静岡県沼津市で船に乗って漁をお手伝いする機会をいただきました。これが本当に大変。漁師さんの仕事は朝早くから重労働。時には海に投げ出される命の危険すらあります。また後継者も不足していました。一番の若手が40代、最高齢はなんと80代。それ以外にも、流通できない未利用魚の廃棄や漁業生産量の減少、海洋プラスチック問題など枚挙にいとまがありません。でも同時に網にかかった魚たちを見ると、多種多様で、私たちが見ている魚たちは本当に一部だったなと気付きました。
その後、対馬でも漁業の現場を見ることができました。対馬の漁師さんとお会いして、漁業や生活を体験し、海の資源の豊かさ、そして美味しさを感じました。
スーパーに並んでいる魚は多くても10数種類しかありません。それ以外にもこんなに多くの魚がいるのだ、と気づき、この海の豊かさを子どもたちにも伝えたい、と思い今回のキャンペーンに至っています。

魚を配送するにあたって障壁となったのは流通経路でした。通常、水産事業者が採った魚は、漁協を通じて集められ、決められた種類・大きさの魚が市場に集まり、そこから全国に発送をされます。ただ、今回は海の豊かさを伝えるために、普段スーパーでは見ないような魚を届けようと思っていました。クエやシイラなど。そんな魚が届いたらインパクト大ですよね。しかも鮮度も良い状態で届けたいと思っていたので、釣り上げてからできるだけ短時間で、漁師さんから消費者の手元に届けたかった。そこで水産事業者から直接魚を仕入れて配送している会社、フーディソンさんを見つけ、お力添えいただきました。
実体験に元にしたモノづくり
──実際に沼津や対馬の漁業に出られていますが、わざわざ現地に足を運ぶのはなぜですか?長年アーケードゲームをつくってきましたが、ゲームづくりは実体験に基づいています。空を飛ぶゲームだったらハングライダーを体験したり、スキーのゲームだったらスキーをしたり。そこでどんな感情が表れるのかを確かめて、ゲームに落とし込んでいきました。今回の釣りスピリッツも同じです。とにかく自分で体験しに行く、その体験が礎となって、新しいプロジェクトが生まれています。
──体験をしてそこから考えていくのですね。ゲームを作り始めた当初からこのようなやり方をしていたのですか?
入社当時のナムコ開発は実体験重視でゲーム開発を行ってきました。しかし、それでも思い込みもあり企画内容にバイアスがかかります。当然、たくさんの失敗もしてきました。これまで100種類以上のゲームをつくり、売上が思わしくなかったゲームもたくさんつくってしまいました。売れている家庭用ゲーム機のまねたこともありましたが、どうもうまくいきませんでした。

当時、自分は『機動戦士ガンダム 戦場の絆』を担当し、試作段階でした。ドーム型スクリーンでガンダムを操作して、コンピューターが操作する敵とバトルをするゲーム内容でした。このときに、シールプリントのチームにいた同期から、絶対にユーザー調査をしたほうがいい、とアドバイスを受けます。「自分がイケると思った直感に頼っていた」と思っていた私にとっては、最初は乗り気がしなかったです。しかし、あまりに強く勧められるので、ユーザー調査をやってみることにしました。
ドーム型スクリーン自体は高評価だった一方で、一人で遊ぶのは飽きてしまう、といった反応がありました。そこで当時のゲームセンターではどこも実現していなかった「リアルタイム店舗間通信対戦」を実装することを決意。結果これが大きなヒットとなりました。そこからは、とにかくユーザーが求めているものを調べて、ゲームをつくるようになりました。
──ゲームづくり以外にもユーザーの視点を取り入れるのでしょうか?
もちろんです。ユーザーの視点は新規顧客を獲得するキャンペーンでも重要です。生活者はゲームのことを四六時中考えているわけではありません。生活の中には、仕事、睡眠、運動、食事などさまざまな要素があり、その一つとして、ゲームがあります。新しいユーザーを取り込んでいくためには、ゲームのことだけを発信していても、既存ユーザーにしか届きません。ほかのなにかと組み合わせていくことが必要です。そうすることで、これまでゲームに興味がなかった人たちをユーザーに取り込んでいくことが可能となります。
『釣りスピリッツ』をやったことがある人よりもやったことがない人の方が圧倒的に多い。だからこそ、新規ユーザーを取り込むことができれば、大きな成長につながります。単なるアーケードゲームの枠組みを超えて、食生活や食文化とつなげていくことが、ユーザーの拡大にも寄与するはず。そしてより多くの子どもたちに『釣りスピリッツ』を遊んでもらうことで、海の多様性についても伝えていけたらいいですね。
──インタビューの間も非常ににこやかにお話してくださった小山さん。ゲームのクリエイターという視点だけではなく、プロデューサーとしてどのようにゲームを広めていくのかまでお話を伺うことができました。本日はお話いただき、ありがとうございました。