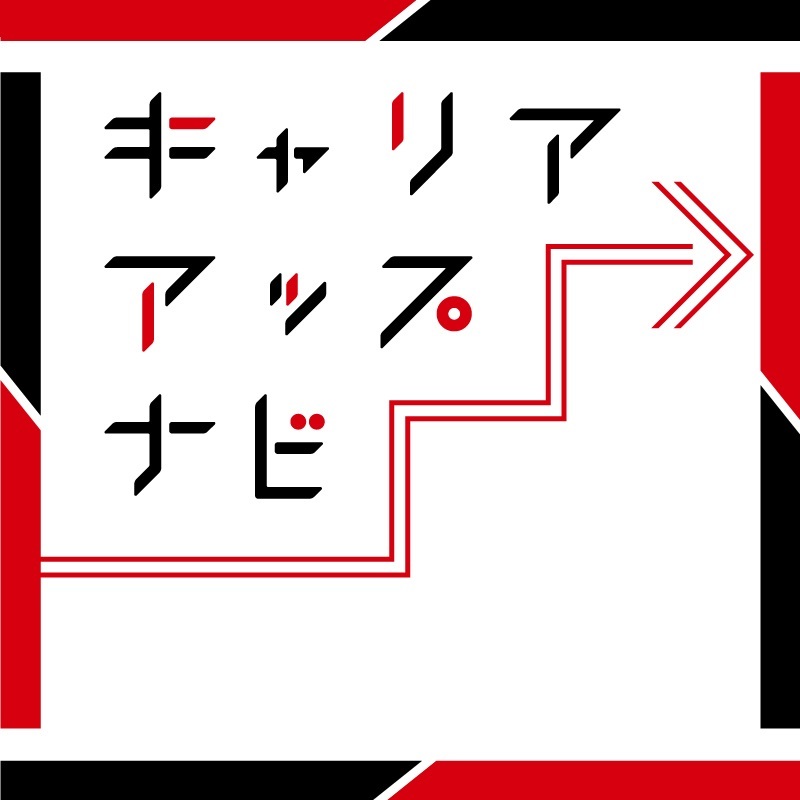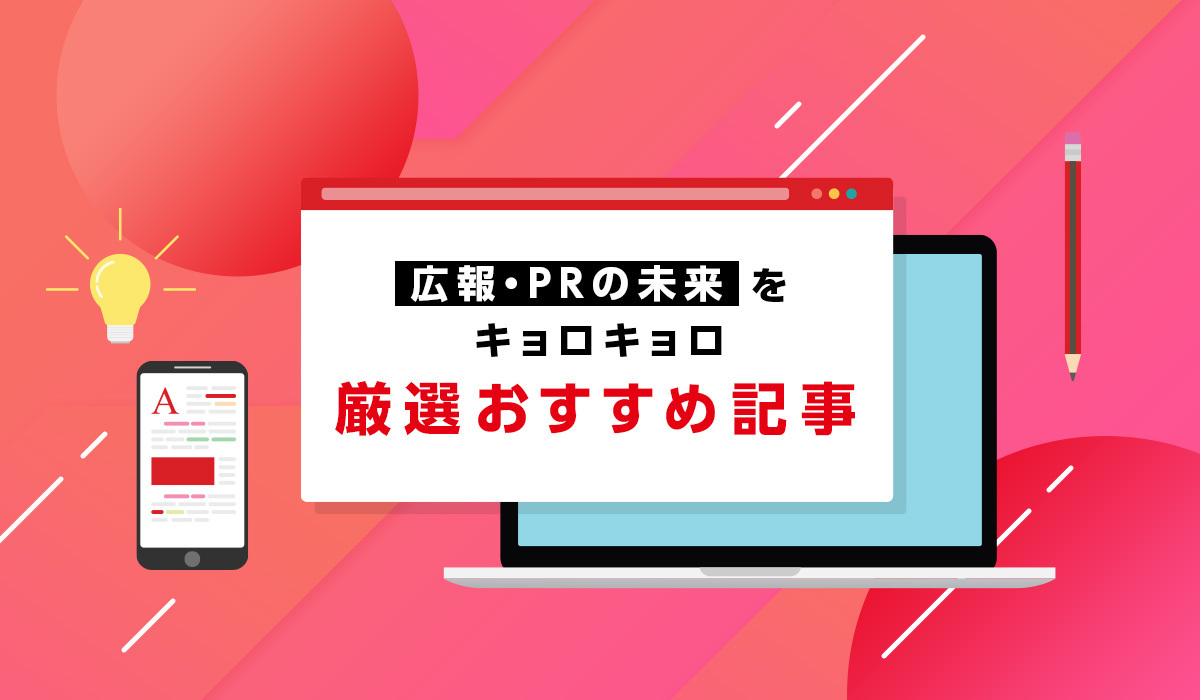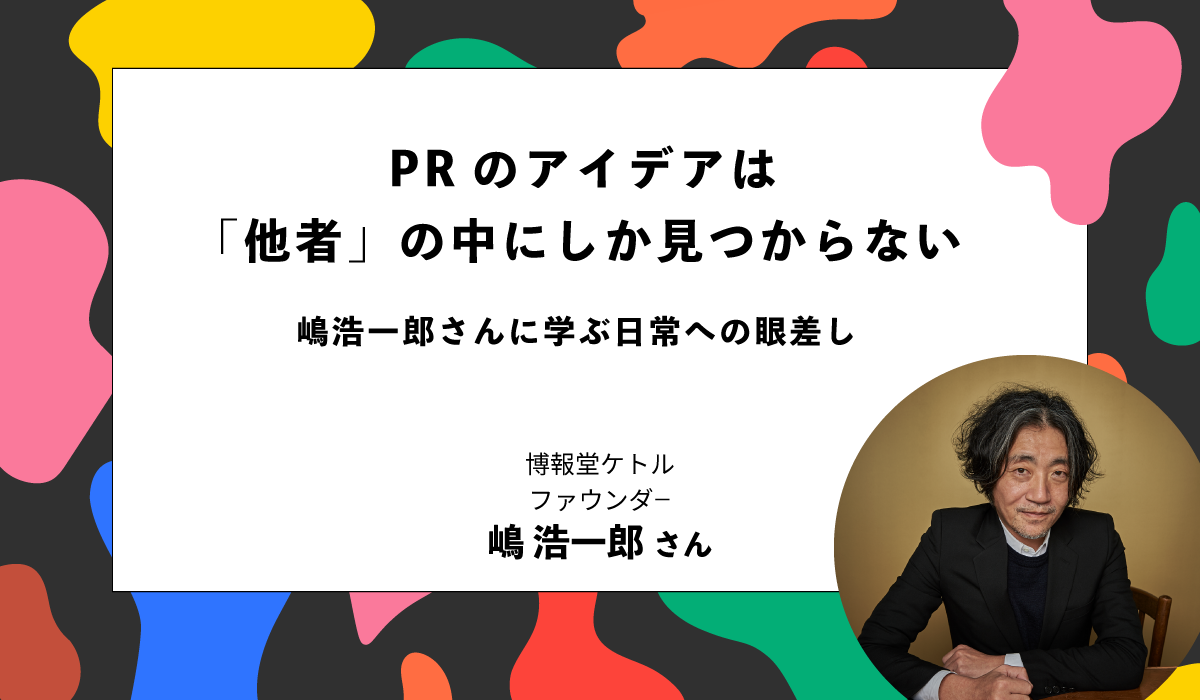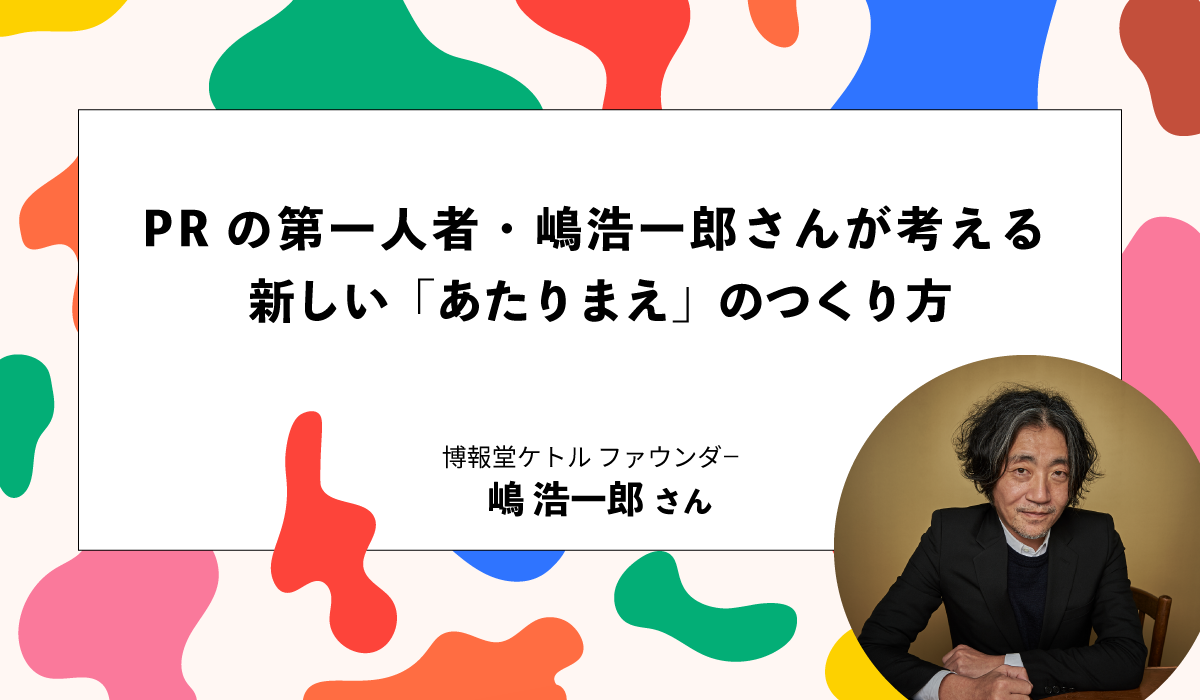Vol.57 目の前のことを頑張れる人にだけ次の扉は開かれる キャリアアップナビ
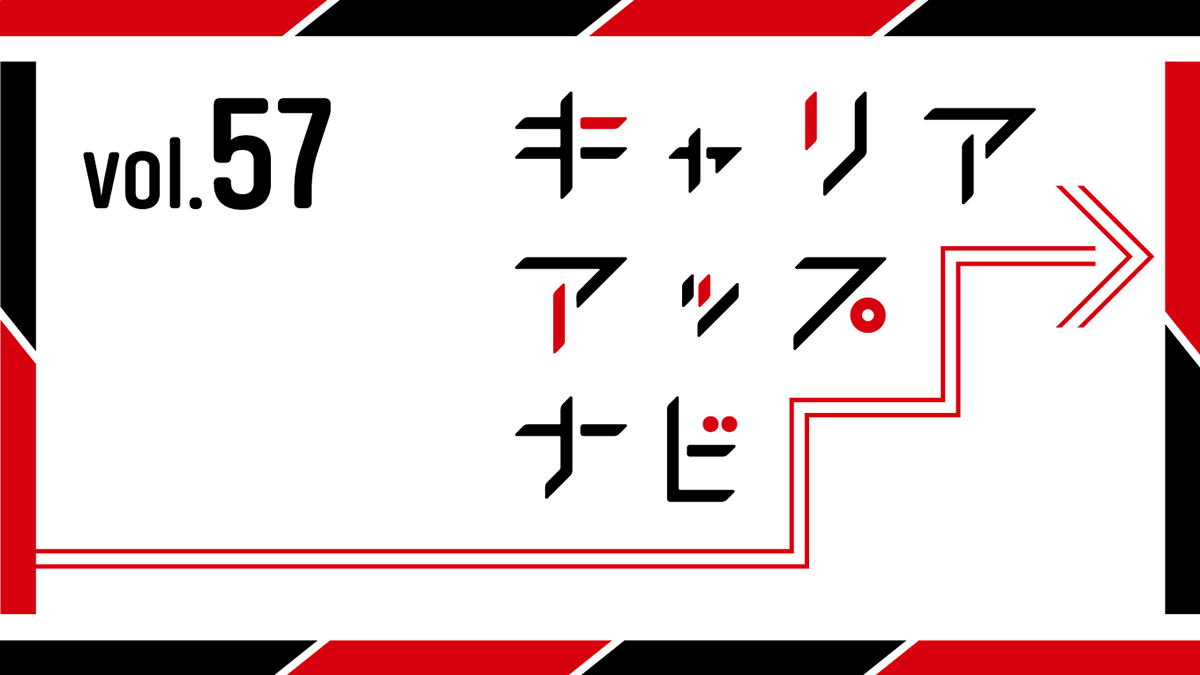
僕は小学生の頃からアルペンスキーをやっていましたが、高校時代にどうしても獲りたいタイトルがあって、高校3年生の時に大学受験を1年先送りにしました。そんな時、クラスメートから卒業アルバム制作委員を頼まれました。
元々写真を撮るのが好きだったこともあり、アルバムが完成した時には感激しましたね。それを見て、人の記憶に残るモノをつくりたいと思うようになり、就活では雑誌の編集者を目指しました。
でも、僕が大学を卒業した1996年は就職氷河期。特にマスコミ業界は厳しく、就活はうまくいきませんでした。
それでも諦め切れず、1年後に再挑戦するつもりで、スキーショップのアルバイトを始めました。偶然なのですが、ショップのオーナーが地元の埼玉新聞の元営業の方で、ある時、古巣の副社長と飲むからおいでと誘ってくれて。その副社長から「なぜ就職しないの?」と聞かれ事情を話したら、「すぐにうちの試験を受けなさい」と。季節は秋に差し掛かった頃。とんとん拍子に話が進み、半年遅れで入社することになりました。

1996年、埼玉新聞入社。整理部を経て翌年から運動部で記者生活をスタート。2000年に読売新聞東京本社に入社し、地方部宇都宮支局に配属。2006年、経済部に異動し、日銀サブキャップ等を務めた。2016年、日立製作所に入社。2017年にサイバー攻撃を受けた際は、情報収集とメディア対応に尽力した。2020年より広報部長、2022年より現職。
──読売新聞への転職の切符はどうつかんだのですか?
記者職として整理部に配属。翌年に運動部に異動し、2年が経った時、高校野球のキャップを命じられました。何十人もの記者の球場の配置などを取りまとめ、県の代表校が決まったら、甲子園に随行して取材します。運動部の若手記者の登竜門となる、なかなか大変な仕事でした。
翌春、お世話になったある高校の監督から突然呼び出され、読売新聞の中途採用試験を受けるように勧められたんです。野球部の父母会に読売の幹部がいて、「面白い記者がいたら紹介してほしい」と言われていたようで。転職など考えたこともなく断りましたが、監督の顔を立てる意味でも試験を受けたら、ご縁があって合格して転職を決めました。その時は、全国紙の運動部でメジャーリーグや欧州サッカーを取材したいという夢も膨らんでいました。
ところが、僕は地方部限定の採用だと知らずに入社してしまっていた。入社後に配属先の宇都宮支局長から「君は運動部には行けないよ」と言われてがく然としました。でも、腐っている暇はなく、毎日、朝刊と夕刊の2回の締め切りが来る。必死で取材に飛び回りました。
転機となったのは、2003年に起きた「足利銀行の破たん・一時国有化」。当時、僕は宇都宮から離れた通信部にいて重大さがピンときませんでした。けれど、キーパーソンとなる政治家に取材して経済への理解が深まるにつれて、これは自分が報じなければいけないと思うようになり、志願して宇都宮支局に戻してもらい、破綻にまつわる多くのスクープを書くことができました。
その姿勢が経済部の目にとまったのか、のちに異動を打診されることに。読売新聞の歴史のなかで、地方部から経済部へ異動したのは、僕が初めてだったと聞いています。
──そこからなぜ日立の広報になったのでしょうか。
2013年の秋、経済部デスクから「川村隆を徹底的に取材しろ」と指示を受けました。日立製作所の会長(当時)で、経団連次期会長の有力候補でした。僕はスクープをとるため、夜討ち朝駆けで川村会長を訪ね、ついにはワシントンDCまで追いかけました。結局、川村会長は経団連会長を固辞しますが、この時の縁で、日立の広報部長から転職を打診されました。
興味はあったものの、記者一筋の自分には無理だと尻込みしていました。そんな時に川村会長とお会いする機会があって、そこでこう言われたんです。「チャンスはみんなに平等に来るものじゃない。目の前にあるのならつかむべきだ」と。川村会長は転職のことはご存じありませんでしたが、その言葉に背中を押されました。

今は空前の転職ブームですよね。転職関連の広告を見ない日はないくらいです。でも僕は、転職ってそんなに気軽にするべきではないと思っています。
採用面接をしていると、川村元会長の言葉をよく思い出すんです。あれは、「目の前のことを一生懸命に頑張っている人にだけ、次の扉が開く」という意味だったんじゃないかと。逆に言えば、今を頑張れない人は、転職しても状況は簡単に好転しないということ。入社前の話と実態が違うなんてことは、どこの会社でも起こりうることですから。
理想と違うと思っても、どうかそこで、もう少しだけ踏ん張ってみてほしい。僕は就活に失敗して埼玉新聞に拾われましたし、2回の転職も自発的に決めたものではありません。誇れるキャリアではないと、ずっと思ってきました。しかし、振り返って思うのは、毎回、良いご縁に恵まれたということ。そういうご縁や転機をものにできる人は、今やるべきことを最後まで努力できる人なのではないかと思います。