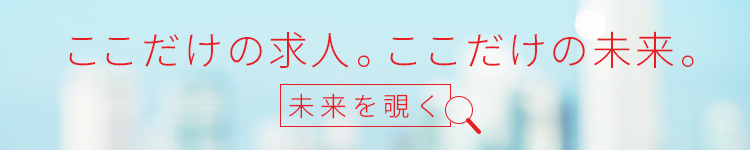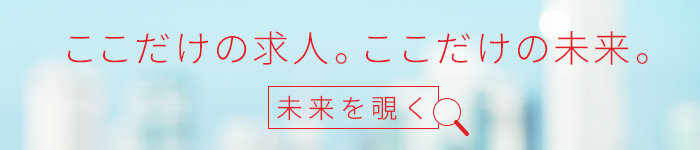「雑誌編集者は、雑誌編集しかできない」を変えたい Sansan Bill One事業部ブランドエクスペリエンス部 部長 ブランドエディター 小池真之介さん/エディター 塚原彩弓さん

編集者といえば、メディア業界のなかでキャリアを重ねていくイメージがありますが、最近は必ずしもそうではないようです。働き方を変えるDXサービスを提供する事業会社、Sansanの小池真之介(こいけしんのすけ)さんと塚原彩弓(つかはらあゆみ)さんは、ともに雑誌編集の経験をもつエディター。入社以来、そのバックグラウンドを活かし、Sansanのブランディングやマーケティング活動に貢献しています。「編集者の活躍の場は広い」と語るおふたりに、入社の経緯と現在の仕事について伺いました。
編集スキルは「使い勝手」がいい
──おふたりとも、Sansanに入る前は雑誌編集の仕事をされていたそうですね。塚原:新卒で出版社に入社して雑誌編集者として働いていたのですが、専門誌だったこともあり、もっと広い世界を見たいと思うようになりました。その後、クライアント企業のコンテンツマーケティングを支援する会社に移り、オウンドメディアの立ち上げ・運用支援やWebキャンペーンなどを手がけていました。
いろいろな業界の仕事に携わって、確かに世界は広がったものの、クライアントワークでは外部の人間には踏み込めない領域があると感じました。それがもどかしくなって、自分自身が事業会社に入って、編集者として働いてみたいなと思ったんです。

塚原彩弓さん
一時期、英語を使った業務を経験してみたくて、エンタメ系のメーカー企業で働いたことがあります。その会社では、編集とはまったく違う業務を担当しました。プロジェクトの進行管理や広報・宣伝、プロモーション企画の補助業務といった仕事でしたが、雑誌の企画や誌面をつくっていくのと同じ考え方やプロセスで仕事を進めてみたら、意外とうまくいったんです。
台割をつくったり、誌面のラフを描くように、企画や資料の構成を考えたり、誌面のラフを書いてデザイナーに伝えるのと同じようにつくりたいものを説明したり、校正作業のようにテキストを整理してみたら、仕事をうまく進められた。
その会社では、私が雑誌編集経験のバックグラウンドを持っていることが周りに知られると、だんだんいろんな仕事に巻き込んでもらえるようにもなりました。編集者のスキルや経験の使い勝手の良さを、私自身も実感するようになりました。

小池真之介さん
小池:Sansanに入社する前に出版社で再び編集者として働いたんですが、改めて出版社ではない環境で編集者としての経験を発揮したい、雑誌編集者が持っているスキルや能力の有用性を事業会社で示したいという気持ちが大きくなったからかなと思います。
Sansanが提供している名刺アプリ「Eight」を使い始めたときに衝撃と感動を覚えたからという理由もあって、Sansanに興味を持って。採用面接で仕事の進め方とか状況を聞いてみたら、どうにかできるかなって思える課題がたくさんあって、「めちゃくちゃ仕事ありそうだし、しばらくはやることに困らなそう」って思いました。
塚原:当時は、ということですよね(笑)。
小池:いやいや。会社や事業が成長と変化を繰り返す限り、どんどん新しい課題が出てきていると思いますよ。だからこそ、やることも尽きない。とはいえ、入社当初は、ここまで仕事が広がるとは思っていませんでしたけど(笑)。
塚原:担当するサービスのWebサイトやダウンロードコンテンツ制作は、定常的に担当する制作物です。その中で、サービス紹介資料をつくったり、顧客へのインタビュー記事をつくったりすることもあります。
でも、それだけではなく、展示会やイベントで配布するパンフレットや掲示物、ノベルティーの制作にも携わります。自社のプレゼンテーションをつくることに携わることもあります。また、担当するブランドで頻出する表現を整理して全社で使うテキスト表現のガイドラインとしてまとめて管理するようなこともしています。
小池:私は、自社のノベルティーとしてオリジナルレシピのクラフトビールをつくったり、オリジナルのアロマ、音声コンテンツをつくったこともあります。サービスブランドのコンセプトやメッセージの設計といった仕事もあります。制作物を制限するつもりはありませんし、目的に対して必要なら何をつくってもいいんです。もちろん、それをつくる理由や目的、得られる成果、費用対効果を踏まえて、しっかりと設計することは実現させるための大前提ではありますが。
エディターは、インハウスのクリエイターとして、最前線に立って高い熱量を持って物事に向き合うような近視眼的な視点と、「最初の読者」としてつくっているものを客観視する、物事を俯瞰するような視点の両方を求められると考えています。そこは編集者として身に付けさせてもらった感覚を応用できるかなと。また、台割や誌面構成は体験設計ですし、誌名やタイトルの考案はコンセプト設計、企画や見出しの執筆はプレゼンテーション、表記統一や校正はブランディングだと思います。Sansanのエディターが関われる仕事の広さは、編集者のスキルが活かせる物事の広さでもあるかなと思います。
【Sansanでは、エディター職を積極的に募集中です。詳細はこちら】
──小池さんは部門長だと思いますが、会社からはどういったところが評価されて、その職を任されているのでしょうか?
小池:マネジメントとしての役割とプレイヤーとしての役割は異なりますし、エディターとして何かをなしたから部長になったわけではないとは思います。ただ、マネジメントの業務でも「編集しているな」と思うことはあります。
編集は、目的や伝えたいことに対して、ベストなヒト、モノ、コトを集めて、ひとつのアウトプットとしてまとめる仕事だと思っています。ライター、フォトグラファー、デザイナー、時にはインタビュー先や監修者など、あるものをつくるために最適な要素を集めて、整理する。つまるところ、一番になれるような突出した何かを持っていなくてもいいとも思ってるんです。
ただ、その分応用が効く。目的があって、そのためにベストな組織、メンバー構成を考えて、誰がどこに立ってもらったらいいか、何をしてもらったらいいかを考えて、組織を編集する。組織の未来を考えるマネジメントにも通ずるところがあるのかなと思っています。

塚原:実はそうでもないんです。私自身、新卒で入社した出版社が、編集者がなんでもやる会社だったので。編集だけではなく、ライティングやインタビューをはじめ、進行管理、広告営業、印刷会社や出版取次とのやりとりなど、自分でやるのが当たり前でした。それで、「何をやってもいい」という環境に慣れていたのかもしれません。
2社目のマーケティング支援会社でも、肩書はコンテンツディレクターでしたが、プロジェクトマネジメントや営業の仕事もやっていました。その時々によって、向き合う対象はインタビュイーだったり、クライアント企業の課題だったりとさまざまでしたが、「まったく違う仕事をしている」という認識はありませんでした。
何の仕事をしていても、根本にあるのは、制作物を通して「読み手にとってわかりやすい形でメッセージを伝えて目的を達成すること」でした。そのために、対象への理解を深めて、デザイナーやライター、フォトグラファーといった、制作に関わる人たちの間に立ち、制作物に一本の筋を通す、共通の軸をつくるのは編集者の経験で培われたスキルだと感じていて、それは今も変わりません。
反対に、これまでと違いを感じた点は、ブランドの根幹やメッセージそのものを自分たちでつくることですね。インハウスのエディターならではの仕事で、最初は大変でした。でも、やりがいがありました。
──おふたりとも、編集という仕事を柔軟に捉えているからこそ、今の仕事につながっているのですね。編集者のキャリアについて、どうお考えですか。
小池:雑誌編集者でいえば、将来のキャリアを考えるときに、「次は何のメディアをやるか」「どんな本や記事をつくるか」と考える方も多いと思います。当社の採用面接に来た人の中にも、「新しいメディアをつくりたい」とか、「オウンドメディアをやりたい」とか、「こんな記事をつくりたい」とか、自身の能力を発揮する場を限定してしまっていると感じる方がいます。編集者として培ったスキルと経験、テクニックがあれば、もっといろんなことに挑戦できるのに、もったいないなと思ってしまいます。メディアや記事をつくること以外にも、編集者として培った能力や経験を発揮する場所がたくさんあることを、もっと多くの編集者の方に知ってもらいたいですね。
──ありがとうございました。
■編集部からのお知らせ
Sansanでのエディターのお仕事に興味をお持ちの方に向けて、小池さんと塚原さんにさらに詳しく伺いました。
詳細はこちら
(マスメディアンWebサイトに遷移します)