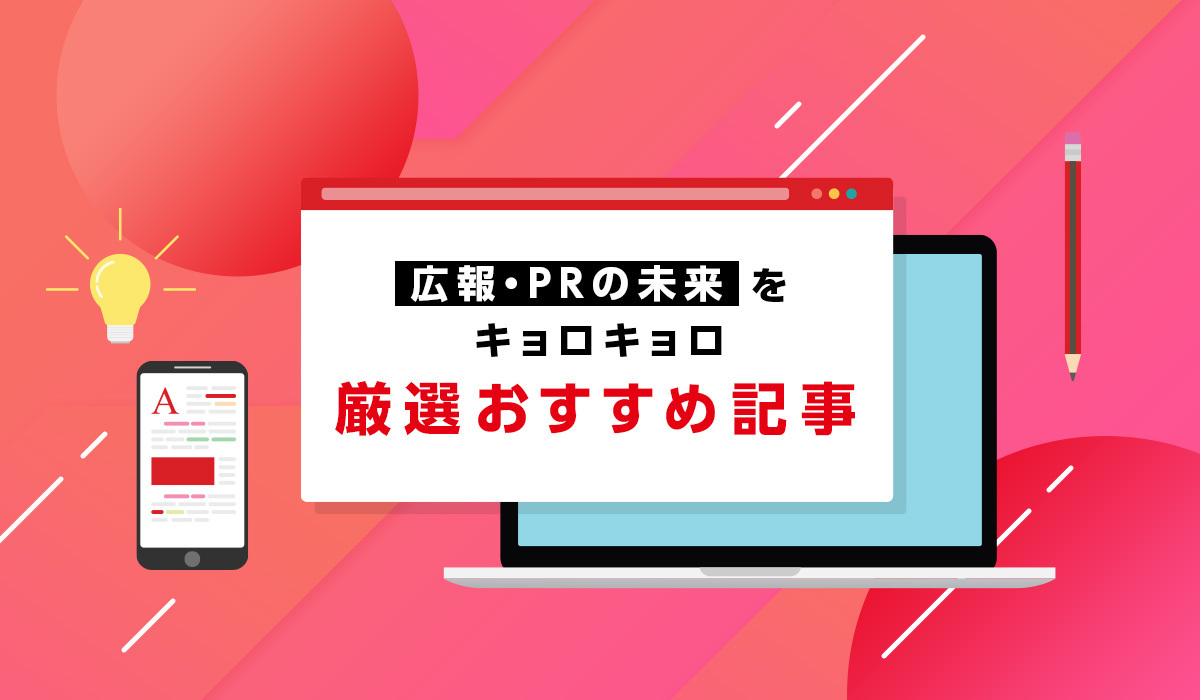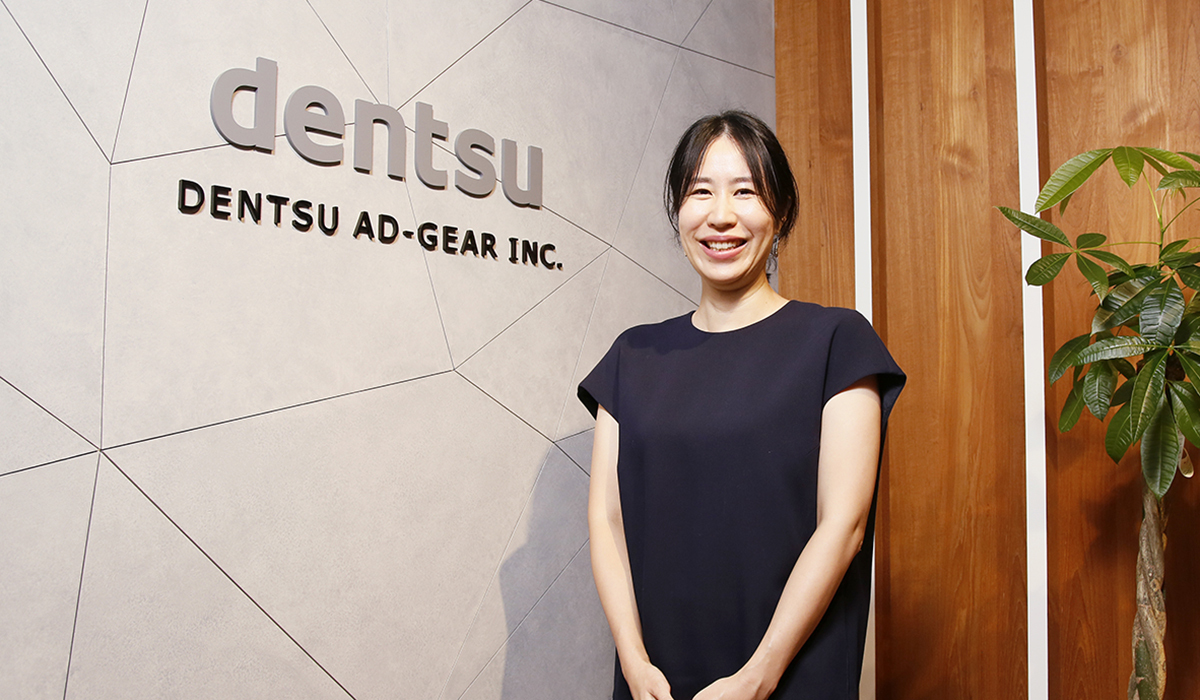求めていたのは、デザインの力で社会を変えられる場所 Accenture Song Droga5 アートディレクター 小出鯉子さん

アクセンチュアに転職して間もなく、住友金属鉱山「DOWN-LESS DOWN JACKET」を手掛けるなど、アートディレクターとして数々の実績を築いてきた小出鯉子さん。現在の活躍までには、デザインスキルを社会のために活かしきれないという葛藤や、やりたいことに気づかせてくれるきっかけとなった、オンライン診療サービス「Oops」での制作体験がありました。後編では、小出さんのこれまでのキャリアと、明るいデザインを生み出すユニークな発想法についてお聞きしました。
この記事は前後編です:前編はこちら
『私がアートディレクターとしてコンサルティング会社にいる理由』
そうなんです。デザイナーを意識し始めたのは高校生のとき、原研哉さんの本を読んだことがきっかけです。そして原さんに憧れて、教授を務めていた武蔵野美術大学の基礎デザイン学科に入学しました。基礎デザイン学科は、デザインの領域をグラフィック、プロダクト、ファッションなどと分けずに、「デザインとは何か」を考え、デザインの本質を学ぶ学科です。
特に面白かったのは、既成のプロダクトなどを再解釈して別の価値を付加する、「ファウンドオブジェクト」という授業です。たとえば、人は切り株に自然と座ってしまう。でも切り株は椅子としてデザインされたものではなく、人間が勝手に椅子として使用しているだけ。そのように人間が自然と想起して使用してしまうデザインを意図的につくれないのか、を探る授業でした。
また、原研哉さんのゼミに所属して、「Ex-formation ふたり」というテーマで卒業制作を行いました。生活におけるさまざまな場面では、友人、親子、恋人などの2人という人間関係が、頻繁に登場し語られます。しかし、その人間の最小構成単位であり、一番身近な「2人」という関係性について、知っているようで知らない情報がまだまだあるのではないかと考えて、それを制作物に表現しました。 ──デザインについて思考し続ける学生時代を過ごされて、卒業後は、広告制作会社や外資系広告会社で、アートディレクターとして実績を積まれました。
──デザインについて思考し続ける学生時代を過ごされて、卒業後は、広告制作会社や外資系広告会社で、アートディレクターとして実績を積まれました。
2013年に広告制作会社へ入社しました。主に販促ツールの企画制作を担当。通信会社の店頭施策や飲料メーカーのグラフィックなどを制作していました。
制作会社だったので業務量は多くて、大変なこともありました。頑張れたのは、尊敬するデザイナーの葛西薫さんの作品集に載っていた、下積み時代に制作したチラシのデザインを見たから。「葛西さんにも努力の時代があったんだ」と、自分を奮い立たせていましたね。今では当時の経験があって本当によかったと思います。
その後、アートディレクターとしてのキャリアを積むため、そして案件の幅を国内だけでなくグローバルまで広げたいと思い、2017年に外資系広告会社に転職。グローバルブランディング案件にも関わるようになり、ブランドフィルムやプロダクトのテレビCMなどに携わりました。
──2社目から外資企業となり、業種も制作会社から広告会社へと変わりましたが、どんな違いがありましたか。
まず、テレビCMやブランドフィルムキービジュアルやデジタルキャンペーンなど、ひとつのブランドやプロダクトに対して、包括的なクリエイティブを担当できるようになり楽しかったです。映像のディレクションは初めてでしたが、絵コンテや企画を書くのは漫画みたいで、子供の頃、漫画家になるためにしていた努力が活かされました。
ただ、言語の違いに苦労する場面はありました。社内やカウンターパートに海外の方が多い環境でしたが、私は英語を話せなかったからです。その反面、デザインの強さを実感する経験もありました。海外本社のクリエイティブディレクターとの打ち合わせで、デザイン案を見せたら「クールだね!」と言ってもらえたんです。英語のコピーは直訳してもいい日本語のコピーになるとは限りませんが、「いいデザイン」は共通なんだなって。
その後、広告業界がコロナ禍の波を受け、私のいた会社でも予算や案件がどんどん減って、すぐに結果が出る企画を求められるようになっていきました。自分が本当にやりたいことは何かと悩んでいたときに、元同僚が立ち上げた、オンライン診療サービス「Oops」を手伝ってほしいと頼まれたんです。それが私のキャリアの軸を変えるきっかけになりました。
Oopsは、世間的にネガティブに捉えられがちで、人には話しにくい体の悩みを、オンラインで気軽に相談できるという診療サービスです。ED診療「Oops LOVE」をはじめ、男性AGA診療「Oops HAIR」、ピル処方「Oops WOMB」などのサービスを展開しています。 私はブランド全体のクリエイティブディレクションを手伝い、パッケージデザインからネーミングまで携わりましたが、0から1でブランドをつくる体験が本当に楽しくて。自分のデザインやアートディレクションのスキルを、広告だけではなくブランドづくりまで活かせたら、もっと楽しいかもと思ったんです。それでそのような環境を探していったら、たどり着いたのがアクセンチュアでした。
私はブランド全体のクリエイティブディレクションを手伝い、パッケージデザインからネーミングまで携わりましたが、0から1でブランドをつくる体験が本当に楽しくて。自分のデザインやアートディレクションのスキルを、広告だけではなくブランドづくりまで活かせたら、もっと楽しいかもと思ったんです。それでそのような環境を探していったら、たどり着いたのがアクセンチュアでした。
Oopsはその後、2022年にPentawardsで金賞、2024年にiFデザイン賞で金賞、D&ADでWood Pencilと、3つのデザインアワードを受賞することができました。
──アクセンチュアでは、NPOのクリエイティブ支援にも関われるのだとか。
アクセンチュアは、コーポレート・シチズンシップ(企業による社会貢献活動)の一環として、プロボノ活動を行っています。私も、もともとソーシャルグッドに興味があり、参加しました。
シングルマザーの自立を支援する「グラミン日本」では、「シングルマザーってかわいそう」という無意識のネガティブなパーセプションを「彼女たちの人生って濃いよね」とポジティブな捉え方に変える、「濃ぃヒー」というドネーション活動に携わりました。コーヒーを一杯買うと、一部がグラミン日本へと寄付される仕組みです。この案件では、寄付のシステムから、キービジュアルやコーヒースリーブのデザインまで、企画から実際に生活者の手に渡るモノまで携わることができ、とてもやりがいがありました。
広告は掲出期間が決まっていますよね。オリエンがあって、3カ月後に納品して、数週間CMが流れOOHが掲出され、それで役目は終わり。私のつくったデザインも短期間で消費されてしまう。コンサルティング会社に入社したことで、社会実装により近いデザインに携われることに非常にやりがいを感じています。特に「Oops WOMB」や「濃ぃヒー」のような、女性をエンパワーするデザインはこれからも積極的に手掛けていきたいです。
仕事でも個人活動でも、明るいデザインで社会をよくしたい、デザインにはその力があるって、私は本気で思っています。そのためには、バイブスの合う仲間と楽しく制作できる環境も大事ですね、その方が明るいデザインが生まれますから。 ──クリエイティブの技術や表現が日々変化する今。未来のデザイナーやアートディレクターに求められる役割は何だと思いますか。
──クリエイティブの技術や表現が日々変化する今。未来のデザイナーやアートディレクターに求められる役割は何だと思いますか。
これまではアイデアのビジュアライズが、デザイナーの仕事でした。でも今は、ビジュアライズは生成AIにもできてしまう時代になりました。それなら私たちデザイナーは、デザインがまとう空気感までつくるべきだと考えています。
「Oops」はED治療薬ですが、「三宿にいるスケーターの男の子が持っていても嫌じゃない空気感」をゴールにしていて。空気感とは、言語化できない、デザインからどうしてもはみ出しちゃう部分みたいなもののことです。AIは「正解」はつくれるかもしれない。でも私は、「正解」に、私がいいなと思う「チャーミング」や「可愛い」を足していく。そうやってデザインの放つ空気まで、コントロールできるアートディレクターでいたいです。
──ビジュアルのパワーを武器に、企業やブランド、そして社会と向き合い続ける小出さん。そのお話は「言葉を必要としないビジュアルこそ、性別や世代、言語や国境を軽々と飛び越えて、まとう空気まで世の中に届けることができるのだ」と、こちらをどんどんと期待させてくれるようでした。小出さんの生み出す明るいデザイン、そして小出さん自身にも、溢れるパワーを感じる取材でした。本日はありがとうございました。

『私がアートディレクターとしてコンサルティング会社にいる理由』
広告だけじゃなく、ブランドからデザインしたい
──子どもの頃はデザイナーではなく、漫画家を目指されていたそうですね。そうなんです。デザイナーを意識し始めたのは高校生のとき、原研哉さんの本を読んだことがきっかけです。そして原さんに憧れて、教授を務めていた武蔵野美術大学の基礎デザイン学科に入学しました。基礎デザイン学科は、デザインの領域をグラフィック、プロダクト、ファッションなどと分けずに、「デザインとは何か」を考え、デザインの本質を学ぶ学科です。
特に面白かったのは、既成のプロダクトなどを再解釈して別の価値を付加する、「ファウンドオブジェクト」という授業です。たとえば、人は切り株に自然と座ってしまう。でも切り株は椅子としてデザインされたものではなく、人間が勝手に椅子として使用しているだけ。そのように人間が自然と想起して使用してしまうデザインを意図的につくれないのか、を探る授業でした。
また、原研哉さんのゼミに所属して、「Ex-formation ふたり」というテーマで卒業制作を行いました。生活におけるさまざまな場面では、友人、親子、恋人などの2人という人間関係が、頻繁に登場し語られます。しかし、その人間の最小構成単位であり、一番身近な「2人」という関係性について、知っているようで知らない情報がまだまだあるのではないかと考えて、それを制作物に表現しました。

2013年に広告制作会社へ入社しました。主に販促ツールの企画制作を担当。通信会社の店頭施策や飲料メーカーのグラフィックなどを制作していました。
制作会社だったので業務量は多くて、大変なこともありました。頑張れたのは、尊敬するデザイナーの葛西薫さんの作品集に載っていた、下積み時代に制作したチラシのデザインを見たから。「葛西さんにも努力の時代があったんだ」と、自分を奮い立たせていましたね。今では当時の経験があって本当によかったと思います。
その後、アートディレクターとしてのキャリアを積むため、そして案件の幅を国内だけでなくグローバルまで広げたいと思い、2017年に外資系広告会社に転職。グローバルブランディング案件にも関わるようになり、ブランドフィルムやプロダクトのテレビCMなどに携わりました。
──2社目から外資企業となり、業種も制作会社から広告会社へと変わりましたが、どんな違いがありましたか。
まず、テレビCMやブランドフィルムキービジュアルやデジタルキャンペーンなど、ひとつのブランドやプロダクトに対して、包括的なクリエイティブを担当できるようになり楽しかったです。映像のディレクションは初めてでしたが、絵コンテや企画を書くのは漫画みたいで、子供の頃、漫画家になるためにしていた努力が活かされました。
ただ、言語の違いに苦労する場面はありました。社内やカウンターパートに海外の方が多い環境でしたが、私は英語を話せなかったからです。その反面、デザインの強さを実感する経験もありました。海外本社のクリエイティブディレクターとの打ち合わせで、デザイン案を見せたら「クールだね!」と言ってもらえたんです。英語のコピーは直訳してもいい日本語のコピーになるとは限りませんが、「いいデザイン」は共通なんだなって。
その後、広告業界がコロナ禍の波を受け、私のいた会社でも予算や案件がどんどん減って、すぐに結果が出る企画を求められるようになっていきました。自分が本当にやりたいことは何かと悩んでいたときに、元同僚が立ち上げた、オンライン診療サービス「Oops」を手伝ってほしいと頼まれたんです。それが私のキャリアの軸を変えるきっかけになりました。
もっと社会実装に近いところでデザインの力を使いたい
──キャリアの転換点になったOopsについて詳しく教えてください。Oopsは、世間的にネガティブに捉えられがちで、人には話しにくい体の悩みを、オンラインで気軽に相談できるという診療サービスです。ED診療「Oops LOVE」をはじめ、男性AGA診療「Oops HAIR」、ピル処方「Oops WOMB」などのサービスを展開しています。

Oopsはその後、2022年にPentawardsで金賞、2024年にiFデザイン賞で金賞、D&ADでWood Pencilと、3つのデザインアワードを受賞することができました。
──アクセンチュアでは、NPOのクリエイティブ支援にも関われるのだとか。
アクセンチュアは、コーポレート・シチズンシップ(企業による社会貢献活動)の一環として、プロボノ活動を行っています。私も、もともとソーシャルグッドに興味があり、参加しました。
シングルマザーの自立を支援する「グラミン日本」では、「シングルマザーってかわいそう」という無意識のネガティブなパーセプションを「彼女たちの人生って濃いよね」とポジティブな捉え方に変える、「濃ぃヒー」というドネーション活動に携わりました。コーヒーを一杯買うと、一部がグラミン日本へと寄付される仕組みです。この案件では、寄付のシステムから、キービジュアルやコーヒースリーブのデザインまで、企画から実際に生活者の手に渡るモノまで携わることができ、とてもやりがいがありました。
仕事でも個人活動でも、明るいデザインで社会をよくしたい、デザインにはその力があるって、私は本気で思っています。そのためには、バイブスの合う仲間と楽しく制作できる環境も大事ですね、その方が明るいデザインが生まれますから。

これまではアイデアのビジュアライズが、デザイナーの仕事でした。でも今は、ビジュアライズは生成AIにもできてしまう時代になりました。それなら私たちデザイナーは、デザインがまとう空気感までつくるべきだと考えています。
「Oops」はED治療薬ですが、「三宿にいるスケーターの男の子が持っていても嫌じゃない空気感」をゴールにしていて。空気感とは、言語化できない、デザインからどうしてもはみ出しちゃう部分みたいなもののことです。AIは「正解」はつくれるかもしれない。でも私は、「正解」に、私がいいなと思う「チャーミング」や「可愛い」を足していく。そうやってデザインの放つ空気まで、コントロールできるアートディレクターでいたいです。
──ビジュアルのパワーを武器に、企業やブランド、そして社会と向き合い続ける小出さん。そのお話は「言葉を必要としないビジュアルこそ、性別や世代、言語や国境を軽々と飛び越えて、まとう空気まで世の中に届けることができるのだ」と、こちらをどんどんと期待させてくれるようでした。小出さんの生み出す明るいデザイン、そして小出さん自身にも、溢れるパワーを感じる取材でした。本日はありがとうございました。