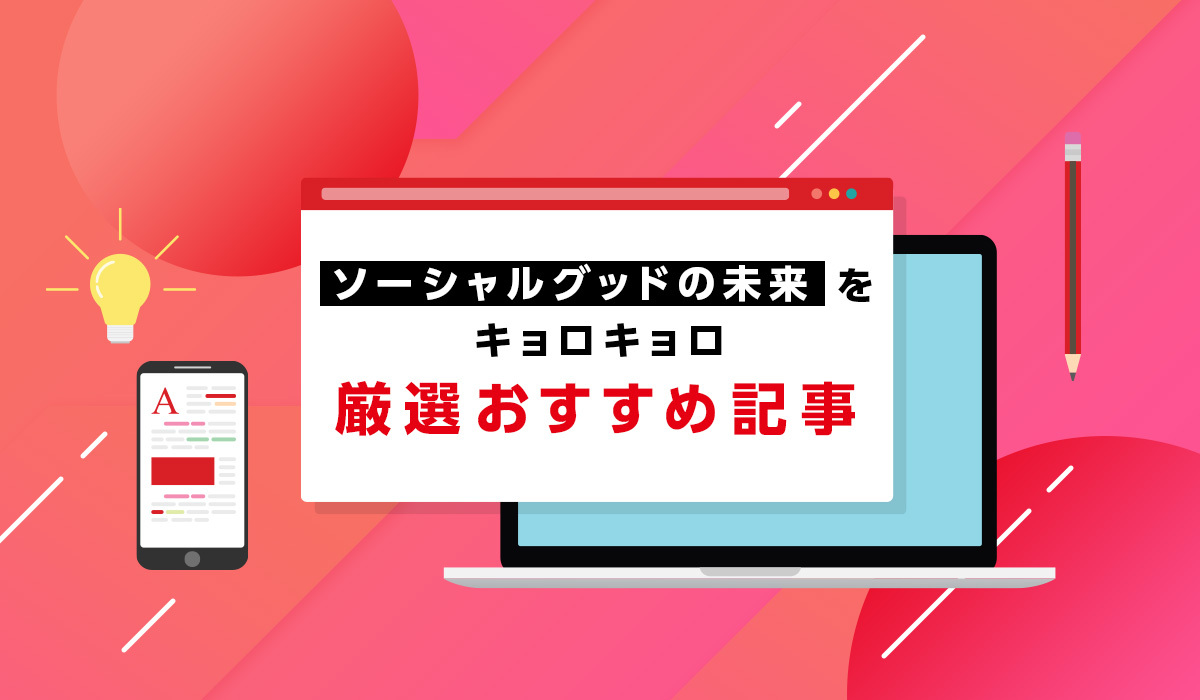出汁は世界を救う! 旨味を探求するフードテックプレイヤーによる対談 椎茸祭 代表取締役 竹村賢人さん、UMAMI Lab 主宰/REDD CEO 望月重太朗さん

人の味覚を構成する甘味、酸味、塩味、苦味に並び、5つ目の基本味に位置する「うま味」。出汁の「うま味」を活かした和食への関心は、いま世界的に高まっています。今回advanced by massmedianでは「食の未来」を探るべく、別々のアプローチで日本の出汁を世界に広めている担い手にお話を伺います。
日本の伝統的な出汁に世界各国の食材やお酒をブレンドすることで、その土地ならではの「うま味」を発見する、移動式のポップアップ出汁ラボラトリーUMAMI Lab。そして、菜食主義やビーガンの方でも安心して飲める椎茸などの素材から抽出した精進出汁を製造販売する椎茸祭。UMAMI Lab主宰の望月重太朗さん(写真右)と椎茸祭の代表取締役の竹村賢人さん(写真左)の対談を実現しました。実は二人ともWeb・IT業界出身者。それが今は、“うま味・出汁”に注目して、活動しています。うま味に注目したはなぜか、どのような和食の未来を描いているのかなどについてお聞きしてきました。
日本の伝統的な出汁に世界各国の食材やお酒をブレンドすることで、その土地ならではの「うま味」を発見する、移動式のポップアップ出汁ラボラトリーUMAMI Lab。そして、菜食主義やビーガンの方でも安心して飲める椎茸などの素材から抽出した精進出汁を製造販売する椎茸祭。UMAMI Lab主宰の望月重太朗さん(写真右)と椎茸祭の代表取締役の竹村賢人さん(写真左)の対談を実現しました。実は二人ともWeb・IT業界出身者。それが今は、“うま味・出汁”に注目して、活動しています。うま味に注目したはなぜか、どのような和食の未来を描いているのかなどについてお聞きしてきました。
──本日はお忙しい中、ありがとうございます。望月さんの持参いただいた壺のようなものが気になるのですが、こちらは一体なんでしょうか?
望月:ワイン用のカラフェなのですが、これにタイプの違う出汁を入れて、日本酒をブレンドして出汁割り酒を提供しています。このような見た目で提供されると「なんですか?」と関心を持ってもらえるじゃないですか。だからカラフェを使っています。実際に、米・オースティンで開催されたSXSW 2019の食をテーマにしたイベントで、海産物をベースにした出汁「Dive into the Sea, 1908」と、ビーガン向けの野菜ベースの出汁「Feel of the Earth, 2045」をサーブしたのですが、とても反響が良かったです。 ──確かに興味を惹きますね。ちなみに“Dive into the Sea, 1908”など面白いネーミングですね。どういった意味なのでしょうか?
──確かに興味を惹きますね。ちなみに“Dive into the Sea, 1908”など面白いネーミングですね。どういった意味なのでしょうか?
望月:「Dive into the Sea, 1908」は「一口飲むと海にダイブする感覚になれる1908年からのストーリー」という意味です。昆布から抽出されたうま味成分のグルタミン酸は、東京帝国大学(現:東京大学)の池田菊苗教授によって発見されました。そしてその後、「グルタミン酸を主要成分とする調味料製造法」に関する特許登録されたのが1908年だから、このネーミングにしました。もう一方の「Feel of the Earth, 2045」は、廃棄する予定の野菜や調理後に捨てられる部分のみから抽出した出汁で、「地球の味を感じるストーリー」を表しています。また2045年には人工知能が人間を超えるシンギュラリティに到達するといわれており、さらには深刻な食糧危機が訪れるという議論もあります。だからこそ、食糧危機がきても、野菜くずなどを煮詰めるだけで美味しいスープをつくることができるというメッセージが込められています。
カラフェにしても、ネーミングにしても、われわれが知っていると思い込んでいる“出汁”や“食糧危機”をまったく違う確度から解釈して、相手の興味関心を刺激していくストーリーをプレゼンテーションしています。この手法は、これまでの僕のキャリアで一貫して取り組んできたものです。
──確かにこのカラフェを通して出汁を提供されながら、こういったストーリーを聞くと、理解度が深まりますね。当事者意識を持つきっかけとなる、良いインターフェースのように感じました。このような手法を一貫して実践してきたということですが、望月さんのこれまでのキャリアについて簡単にお話いただけますか?
望月:まさにインターフェースにまつわる仕事にずっと携わってきました。2003年に博報堂アイ・スタジオに入社し、デジタルを活用したプロモーションの企画立案や実制作を行い、2014年からは博報堂アイ・スタジオ内のR&D部門であるFuture Create Labで、クリエイティブと最新テクノロジーを組み合わせたプロトタイプを開発してきました。
いま取り組んでいるUMAMI Labもその地続きにあって、ある意味“食のインターフェースを良くしたい”、“新しい食のインターフェースを生み出したい”という思いからスタートしています。 ──そのように思ったきっかけはなんだったのでしょうか?
──そのように思ったきっかけはなんだったのでしょうか?
望月:子どもが生まれて、「安全で栄養のあるご飯を食べて育ってほしい」と思ったことが一番のきっかけです。化学調味料を使わずに「いいお出汁を飲んでほしい」という思いから、鰹節や昆布から出汁を引き始めました。その過程の素材選びから加工・提供までのプロセスが、これまで取り組んできたデザイン工程と同じという面に気づき、どんどんハマっていきました。
あとプロトタイプ開発のサイクルが食は速くて、それも魅力的ですね。これまでの制作物と違って、開発から消費までのサイクルが超短期な構造は開発者にとっては動きやすかったです。それもいまフードテックが注目されている理由の一つだと思います。
──開発スパンの速さも開発者を引き寄せる要因なのですね。竹村さんは2017年に椎茸祭を創業していますが、きっかけはなんだったのでしょうか?
竹村:私の当時の彼女(編集部注、現在は妻)がベジタリアンで、肉や魚を食べられなかったことが直接的なきっかけです。肉や魚を食べられないので、キノコ類でうま味を出すという精進料理的な考えです。このため望月さんと同じで身近な経験からですね。
──食は生活に密接に関係していますからね。竹村さんのキャリアも、望月さんと近しい業界ですよね。
竹村:そうですね。私は2010年にNTTコミュニケーションズに新卒入社したのですが、1年で退職してインドへ移住してプログラマーをしていました。インドは人口の40%の人がベジタリアンで、それなら自分も試してみようと実践してみました。肉を食べない生活を続けるともちろん食べたくなるのですが、肉を食べたい欲求を抑えるほどのうま味がキノコ類にはあることを発見しました。これが最初のきっかけです。 ──それで椎茸祭を起業したのでしょうか?
──それで椎茸祭を起業したのでしょうか?
竹村:いえ、すぐに起業をしたわけではありません。もともと大学生のころから、いつか起業しようと思いつつ、10年以上の月日が流れてしまっていました。2013年に日本に帰国して、デジタルアート集団「チームラボ」に入社したことが、一番の転機になりました。
──チームラボに入社したことが、椎茸祭を起業するきっかけになったのですか。どういうことでしょう?
竹村:チームラボのデジタルアートで、鑑賞者が自分のほかにいることで一人で見るよりもより綺麗に見えるような作品があります。“自分と他人”、“自分とアート”の境目をなくす「ボーダレス」な理念が好きで。人口増加が予想されるインドでは、多くの人が宗教上の理由で肉や魚を食べられません。しかし、こうした人でも、キノコや野菜のうま味成分を凝縮された出汁があれば、ボーダレスに美味しさを分かち合えます。さらに調理という垣根をなくすために、お湯で溶かせば誰でも美味しいスープが飲める形状にしようと思い、oh!dashiを開発しました。 ──そういった思いがあったのですね。竹村さんの「垣根をなくす」という考え方は、望月さんの「食のインターフェースを良くする」活動に通じるところがあるように感じます。
──そういった思いがあったのですね。竹村さんの「垣根をなくす」という考え方は、望月さんの「食のインターフェースを良くする」活動に通じるところがあるように感じます。
竹村:椎茸祭は出汁を世界中に日常に根ざす形で広めることを目指しています。望月さんのようにプロセスを設計して、食の楽しさを演出することは、主体的なものの延長にあると思っていて。私たちはまず、主体よりも客体、より多くの人に届けるために、ユーザーインターフェースを工夫して、世界のさまざまな国で出汁文化の普及をしていきたいと思っています。
望月:僕はどちらかというと、プロセスのエンタメ化ですね。強烈な体験を提供していくことを目指しています。例えば、インスタントコーヒーを飲んでいる人も、ハンドドリップコーヒーやサイフォン式コーヒーを体験すると、自分でもやってみたいと思うじゃないですか。この考えをうま味でも取り込めないかなと。 竹村:違う思想ながら、“出汁・うま味”に対して別々にアプローチしている感じですね。
竹村:違う思想ながら、“出汁・うま味”に対して別々にアプローチしている感じですね。
望月:僕も竹村さんもWeb・デジタル業界出身で、扱う素材は変わりましたが、いままで積み上げてきたデザインやエンジニアリングを駆使して、食べる人にとって体験価値の高いユーザーインターフェースを提供しているんです。
僕は現在、UMAMI Labとは別にREDDという会社を起業し、代表取締役を務めています。社名は、Research/Education/Design/Developmentの頭文字をとっており、世の中を知った上で、プロトタイプを設計・開発する会社です。ここで重要なのはEducation(教育)。プロトタイプをつくることで蓄積されたナレッジを未来に引き継ぎ、新しい価値を創造する仲間を増やし、オープンイノベーションを形成していくべきだと考えています。そうすることで、本業や副業を超えたギルド型のコミュニティが生まれ、新たなプロダクトが生まれるかもしれないなと。
──お二人が協業する未来があるかもしれないわけですね。楽しみです! では話を変えまして、フードテック関連はこの先どうなっていくと思いますか?
望月:昨年オランダに、空きビルを貸し切って各階を農場にする、いわゆるヴァーティカルファーミング(垂直農法)を見学しました。街のレストランやカフェで淹れたコーヒーのカスを堆肥にしてキノコを栽培していたり、別フロアではバイオフィルターで水質管理された水槽があり、そこでは淡水魚が養殖されたりしていました。また水耕栽培でハーブやトマトも栽培しているのですが、フロア内に益虫やミツバチを放って生態系のバランスをとることで無農薬栽培を可能にしています。このヴァーティカルファーミングのシステムを世界各国に技術提供し、その売上金をさらなる研究開発に再投資しています。まさに循環型経済システムとサスティナビリティ(持続可能性)をビル一棟内で実践しているわけです。いままで農業は広大な大地に限られていましたが、このような技術が発達することで、空きビルなどの未使用空間を有効活用、果てには宇宙空間の農地化や深海の水耕プラント化が実現するかもしれません。そのためには、妄想だけでなくプロトタイプを先んじてつくっていきたいですね。
 竹村:東京のような人口の一極集中しているエリアでは、特に垂直農法の可能性は大きいですよね。今は人口の多い東京に対して、周縁部の県から作物を輸送しているわけですが、それよりも、消費地の近くで必要なものを必要な分だけ栽培するほうが効率はいい。東京はとても狭くて、農地は多くないので、垂直農法などを取り入れることで都市農業そのものが変わるチャンスになりそうですね。
竹村:東京のような人口の一極集中しているエリアでは、特に垂直農法の可能性は大きいですよね。今は人口の多い東京に対して、周縁部の県から作物を輸送しているわけですが、それよりも、消費地の近くで必要なものを必要な分だけ栽培するほうが効率はいい。東京はとても狭くて、農地は多くないので、垂直農法などを取り入れることで都市農業そのものが変わるチャンスになりそうですね。
──最後に“食の未来”について、お二人から意見をお聞きしたいと思います。
望月:日本には古来より出汁によって素材本来のうま味を引き出す食文化がありましたが、うま味の受容体が舌にあると科学的に証明されたのは2000年以降なんです。つまり世界的にうま味が理解されるようになったのは最近のことなのです。そのなかで日本は古くからうま味に対するノウハウを蓄積してきました。それを発展させる未来が来るように思います。例えばうま味をベースにした料理は、糖質や脂質を抑えても美味しく感じるため、成人病の予防に効果的といわれています。健康への関心はますます高まる中で、出汁やうま味も比例して注目されるでしょうね。
竹村:心が健康な状態である“リラックス”の一番しっくりくる和訳は、”息抜き“だと思っています。湯船に浸かるときや美味しい出汁を飲んだときホッと一息つけますよね。こういった呼吸という動作とともに風味を感じます。 望月:確かに風邪を引くとご飯が不味く感じるのは、風味を感じなくなるからですよね。うま味だけではなくて、風味や食感、温度も重要な要素といえます。あともう一つ、日本食の特徴は発酵と熟成。これも忘れてはいけないですね。
望月:確かに風邪を引くとご飯が不味く感じるのは、風味を感じなくなるからですよね。うま味だけではなくて、風味や食感、温度も重要な要素といえます。あともう一つ、日本食の特徴は発酵と熟成。これも忘れてはいけないですね。
竹村:腸内で消化を促す菌も重要ですよね。けれども、菌の90%以上はいまでもよくわかっていないみたいなんです。昔、寿司職人の10年の修行不要説がネットで議論されていましたが、別の味方もあるなと思っています。寿司職人は10年ほどの修行で、ある程度最適な菌を手の環境で構築するのではないかと最近思い始めました。今後は寿司職人の握る手にいるべき常在菌や、一緒に口にする木の器にいるべき常在菌などが科学的に解き明かされ、本当の美味しさ料理、さらには未病につながる料理が見える化されてくるのではないかと思っています。
望月:見えなかったものを可視化するテクノロジーは確かに実現しますね。あとはさまざまなうま味調味料が流通したことで均一化されてしまった味に対する揺り戻しが来ると予想しています。音楽でもアートでもその潮流が見られますが、食でも“ゆらぎ”を許容する社会が訪れる。うま味調味料によって均一化してしまった家庭の味、おふくろの味が、天然成分の出汁によって多様性が取り戻される。そうなると家庭料理のベースアップが起きて、価値も高まります。一流のシェフだけでなく、家庭料理をつくるお母さんやお父さんがプレイヤーとして参入するとますます面白くなっていくような気がします。日本には世界でも有数の発酵と熟成の文化とテクノロジーがあります。現状はプレイヤーも少ないですが、ここにチャンスがあると思います。 ──食のインターフェース、宇宙空間の農地化や深海の水耕プラント化、はたまたテクノロジーによる発酵・熟成の可視化と、フードテックにまつわるさまざまな可能性が議論されました。食の未来を切り開くお二人による刺激的なお話ありがとうございました。
──食のインターフェース、宇宙空間の農地化や深海の水耕プラント化、はたまたテクノロジーによる発酵・熟成の可視化と、フードテックにまつわるさまざまな可能性が議論されました。食の未来を切り開くお二人による刺激的なお話ありがとうございました。

望月:ワイン用のカラフェなのですが、これにタイプの違う出汁を入れて、日本酒をブレンドして出汁割り酒を提供しています。このような見た目で提供されると「なんですか?」と関心を持ってもらえるじゃないですか。だからカラフェを使っています。実際に、米・オースティンで開催されたSXSW 2019の食をテーマにしたイベントで、海産物をベースにした出汁「Dive into the Sea, 1908」と、ビーガン向けの野菜ベースの出汁「Feel of the Earth, 2045」をサーブしたのですが、とても反響が良かったです。

望月:「Dive into the Sea, 1908」は「一口飲むと海にダイブする感覚になれる1908年からのストーリー」という意味です。昆布から抽出されたうま味成分のグルタミン酸は、東京帝国大学(現:東京大学)の池田菊苗教授によって発見されました。そしてその後、「グルタミン酸を主要成分とする調味料製造法」に関する特許登録されたのが1908年だから、このネーミングにしました。もう一方の「Feel of the Earth, 2045」は、廃棄する予定の野菜や調理後に捨てられる部分のみから抽出した出汁で、「地球の味を感じるストーリー」を表しています。また2045年には人工知能が人間を超えるシンギュラリティに到達するといわれており、さらには深刻な食糧危機が訪れるという議論もあります。だからこそ、食糧危機がきても、野菜くずなどを煮詰めるだけで美味しいスープをつくることができるというメッセージが込められています。
カラフェにしても、ネーミングにしても、われわれが知っていると思い込んでいる“出汁”や“食糧危機”をまったく違う確度から解釈して、相手の興味関心を刺激していくストーリーをプレゼンテーションしています。この手法は、これまでの僕のキャリアで一貫して取り組んできたものです。
──確かにこのカラフェを通して出汁を提供されながら、こういったストーリーを聞くと、理解度が深まりますね。当事者意識を持つきっかけとなる、良いインターフェースのように感じました。このような手法を一貫して実践してきたということですが、望月さんのこれまでのキャリアについて簡単にお話いただけますか?
望月:まさにインターフェースにまつわる仕事にずっと携わってきました。2003年に博報堂アイ・スタジオに入社し、デジタルを活用したプロモーションの企画立案や実制作を行い、2014年からは博報堂アイ・スタジオ内のR&D部門であるFuture Create Labで、クリエイティブと最新テクノロジーを組み合わせたプロトタイプを開発してきました。
いま取り組んでいるUMAMI Labもその地続きにあって、ある意味“食のインターフェースを良くしたい”、“新しい食のインターフェースを生み出したい”という思いからスタートしています。

望月:子どもが生まれて、「安全で栄養のあるご飯を食べて育ってほしい」と思ったことが一番のきっかけです。化学調味料を使わずに「いいお出汁を飲んでほしい」という思いから、鰹節や昆布から出汁を引き始めました。その過程の素材選びから加工・提供までのプロセスが、これまで取り組んできたデザイン工程と同じという面に気づき、どんどんハマっていきました。
あとプロトタイプ開発のサイクルが食は速くて、それも魅力的ですね。これまでの制作物と違って、開発から消費までのサイクルが超短期な構造は開発者にとっては動きやすかったです。それもいまフードテックが注目されている理由の一つだと思います。
──開発スパンの速さも開発者を引き寄せる要因なのですね。竹村さんは2017年に椎茸祭を創業していますが、きっかけはなんだったのでしょうか?
竹村:私の当時の彼女(編集部注、現在は妻)がベジタリアンで、肉や魚を食べられなかったことが直接的なきっかけです。肉や魚を食べられないので、キノコ類でうま味を出すという精進料理的な考えです。このため望月さんと同じで身近な経験からですね。
──食は生活に密接に関係していますからね。竹村さんのキャリアも、望月さんと近しい業界ですよね。
竹村:そうですね。私は2010年にNTTコミュニケーションズに新卒入社したのですが、1年で退職してインドへ移住してプログラマーをしていました。インドは人口の40%の人がベジタリアンで、それなら自分も試してみようと実践してみました。肉を食べない生活を続けるともちろん食べたくなるのですが、肉を食べたい欲求を抑えるほどのうま味がキノコ類にはあることを発見しました。これが最初のきっかけです。

竹村:いえ、すぐに起業をしたわけではありません。もともと大学生のころから、いつか起業しようと思いつつ、10年以上の月日が流れてしまっていました。2013年に日本に帰国して、デジタルアート集団「チームラボ」に入社したことが、一番の転機になりました。
──チームラボに入社したことが、椎茸祭を起業するきっかけになったのですか。どういうことでしょう?
竹村:チームラボのデジタルアートで、鑑賞者が自分のほかにいることで一人で見るよりもより綺麗に見えるような作品があります。“自分と他人”、“自分とアート”の境目をなくす「ボーダレス」な理念が好きで。人口増加が予想されるインドでは、多くの人が宗教上の理由で肉や魚を食べられません。しかし、こうした人でも、キノコや野菜のうま味成分を凝縮された出汁があれば、ボーダレスに美味しさを分かち合えます。さらに調理という垣根をなくすために、お湯で溶かせば誰でも美味しいスープが飲める形状にしようと思い、oh!dashiを開発しました。

竹村:椎茸祭は出汁を世界中に日常に根ざす形で広めることを目指しています。望月さんのようにプロセスを設計して、食の楽しさを演出することは、主体的なものの延長にあると思っていて。私たちはまず、主体よりも客体、より多くの人に届けるために、ユーザーインターフェースを工夫して、世界のさまざまな国で出汁文化の普及をしていきたいと思っています。
望月:僕はどちらかというと、プロセスのエンタメ化ですね。強烈な体験を提供していくことを目指しています。例えば、インスタントコーヒーを飲んでいる人も、ハンドドリップコーヒーやサイフォン式コーヒーを体験すると、自分でもやってみたいと思うじゃないですか。この考えをうま味でも取り込めないかなと。

望月:僕も竹村さんもWeb・デジタル業界出身で、扱う素材は変わりましたが、いままで積み上げてきたデザインやエンジニアリングを駆使して、食べる人にとって体験価値の高いユーザーインターフェースを提供しているんです。
僕は現在、UMAMI Labとは別にREDDという会社を起業し、代表取締役を務めています。社名は、Research/Education/Design/Developmentの頭文字をとっており、世の中を知った上で、プロトタイプを設計・開発する会社です。ここで重要なのはEducation(教育)。プロトタイプをつくることで蓄積されたナレッジを未来に引き継ぎ、新しい価値を創造する仲間を増やし、オープンイノベーションを形成していくべきだと考えています。そうすることで、本業や副業を超えたギルド型のコミュニティが生まれ、新たなプロダクトが生まれるかもしれないなと。
──お二人が協業する未来があるかもしれないわけですね。楽しみです! では話を変えまして、フードテック関連はこの先どうなっていくと思いますか?
望月:昨年オランダに、空きビルを貸し切って各階を農場にする、いわゆるヴァーティカルファーミング(垂直農法)を見学しました。街のレストランやカフェで淹れたコーヒーのカスを堆肥にしてキノコを栽培していたり、別フロアではバイオフィルターで水質管理された水槽があり、そこでは淡水魚が養殖されたりしていました。また水耕栽培でハーブやトマトも栽培しているのですが、フロア内に益虫やミツバチを放って生態系のバランスをとることで無農薬栽培を可能にしています。このヴァーティカルファーミングのシステムを世界各国に技術提供し、その売上金をさらなる研究開発に再投資しています。まさに循環型経済システムとサスティナビリティ(持続可能性)をビル一棟内で実践しているわけです。いままで農業は広大な大地に限られていましたが、このような技術が発達することで、空きビルなどの未使用空間を有効活用、果てには宇宙空間の農地化や深海の水耕プラント化が実現するかもしれません。そのためには、妄想だけでなくプロトタイプを先んじてつくっていきたいですね。


出典:オランダの都市型農場に、サスティナブルの正しい可能性を見た - Border Sessions 2018 Report(2)
──最後に“食の未来”について、お二人から意見をお聞きしたいと思います。
望月:日本には古来より出汁によって素材本来のうま味を引き出す食文化がありましたが、うま味の受容体が舌にあると科学的に証明されたのは2000年以降なんです。つまり世界的にうま味が理解されるようになったのは最近のことなのです。そのなかで日本は古くからうま味に対するノウハウを蓄積してきました。それを発展させる未来が来るように思います。例えばうま味をベースにした料理は、糖質や脂質を抑えても美味しく感じるため、成人病の予防に効果的といわれています。健康への関心はますます高まる中で、出汁やうま味も比例して注目されるでしょうね。
竹村:心が健康な状態である“リラックス”の一番しっくりくる和訳は、”息抜き“だと思っています。湯船に浸かるときや美味しい出汁を飲んだときホッと一息つけますよね。こういった呼吸という動作とともに風味を感じます。

竹村:腸内で消化を促す菌も重要ですよね。けれども、菌の90%以上はいまでもよくわかっていないみたいなんです。昔、寿司職人の10年の修行不要説がネットで議論されていましたが、別の味方もあるなと思っています。寿司職人は10年ほどの修行で、ある程度最適な菌を手の環境で構築するのではないかと最近思い始めました。今後は寿司職人の握る手にいるべき常在菌や、一緒に口にする木の器にいるべき常在菌などが科学的に解き明かされ、本当の美味しさ料理、さらには未病につながる料理が見える化されてくるのではないかと思っています。
望月:見えなかったものを可視化するテクノロジーは確かに実現しますね。あとはさまざまなうま味調味料が流通したことで均一化されてしまった味に対する揺り戻しが来ると予想しています。音楽でもアートでもその潮流が見られますが、食でも“ゆらぎ”を許容する社会が訪れる。うま味調味料によって均一化してしまった家庭の味、おふくろの味が、天然成分の出汁によって多様性が取り戻される。そうなると家庭料理のベースアップが起きて、価値も高まります。一流のシェフだけでなく、家庭料理をつくるお母さんやお父さんがプレイヤーとして参入するとますます面白くなっていくような気がします。日本には世界でも有数の発酵と熟成の文化とテクノロジーがあります。現状はプレイヤーも少ないですが、ここにチャンスがあると思います。