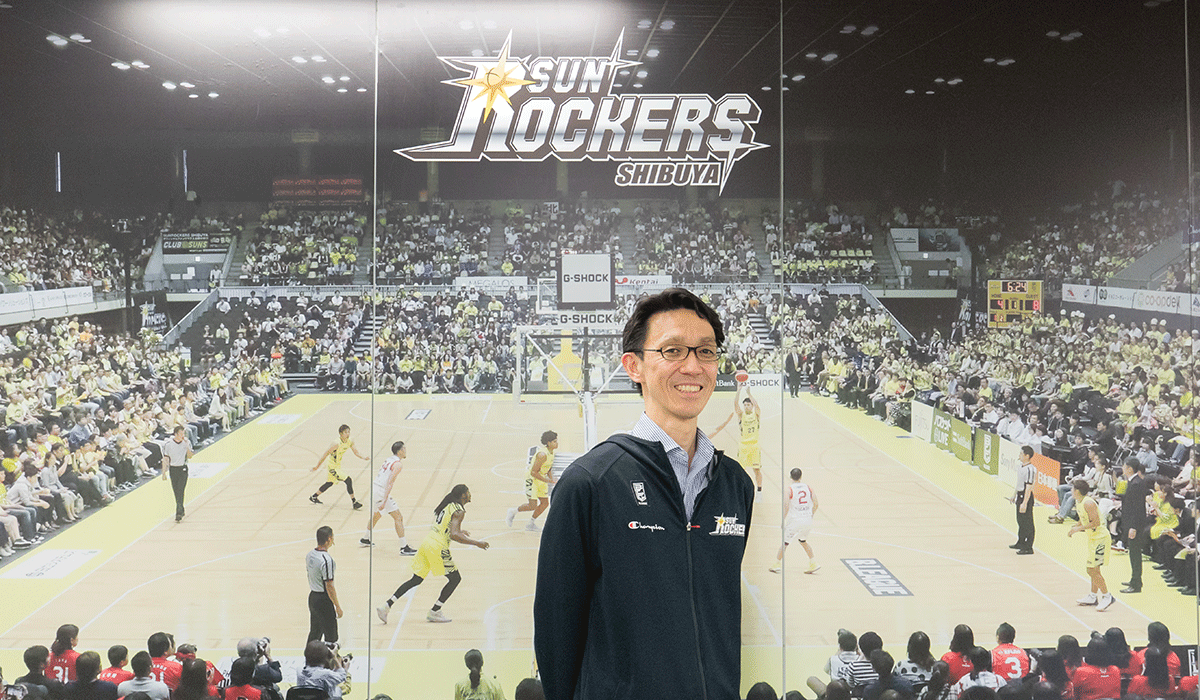eスポーツリーグ「RAGE」の担当者が語る、eスポーツが日本に根ざすための課題とは CyberZ eスポーツ事業部 マネージャー 大﨑章功さん

エレクトロニック・スポーツ。通称eスポーツと呼ばれる競技にいま、注目が集まっています。2018年には流行語にもノミネートされ、一大文化となるべく猛スピードで成長を遂げています。今回は日本のeスポーツプロリーグの一つ「RAGE」の運営を行う、CyberZでeスポーツ事業部 マネージャーを務める大﨑章功(おおさきあきのり)さんに、日本のeスポーツ文化とプロリーグ「RAGE」についてお話をお聞きしました。日本でeスポーツ文化が根ざしていくためにクリアせねばならない課題とはなにか。主にeスポーツリーグの運営という視点から、その胸中を語っていただきました。
日本のeスポーツ文化の現状
──CyberZではeスポーツリーグ「RAGE」を運営されていますが、RAGEとはどのようなeスポーツリーグになっているのでしょうか?「RAGE」は我々CyberZに加えて、エイベックス・エンタテインメントとテレビ朝日の3社で協業しているeスポーツブランドです。オープン制や賞金制をはじめとするeスポーツ大会、一般来場者による参加型のeスポーツイベント、eスポーツのプロ選手による競技を配信する観戦型のeスポーツリーグ、この3つのプロジェクトを主に手がけており、eスポーツリーグはこのうちの1つとなります。大会では、さまざまなゲームタイトルのeスポーツ王者を決める大会を行っており、賞金制の大会も実施しています。プロ選手などが参加するeスポーツリーグは、「RAGE Shadowverse Pro League」や「RAGE STREET FIGHTER V All-Star League powered by CAPCOM」を運営しています。

そうです。「RAGE Shadowverse Pro League」では、KDDIがプロeスポーツチームのDetonatioN Gamingとスポンサー契約を締結し生まれたチーム「auデトネーション」、同じく吉本興業とプロeスポーツチームのLibalentがタッグを組み結成した「よしもとLibalent」、ほかにも、おやつカンパニーが名古屋で活躍するeスポーツチームと「名古屋OJA ベビースター」を結成し、日本テレビ放送網は「AXIZ」と組み、2019年には読売巨人軍が選手を募集して結成した「G×G」も加わり、現在7チームとなっております。また、10月から「福岡ソフトバンクホークス」もこのリーグに参戦する予定です。

「RAGE Shadowverse Pro League」の参加チーム

2019年10月より、福岡ソフトバンクホークスの参入も決定した。
──確かに、企業以外にもプロサッカーチームを持つ「横浜 F・マリノス」なども参入されていますよね。
サッカークラブチームである「横浜 F・マリノス」や、バスケットボールチームのレバンガ北海道とサッポロビールによる「レバンガ☆SAPPORO」、野球界からは、読売巨人軍ブランドの「G×G」と「福岡ソフトバンクホークス ゲーミング」などのスポーツチームも「RAGE Shadowverse Pro League」には参入しています。横浜 F・マリノスはマンチェスター・シティFCを有するシティ・フットボール・クラブの一員です。そのマンチェスター・シティFCもeスポーツチームを抱えているんです。世界中のサッカークラブがeスポーツに力を注いでいく流れにあり、その流れを日本もくみ、横浜 F・マリノスが参入することになりました。

2018年より、横浜F・マリノスもeスポーツへ参入している
なぜ海外のeスポーツ文化は日本の先を行くのか?
──『FIFA eワールドカップ』が2018年にも開かれるなど、海外でのeスポーツへの取り組みは日本よりも盛んなイメージがあります。おっしゃるとおり、eスポーツ文化は日本よりも海外で、文化として強く根付いていますね。それに海外では、ほかのフィジカルスポーツと同じように年収1億円を超えるeスポーツ選手も現れてきています。年齢も20代と、とても若い選手が活躍しています。去年11月に実施した「RAGE」でも、韓国のプロ選手Fakerさんをご招待しました。この方はサッカー界で言うところのメッシ選手やクリスティアーノ・ロナウド選手のようなスター選手であり、実際に来日した際は、かなり大きな反響がありました。
──日本には世界でも愛されているゲームやメーカーが多いイメージがあるのですが、どうして日本のeスポーツ文化は海外に比べて遅れをとっているのでしょうか?
日本のゲームは「一人で楽しむ」という傾向が強いというのが遅れをとっていると言われる理由の一つかもしれません。日本がこれまで築き上げてきたゲーム文化は、プレイステーションやファミコン、64、ゲームキューブなどのいわゆるテレビゲームと呼ばれるもの。日本のゲーム文化は、国内テレビゲームが圧倒的なシェアを持ち、一人でも楽しめるコンテンツとして根付いてきたのです。しかし、海外のゲーム文化は「PCゲーム」が主流。この違いはとても大きく、ゲームが「一人で楽しむ」ものなのか、「複数人で楽しむもの」なのかという文化の違いを生んだのです。

──テレビゲームとPCゲーム、そして「競技性」の部分が日本と海外では異なったと。
ほかにも、それぞれの国の文化や慣習の違い、法律の問題なども加味した上での現状であると思います。ただ、近年の日本での成長率は、目をみはるものがあります。2018年の流行語にもeスポーツはノミネートされましたし、日本プロ野球機構(NPB)もプロ野球の12球団でeスポーツへの取り組むことが発表されました。RAGEとしても2018年で大会やリーグの総視聴数は3000万回を越え、大会の来場者数も10万人を突破、日本のeスポーツにはいま追い風が吹いています。これからますます盛り上がっていくことは間違いないと思いますね。
スポーツ中継の技術をeスポーツへ
──2019年7月にRAGEが新たにテレビ朝日と協業して運営していくことが発表されました。これにはどのような狙いがあるのでしょうか?eスポーツ市場のさらなる発展が狙いです。エイベックス・エンタテインメントとは主にイベントの制作とプロデュースを、そしてテレビ朝日とは映像制作とeスポーツの試合を地上波放送という点で連携していく予定です。

今年の7月に「RAGE」の協業運営を発表した。
──確かに、あれがあることで水泳がかなり見やすい競技になったと思います。そのような工夫は多くの人が触れるきっかけになりますね。
そうなんです。年内中にも放送できるように現在準備を進めています。一般の方にとって少しでもeスポーツを身近なものにしていきたいですね。ひとえにeスポーツとくくっても、そのジャンルはかなり多岐に渡りますし、さまざまなタイトルがありますから、きっと好きになるものがあると思います。

2018年に大流行した『フォートナイト』などの「バトルロワイヤルゲーム」が最近流行ったカテゴリとしては、顕著ですね。大会やリーグの運営をする我々は、業界の流行を的確に把握していなければいけません。ゲームは普及するスピードがとても速い。そのスピードに遅れずに、各タイトルのユーザーや視聴人口がどのくらい期待できるのかを把握し、大会やイベントを設けること。それが僕たち運営側の仕事です。ここがある意味で一番難しい部分かもしれないですね。
臨場感でも劣らず
──そもそもなのですが、大﨑さんがeスポーツ業界に携わることになったのは、いつからなのでしょうか?元々、サイバーエージェントに新卒で入社してずっと広告事業で仕事をしていました。eスポーツ業界に携わるきっかけになったのは、「RAGE」の総合プロデューサーを務めている大友と話し、2017年にCyberZへ異動してからです。それまではeスポーツに対する見識も深くなく、実際に試合を観たこともありませんでした。しかし、初めて生で観た試合の雰囲気と熱気が凄まじく、圧倒されました。
僕はサッカー経験者なのですが、eスポーツの試合もサッカーなどのスポーツ観戦と同じくらいの迫力があります。会場では、プロによる実況や解説もあり、歓声で地響きが湧いて盛り上がる。きっと、観客の様子だけを眺めてみると、ほかのスポーツと比べてみても、どちらがeスポーツの画なのか判別がつかないほどだと思います。韓国で開かれた大規模な世界大会では、サッカーのFIFAワールドカップ会場として使われていた4万人ほどのキャパシティを持つスタジアムに人がびっしりと入っていたこともありました。「ただのゲーム大会ではない」と、完全にイメージが覆りましたね。

「RAGE」会場の様子
「RAGE」の運営指針としても、ほかのプロスポーツと同じように興行システムを構築したビジネスを目指しています。観に来て楽しんで帰ってもらうこともそうですし、スポンサー側にも人が集まるところに露出できることをメリットに感じてもらいたいです。ゲームメーカーではなく、サード-パーティーの僕たちだからやれることを、「RAGE」を通して実現していきたいと思っています。
特に考えているのは、どれだけ感情移入して観られるかという、「ストーリーづくり」の部分です。例えばですが、「甲子園にはドラマがある」とよく言われます。それぞれの選手や学校にそこに至るまでの背景がある。地方の大会から代表が決まって、本大会があって。さらにそこから活躍した選手がプロになって…というようにストーリーが続いていきます。そのような、選手一人が成長していく過程のストーリーに惹かれて、ファンになり、応援していく。これはスポーツビジネスでかなり肝になる部分なのではないかと思っています。このような中長期のストーリーをeスポーツでどのように展開していくか。そのために、ほかのスポーツや人の内面を研究しています。
──具体的にどのようなところを参考にするのでしょうか?
選手の内面やどのような考え、理由を持ってその競技に取り組んでいるのかという動機の部分。それとそれぞれが思い描く将来のビジョン。これらの要素が、人が持つ「魅力」という部分になっていくのではないかと思っています。だからこの部分を視聴者に伝わるような映像やイベントをつくっていきたいですね。目新しい部分が多いeスポーツも、結局中心にいるのは“人”です。これはほかのスポーツと変わりません。主役はゲームではなく、人なのです。
もう一つ参考にしているのが「チーム戦」です。eスポーツでは個人だけでなく団体戦も増えていて、格闘ゲームでも3人制でチームを組み参加する大会を「RAGE」では開催しています。チームスポーツにそれぞれのポジションの役割やフォーメーション、作戦タイムがあるように、チーム戦ならではの見せ方がある。それらもシーンづくりの参考にしています。

──前半にお話いただいたサッカークラブのようなスポーツチームがeスポーツチームも持つようになっているというお話がまさにその通りというわけですね。地上波のテレビでeスポーツ中継が観られる未来が楽しみです。お話しいただきありがとうございました!
※2019年10月4日(金)記事を一部修正いたしました。