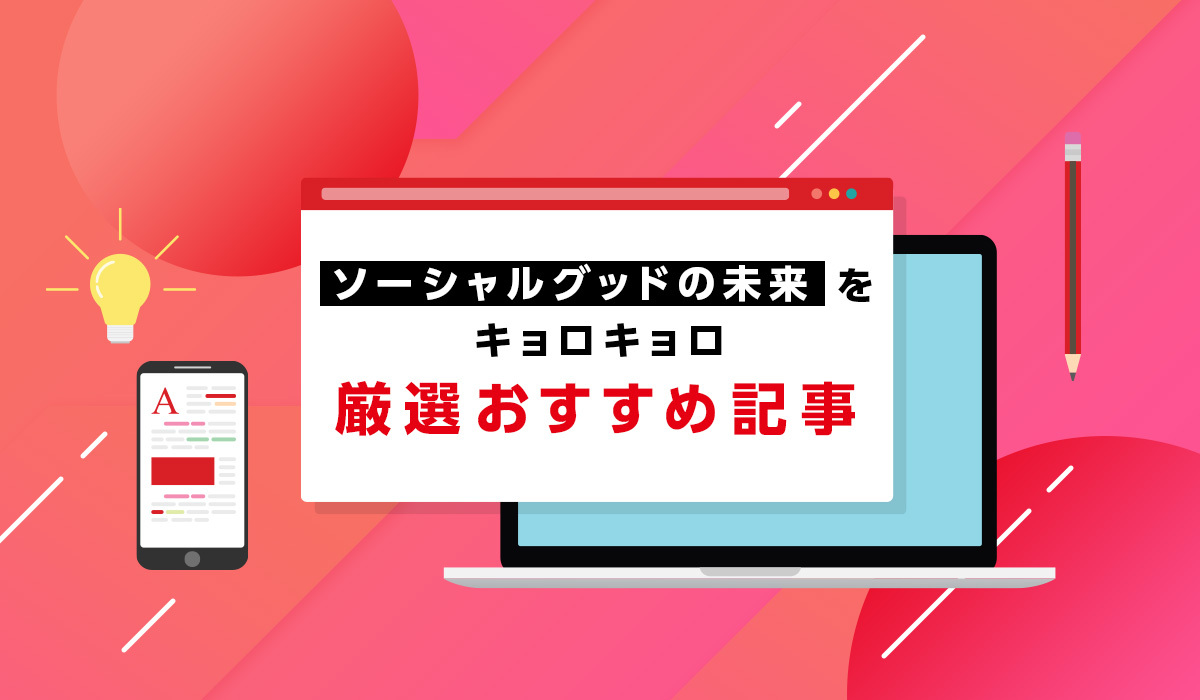“電子国家”エストニアと“消滅可能性都市”秋田県大館市から学ぶ、教育の未来とは LiveYourDreams 代表取締役 河﨑呈さん

ゆとり教育の撤廃やプログラミング教育の導入、センター試験の廃止。昨今、大きな変化が日本の教育現場で相次いでいます。そのような状況のなか、ロボットや映像を活用した教育事業を手がけ、注目を集めるLiveYourDreamsという会社があります。同社の着目するべきポイントは、その事業を手がける拠点にあります。本社を秋田県大館市に構える一方、2019年9月にはエストニア共和国に支社を構えたことを発表しました。なぜ秋田県とエストニア共和国で事業を展開していくことを選んだのか。代表取締役を務める河﨑呈(かわさきてい)さんにその理由についてお聞きしました。
秋田とエストニアに拠点を持つ理由
──LiveYourDreams(以下、LYD)ではロボットや映像を通した教育事業を展開していますが、本社を秋田県の大館市に構えていますよね。さらに、2019年9月にはエストニア共和国にも支社を設けたとか。これはどうしてなのでしょうか?LYDの立ち上げ以前、私は映像制作などを主に手がけるクリエイターとして活動していました。あるとき秋田県大館市の街の方と紹介ムービーをつくるということになりました。それが秋田県大館市との最初のご縁でした。このオファーというのが、単純な映像制作の依頼ではなく、「この都市でビジネスをしていく道を一緒に探してほしい」というもの。実はこの大館市は、今後存続できなくなる恐れがある、消滅可能性都市にリストアップされています。そのため、政府や自治体主導でビジネスパーソンやクリエイターに向けたサテライトオフィス誘致の取り組みを行うなど、ビジネスが成り立つ道を模索しています。
──国土交通省によれば、秋田県は消滅可能性都市が最も多い場所とされていますよね。消滅に対する危機感はほかの土地よりも如実だと思います。
私自身も田舎出身であったので、田舎が生き残るためのチャンスを探す、この状況には親近感を覚えました。このような田舎で、自分が培ってきた技術を惜しみなく提供できる価値はなにか。考えた結果、自分が持つ映像制作やロボットプログラミングなどのノウハウを子どもたちへ伝えていくことだと思いました。それがLYDの立ち上げのきっかけでした。

──秋田と同じく、エストニア共和国(以下、エストニア)という国を選んだことにもなにか経緯があるのでしょうか?
今年7月からエストニアでの活動を開始したのですが、事業を展開していく準備は3年以上前から進めていました。人口130万人という小国でありながらも、IT先進国として注目され、SkypeやTaxifyなど多くのユニコーン企業がエストニアでは立ち上がっています。また、起業発生率が高く、欧州内でも起業活動が活発な国の一つです。その理由として、外国からでも法人登記が簡単に行える「e-Residency」と呼ばれるサービスがあります。
ですが、根本的な理由はそれだけではありません。エストニアの「人の育て方」、つまり教育システムが大きく影響しているんです。エストニアは、2002年に世界ではじめて学校教育にプログラミングを取り入れるなど、世界でもいち早くICT教育を取り入れています。現在成人を迎えているほとんどの人が、すでにプログラミング教育を受けているというわけです。LYDの目指す、地域に左右されることなくビジネスを行っていく道は、エストニアなら実現できると考えました。
──17年前にすでにプログラミング教育を取り入れていたのですか…! IT先進国という印象が強くありましたが、教育がその礎になっているのですね。
そもそもエストニアが早々にプログラミング教育を始め、電子国家となっていく道を選んだのは、歴史的・地理的な背景が影響しています。1991年にソ連から独立し、お金も観光資源も持たないなか、昔からいろいろな国に攻め込まれてきました。いつまた戦争に巻き込まれるかもわからない。だからこそ、若者や子どもが他国に出ていっても自分でビジネスを立ち上げて、生き残っていけるような教育を目指したという背景があります。そして、エストニア国内が落ち着いた時に、いつ戻ってきても自分がどこの何者かを証明できるよう、公的手続きが電子化し「e-Residency」という電子居住権の仕組みが整えられたのです。

河崎さんのエストニア視察の様子
日本の学校教育は、カリキュラムと学習指導要領によって定められたレベルをいかにクリアして、いかに優れた企業人になるかという育て方をしています。一方、エストニアは、世界で戦えるビジネスパーソンになるために、知識と挑戦する機会を得られる環境として学校教育が用意されています。カリキュラムも学習指導要領もありますが、あくまで選択肢の一つであり、個性や発達レベルに合わせて挑戦することができます。「e-Residency」により容易に会社を立ち上げることもできるため、小中学校の段階で実際に会社をつくる授業なども受けています。エストニアの学生の日常では、自分の所属する部活動やクラスの話題に加えて、自分が起こした会社についての話をすることも当たり前なんです。
──日本の教育現場では見られない光景ですね…。
エストニアの教育で重要視しているのは、挑戦する機会をどんどん与えて、「うまくいった! 失敗した!」などの体験を積み上げていくことです。この機会とそこで得られる知識や経験値の違いは、5年、10年と時間が経つにつれて、大きな差として表れると思っています。国内のユニコーン企業の数にも影響しますし、ビジネスパーソンとして個人が持つスキルのレベルにも差が表れます。このような教育の土壌がエストニアではすでに形成されています。LYDでは、そのエストニアの教育の土壌を日本の教育現場にも還元していくために、エストニアに支社を設けるに至りました。

ロボットがいる生活
──LYDではロボット活用事業にも力をいれているとのことでしたが、具体的にはどのような活動をしているのでしょうか?ソフトバンクロボティクスが開発したコミュニケーションロボット「NAO」を活用して、「ロボチューバー」と題したYouTube動画を配信しています。人間と「NAO」が早口言葉対決をしてみたり、料理をしてみたり。さまざまな企画をしていますが、この活動の目的は、ロボット活用のイメージ喚起なんです。ソフトバンクロボティクスが販売している「Pepper」を飲食店やホテルの受付などのいろいろな場所で見かけることがあると思います。ただ、ほとんどの人は実際に利用したことはなかったり、電源が落ちていて機能していなかったりすることが多いのではないでしょうか。
その理由の一つは、ロボットを使う人たちに、ロボットが生活の一部になるビジョンが見えていないからだと思います。ドラえもんが実際にいたらどんなふうに遊びたいか。アニメや漫画を見たことがある人なら、きっと誰もが想像つくけれど、「NAO」や「Pepper」などのロボットが生活にどのように馴染んでいくかを、想像できない人が多いのだと思います。我々が行うロボチューバーの活動は、ロボットと暮らす近未来を、人々に想像してもらうための取り組みなんです。
──確かに、ドラえもんもそうですが、実際に他愛のない行動をしている映像を見ることで、イメージのしやすさが格段に上がりますよね。ロボットとの生活への解像度を上げて、興味を持つ機会をつくっていると。
「NAO」や「Pepper」は、もともと発達障害を持った子たちのトレーニングや、医療機関の研究のためにつくられました。しかし、私たちは教育現場でもこれらのロボットは活用できると思っています。具体的に言うと、自閉症やアスペルガー症候群、ADHDなどコミュニケーションを苦手としている子どもたちへの教育への活用です。ほかの子と比べると、「変わっている子」と思われがちな彼らのコミュニケーションを取る練習相手にロボットはなり得るのです。これはADHDである私自身の経験から感じていることです。

LYD主催のワークショップの様子
©Softbank Robotics
©Softbank Robotics
──河﨑さん自身の原体験があったからこそ、いまのLYDの事業を手がけているわけなのですね。
とはいえ、「教育で世界を変えるぞ!」なんて大それたことは思っていませんが、「世界には面白いことがある」と気づくきっかけをLYDがつくっていきたいです。なにかに触れて感動したり、楽しいと感じたりする機会があれば、それがなにかのきっかけになるかもしれない。それだけで未来は大きく変わっていくと思うのです。この先、ロボットやAIなど新たなテクノロジーが、いま以上に社会に入り込んでいきます。そんな社会で、新しい可能性を見つける機会づくりとして、映像制作スキルやプログラミングスキル、ロボットを扱えるスキルは有効な領域なのではないでしょうか。
教育のイノベーション。その未来は?
──2020年からはプログラミング教育の必修化も小学校では控えています。プログラミング教育についてはLYDでもなにか展開していくのでしょうか?まず、2020年から必修化するプログラミング教育は、実は明確な授業内容が指定されていません。この教育の趣旨は、「プログラミング的思考、論理的思考ができる子どもを育てる」というもので、パソコンを使った本格的なプログラミングは必須ではないのです。例えば、卵焼きというゴールを設定して、そこに行き着くためにはどんな手順を踏めば良いのかを考える。今後は、このような論理的思考を求める授業もあり得ると思います。

──エストニアのような、実生活に直結する課題に挑戦していく授業ですね。そこから成功や失敗も経験できる機会を提供していくと。
そうですね。大館市に限らず、日本全体の学校教育が、もっと子どもの選択肢を増やせるものに変わっていく方向へ進んでほしいと、私は思っています。学年ごとに定量化された学力を追う現在の方法だけでなく、アイデンティティに合わせて個別に選択できる新しい方法も加えていく。そんな柔軟な教育が日本でも受けられるようになってほしいです。

©Softbank Robotics
──「テクノロジー×教育」ですか。インターネットが生活のなかに、当たり前として根ざしているからこそ、テクノロジーを自在に扱える人材がこの先求められますね。
おっしゃるとおり、テクノロジーを駆使できる人は、教育現場に限らず社会全体で必要になります。この先さらにテクノロジーが社会に入り込み、それを駆使するスキルが求められます。私たちが展開する教育事業もそのきっかけの一つとして機能し、多くの人に新しい選択肢を与えるものになるよう尽力していきます。それによって、暮らす場所や育ち方に関わらず、自分の持つ個性を活かせるようになれば嬉しいですね。
──エストニアとの対比により、日本の教育の現状をお話いただきました。日本の教育現場が今後どのように発展していくのか。それは日本の未来の転換点の一つになっていくと思います。LiveYourDreamsの事業がもたらす学びのイノベーションも今後、目が離せません。本日はありがとうございました!