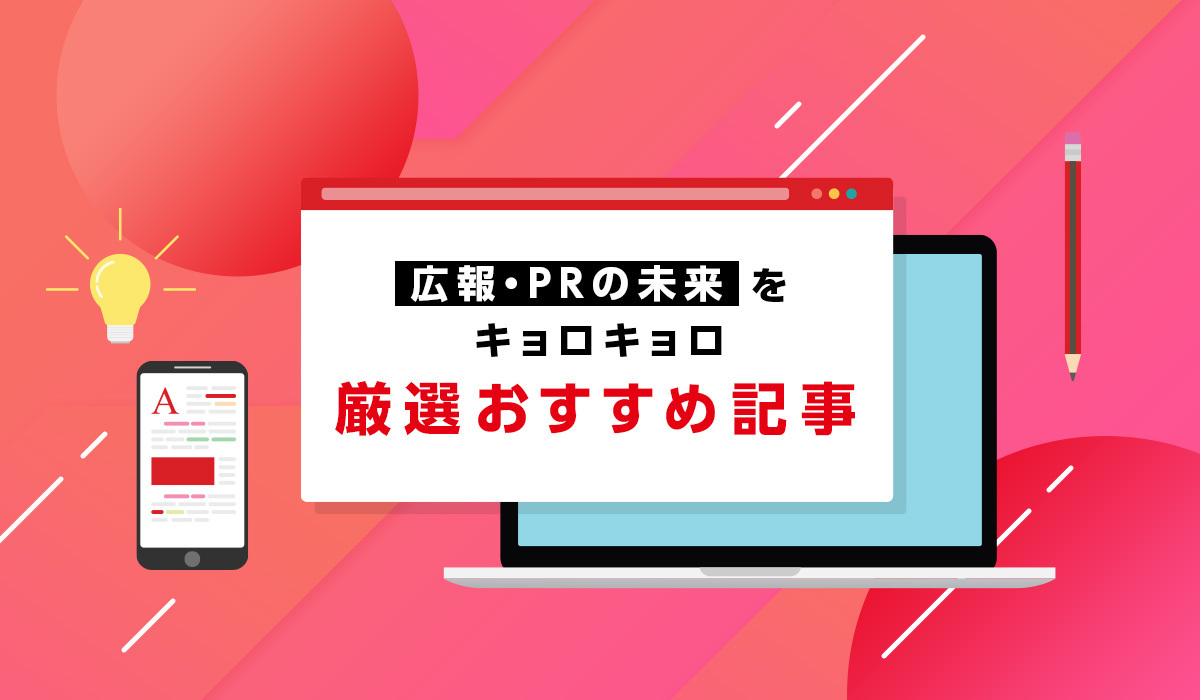マルチクリエイター草野絵美、「マイノリティを武器に、エイリアンポジションで人生切り開く」。市原えつこが聞く #クリエイターの生存戦略 アーティスト 草野絵美さん

Yahoo! JAPANのデザイナーを退職し、現在はフリーランスのメディアアーティストとして活動する市原えつこさんが、さまざま分野のクリエイターや専門家に話を伺い、クリエイターの生存戦略のヒントを探す新連載を開始します。第一線で活躍するクリエイターたちがどのようにキャリア構築をしてきたのか、今後はどのように歩を進めようとしているのか、対談形式でインタビューしていきます。
初回は、歌謡エレクトロユニット『Satellite Young(サテライトヤング)』を主宰し、歌手/タレント/アーティストとして活躍している草野絵美さん。ミュージックやアートを創作するクリエイターでありながら、「Adobe」や「サンテPC」のCMにもタレントとして起用され、海外にも多くのファンがいらっしゃいます。そんな彼女は、どのような生存戦略を描いているのかお聞きしました(マスメディアン編集部)。
初回は、歌謡エレクトロユニット『Satellite Young(サテライトヤング)』を主宰し、歌手/タレント/アーティストとして活躍している草野絵美さん。ミュージックやアートを創作するクリエイターでありながら、「Adobe」や「サンテPC」のCMにもタレントとして起用され、海外にも多くのファンがいらっしゃいます。そんな彼女は、どのような生存戦略を描いているのかお聞きしました(マスメディアン編集部)。
「両親と同じアーティストにはならない」というビジネス志向から一転。自分自身がアーティストへ
市原えつこさん(以下、市原):私は現在、フリーランスのメディアアーティストという奇妙な立場にいまして……。いろんなお仕事でなんとかいまは食えてはいるものの「今後どう歩んでいくべきか」という生存戦略が目下の関心事です。今回、連載を始めるにあたって、クリエイターのみなさんが考える生存戦略をいろいろとお聞きしていこうと思いました。その中で、草野さんはすごく特殊なキャリアですよね。高校生のときからフォトグラファーとして活躍していて、大学時代に起業して、21歳で子どもを産んだのちに音楽ユニットを始め、その後広告会社に就職して、また今は独立してアーティスト活動をしている。猛スピードで人生を疾走している気がして、お話を聞きたくてお声がけしました。まずはじめに、最近力を入れている音楽ユニット『Satellite Young』についてお聞きしたいのですが、どういう想いからスタートしたのでしょうか?
草野絵美さん(以下、草野):昔から、産業やテクノロジーが発達して出てきた50年代以降の人間の生活が異様に好きで、とくにファッションの分野が好きで、60年代のモンドリアンドレスを自作して人形に着せてるような子どもだったんです。なぜファッションだったかというと、ファッションは年代ごとの価値観を色濃く表し、それらを考察するのがすごく楽しかったから。その時代にまるでタイムスリップしたみたいで。
他にも『がんばれ!!ロボコン』や『ひみつのアッコちゃん』などの60年代、70年代の作品と、2000年代につくられたリバイバル作品の違いを通して、時代ごとのジェンダー観や未来観みたいなものを比較研究したりしてました(笑)。同じ作品でも、時代が違うとヒロインの性格や父親の職業がまったく違うんですよ。

草野:あとはSFも大好きで。SFって未来と言いつつ、なんだかんだ現代なんです。最近のSFドラマを観たら、人工知能の発達やスマートスピーカーの普及とか、現代に起きている事象が詰まっているのがわかります。50年代のSF映画はユートピアだけど、80年代はディストピアだったり、未来に対しての観念がまるで違う。そういうレトロフューチャーなものがすごく好きで、大学でもレトロフューチャーの生みの親と言われる先生に教わったりしていました。ただ、そういった偏愛のバックグラウンドはありつつも、これまで自分の作家性をベースに作品はつくってこなかったんです。
市原:自分の世界観を表現するのではなく、フォトグラファーとして既にあるものを切り取る活動が多かったんですね。言われてみれば、クリエイターとして長く活動しているイメージがありましたが、プロデューサー的に俯瞰するような活動が多かったかもしれないですね。
草野:そうですね、フォトグラファー時代も表現というよりは完全に社会勉強のためのコミュニケーションツールとしてカメラを持っていて。両親がアーティストだったから、反面教師で私はアーティストにはならないって決めていたんです。父親は画家だったのですが、芸術家肌すぎて、交友は少なく、お金も安定しなかった。だから自分はビジネススキルを持とうと思って、美大ではなく慶応義塾大学に入学しました。フォトグラファーの後、ラジオパーソナリティや番組MCもしたのですが、コミュニケーションを生業にすることが多くて。自分がメディアになってアーティストを発掘する側になろうという指向性が強く、自分自身はアーティストになりたくないと思っていたんですよね。
でも、大学に入って勉強して、起業して、結婚した後に、やっぱり自分の世界観を表現したくなって。子どもの頃は自分で60年代の服をつくって人形に着せたりしてたなと、妊娠中に突如、初期衝動が湧き出したんです。それが歌なのかアートなのか、カテゴライズをまったく意識せずスタートした最初の作品が『Satellite Young』でした。
これは私のこれまで歩んできた道がすべてつながっていて。それこそ大学時代に起業したのですが、2011年当時ってSNSバブル&スタートアップバブルで、学生起業家も多かったしお金も集まりやすい時期だったんですよね。私もシリコンバレーに行って、投資家の前でプレゼンする機会もあったりして。「ピボットしちゃいなよ!」とかカタカナが飛び交う感じがまさに超バブリーで。そういった華やかな空気感が、80年代のバブル時代への憧憬とどこかリンクしたんです。それで、Twitter社CEOの「ジャック・ドーシー」の名前をもじって『ジャック同士』という80年代テイストの楽曲を制作しました。本当に初期衝動で始まった感じですね。
市原:「ポッと出の思いつきで」というよりは、昔からずっと好きだった世界観をようやく具現化しはじめたんですね。
草野:それが自分の作家性だったり、自分の「枯れない泉」なんだなっていうのを自覚したんですよね。
広告会社に新卒入社した、異例のアーティスト・ママ
市原:『Satellite Young』をスタートした後に、大手広告会社に新卒入社されたんですよね。どのような職種だったのでしょうか?草野:普通にデジタル系のプランナー職で入社しました。人と違ったのは、新卒で会社に入った段階で既に保育園に通っている子どもがいて、アーティスト活動もしていたこと。恐らくぶっ飛び枠採用だったんだと思います。でも、入社後は普通に新人としてトレーニングを受け、その後かなり多忙な部署に配属になりました。けど、子どものお迎えがあるから新人なのに必ず6時に帰らなくてはいけないし、最初の上司はどうマネジメントしたらいいかわからず困っていたようでした。
その後、異動した部署の上司がすごく理解のある方で、アーティストとして受ける取材やTV出演も「全然いいよ」と快諾してくれたりして。テクノロジーに特化したキャスティングやプランニングを部署で、デジタル系クリエイターのキャスティングをしたり、社内で最新テクノロジーの啓発セミナーを開いたり、元々の得意分野が活かしやすい環境になったんです。
市原:長らく兼業か専業化で悩まれている印象がありましたが、うまく落ち着いたのですね。私が会社員の頃は個人のアーティスト活動と本業があまり一致していなかったので、羨ましい環境です。以前、会社勤めをして業界の裏側が見えるのは、個人のアーティストとしても良いというお話をされていましたね。どういう意味でしょうか?

会社は居心地良いし、お給料ももらえるし、いろんな業界を見れて好奇心が満たされて楽しい。なんならもっと長く在籍しても良かったのですが、やはりアーティスト活動と育児をしながら毎日通勤するのはなかなか厳しくて。それに会社組織だと個人として目立つのはダメというか、「自己顕示欲は悪」ってなってしまうのが苦しかった。
市原:会社員やりながら、それほどの年次でもないのに副業で目立ってしまうのって、居心地が悪いですよね……。まだ一人前じゃないのに、みたいな。私もベテラン社員さんがたくさんいらっしゃったので、少し肩身が狭かったなと思い出しました。たとえ勤務時間中は頑張っても、一般的な日本企業の価値観だと、個人が使える時間はフルコミットして、プライベートの時間もある程度は会社の人と付き合って、というのが普通なので。
草野:良くも悪くも大人になっていく感じがしますよね。でも、大人になりたくないって思ってしまったんです。
市原:最後に子ども心が爆発したんですね。実際に辞めてみてどうでしたか?
草野:かなり精神が潤いました。もちろん別の不安の波が押し寄せることもあるけど。自分がボスなのでメリットもデメリットもどちらもあります。
市原:上司がいないのは不安だけど、何をするにも誰の承認もとらなくていいのは良いですよね。自分の24時間の使い方を自分で決められるのはすごく心地良いです。
クリエイターに必要な「枯れない泉」
市原:改めてこれまでの変遷をお聞きして、キャリアの変動が凄まじいなと感じます。草野:でも、どの活動も自分のアイデアや目的を形にしたくてやっているだけなんです。フォトグラファーの頃もコミュニケーションが目的だったから写真を撮ること自体に執着があったわけではありません。今も音楽自体が大好きなわけではなく、自分が子どもの頃から大好きだったレトロフューチャーの世界観を表現するためのひとつの手段にすぎません。起業もそうでした。ツールや表現手法にこだわりはなくて、そのときに必要なメディアを使って、その都度やりたいことを達成しているだけなんだと思います。市原さんもそうじゃないですか?
市原:私の場合はやや範囲が狭いのですが、その感覚はとてもわかります。VRやロボットなど特定のテクノロジーが好きなわけではなく、その時々の興味分野や、自分にとってホットなことを表現するのに適した媒体を選んでいる気がします。
草野:その人にしかないアイデンティティや枯れない泉があれば、何をやっても自分っぽくなる。つい最近、メディアアートをつくったんです。80年代以降に普及したカラオケに人工生命が宿って、人間に歌わせたら…という作品。それも世界観が完全にSatellite Young的で、きっとこれに限らず何に展開させてもそうなっていく。
市原:子どもの頃からずっと煮えさせてきたものは強いですよね。
草野:そうそう! ソロ活動としてまた写真や物を色々とつくろうと思ってるんですけど、それもレトロフューチャーな感じになりそうです。いろんな年代にタイムスリップして、テクノロジーへの愛憎や両義性を表現したい。やっぱり「枯れない泉」を持って創作するのがいいんですよ。流行りに飛びつくとすぐに枯れるから。アートユニットの明和電機さんも、誰がどの作品見ても完全に明和電機ってわかるじゃないですか。そういう「誰が見てもこの人」みたいなものをつくれるようになりたい。明和電機の土佐さんは本当に憧れますね。
市原:明和電機さんのブランディングの強さは圧倒的ですよね。一定の世界観と執着から、アートプロジェクトを展開させる形で一大ビジネスを起こしている。たとえば『オタマトーン』もそうですよね? 作品を商品化して大ヒットを飛ばしている。大学時代に聞いた彼の講演で面白かったのが「アーティストはカルピスのようなドロドロの原液を持っていて、でもそれをそのまま出すとエグいから、カルピスソーダみたいに色んなもので割って薄めて売る」という話。すごく納得しました。まさしく「枯れない泉」ですよね。本当にそれがあるかどうかがアーティストか否かを左右する気もします。その人の強烈な原体験とか、幼少の頃の憧憬が作家性に紐づいている人は息切れしない印象がありますね、本人の「枯れない泉」に根ざしていないとトレンドですぐ消費されてしまう。
草野:実は最近マネージャーに言われたことなんです。「枯れない泉で仕事したほうがいいよ」って。
市原:アーティストのマネジメントも非常に気になるテーマでして……。アーティストに限らず個人クリエイターが活躍する時代が来る中で、皆さんの悩みの種になるかと思います。私自身マネジメント会社と契約していないのですが、マネージャーいるのってどうですか?
草野:いいですよ。今はマネージャーさんが2人いて分業体制になっています。彼らと毎週1~2時間作戦会議をしていて、「こういう依頼がきたんだけどどうしよう?」みたいな悩み相談に乗ってくれる。あと、現場に同行して名刺交換してくれたり、名刺交換した人にその日のうちに挨拶してくれたりする。それがあるだけで、精神的にすごくありがたいです。
市原:わかります!! クリエイターがやらねばと思いながらもなかなかやれないやつですね……。
草野:頑張ればなんとか自分でもできますが、マネージャーがいると本当に精神的に安定します。お仕事を断ると罪悪感が湧くけれど、そういうときに一緒に判断してくれる人がいるだけで心強い。細かいことですがプロフィールの文字を変えてくれたり、アー写撮影のスケジュールを立ててくれたり。CM案件など個人で対応するには複雑すぎるような案件では、間にしっかり入ってもらえるのも魅力です。市原さんも、自分でマネジメントできる人だと思うけど、やっぱり捌く量が多いとツライから、つけたほうが楽になると思う。自分でマネジメントできるからこそ出せる指示もあるので。
市原:確かにCM案件は関係者が多すぎて、個人だけで関わるのは難しい分野ですね。自由を好んで独立したクリエイターの場合、事務所のマネジメントがガチガチだとツライけど、苦手なところだけアウトソースできる関係性は本当に羨ましいです。
「エイリアンポジション」を強みに、国内外で自在に働く
市原:話は変わりますが、私はこれまで超ドメスティックに作家活動をしてきましたしてたんです。そもそも英語が得意じゃないし、作品自体がも日本の文化に根ざしていたし、英語も得意じゃなかったのでのでるという理由もあり。ただ、今年になって初めて海外のアートフェスティバルに出展してみたら世界中からめちゃくちゃ面白いアーティストや研究者が集結している上にスケールも大きくて、「海外展示ってこんなに楽しかったのか!」と感動してしまって。とはいえ海外進出については日本人特有の難しさがあると感じました。言語の問題もあるし、東洋と西洋で宗教的なバックグラウンドの違いもあるし、スキンシップ文化なんかも全然違う。仮に私が英語をペラペラに喋れるようになったとしてもそういった文化的背景の違いで少しずつストレスは蓄積されていく気がして。草野さんには国籍の違う友達がたくさんいますが、そういった壁は感じないですか?草野:それが、あまりないんです。自分はマルチカルチュアルだって思っているから。高校のときにアメリカ留学して帰国後はセミインターナショナルスクールにいて、日本語と英語半々ぐらいの環境でした。高校以降も、そういった多国籍コミュニティを自ら選んでいました。今もSatellite YoungのMVは多くの外国人クリエイターと一緒につくっています。英語を話しているときの自分にも濃いアイデンティティが流れているからかもしれないです。英語で思考するときと日本語で思考するときに人格が変わると思っていて。英語の方が論理的で自信があって、日本語の方が抽象的で感性的な思考ができる。そして謙虚。それぞれ違うアイデンティティが形成されていると思っています。
市原:東洋人女性は西洋の文化圏でマイノリティだと思うのですが、それはクリエイターとしての強みにできると思いますか?
草野:それは私の得意技で、意図的にどこにいても自分がマイノリティになるよう、ある意味生存戦略を立てて、切り抜けてきたんです。私はのび太くんタイプで、運動神経も悪いし、勉強もそんなに得意ではなかったけど、何か一つでも得意なことがあれば目立てる。アメリカに留学したときも周囲がみんな白人かつ敬虔なモルモン教信者の中で、自分だけ国籍も信仰も違ってマイノリティだったし。帰国したら海外育ちのガチの帰国子女クラスに入れられて、日本で育ってきたのは自分だけだったし。大学のゼミでも自分だけ起業して異色だったし。会社でも髪の毛を青く染めていたのは私だったし。人生の順番も違って、21歳の大学生で子どもを産んで母親になって、その後就職するのも異例だったし。とにかくずっとマイノリティだったんです。
自分でそれを「エイリアンポジション」って言っていて。そうすると自分の都合のいいように動けるんです。これは会社員の人もやったほうがよくて。逆張りの発想で、皆できることがうまくいかず悩むのではなく、得意なことに特化した方が生きやすい。だからエイリアンポジションの人が組織にいてもいいし、エイリアンポジションの人が活躍できる社会になったらもっとハッピーになれると思う。

草野:浮いててよかったってことが多いですよね。アーティストとしては。
市原:今の世界はあらゆるマイノリティを受け入れようという流れになっているから、そういう意味で日本人が海外に出ていくのに良い時代かもしれません。
草野:私は人種を気にしたことはあまりないですが、日本ですらマイノリティになろうとしてますからね。髪も青くしてよかったです。会社でかなり悪目立ちして知らない先輩に目をつけられることもあったけど、逆に「イケてる髪のやついるじゃん!」って声をかけてくれるアントレプレナー精神をもった社員さんが仕事をくれたりしました。相性が良い人からは好かれて、合わない人からは嫌われる。結果的に堅くないクライアントを多く担当させてもらえました。そういう面で得意なことしかやらないぞっていう意思表明になりました。
市原:クリエイターとして生き抜いていく上で、今後やりたいことは何ですか?
草野:アーティストとして作品を増やしたいです。Satellite Youngも引き続き精力的にやっていくけど、ソロでもアート作品を発信していきたいです。来年はそういう年にしたい。自分の作家性を形にしていく。そんなことを考えています。具体的に言うと、架空のプロダクトや広告などをつくってみたいです。Satellite Youngで、ある種の架空の未来から来た昭和アイドルを造りあげてきたので、これからもレトロとフューチャーが混在した世界の中で、架空のアトラクションをつくっていきたいです。期待しててください!
市原:ソロ活動は大事ですよね。ずっとチームで創作していると、表現がどのメンバーの作家性なのかだんだんわからなくなって、苦しくなることがあります。私もユニットだけでなく個人での活動を多くした時期があったんですけど、すごく良かったです。そもそも自分が何をやりたくて、どういうスキルがあって、というのが洗い出せるので。会社を辞めて、自由になって、これからますます作家活動が爆発するのですね。応援してます!