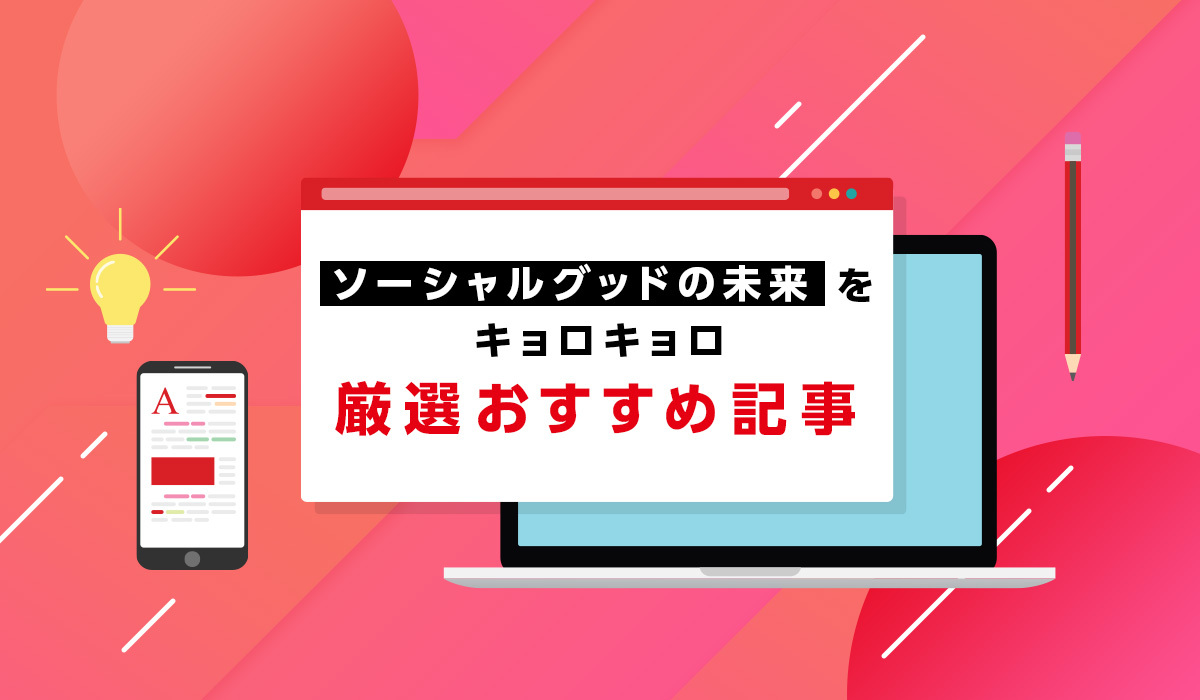世界をアップデートするのは熱量。スポーツ✕教育で、アスリート界に革命を co-step 代表取締役CEO兼ディレクター 林諒さん

現役アスリートからスポーツを教わる時代がすぐそこまでやってきているかもしれません。マーケティング・クリエイティブ事業とスポーツ・アスリート事業を手がけるco-step代表取締役CEO兼ディレクターの林諒(はやしりょう)さんには実現したい未来があります。それはスポーツを通じて、社会での自立した能力を育成していく、キャリア教育を実現させること。26歳で起業に至った林さんの熱い思いや日本のアスリート事情を通じて、スポーツと教育の未来を見つめます。
──co-stepでは現在、新規事業としてスポーツレッスンのCtoCサービスを開発中とうかがいました。その新規事業「spoit(スポイト)」とはどのようなサービスでしょうか?
「spoit」とは、スポーツレッスンのCtoCサービスです。すべてのスポーツ経験者が持つスキルを、レッスンを通してスポーツを学びたい人へとつなげていくことが可能になるサービスです。もっと噛み砕いて言うと、モノではなく、スポーツスキルを売買するメルカリのようなものといえばわかりやすいでしょうか。CtoCサービスは2020年内のローンチを予定し開発を進めています。2019年11月現在は「スポーツを知る」ための機会として、「スポーツ初心者女子向けスポーツメディア」を先にローンチしています。
スポーツレッスンのCtoCサービスとは?
──スポーツスキルが資産になるCtoC向けサービスというわけですね。なぜspoitを立ち上げようと思ったのでしょうか?スポーツでキャリア教育をしたいという思いと、アスリートに自分のスキルがお金に変わる仕組みを提供したいという思いがきっかけです。

また、ボブスレーは競技の性質上、スピードが速すぎて広告が見えず、広告効果が見込めないため、スポンサーが付きづらいスポーツなんです。ヘルメットを常に装着しているため選手の顔が見えないのも致命的。だからメディアでも取り上げられない。それも要因となって、ボブスレーの知名度はとても低く、選手への負担ばかりが重なり生活は苦しいものとなっています。

ボブスレーの競技シーン。競技中の最高速度は時速130キロメートルにも及ぶ。
──スポーツ体験の機会提供だけでなく、スキルを持つアスリートたちの収益源にもなり得るサービスでもあるということですね。日本ではスポーツでマネタイズするのはハードルが高いイメージがありますが、どのようなことが原因だと思いますか?
いまの日本では、スポーツスキルが社会に開放されていないことで価値として認められづらい環境になっているからだと思います。「スポーツ(部活)の経験は、指導やプロセスを仕事に活かすもので、スキルそのものは仕事にならないよね」というのが常識です。しかしスポーツ市場は2012年時点で5.5兆円あり2025年には15兆円になると言われています。広告が6.5兆円、コンビニが11兆円なので、スポーツの経済価値がいかに高いかがわかると思います。アメリカではすでに50兆円以上で自動車産業をも超えています。それなのに「スポーツスキルに価値はない」とする社会はさすがに強引ですよね。だから「spoit」を通じてスポーツスキルをオンライン上に開放する必要があると思っています。

だからこそ、スポーツ業界にも働き方改革が必要だと思います。「spoit」を通じて、「アスリートが自分のスポーツスキルを人に教えて、お金を稼ぐ」「閉鎖的になりがちなアスリートの世界で、社会との結びつきをつくる」「そこでできたつながりの輪から認知を広げていき伝播していき、応援してもらえるようなきっかけをつくる」、この3つを実現していきたいと考えています。アスリートの働き方改革に一石を投じる、そんな存在をspoitでは目指していきたいと思います。
──いまの話を聞く限り、サッカーや野球といったメジャースポーツのアスリートに比べ、マイナースポーツのアスリートはかなり苦しい現状だと感じ取れます。メジャー・マイナーに関わらず、アスリートがこのような状況にあるのは、日本だけなのでしょうか?
日本だけだと思います。特に日本と海外、とりわけアメリカとはまったく異なり、アスリートに対する価値観自体が異なっています。例えばアメリカでは、NCAA(全米大学体育協会)が「学生の本分は勉強である」と明確に定義していて、練習時間は週20時間まで。通知表の成績はオール3以上でないと部活禁止など厳格なルールがあります。そのため、いくらスポーツができても、学校の成績が悪いと大学へ進学もできません。スポーツだけでなく、勉強もできないといけない。みんなの憧れの象徴として、人々を引っ張っていく。それがアメリカでのアスリートという存在です。しかし日本では、教育面でスポーツが神聖化されすぎていると感じています。

アメリカのアスリートは、自身を売り込むためのポートフォリオを作成し、企業と直接交渉などもしますが、日本ではまずありえないでしょう。そのため日本では、スポーツ一本で進み続けたアスリートがいざ社会に出たとき、一人で歩くことすらできなくなってしまう場合がある。これらは日本の「スポーツを神聖化する」価値観や教育観により生まれた独自の問題と言えると思います。
──スポーツ選手に対する価値観や教育観が日本とアメリカでそこまで異なるとは…。
また、2020年に控えた東京オリンピックにより、メジャー・マイナーを問わず多くのアスリートが注目されていますが、これらも一過性のムーブメントになってしまうと強く感じています。
東京オリンピックによりフィーチャーされ、メーカーとプロ契約を結ぶアスリートはたくさんいます。しかし、オリンピックという一大イベントが終わったあとに、すべてのメーカーがスポンサービジネスとしてアスリートとの契約を続けていくでしょうか? オリンピックが終わったあとに契約が解消され、路頭に迷うアスリートが現れるのは目に見えています。もしそうなれば協会も広告主も、誰も守ってくれない。それを理解し、そうなったときにどうやって自分自身で生きていくのか、キャリアをつくっていくのか、日本のアスリートは考えなければなりません。
世界をアップデートするのはデータの上に注ぐ熱量
──アスリートやスポーツに対して熱い思いをお持ちですが、林さんもかつてなにかスポーツに打ち込んでいたのですか?僕は小学校から大学までずっと陸上競技に打ち込んできましたが、中途半端な成績でした。中学のころ、中国地方で一番になったこともありましたが、高校、大学と進むうちに、上には上がいることを痛感しました。陸上選手として将来的に食べていくことは、自分の実力では不可能だと悟ったのです。そこから、大学のゴールを陸上から就職活動にシフトチェンジし、やりたいことが見つかったとき、すぐにその道を選択ができる状態でいるために、「自分探しではなく、自分づくりをしよう」と決めました。ベンチャー企業でフルタイムバイトをして働いたり、米国のNPOで働いたり、とにかくいろいろな経験をし、たどり着いた答えは「教育」でした。そして新卒で教育業界大手のベネッセコーポレーションに入社しました。

ベネッセでは高校生向けに講演会や研修を年間200本以上行ったり、模試などの客観データに基づく進路サポートを行ったりする仕事に携わってきました。そしてそのなかで、ある課題を感じるようになりました。それが教育におけるエンターテインメント性です。
教育におけるエンターテインメント性とは、いかに「勉強を勉強っぽくなく魅せるか」ということです。日本の学校教育の基本は、基礎となる教科書にしっかり従うことです。しかし、それだけでは生徒はつまらない。講演をしていても、真面目に自宅学習時間の重要性を説いたところで聞いてくれる生徒と、そうではない生徒の差が顕著でした。
その状況を打破しようと試行錯誤をしていたあるとき、講演の冒頭に当時流行っていた教育を題材にしたドラマの話を織り交ぜたり、動画を使ったりしたら生徒の反応がすごく良くなったんです。そこで思いを伝えるには魅せ方や、エンターテインメント性が重要だと強く感じました。
それをきっかけに、モノづくりとエンターテインメント性を追求し、それを教育に組み込ませた事業を将来立ち上げたいと思うようになりました。それをかなえるため、ベネッセは退職し、大手制作会社のROBOTに転職。そこでクリエイティブの武者修行をしたのちに、マーケティング・クリエイティブ事業とスポーツ・アスリート事業を両輪で手がけるco-stepを起業しました。

クリエイティブに携わるようになって感じていることは、熱量がなによりも大切であるということです。それを体現する仕組みとして、co-stepではプランナーやデザイナーなど、職能で縦割りをするのではなく、一人のディレクターが一気通貫して案件を担当する体制を整えています。
通常、広告・クリエイティブ業界ではプランニングはプランナー、進行管理はPM(プロジェクトマネージャー)が担当する、完全縦割りスタイルであることが多いと思います。確かに効率的ではありますが、同時に弊害も存在していると思っています。
──それはどのような弊害なのでしょうか?
分業をすると、クライアントの課題に対して上流のマーケティング戦略を考える人はマーケターやプランナーだけ。本来はアウトプットを担当するクリエイター(デザイナー/エンジニア)が上流部分を理解していないと良いクリエイティブはできないですが、「マーケター/プランナー」⇒「営業」⇒「制作現場のディレクター」⇒「デザイナー/エンジニア」と伝言ゲームのように降りてきたプランを形にするだけ。という自分の職能が持つ領域のみを考えることに陥る場合があるからです。それではクライアントの真意が伝わりにくく、クライアントが本当に求めているものが実現しにくい。
そういう仕組みで発生するもう一つの弊害が、問題が起きたときに誰も責任を持たなくなるということです。「これは営業のせいだ」、「そもそもプランナーの企画が間違ってる」など、問題が起こったときに他人のせいにできる環境が生まれてしまう。そんな環境で生まれたものに、果たしてクライアントは満足するでしょうか?

──つくり手の慢心はユーザーにも熱として伝わっていくと。
おっしゃるとおり、モノづくりにかけた熱量はそのままユーザーにも届きます。そして、熱量が正しく届いて伝わることによって人の心は動かされるんです。
テクノロジーが発展したいまでこそビッグデータを分析し、答えを導くことは重要ですが、データだけでは世の中をアップデートすることはできません。なぜなら人間が築き上げてきた2000年の歴史で、人の心を動かすために熱量は常に存在し続けていたからです。革命や維新など、世の中をアップデートしていったのはいつの時代でも熱量なんです。
現代は合理的なモノ/サービスが大量に生産され、同時に大量に消費されています。そのため一つひとつにつくり手の想いが薄れてきてしまっているのではないかと思っています。だからこそ、次の時代の一歩先へ進むのに必要なものは熱量です。co-stepではマーケティングやクリエイティブ、そして新規事業の「spoit」に熱量を込めて、それを反映させていきたいと考えています。
──日本のアスリートが抱える問題。それを解決する一つのプラットフォームを目指すスポーツレッスンのCtoCサービス「spoit」がこの先をどのようにアスリートの生活シーンを変えていくのか。とても期待がかかりますね。そして合理化の時代だからこそ熱量が必要である。とても熱く、かつロジカルにお話いただきました。お話いただきありがとうございました!