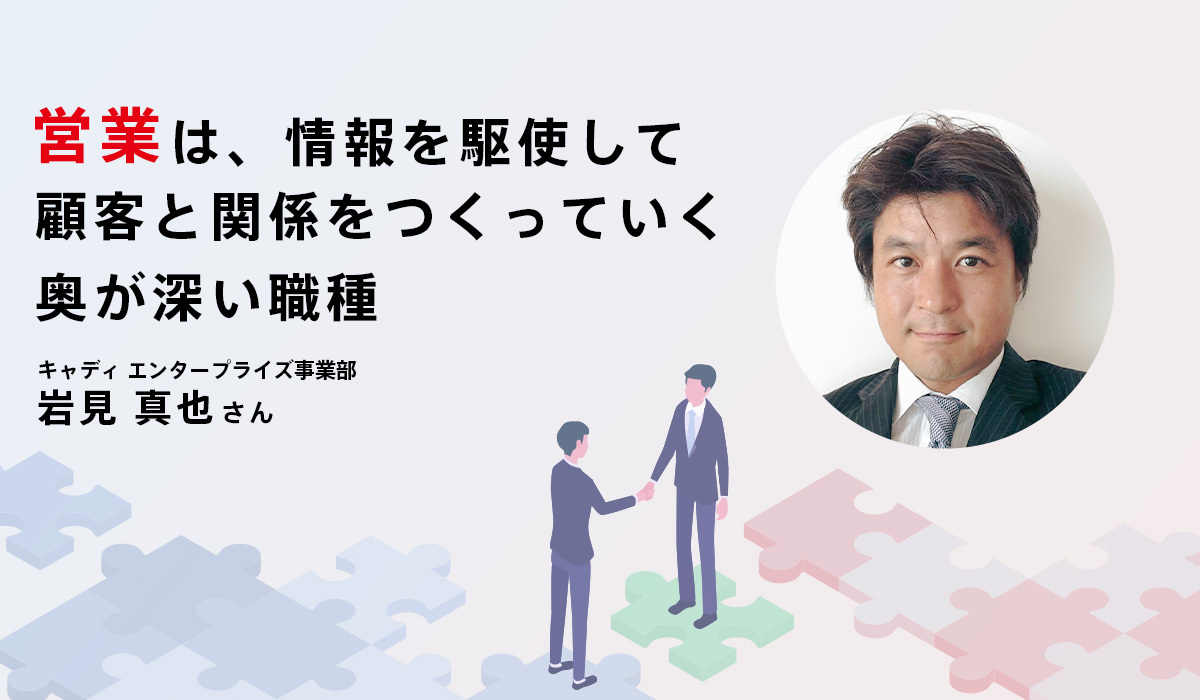ボードゲームづくりは真っ暗な洞窟探索。「好きを仕事に」でしか味わえないやりがいと苦悩 バンソウ 取締役/ボードゲームデザイナー 宮﨑雄さん

近年注目を集めているボードゲーム。子どもの知育玩具としてはもちろん、コミュニケーションツールの1つとして、大人にも人気です。株式会社バンソウでは、脳がとろける超理系カルタ「トポロメモリー」、“言葉の重さ”で遊ぶパーティーゲーム「コトバグラム」などを制作。それらを手掛けるのは、同社の取締役であり、ボードゲームデザイナーの宮﨑雄さん。大学時代からボードゲームで遊んでいたという宮﨑さんですが、現在は一般向けに留まらず、企業の研修や社内行事向けにもボードゲームを制作されています。
advanced by massmedianでは「好きを仕事に」をテーマに、さまざまな領域で、“好き”を追求し、活躍している方々を取材。今回は宮﨑さんに「好きを仕事に」する際の注意点や、ボードゲームの可能性について語っていただきました。
advanced by massmedianでは「好きを仕事に」をテーマに、さまざまな領域で、“好き”を追求し、活躍している方々を取材。今回は宮﨑さんに「好きを仕事に」する際の注意点や、ボードゲームの可能性について語っていただきました。
好きと愛、好きと得意
──宮﨑さんはもともとボードゲームがお好きで、いまは「トポロメモリー」シリーズや「コトバグラム」、さらにはコンテンツスタジオCHOCOLATEとの共作の「DEATH NOTE人狼」などユニークなボードゲームを次々に生み出していますよね。まさに「好きを仕事に」を実践されている印象があります。厳密に言うと、私はボードゲームが「好き」で、ゲームの仕組みを考えることが「得意」なんです。ただし、ここでいう「好き」は「Love」ではなく、「Like」のニュアンス。いくら好きだと言っても、ボードゲームという形に固執してしまっては、得意なことを活かしきれないことがあります。これまでに手掛けた作品も、得意を活かすことが念頭にあり、その表現方法としてボードゲームがマッチしただけなんです。
──優先しているのは「好き」よりも「得意」なのですね。
「好き」と「得意」のどちらに進むべきか悩んでいる人は、まず「得意」なことを仕事にしてみることをおすすめします。得意なことを仕事にすると、自然と成果が出しやすい。成果を積み重ねると、お客さんや仲間からの信頼度も上がっていくので、新たな仕事にチャレンジしやすくなります。このサイクルを続けていくなかで、「好き」なことが舞い込んでくるようになり、結果的に「好きであり得意」なことができるようになります。
私の場合は漫画『DEATH NOTE』が好きだったのですが、実績を重ねてきたおかげで、CHOCOLATEさんから声をかけてもらい、「DEATH NOTE人狼」を制作することになりました。まずは得意なことで尖った存在になる。そうすれば、好きなことをできる確率が上がるのだと感じました。

実際にプレイすることも楽しいですが、この仕事はゲームの仕組みそのものを考えることができるので、また違ったやりがいを感じますね。「このルールは面白いのではないか」というアイデアをひらめいた瞬間は、とてもワクワクします。人の心を動かす手段としては、言葉や映像でメッセージを届ける方法がメジャーだと思います。しかし、ボードゲームは体験を通して楽しませることができるので、ほかにはない特別な魅力を秘めているんです。

忘れてはならないのが、あくまで仕事だということ。遊びのその場のノリでゲームをつくっているわけではありません。再現性がある仕事をしているということを発信していく必要があります。いまの時代はTwitterやnoteなど、情報発信の手段に困ることはありません。だからこそ、情報の内容には十分に配慮すべきです。「好き」という想いだけではなく、あくまで仕事として論理的にゲームを分析し、私たちのつくるゲームに価値があるということを伝えるべきだと考えています。そういった情報発信を行うからこそ、再現性があると思ってもらえるし、結果を出せると見込んでくれたクライアントから依頼をいただけています。
ゲームはメディアなので、「ゲームつくりたいからゲームつくる」だとずれそう。「◯◯を伝えたり、媒介するのにゲームをつくる」のほうがスッといける。マンガとか小説でも同じじゃないだろうか。メディアは手段であって、目的ではない。
— ミヤザキユウ | ボードゲームデザイナー@バンソウ (@zakimiyayu) February 21, 2020
──宮﨑さんは、大学生の頃からボードゲームで遊んでいたのですよね。自分でつくろうと思ったきっかけなんだったのですか?
社会人2年目のときに、ボードゲームづくりを体験できるワークショップに参加したんです。それまではボードゲームをつくるという発想がなかったので、とても新鮮でした。実際につくってみると、自分のアイデアを形にできることが楽しくて、気がつくと夢中になっていましたね。それから、ワークショップで出会った仲間たちと東京ゲームメイカーズを立ち上げ、みんなでつくったゲームで遊んだり、イベントに出店して販売したりしていました。そして2018年6月にバンソウを起業し、仕事として本格的にボードゲームをつくるようになったんです。
“好きを仕事に”は苦しい
──宮﨑さんがこれまでに手掛けたボードゲームのなかで、特に印象に残っている作品を教えてください。強いていえば「コトバグラム」ですね。これは完成するまでに半年ほど掛かりました。きっかけは、デイリーポータルZの「『愛してる』をてんびんで釣り合わせたい」という記事です。「言葉の重さ」という概念に注目し、「愛してる」に相当する言葉を見つけていく内容です。これに触発されて開発した「コトバグラム」は、プレイヤーごとに4段階の重さを表現するカードを駆使して、お題となる言葉の重さがどれくらいかを当てる、というゲームです。


「これはゲームになりそうだ」というきっかけを掴んだ瞬間や、基準のないところから、ゲームを面白くするルールや仕組みを考えられたときは最高に楽しいです。それ以外の時間は、正直不安しかないですね。ゲームづくりは、暗い洞窟を走り続けることと同じです。ゲームをつくるプロセスは不確実性が高く、正解がありません。ワクワクしながら飛び込んだ洞窟でも、その道が本当に正しいのか、そもそも出口があるのかもわからない。だからといって、洞窟に挑まないことには、答えは見つからない。面白いゲームを生み出すためには、暗闇を進み続けなければならないんです。仕事をしているときは不安だらけですが、完成したゲームが店頭に並び、一般の方が手に取って楽しんでくれたときは、とても安心しますね。
──暗い洞窟に挑み続けているからこそ、魅力的な作品が生まれているのですね。ボードゲームづくりを通して、この先目指していることなどはありますか?
日本では、ゲームに娯楽のイメージを持たれてしまうことが多いですが、実際はもっと幅広い意味を持っています。娯楽としてだけでなく、さまざまな場所にゲームを取り入れるべきだと思うんです。人の営みには、すべてゲームの要素が含まれています。日本の資本主義というシステムでさえ、ある意味ゲームなんです。そんな風に考えられるようになれば、人生を楽しめる人はもっと増えていくと思います。私は、ゲームをもっと身近なものにしていきたいんです。
最近は、企業の研修の一環でゲームをつくらせていただく機会も増えてきました。研修にゲームを取り入れると、コミュニケーションを活性化しつつ、学びを得られるようになります。そんな風に、難しいことや身近に感じられずに敬遠してしまうことでも、ゲームとして楽しみながら接することで、距離を近づけることができます。遠い存在のものをゲーム化し、身近に感じられるようにする。この流れをいかに面白い形で提供できるか、今後も挑み続けていきたいと思っています。
──宮﨑さんの“好き”が詰まったボードゲームが、世の中に新たな価値観を与える日が近いかもしれません。次はどんなアイデアで私たちを楽しませてくれるのか、今後も注目していきたいと思います。本日はありがとうございました!