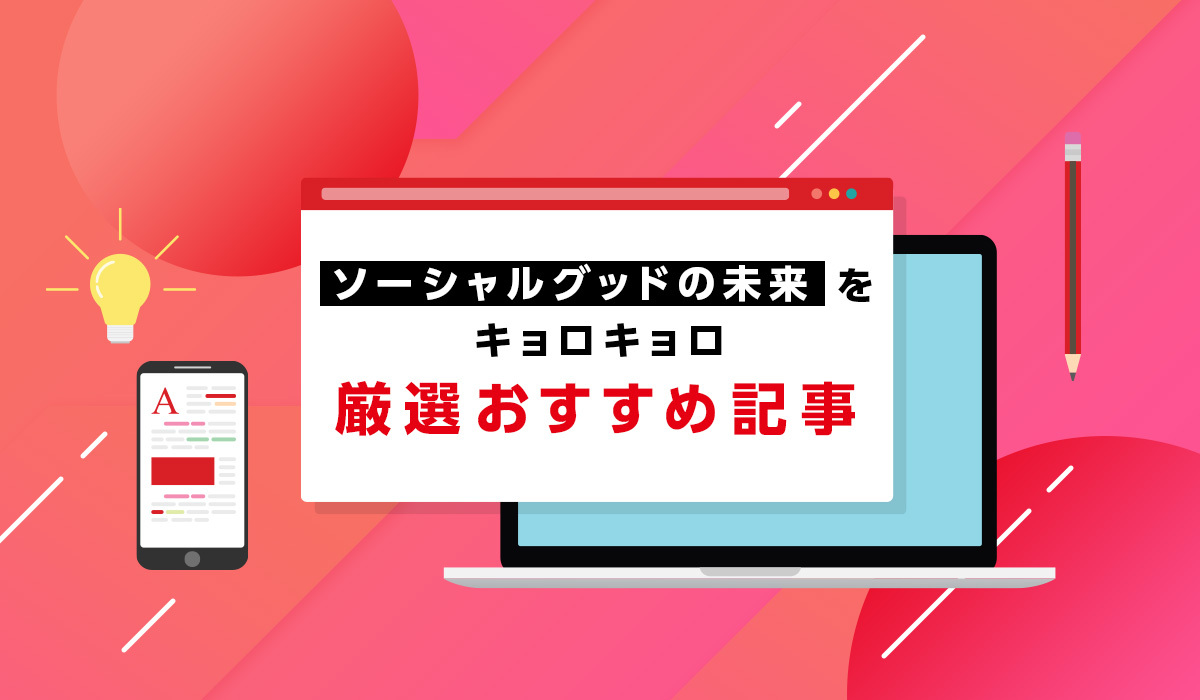ガラパゴス化するな! クロスボーダーをして価値を見つめ直す 日本酒応援団 代表取締役 古原忠直さん

日本酒が大好き! そんな強い想いから立ち上げられた会社があります。名前は「日本酒応援団」。企業サイトのドメインも“we love sake”という徹底ぶり。同社は、「日本酒のあるライフスタイルを、世界中に。」というコンセプトのもと、1県1蔵の酒蔵とパートナーシップを結び、共同で新しい日本酒を造り独自ブランドを立ち上げています。2014年にボランティアとしてプロジェクトが始動し、2015年に一念発起して起業。わずか3年で6銘柄を展開するに至っています。
日本酒業界が陥っている「地方の小さい酒蔵の廃業」や「酒蔵近辺の耕作放棄地」などの諸問題を解決するエコシステムを構築すべく日々奮闘する日本酒応援団・代表取締役の古原忠直(こはらただなお)さん。業界の慣習や偏見にとらわれず、俯瞰的でグローバルな視点は我々に多くに気づきを与えてくれます。会社の立ち上げ経緯から、これからのブランド論まで幅広くお話を伺いました。
日本酒業界が陥っている「地方の小さい酒蔵の廃業」や「酒蔵近辺の耕作放棄地」などの諸問題を解決するエコシステムを構築すべく日々奮闘する日本酒応援団・代表取締役の古原忠直(こはらただなお)さん。業界の慣習や偏見にとらわれず、俯瞰的でグローバルな視点は我々に多くに気づきを与えてくれます。会社の立ち上げ経緯から、これからのブランド論まで幅広くお話を伺いました。
──まずは、日本酒応援団を立ち上げた経緯についてお話しいただけますか。
僕がもともと消費者として日本酒が大好きだということが根底にあるのですが、はじめは法人ではなく、ボランティア組織としてスタートしました。きっかけとなったのは、島根県にある友人の実家の酒蔵です。この蔵は、年に一度だけ地元の方と一緒に飲むために極少量のお酒を造っていました。このため、もう10年以上、本格的なお酒造りを停止しているという話を聞いたんです。業界全体でも、1980年代には約3000蔵あったのに対して、現在は約1400蔵と、30年で半減している。地産地消でやってきた家族経営の蔵が多いので、過疎化が進んで地元の消費が落ちると、生産量も減らさざるを得ない。さらにつくり手も減ってしまい廃業に追い込まれるという事態が増えていたのです。加えて日本では、基本的に新規の製造免許を付与しないという背景もありました。こうした現状を知って、一人の消費者としておいしいお酒をつくる人が減っていくのは悲しいなと感じ、まずは島根の蔵が生産を再開できるようにお手伝いしてみようと、ボランティアとして日本酒応援団というプロジェクトを立ち上げました。そこで、昔の蔵人さんを呼び戻して実際に日本酒をつくってみたことで、蔵が直面している問題や、地元の人たちの想いを改めて知りました。酒蔵って地元のプライドの1つなんですよね。日本酒の原材料はお米で、地元の農家さんがつくっていた。けど、廃業した蔵のまわりを見渡すと耕作放棄地だらけで、問題が浮き彫りになっている。そういうものを見ていくなかで、本腰を入れて事業にしようと2015年の7月に法人化しました。
いえ、新卒で三菱商事に入社して、その後も国内外の投資会社でベンチャー投資の仕事をしていて、お酒どころか製造も小売もやったことがなかったんです。ほかのメンバーも含め、純粋に飲み手として日本酒が好きな人たちが集まったのが当社の始まりですね。仕事として日本酒に携わってきたわけでもなければ、僕の場合は酒蔵を継ぐ必然性もない。危機感でもなければ、事業性でもない、なんとかしたいという気持ちだけだったんです。僕はよく「日本酒愛」と言っているのですが、好きという気持ち、そしてそこに本気でコミットしていこうという熱意が、何をするにおいても一番大切だと思います。
──持続可能で長く社会に求められるためには、儲けありきではなくて、ミッションやビジョンから湧き出る熱量が大事なんですね。
そうですね。もちろん儲けを出さないと継続できないので、両立が大事だと思います。僕は三菱商事のときも含めて12~13年、ベンチャー投資の仕事をしていました。起業する方々と仕事をする機会が多くあったので、たくさんの成功例や失敗例を見てきたのですが、ベンチャーが失敗する最大の要因って人なんです。やる気が続かない、途中で諦めてしまうという問題は、成功するまでコミットし続けられる、ドライブし続けられる熱量を持っているかに懸かっています。そのうえで、市場性も非常に重要なので、マーケットにおいて商品やサービスを求めている人がいて、成長が見込めるのであれば、会社として収益を出すことができて事業を成長させられる。その両輪だと思います。後者だけだと絶対に続かないんです。
島根の蔵でつくった「KAKEYA」をはじめ、すべて町の名前がそのままお酒の名前になっています。いずれも小さな酒蔵ですが、それぞれ技術力も高く丁寧なお酒づくりをされていて、日本酒を世界に広げていきたいという当社のビジョンや、ローカルにこだわった商品づくりに共感いただいています。町の名前がついているのは、そこで酒をつくっているだけでなく、原料のお米や水も地元のものを使っているからです。また、地元の食文化に合う味わいにもこだわっています。食文化ってお酒の味わいを大きく左右しているんですよ。大分県にも蔵があるのですが、たとえば醤油だと、九州、特に大分のものって甘いんです。甘い味付けの食事に合うのは、味わいがしっかりとした甘めのお酒なので、大分では伝統的に甘口のお酒がつくられていました。今はどの蔵でも辛口から甘口まで全部つくっていることが多く、山田錦という兵庫県のお米がよく使われているのですが、そればかりでは個性がなくなってしまいますよね。もちろん山田錦は優れたお米ですし、最終的には飲む方の好みなので正解はないですが、我々はローカルであることに強くこだわっています。 ──ワインで言う「テロワール」のような、地元の食文化とのペアリングを意識されているのですね。ビジネスモデルとしては、この6品種を製造して、流通も自社で行っているということでしょうか。
──ワインで言う「テロワール」のような、地元の食文化とのペアリングを意識されているのですね。ビジネスモデルとしては、この6品種を製造して、流通も自社で行っているということでしょうか。
自社で蔵を持っているわけではないので、工場を持たないメーカーという感じでしょうか。企画段階から携わって開発したまったく新しい商品なので、そういう意味でメーカーだと思っています。販売に関しては、高島屋さんと一緒にさせていただいたり、インターネットを使った直販をしたりと様々です。ちなみに、高島屋さんは売り手の立場にはなりますが、必ず酒蔵に足を運んでもらっているんですよ。田植えや作付けから一緒に行い、製造の現場をきちんと見て、直に触れていただくことで、我々の熱量を共有しています。
──酒蔵さんは、自社ブランドとは別に、貴社ブランドの製造を行っているということでしょうか。
そうです。たとえば大分の萱島酒造さんは、もともと「西の関」というブランドでお酒をつくっています。既存につくっているものを当社が卸売やインターネットで販売するというのは、チャネルは増えるけど純生産量アップにはならないですよね。一方、当社でつくっている「KUNISAKI」はまったく新しいお酒なので、酒蔵にとっては、完全なる上乗せで生産量が増えます。この場合、お米もすべて地元の国東でつくっているので、この土地でのお米の生産量も増える。そういう形で、地元にきちんと還元していきたいという強い思いがあります。
かなり密に、商品づくりを0から行っています。どんな商品をつくりたいかを考えるとき、その土地らしいお酒、また、その蔵が得意な技術を活かせるものはなにかというところから始めます。というのも、日本酒ってだたの「飲料」と言ってしまえばそれまでなのですが、「価値」はその背景を体験するところにあると思っているんです。たとえば、産地について知ることで味わいが変わってくる。地元の蔵の方から話を聞きながらそのお酒を飲んで、地元の醤油と合わせて刺身を食べると何倍もおいしいですよね。すべての場所に行ってそれを体験するのは難しいですが、それに近い体験をしてほしいという思いがあります。また、お酒を飲んだときに、純度がどうとかスペックの話だけだとあまり面白くないですよね。だから、裏ラベルには、スペックではなくそのお酒を表すキャッチコピーを書いています。実はこれを考えるのに半年くらいかかっているんですよ。どうしてこういう味わいになったのか、蔵元さんのちょっとしたストーリーになっているんです。それがひとつの個性ですよね。当社が目指しているのは、単純に飲料としての日本酒を飲むだけでなく、背景にあるものも一緒に体験してもらうという世界観です。それぞれのストーリーを飲む方にロスなく提供したいので、ロゴひとつとっても、すべてのデザインに理由があります。もちろんすべてを伝えきれるわけではないですが、ローカルな個性を活かした商品づくりを通して、ひとつの体験として今回は大分に行ったから次は能登に行ってみようというように楽しんでもらいたいですね。 ──たしかにスペックだらけで情報量が多いと敬遠してしまいますね。
──たしかにスペックだらけで情報量が多いと敬遠してしまいますね。
ほかの日本酒のラベルを見てみると、専門用語が多いですよね。僕自身もこの業界に入る前は、大吟醸とか生酒とか、よくわからないものもが多いなと感じていました。このため当社ではわかりやすくシンプルに伝えることを重要視しています。だから、当社のお酒は純米かつ生のお酒なんです。スペック部分を統一してしまって、迷わせることのないようにしようと思ったんです。いろいろ違いがあると、それもきちんと説明しないといけないけど、「当社のお酒=純米で生」なので説明がいらない。一応書いてはいますが、それよりも地域性や個性を楽しんでほしいんです。すべてのスペックを我々がカバーできるわけでもないですし、日本酒を含めた嗜好品が最終的に行き着くのは個性だと思うんです。だから、何を捨てるのかも大切ですね。情報量が多すぎても圧倒されてしまうし、こちらが伝えたいことが100あっても、その100を同じ熱量で受け取れるわけではない。買うお酒を決めるのも一瞬の判断ですし、飲むときもそんなに長い時間接しているわけではないので、短い時間でいかにきちんと伝えられるかが我々の仕事ですよね。
──無駄なものを削ぎ落とすという感覚はどこで培われたものなのでしょうか?
ひとつは飲み手としての経験ですね。日本酒の知識があまりなかった時期を思い出すと、専門用語を使うことが本当に必要なのかな、理解されるのかなと感じますよね。日本酒が大好きで、かつ仕事にしているわけでもなかったので、偏見なく良し悪しを見られたんだと思います。また、もうひとつは、シリコンバレーでの留学経験やベンチャー投資の仕事を通して叩き込まれたものかもしれないですね。引き算をして、シンプルにわかりやすく伝えないと、そもそもなにも伝わらない。シリコンバレー発のAppleやTwitter、Instagramいずれもシンプルですよね。とにかくフォーカスしろということをひたすら叩き込まれるんです。
我々も創業4年目のベンチャーですし、そういった新しい取り組みが増えるのは非常に良いことだと思います。ひとつの業界や市場が盛り上がるときには、必ず多くの参加者がいて、トライアル&エラーを繰り返していますよね。淘汰されるものもあるなかでイノベーションが起きていると思うんです。だから、プレイヤーが増えていろいろなことが試されることで、世間の注目が集まり飲み手が増えるのは非常に嬉しいことですよね。やっぱりひとつの大きな波が来ないといけない。さらに増えていってほしいですし、業界にとってもポジティブなことだと思います。 ──では業界ではなく、日本酒自体の未来はどのように見据えていらっしゃいますか?
──では業界ではなく、日本酒自体の未来はどのように見据えていらっしゃいますか?
個性に尽きると思います。先ほど現在の蔵の数が約1400と言いましたが、各社さん何銘柄かつくっているので、世の中にある日本酒の種類は1万を超えています。そこで、みんなが同じスペックのものをつくっても個性が出ないです。そうなると、量産できるメーカーのほうが安くつくれるし、流通チャネルが多いところほど多く露出できる。消費者がそれに飽きてくると市場は縮小していきます。だから、ひとつひとつの商品が、個性を持ってユニークさで尖っていくことが重要です。
──特に日本酒のような嗜好品はそれが強く求められるのでしょうね。
そうなんですよね。メーカーという立場としては、兵庫県産の山田錦を使った方が短期的には売りやすいんですよ。印籠のようなものですし。そういうなかで、我々は逆張りでローカルに回帰していっています。埼玉のお酒だと、お米だけではなくて、酵母も埼玉県が開発したものを使っているんです。それぞれの蔵のストーリーってひとつしかない、それって真似できないものですよね。オンリーワンの個性を極めていくということが大事だと信じてやっています。時間もかかるし、引き算をしていくのは勇気もいります。かつ、それが飲む方にとっておいしいものでないといけないので、そのバランスが重要ですよね。日本酒の製造は、年に1回しかPDCAを回すことができないのですが、伝え方やいかに体験してもらうかという面ではもっと早く回せるので、そこは意識してやっています。
幼少期と大学時代で計10年ほどアメリカに住んでいたので、日本という国を外から見る機会は比較的多かったですね。そこで感じたのは、今後、日本酒を含めたあらゆるものが、垣根を超えてクロスボーダーしていくということです。多大な情報が流通して、人の行き来も増えると、国や人種の単位もだんだん曖昧になってくると考えています。そういう世の中で日本酒のあり方を考えると、蔵だからここまでしかやらないとか、販売者だから、飲み手だから、という垣根すらも少なくなっていくのではないかと思っているんです。さらに、今後成長が見込める海外市場においても、国内・海外という捉え方でなく、普遍的な視点で見る必要があると思います。ワインの市場を見ても、フランス産なのかナパバレー産なのかではなく、もっとグローバルな視点でものごとを考えていますよね。
──海外で日本酒がブームになってきているので、海外産の日本酒の逆輸入みたいなことも起こり得ますよね。
容易にあると思いますね。これまで日本酒はガラパゴスの中で育まれて、規制があったからこそ蔵は長く続いた。そのなかで個性が出てきたという側面もあるので、すべてが悪いとは思いません。ただ、海外から日本を見たときに、その特殊性は感じますね。携帯電話も同じだと思うのですが、2000年代前半には日本の技術が圧倒的に世界をリードしていたはずなのに、今では逆転が起きていますよね。やはり日本酒も含め、あらゆるものにおいて、一度ボーダーを取っ払って、どうあるべきかを考える必要があるのではないでしょうか。どの業界においても大事なことですが、特に日本酒は顕著なのかもしれないですね。 短期的に見ると、実際に和食ブームだと思いますし、日本酒の輸出も年々増えています。ただ、日本酒の輸出額は2017年で180億円。フランスワインの輸出額の100分の1なんです。日本酒市場全体で見てもおそらく2~3%です。たしかに、前年比で150%以上増えているのは立派なことですが、その延長線上に未来を考えるのは違うと思っています。現在、海外でも日本酒をつくりはじめている動きがあるのですが、日本は、国内でつくったものだけを「日本酒」と呼んで、海外でつくったものは名乗れないという法令をつくって強制力を持たせようとする動きもあるそうです。国内の酒蔵が保護されるいい面もあるかもしれませんが、長期的に日本酒市場が世界で伸びていき、結果的に国内の酒蔵もその恩恵を受けるために、それが本当に良いのか。世界で普遍的な存在になるって、そういうやり方だけではないのではと思っています。
短期的に見ると、実際に和食ブームだと思いますし、日本酒の輸出も年々増えています。ただ、日本酒の輸出額は2017年で180億円。フランスワインの輸出額の100分の1なんです。日本酒市場全体で見てもおそらく2~3%です。たしかに、前年比で150%以上増えているのは立派なことですが、その延長線上に未来を考えるのは違うと思っています。現在、海外でも日本酒をつくりはじめている動きがあるのですが、日本は、国内でつくったものだけを「日本酒」と呼んで、海外でつくったものは名乗れないという法令をつくって強制力を持たせようとする動きもあるそうです。国内の酒蔵が保護されるいい面もあるかもしれませんが、長期的に日本酒市場が世界で伸びていき、結果的に国内の酒蔵もその恩恵を受けるために、それが本当に良いのか。世界で普遍的な存在になるって、そういうやり方だけではないのではと思っています。
シャンパーニュでつくったものを「シャンパン」と呼ぶように、産地を限定したものはありますね。だた、それはブランドの話です。実はフランスで、1976年に「パリスの審判」と呼ばれるセンセーショナルな出来事がありました。当時、ワインはフランスつくったものが圧倒的な存在で、そのほかはワインではない別物だとみなされていたんです。そのような状況で行われた有名なブラインドテイスティングの場で、ジャッジも全員フランス人だったのですが、1位から10位を米・ナパバレーのワインが独占したんです。フランスにとっては衝撃的な出来事でしたが、実はその後、フランスワインの輸出も伸びたんですよ。世界中でつくられるようになることで、ワインをもっと気軽に楽しむ層が増えたんです。そのなかで、やっぱり老舗がおいしいということで、フランスのワインも飲んでみようという消費者が増えた。日本酒も同様になっていくかはわからないですが、世界中でもっと身近な存在になって、そのなかでもやっぱり日本のお酒がおいしいとなればいいなと思いますし、それは飲む方が判断することであって国が認定をして判断するものではないですよね。
──飲み手の日本酒リテラシー、ワインリテラシーが上がることで、おいしさがわかるようになるからこそ、原点回帰をしてそのルーツの消費も上がるということなんですね。
そうなんですよ。最終的には自由競争だし、飲み手に支持されないといけない。今の日本酒の現状って、国内では2000円ほどで売っているものが、海外に行くと3~4倍の値段がついているんです。輸出の量が少ないことも要因ですが、その値段では市場が広がるはずないんですよ。ワインはそこをクリアしているんですよね。さまざまな地域でつくられたてきた歴史があって、大手が独占しているというわけでもなく、小さなプロデューサーがたくさんいる。ナパバレーのワイナリー数だけで、日本の酒蔵の数より多いんですよ。そういうことを考えると、守る方向よりもクロスボーダーしていくべきだし、世の中の流れもそうなっているので、それを見据えてなにができるかを考えることが非常に重要だと考えています。我々としては、ローカルにこだわって、ほかにはない体験を商品価値として提供していくことを個性としていきたいなと思います。
──自分のアイデンティティをしっかりと認識したうえで、そこに閉じこもるのではなく、飛び越えクロスボーダーしていくことが重要なんですね。興味深いお話、ありがとうございました!

僕がもともと消費者として日本酒が大好きだということが根底にあるのですが、はじめは法人ではなく、ボランティア組織としてスタートしました。きっかけとなったのは、島根県にある友人の実家の酒蔵です。この蔵は、年に一度だけ地元の方と一緒に飲むために極少量のお酒を造っていました。このため、もう10年以上、本格的なお酒造りを停止しているという話を聞いたんです。業界全体でも、1980年代には約3000蔵あったのに対して、現在は約1400蔵と、30年で半減している。地産地消でやってきた家族経営の蔵が多いので、過疎化が進んで地元の消費が落ちると、生産量も減らさざるを得ない。さらにつくり手も減ってしまい廃業に追い込まれるという事態が増えていたのです。加えて日本では、基本的に新規の製造免許を付与しないという背景もありました。こうした現状を知って、一人の消費者としておいしいお酒をつくる人が減っていくのは悲しいなと感じ、まずは島根の蔵が生産を再開できるようにお手伝いしてみようと、ボランティアとして日本酒応援団というプロジェクトを立ち上げました。そこで、昔の蔵人さんを呼び戻して実際に日本酒をつくってみたことで、蔵が直面している問題や、地元の人たちの想いを改めて知りました。酒蔵って地元のプライドの1つなんですよね。日本酒の原材料はお米で、地元の農家さんがつくっていた。けど、廃業した蔵のまわりを見渡すと耕作放棄地だらけで、問題が浮き彫りになっている。そういうものを見ていくなかで、本腰を入れて事業にしようと2015年の7月に法人化しました。

事業継続の源は?
──古原さんは以前のキャリアでもお酒に関わるお仕事をされてきたのですか。いえ、新卒で三菱商事に入社して、その後も国内外の投資会社でベンチャー投資の仕事をしていて、お酒どころか製造も小売もやったことがなかったんです。ほかのメンバーも含め、純粋に飲み手として日本酒が好きな人たちが集まったのが当社の始まりですね。仕事として日本酒に携わってきたわけでもなければ、僕の場合は酒蔵を継ぐ必然性もない。危機感でもなければ、事業性でもない、なんとかしたいという気持ちだけだったんです。僕はよく「日本酒愛」と言っているのですが、好きという気持ち、そしてそこに本気でコミットしていこうという熱意が、何をするにおいても一番大切だと思います。
──持続可能で長く社会に求められるためには、儲けありきではなくて、ミッションやビジョンから湧き出る熱量が大事なんですね。
そうですね。もちろん儲けを出さないと継続できないので、両立が大事だと思います。僕は三菱商事のときも含めて12~13年、ベンチャー投資の仕事をしていました。起業する方々と仕事をする機会が多くあったので、たくさんの成功例や失敗例を見てきたのですが、ベンチャーが失敗する最大の要因って人なんです。やる気が続かない、途中で諦めてしまうという問題は、成功するまでコミットし続けられる、ドライブし続けられる熱量を持っているかに懸かっています。そのうえで、市場性も非常に重要なので、マーケットにおいて商品やサービスを求めている人がいて、成長が見込めるのであれば、会社として収益を出すことができて事業を成長させられる。その両輪だと思います。後者だけだと絶対に続かないんです。
ローカルが個性に
──4年目を迎えた現在は6品種を展開されているそうですが、どのようなお酒なのでしょうか。島根の蔵でつくった「KAKEYA」をはじめ、すべて町の名前がそのままお酒の名前になっています。いずれも小さな酒蔵ですが、それぞれ技術力も高く丁寧なお酒づくりをされていて、日本酒を世界に広げていきたいという当社のビジョンや、ローカルにこだわった商品づくりに共感いただいています。町の名前がついているのは、そこで酒をつくっているだけでなく、原料のお米や水も地元のものを使っているからです。また、地元の食文化に合う味わいにもこだわっています。食文化ってお酒の味わいを大きく左右しているんですよ。大分県にも蔵があるのですが、たとえば醤油だと、九州、特に大分のものって甘いんです。甘い味付けの食事に合うのは、味わいがしっかりとした甘めのお酒なので、大分では伝統的に甘口のお酒がつくられていました。今はどの蔵でも辛口から甘口まで全部つくっていることが多く、山田錦という兵庫県のお米がよく使われているのですが、そればかりでは個性がなくなってしまいますよね。もちろん山田錦は優れたお米ですし、最終的には飲む方の好みなので正解はないですが、我々はローカルであることに強くこだわっています。

自社で蔵を持っているわけではないので、工場を持たないメーカーという感じでしょうか。企画段階から携わって開発したまったく新しい商品なので、そういう意味でメーカーだと思っています。販売に関しては、高島屋さんと一緒にさせていただいたり、インターネットを使った直販をしたりと様々です。ちなみに、高島屋さんは売り手の立場にはなりますが、必ず酒蔵に足を運んでもらっているんですよ。田植えや作付けから一緒に行い、製造の現場をきちんと見て、直に触れていただくことで、我々の熱量を共有しています。
──酒蔵さんは、自社ブランドとは別に、貴社ブランドの製造を行っているということでしょうか。
そうです。たとえば大分の萱島酒造さんは、もともと「西の関」というブランドでお酒をつくっています。既存につくっているものを当社が卸売やインターネットで販売するというのは、チャネルは増えるけど純生産量アップにはならないですよね。一方、当社でつくっている「KUNISAKI」はまったく新しいお酒なので、酒蔵にとっては、完全なる上乗せで生産量が増えます。この場合、お米もすべて地元の国東でつくっているので、この土地でのお米の生産量も増える。そういう形で、地元にきちんと還元していきたいという強い思いがあります。

体験が個性に
──製造責任は蔵元に任せつつ、貴社はマーケットのニーズを反映した商品を一緒に開発していくわけですね。かなり密に、商品づくりを0から行っています。どんな商品をつくりたいかを考えるとき、その土地らしいお酒、また、その蔵が得意な技術を活かせるものはなにかというところから始めます。というのも、日本酒ってだたの「飲料」と言ってしまえばそれまでなのですが、「価値」はその背景を体験するところにあると思っているんです。たとえば、産地について知ることで味わいが変わってくる。地元の蔵の方から話を聞きながらそのお酒を飲んで、地元の醤油と合わせて刺身を食べると何倍もおいしいですよね。すべての場所に行ってそれを体験するのは難しいですが、それに近い体験をしてほしいという思いがあります。また、お酒を飲んだときに、純度がどうとかスペックの話だけだとあまり面白くないですよね。だから、裏ラベルには、スペックではなくそのお酒を表すキャッチコピーを書いています。実はこれを考えるのに半年くらいかかっているんですよ。どうしてこういう味わいになったのか、蔵元さんのちょっとしたストーリーになっているんです。それがひとつの個性ですよね。当社が目指しているのは、単純に飲料としての日本酒を飲むだけでなく、背景にあるものも一緒に体験してもらうという世界観です。それぞれのストーリーを飲む方にロスなく提供したいので、ロゴひとつとっても、すべてのデザインに理由があります。もちろんすべてを伝えきれるわけではないですが、ローカルな個性を活かした商品づくりを通して、ひとつの体験として今回は大分に行ったから次は能登に行ってみようというように楽しんでもらいたいですね。

ほかの日本酒のラベルを見てみると、専門用語が多いですよね。僕自身もこの業界に入る前は、大吟醸とか生酒とか、よくわからないものもが多いなと感じていました。このため当社ではわかりやすくシンプルに伝えることを重要視しています。だから、当社のお酒は純米かつ生のお酒なんです。スペック部分を統一してしまって、迷わせることのないようにしようと思ったんです。いろいろ違いがあると、それもきちんと説明しないといけないけど、「当社のお酒=純米で生」なので説明がいらない。一応書いてはいますが、それよりも地域性や個性を楽しんでほしいんです。すべてのスペックを我々がカバーできるわけでもないですし、日本酒を含めた嗜好品が最終的に行き着くのは個性だと思うんです。だから、何を捨てるのかも大切ですね。情報量が多すぎても圧倒されてしまうし、こちらが伝えたいことが100あっても、その100を同じ熱量で受け取れるわけではない。買うお酒を決めるのも一瞬の判断ですし、飲むときもそんなに長い時間接しているわけではないので、短い時間でいかにきちんと伝えられるかが我々の仕事ですよね。
──無駄なものを削ぎ落とすという感覚はどこで培われたものなのでしょうか?
ひとつは飲み手としての経験ですね。日本酒の知識があまりなかった時期を思い出すと、専門用語を使うことが本当に必要なのかな、理解されるのかなと感じますよね。日本酒が大好きで、かつ仕事にしているわけでもなかったので、偏見なく良し悪しを見られたんだと思います。また、もうひとつは、シリコンバレーでの留学経験やベンチャー投資の仕事を通して叩き込まれたものかもしれないですね。引き算をして、シンプルにわかりやすく伝えないと、そもそもなにも伝わらない。シリコンバレー発のAppleやTwitter、Instagramいずれもシンプルですよね。とにかくフォーカスしろということをひたすら叩き込まれるんです。
日本酒の未来
──そういう意味で、近年の日本酒業界では、AIがその人に合った日本酒をレコメンドするサービスなど、シンプルで尖った取り組みも増えてきているように思いますが、業界の今後はどうなっていくとお考えでしょうか?我々も創業4年目のベンチャーですし、そういった新しい取り組みが増えるのは非常に良いことだと思います。ひとつの業界や市場が盛り上がるときには、必ず多くの参加者がいて、トライアル&エラーを繰り返していますよね。淘汰されるものもあるなかでイノベーションが起きていると思うんです。だから、プレイヤーが増えていろいろなことが試されることで、世間の注目が集まり飲み手が増えるのは非常に嬉しいことですよね。やっぱりひとつの大きな波が来ないといけない。さらに増えていってほしいですし、業界にとってもポジティブなことだと思います。

個性に尽きると思います。先ほど現在の蔵の数が約1400と言いましたが、各社さん何銘柄かつくっているので、世の中にある日本酒の種類は1万を超えています。そこで、みんなが同じスペックのものをつくっても個性が出ないです。そうなると、量産できるメーカーのほうが安くつくれるし、流通チャネルが多いところほど多く露出できる。消費者がそれに飽きてくると市場は縮小していきます。だから、ひとつひとつの商品が、個性を持ってユニークさで尖っていくことが重要です。
──特に日本酒のような嗜好品はそれが強く求められるのでしょうね。
そうなんですよね。メーカーという立場としては、兵庫県産の山田錦を使った方が短期的には売りやすいんですよ。印籠のようなものですし。そういうなかで、我々は逆張りでローカルに回帰していっています。埼玉のお酒だと、お米だけではなくて、酵母も埼玉県が開発したものを使っているんです。それぞれの蔵のストーリーってひとつしかない、それって真似できないものですよね。オンリーワンの個性を極めていくということが大事だと信じてやっています。時間もかかるし、引き算をしていくのは勇気もいります。かつ、それが飲む方にとっておいしいものでないといけないので、そのバランスが重要ですよね。日本酒の製造は、年に1回しかPDCAを回すことができないのですが、伝え方やいかに体験してもらうかという面ではもっと早く回せるので、そこは意識してやっています。
垣根で囲うのではなく超える
──では、グローバルな視点から見た未来はいかがでしょうか。幼少期と大学時代で計10年ほどアメリカに住んでいたので、日本という国を外から見る機会は比較的多かったですね。そこで感じたのは、今後、日本酒を含めたあらゆるものが、垣根を超えてクロスボーダーしていくということです。多大な情報が流通して、人の行き来も増えると、国や人種の単位もだんだん曖昧になってくると考えています。そういう世の中で日本酒のあり方を考えると、蔵だからここまでしかやらないとか、販売者だから、飲み手だから、という垣根すらも少なくなっていくのではないかと思っているんです。さらに、今後成長が見込める海外市場においても、国内・海外という捉え方でなく、普遍的な視点で見る必要があると思います。ワインの市場を見ても、フランス産なのかナパバレー産なのかではなく、もっとグローバルな視点でものごとを考えていますよね。
──海外で日本酒がブームになってきているので、海外産の日本酒の逆輸入みたいなことも起こり得ますよね。
容易にあると思いますね。これまで日本酒はガラパゴスの中で育まれて、規制があったからこそ蔵は長く続いた。そのなかで個性が出てきたという側面もあるので、すべてが悪いとは思いません。ただ、海外から日本を見たときに、その特殊性は感じますね。携帯電話も同じだと思うのですが、2000年代前半には日本の技術が圧倒的に世界をリードしていたはずなのに、今では逆転が起きていますよね。やはり日本酒も含め、あらゆるものにおいて、一度ボーダーを取っ払って、どうあるべきかを考える必要があるのではないでしょうか。どの業界においても大事なことですが、特に日本酒は顕著なのかもしれないですね。

個性のあるブランドが世界中から求められる
──ちなみに、フランスのワインにも同様の保護政策みたいなものはあったのでしょうか。シャンパーニュでつくったものを「シャンパン」と呼ぶように、産地を限定したものはありますね。だた、それはブランドの話です。実はフランスで、1976年に「パリスの審判」と呼ばれるセンセーショナルな出来事がありました。当時、ワインはフランスつくったものが圧倒的な存在で、そのほかはワインではない別物だとみなされていたんです。そのような状況で行われた有名なブラインドテイスティングの場で、ジャッジも全員フランス人だったのですが、1位から10位を米・ナパバレーのワインが独占したんです。フランスにとっては衝撃的な出来事でしたが、実はその後、フランスワインの輸出も伸びたんですよ。世界中でつくられるようになることで、ワインをもっと気軽に楽しむ層が増えたんです。そのなかで、やっぱり老舗がおいしいということで、フランスのワインも飲んでみようという消費者が増えた。日本酒も同様になっていくかはわからないですが、世界中でもっと身近な存在になって、そのなかでもやっぱり日本のお酒がおいしいとなればいいなと思いますし、それは飲む方が判断することであって国が認定をして判断するものではないですよね。
──飲み手の日本酒リテラシー、ワインリテラシーが上がることで、おいしさがわかるようになるからこそ、原点回帰をしてそのルーツの消費も上がるということなんですね。
そうなんですよ。最終的には自由競争だし、飲み手に支持されないといけない。今の日本酒の現状って、国内では2000円ほどで売っているものが、海外に行くと3~4倍の値段がついているんです。輸出の量が少ないことも要因ですが、その値段では市場が広がるはずないんですよ。ワインはそこをクリアしているんですよね。さまざまな地域でつくられたてきた歴史があって、大手が独占しているというわけでもなく、小さなプロデューサーがたくさんいる。ナパバレーのワイナリー数だけで、日本の酒蔵の数より多いんですよ。そういうことを考えると、守る方向よりもクロスボーダーしていくべきだし、世の中の流れもそうなっているので、それを見据えてなにができるかを考えることが非常に重要だと考えています。我々としては、ローカルにこだわって、ほかにはない体験を商品価値として提供していくことを個性としていきたいなと思います。
──自分のアイデンティティをしっかりと認識したうえで、そこに閉じこもるのではなく、飛び越えクロスボーダーしていくことが重要なんですね。興味深いお話、ありがとうございました!