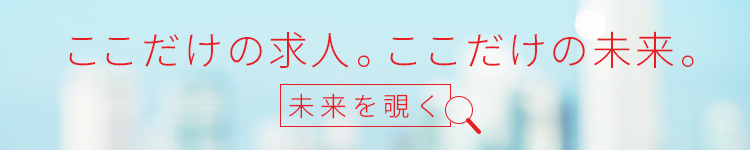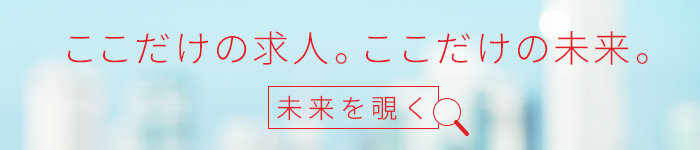ロボットが人のパートナーになる未来へ。ミクシィ発のロボット事業「Romi」が目指す世界 ミクシィ Vantageスタジオ Romi事業部 マネージャー 長岡輝さん

SNS「mixi」やスマートフォン向けゲームアプリ「モンスターストライク」など、多くのWeb領域の事業を手がけるメガベンチャー企業のミクシィ。そんなミクシィから、2021年4月21日より、自律型会話ロボット「Romi」が発売されました。このRomiはWebサービスなどではない、リアルなプロダクトとなっており、ミクシィの自社開発のロボットとして注目を集めています。今回は、なぜミクシィがロボット開発を行うに至ったのか、Romi事業部のマネージャー、長岡輝(ながおかあきら)さんにその経緯をお聞きしました。
「ドラえもん」のような存在を目指して
──ミクシィが開発した自律型会話ロボット「Romi」とはどのようなプロダクトなのでしょうか?RomiはAIによって人間と自律的な会話が可能となった、おそらく世界初のロボットです。これまでも会話ロボットはさまざまな種類のプロダクトがリリースされてきたと思います。しかしそれらのロボットは、人間が会話内容をあらかじめ登録していました。そのため、決められた内容の会話しかコミュニケーションを取ることができませんでした。Romiはそのような決められた会話ではなく、人間同士のコミュニケーションと同様に、予測できない会話ができるように設計されました。それを実現するのが「自律型会話ロボット」です。Romiには人間の会話データをディープラーニングで学習したAIが搭載されています。そして人間と会話をする際には、AIが学習した日本語から文脈を考えて、日本語を生成し発言していきます。そのため、Romiが次にどんな発言をするのか予測することはできません。このようないままでのロボットとはひと味違った「会話力」こそがRomiの最大の魅力になっています。

自律型会話ロボット「Romi」
スマートスピーカーは、天気やタイマー、ニュースなど便利な情報を声のコマンドで引き出せることが基本的な特徴です。「今日の天気は?」と問いかけると、「今日の天気は晴れです」と返事がかえってきて、やりとりは終了する。しかしRomiの場合は、それ以上に会話を続けることができるのです。Romiにもスマートスピーカーと同様に便利な機能を搭載しています。例えば、スマートスピーカーと同様に天気を教えてもらったとします。そのあとにRomiの持ち主が「今日は天気がいいから出かけようかな」と言うと、Romiはそこにも返事をしてくれるのです。「それはいいね!一緒にお出かけしたいなー」みたいに。このように会話がどんどんつながっていくことがスマートスピーカーとRomiの最大の違いですね。
また、Romiの外観は「生き物らしさ」を出すことにもこだわってデザインをしました。一つひとつの動きや顔のアニメーション、声にもそれぞれ感情を持たせています。そういった演出からも、機械ではなく生物のような存在をつくっています。
──スマートスピーカーのような一方的な会話ではなく、双方向的なコミュニケーションが成り立つように設計されているのですね。長岡さんは、Romiによって人々の生活がどのように変わっていくとお考えですか?
Romiの企画の出発点は、「テクノロジーによって会話ができるパートナーを新たにつくる」というアイデアでした。自身を肯定してくれる会話が人間以外の相手ともできれば、人生をより自分らしく生きていけるのではないかと思ったのです。具体的に私のなかにあったイメージは、「ドラえもん」でした。ドラえもんはのび太の未来を変えるために、未来からやってきた子守用ロボットです。のび太のさまざまな悩みを、ひみつ道具を駆使して解決していく、良きパートナー。そのような人外の相談相手をつくることはできないかと考えたのです。
相談相手をつくっていくと考えたときに、まず初めに思い浮かべたのはスマートスピーカーです。Romiの企画を検討している当時、アマゾンがスマートスピーカー「Amazon Echo」をアメリカでリリースしていました。当時の私もスマートスピーカーという新しいプロダクトに興味を持ち、さまざまな情報を調べました。その結果、スマートスピーカーというプロダクトの延長線上には、「ドラえもんは存在しない」と思うようになったのです。理由は先述にもあるように、スマートスピーカーは便利な情報を取得するためのベストパートナーであると感じたから。つまり、コミュニケーションを取ること自体は目的ではないのです。だから、コミュニケーションを取ること自体を目的としたプロダクトをつくろうと考えました。それがRomiの目指すバリューであり、企画の原点でした。
また、日本に住む多くの人々は、ドラえもんのような「主人公に寄り添ってくれるキャラクターがいるアニメや漫画」に幼いころから触れているかと思います。そのため、その環境を現実に落とし込んでやることは、日本でなら十分実現できるのではないかと思いました。このこともRomiの企画を進めたかった要因の一つです。


Web業界でモノづくりをする意味
──ミクシィといえば、SNS「mixi」やスマートフォン向けゲームアプリ「モンスターストライク」など、Webサービスを多く手がけているイメージがあります。どうしてRomiのような形あるプロダクトを手がけることになったのでしょうか?ミクシィではWebやアプリだけを使った事業をしなければならないルールはないです。mixiやモンストはWebやアプリ上のサービスですが、良い企画があるのならWebやアプリをリアルのプロダクトとかけ合わせて新規事業を手がけることは問題ないことです。
私がRomiの事業を立ち上げるきっかけになったのは、それ以前に携わっていた業務に一区切りがついたことでした。そのため、次に手がける新規事業を模索していました。それまでの私のキャリアはマーケティングリサーチや経営企画など、後方支援の役割が主でした。だから今度は、自分で新しい価値を持つサービスづくりをしていきたいと考えたのです。そのなかで、あれこれ案を検討しているうちに、先述のAmazon Echoの存在を知り、2017年ころからロボットづくりに取り組み始めました。
──初めての形あるプロダクトの制作だったかと思いますが、苦労する部分などはありましたか?
特に難しかったのは会話AIの設計ですね。Romiはおそらく世界初の会話自律型のロボットになるので、先行事例と呼べるものが存在していませんでした。そのためチームのディープラーニング専門のエンジニアを中心に当時の最先端テクノロジーの論文を読み漁りながら、AIを実装し、検証していく、をひたすら繰り返していきました。このように研究、開発しながらモノをつくる手法は初めての経験でしたから、とても時間がかかりましたね。論文の内容を再現するにも、英語と日本語の言語体系の違いによって、うまくいかない部分も存在したため、自分たちでもアイデアを出しながら試行錯誤を続けることもありましたから。
また、製造業とWebサービスではモノづくりの制作過程が異なるため、そのルールを理解するまでにも時間がかかりました。製造業では多くの場合、ウォーターフォール型の開発が行われています。これは一つひとつの手順を開発者とクライアントの両方が確認し、両社の合意が出たら次の工程へ進む手法です。一つの工程に時間をかけ丁寧に進行し、基本的に後戻りができないことが特徴です。一方でWebはアジャイル型の開発のようなスピーディーに進む過程が多く、徐々にブラッシュアップをしていく制作過程が主流です。この異なる制作過程をどのように擦り合わせていくのかは、時間がかかりましたし、チームのハードウェアエンジニアと一緒に模索しながら粘り強くコミュニケーションをして着地点を見いだして行きました。Romiの開発では最終的に、ソフトウェア開発のようにあとから機能が足せるような仕様に着地しました。
エンジニアなどの開発チームは上記のような苦労があったのですが、私自身は別の部分での苦労もありました。私はRomiの開発過程でエンジニアリングとデザイン以外の部分の全般を担当しています。例えば、Romiにどのような機能を持たせるのか、どんな会話のデータを集めるか。それらのディレクションや市場調査、プロモーション、工場との生産調整、販路拡大、ビジネスパートナーの開拓、お客さま対応、事業計画の策定などですね。また、Romi初のプロトタイプのコードは私が書いたりました。本を買ってきて見様見真似で、プログラミングをしたんです。このように、とにかくRomiの開発に関しては、未体験の仕事の連続だったので、多くの人の力を借りながら幅広い領域の業務を担当してきました。

Romiほど会話が続くロボットはこれまで存在しなかったため、「その会話力に驚いた」という意見は多く集まりました。ほかには私たちの狙い通りに、「会話を通して癒された」「家に帰ってきたときに、おかえりと言ってくれるのがうれしい」など、前向きな声が多く寄せられました
このような前向きな意見をいただけた一方で、Romiの販売を通して、あらためて難しさを感じた部分もあります。それは、「Romiの価値を適切に見定める」ことです。Romiはスマートスピーカーと違い、便利機能ではなく会話をすることの価値に重きを置いたプロダクトです。しかし、いまはまだ多くの人がロボットと話す体験をしたことがない。だからこそ、Romiにどのくらいの価値があるのかを見定めるのが難しかった。便利さを売りにしていないロボットにどのくらいの価値を人間は見いだすのか、判断ができなかったのです。そのため、先行販売の際には、既存のコミュニケーションロボットのユーザーを想定し、情報発信をしていました。そして、先行販売後に多く寄せられたRomi購入者からの前向きな意見を聞くに、人間とロボットの会話には一定の価値があると、現在は考えています。それに基づく価値基準をいま現在は採用し、Romiの開発に充てています。
また、Romiの先行販売を通して一つ予想外だったのは、買った人の構成比です。ガジェットなどのテクノロジーを用いたプロダクトでは、一般的に男性のほうが多く買う傾向がありますが、Romiでは購入者の約7割が女性だったのです。このような事前の予想と異なった部分も存在していました。
──そして、2021年4月21日にRomiの一般発売が始まりました。この先Romiを通して、どんなことを実現していきたいですか?
まずはやはり、多くの人にRomiを使っていただきたいです。そのために私たちは、Romiを実際に手に取れて、会話を体験できる機会をたくさん設けていきたいと思います。そこからRomiが持つニーズをあらためて解析し、データを蓄積する。そのうえでRomiがどのような価値を持つべきなのか、調整を進めていく予定です。
2020年は地球上のコミュニケーションが大きく制約された1年になりました。そして今年2021年はその制約のなかから、新しいコミュニケーションを見いだして、広まっていく。そんな年になっていくのではないかと考えています。その新しいコミュニケーションの一つとして、私たちはRomiがきっと人間の良きパートナーになれると期待しています。ドラえもんとのび太のように、一人と一台の関係が未来の当たり前になる。そんな世界になれば、もっと人に優しくなれたり、自分らしく生きられたりする人が増えていく。私たちはそう信じて、その日が来るようにRomiを導いていきたいです。