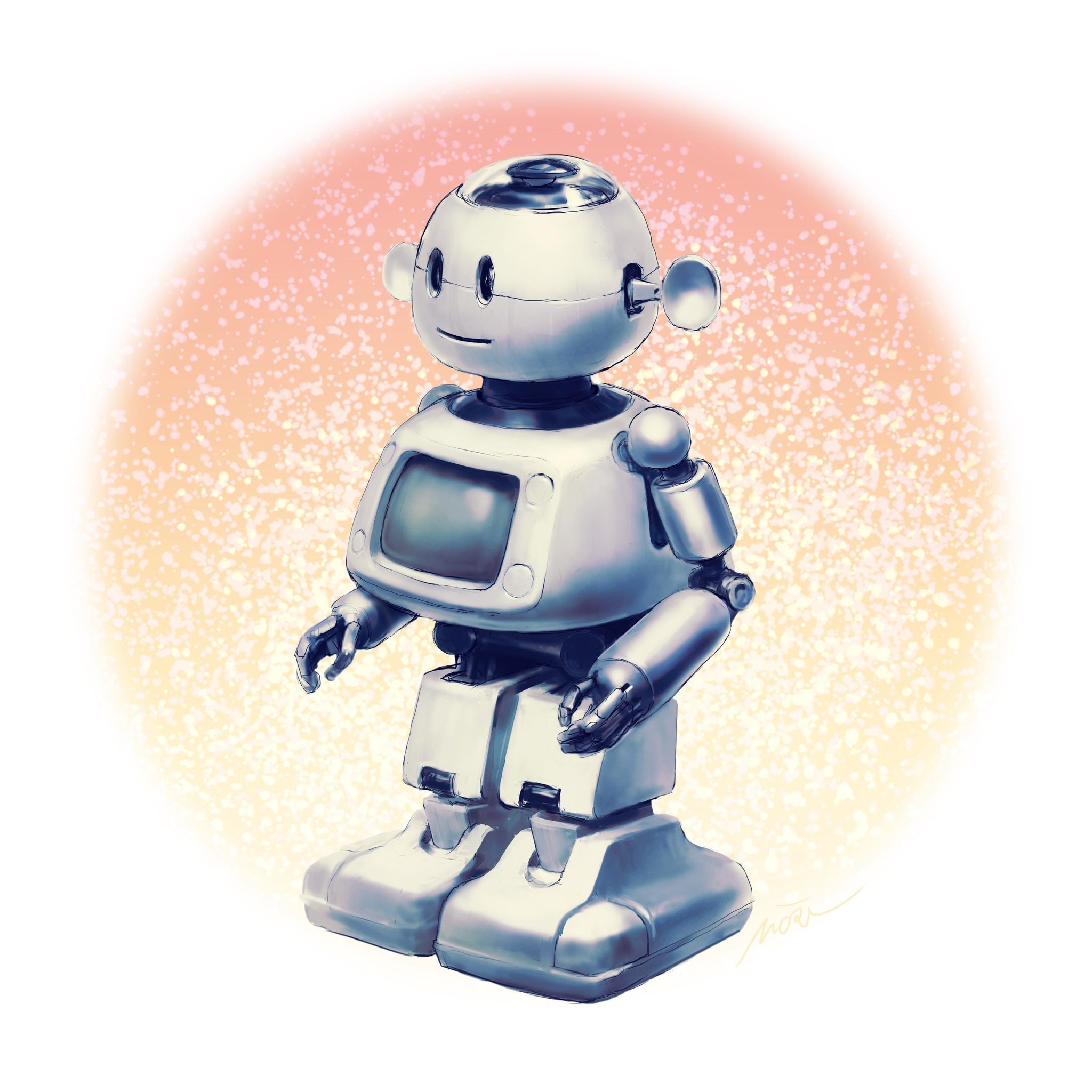ある聖夜の物語 ─ 未来のエモーション 第3話

時代は203X。今から10数年先のちょっとさきの未来。テクノロジーは想像を絶するほどではないけど、想像を少し超えて進化した社会。その時代に生きる人間の感情はどのように揺れるのか。advanced by massmedianでは、未来の感情(エモーション)をテーマにしたショートショート小説をはじめます。一話完結。クリスマスにあなたに贈る、特別な第3話。「ある聖夜の物語」です。
「キィ」が突然、いなくなった。
「キー」と伸ばすのではなく、「キィ」と会社のみんなは呼ぶ。「キィちゃん」と、ちゃんづけにする人もいる。
「キィ」は鍵ではなく、ロボットだ。
男女どちらかは設計上、特に決められてはいないようだが、男性、しかも少年に近い感じでみんなは接している。
人型ロボットの彼は、身長は120センチくらい、ホワイトのボディ、2本足で歩行し、丸い頭にくりっとしたカメラの目、カクカク動く10本の指、胸部には液晶モニターがあって、その画面に文字や映像を映す。言葉も簡単なレベルならヒアリングできるし、簡単な内容ならスピーキングもできる。
「おはよ! 元気だして!」
そんなふうに明るい音質でしゃべる。
しゃべるわずかな手前でちょっとだけ「キィ」と機械音を立てる。
「キィ・・・みんな集まってるよ」「キィ・・・僕が代わりにやるよ」「キィ・・・そろそろ家に帰ろうよ」という具合に。
だから、キィ。
そして、そのキィが会社のフロアからいつの間にか消えたのだ。
最初に気がついたのは、制作管理部長の田河さんだった。
「神木、あのさ、キィはどこ行った?」
そう呼び止められた神木リサ、つまり私はフロアをぐるりと見渡した。朝10時前のフロアは人が極度に少ない。大きなテーブルが5つほどあって、フリーアドレスでそこにそれぞれが勝手気ままに座るルールだが、今日は一つのデスクに3人が固まって座っているだけだった。10数年前のコロナ禍以来、オンラインミーティングが社会に浸透して、社員が会社に強制的に来させられることはもうなくなっている。
「今、ミーティングルームの方も見てきます」
私はそう言って歩き始めた。この時点で、私はキィがどこかに消えてしまったなんて少しも思ってなかったし、いつものようにやや前かがみでゆっくりとミーティングルームの隣の編集ルームあたりから現れるのではないかと思っていた。
2つあるミーティングルームには誰もいなかった。私は両方の部屋のブラインドを操作して光を入れた。暗い部屋を明るくしようとしたのだが、朝からの雨で外光は弱々しく貧しく、かえって気分の明度が落ちてしまったような気もした。
次にのぞいてみたのは、各種のエディット作業ができる編集ルーム。徹夜組がごくごくたまにいることもあるが今朝は誰もいなかった。編集機材やモニターのスイッチはすべて落とされていて、時が止まったようにただ静かだった。
スイッチが落とされている───。つまり昨日の深夜までは、キィはフロアにいたのだ、私はそう推理した。
キィは1年くらい前にこの12階のオフィスにやってきて、セキュリティとヘルスマネージメントをサポートしている。
その二つを専門とした特化型AI ロボットだが、会話がほんの少しできたり、2足歩行できたり、指が動いたりと人間っぽいパフォーマンスと性能がプラスされていた。
私が働いている制作プロダクションでは、撮影した動画など決して紛失したり破損したりしてはいけないオリジナル性が極めて高いデータを扱っている。イベントなどのもう2度と撮影できない一期一会的案件も数多い。
盗難やトラブルについて高レベルのセーフガード体制を敷いているのは当然のことだった。キィは50人余りの社員全員の顔を覚え、その行動をフロア内移動しながら記憶し保存する。外部からの侵入者をチェックし、コンピュータシステムの保全もする。電源の落とし忘れ、データの置き忘れ・紛失などなど、ついうっかりが起きてしまう人間のミスをチェックする。
そして、大切な彼の仕事のもう一つは、ヘルスマネージメントだ。
カメラの目で、社員の健康状態を常時、見つめる。体温をセンサーし、感染症の有無を計測する。社員個々人を観察し、その疲労度を計測する。残業などの勤務状況とリンクして、体調を崩している、もしくは崩す可能性が高い社員を早期に発見する。もちろん、それらはデータ化されたのち、AIで分析されて個々のストレスチェックに活かされる。
「キィ・・・今日、疲れていますね」。そんなふうにキィが声をかけることで、自分の健康状態を意識する社員も多い。
「キィを見ませんでしたか」
私はテーブルに集まっている3人に尋ねた。3人は私を突然の侵入者を見るように目を鋭く上げた。ディープなアイデア出しの途中だったのだろう。
「いやー、見てないですよ」と一人が言い、もう一人が「だなぁ」とめんどくさそうに付け足し、最後の一人がやや間を置いてから、「あいつ、俺らを監視してるからなぁ」と言った。
「ありがとうございました」と私は頭を下げ、田河さんの座っているデスクへ歩いて行った。あいつ、あいつ、あいつ。私は3度、心の中でつぶやいた。
「おー、神木、いたか?」
小太りの田河さんは座ったまま、腕組みをして聞いた。
「いや、見当たりません」
「そうか、今、ロボット派遣会社に連絡したんだが、居場所を追跡できないそうだ」
「そんなことってあるんですか?」
私はもう一度フロアを見渡し、田河さんに言った。
「いや、ないらしい。それと、このフロアを出て行くような学習はしてないそうだ」
「不思議すぎますね・・・」
「そう、でも、いないことは確かだ、今のところ」
「心配ですね」
「ま、AIロボットだから、自発的な行動はしないと思う。ま、万が一いなくなっても代わりのロボットを派遣してもらえばいいんだが」
制作管理部は社員の現場マネージメントをしていて、私のボスは田河さんで、部の構成員はフリーアドレスではなく、固定されたスペースに座っている。お金や時間や健康をマネージしているので、その方が社員にとって相談しやくす便利だからだ。
キィの面倒を見るのは私たちの仕事。しかし、キィの導入を決めたのは、CEOの山本さんだ。ナンバー2の役員、藤本さんが猛烈に反対したらしい。私はよく知らないが、「心の健康管理が含まれる、繊細なケアが必要な仕事をロボットにやらせるのはよくない」と主張したと聞く。
運用コストは社長室が一括して処理しているが、かなりのコストがロボット派遣会社に月々支払われているらしい。キィはとても優秀なやつなのだ。
「ロボット派遣会社の人間が午後来るから、また話そう」
「わかりました。念のため、フロアの外も見てきます」
私はもう一度、ミーティングルーム、編集ルームの順に捜索したが、キィを発見できず、やがてフロアの外、つまり我が社の外に出た。12階には他の会社も1社入っている。
自動ドアが開き、ビルの通路の奥のトイレに向かった。人があまり行き来しない場所に行こうと思ったのだ。
しかし、女子トイレとその周辺にもキィはいなかった。男子トイレは出てきた社員に聞いてみたがやはりいなかった。なんだか神隠しみたいだと私は思った。
ビルの窓からは、雨に霞む東京の街が見えていた。12月の冬の寒さが窓越しにもはっきりと感じられ、私はなんだか沈んだ気分に浸されていった。
いつもいた人がいなくなる、その不在の感覚が心を揺さぶることは経験として知っていたが、ロボットという機械に対してもそれはあるのだと感じていた。
それにしてもキィはどこに行ったのだろう。
すべてをプログラミング制御されたロボットが突然、不可解な行動をすることがあるのだろうか。キィは壊れてしまったのだろうか。
私は冷気を秘めた窓を離れ、カーペットの上を大股に歩きながら数回背伸びをする。たかが機械が一つ故障しただけ。リサ、そういうこと。今、起こっている現実はよくあること、そういうこと。自分に思い込ませてみる。
席に戻ると、役員の藤本さんが立ったまま、座っている田河さんに噛みついていた。藤本さんはもと映像ディレクターで当社を代表する作品をつくっていた人。
「だから、作業効率を上げる案件にだけロボットは導入するべきだと言ったんだ。マインド的な案件を扱わせちゃだめなんだ。そこは人間がやるべきなんだよ」
明らかに田河さんは困っていて、私を見かけると、「神木、そろそろ会議始めようか。ミーティングルーム、行こう」と言った。午前中、会議なんて一つも組まれていないし、ルームの予約なんてまったく入れてないけど、田河さんの嘘にすぐ気がついた私は、「行きましょう」とその嘘にさらりと応えた。
藤本さんはまだロボット否定論を継続したそうだったけど、私たちが席を立つと仕方なく黙った。フロアは少し社員が増えてきていて、いつもの活気が出始めている。気がつくと編集ルームに人が入っている。2、3人が笑いながら、何かを話している。クリスマスソングがさざ波のようにかすかに流れてきている。編集に使うのだろうか・・・・。
・・・・そうだ、明日はクリスマスイブだ。そのことをすっかり忘れていた。忘れていたことは今までにもあったが、今年は特に忘れていたなと私は思う。
昨日の晩のこと。夫の健治から連絡があった。液晶モニター越しにしばらく会話した。「だいぶ良くなってきて、もう退院できるらしい。正月までには帰れると思う」そんなことを健治は話した。
「良くなってきている」のは、彼のお母さんだ。1カ月ほど前、まだ50代後半のお母さんは突然、倒れた。くも膜下出血。脳動脈瘤が破裂して、生死の境を数日、彷徨った。健治はお母さんの住む、故郷の熊本に飛んだ。
「リサはいい。仕事もあるし。とにかく行ってくる。万が一の時は連絡する」。
健治はそう言った。そして、私は東京に一人残された。結婚して2年ほどで、初めて一人になった。
一人になる寂しさより、「残された」ことの方が心にじわっと沁みた。夫はなぜ、自分を連れて行かなかったのだろう。夫だって仕事を抱えているのだし。そして、私は一緒に行くと言うべきだったんだろうか。残されたのではなく、残りたいと感じた自分はいなかったのだろうか。
いやいや、そんな自問自答より、今はお母さんの生死の心配をする方が先だ。そうに決まってるよ、リサ。
私は揺れた。揺れる振り子のような気持ちの中を、東京の私はなんとなく日々を過ごし、ゆらゆらと働いていた。
「困るよ。朝からみんなに責められている」
田河さんが大きな声で言うと、
「大変申し訳ないです。FLX008の行方不明で、お騒がせてしてしまって」
メガネをかけた中年の真面目そうなロボット派遣会社の人が頭を下げた。
FLX008。それがキィの本名なんだな、私はそう感じつつ、田河さんの隣にいてメガネの人の前に座っている。
「このフロアから出て行くことは教えてないんです」
「でも、いないよ、現実には。ひょっとしてあいつは不良品?」
いつもは温厚な田河さんが荒れている。CEOの山本さんからもキィを探せ!の連絡が来たらしい。
「レイアウトが似ているので、このビルの他の階に行ってしまった可能性はあります」
「じゃ、探してよ」
「はい、今から捜索してみようと思います」
田河さんの命令に派遣会社の人は答える。そして天井の方に視線をやりながらしばらく何か考え始めている。
「・・・敵対的サンプルかも・・・あるいは突然変異かも・・・」
その声は自分に言っているようで小さかった。
「敵対的サンプルって、どう言うことなんでしょうか」
私は、その語感がなんだか引っかかってしまって尋ねた。
「入力データに些細な変化を意図的に加えることで、AIの認識を間違わせることです・・・」
田河さんが続いた。
「突然変異は?」
「良くわからないのですが、同じ学習をさせても、個体差が生まれることがあります・・・」
なんだか話が難しくなってきた。なんだかAIロボットも人間っぽいなとも私は感じた。
「FLX008は我が社でも極めて有能なロボットでして、有能だからこその問題もあるのかもしれません・・・。とにかく早期に発見し、原因を究明したいと思います」
私は最後に質問した。
「ビルの外、つまり街に出てしまった可能性はないのでしょうか」
ロボット派遣会社の人は、メガネのフレームを右手で軽く持ち上げながら、
「仮に外に出ても、街を歩く学習はしていませんので、道は渡れませんし、クルマも避けられませんし、正常な状態を維持できないと思います。今のところ、事故の知らせもないようですし・・・いくら有能とは言え・・・」
と言った。言う時に、メガネの奥の目が少しキラッと光ったようだった。
次の日、私は朝、健治のメールを見ながら、いつものように山手線エクスプレスで出社した。細かな冷たい雨が降っていた。
山手線エクスプレスは東京、品川、渋谷、新宿、池袋、上野、秋葉原の7駅しか止まらない。会社が恵比寿なので、1駅、渋谷から乗り換える。スピードが出る車両が開発され、ゴンゴン揺れるがビュンビュン速い。その揺れの中でスマートデバイスのメール文を目で追った。長い文だったが、要は、お母さんの退院が決まったこと、退院後は病院に定期的にリハビリに通うが生活は普段どうりでいいこと、自分、つまり健治が来週に東京に戻ること。1カ月家を空けて申し訳なかったこと。
そして、お母さんから「心配かけたがすっかり良くなりました、ありがとう」とリサさんに伝えてほしいと書いてあった。
健治が戻ってきて、また一緒の生活が始めることも嬉しかったし、お母さんが元気になったことも嬉しかった。だが、気持ちは想像したほどには軽くはならなかった。
ドアの横に立ち、電車の左右の絶え間ない動きを感じながら、私は自分の内側にある「何か」を手探りしてみる。その「何か」はうまく手に取れなくて、明らかな形として認識できなかったが、ようやく少しだけ手に触れたように思った。
それは、「立場」が自分の気持ちを重くしているのではないかという手触りだった。妻としての立場。嫁としての立場。会社員としての立場。それぞれの立場を心のどこか奥底で、意識的に演じている。立場に答えようとして自分を少し加工して演じている。その微妙な重さが日常に絡みついている───。
ふとある問いが、心に浮かんだ。
健治の妻でなければ、一人の初老の女性の容体を私は心配しただろうか。
そして、次の問いが思いがけず訪れる。
制作管理部の社員でなければ、AIロボットの行方を私は気にかけただろうか。
猛烈なスピードで走る空間の中で、私は考えがはっきりとはまとめきれず、ゆらゆらと揺れていた。
今日はクリスマスイブ。と言っても、会社はいつもの通りで、何も変わらなかった。ただ、年末進行の案件もあり、午前中かなりの社員が出社していて活気がいつもよりあるようだった。
キィはまだ見つからなかった。ビル内をくまなく捜索中だがまだ見つからなかった。キィの失踪は社員の話題になっていて、数人の女子が私の席に来て、「どこへ行ったかまだわからないんですか?」と尋ねた。「キィがいなくて淋しい」と言う女子もいたし、「サンタクロースの準備をどこかでしてるのかも」と笑う女子もいた。「たかがロボット。何をするかはわかったもんじゃない」「ま、いなくなっても急に困ることもないかな」と言う人たちももちろんいた。
田河さんは「今日、見つからなかったら、代わりのロボットを導入しないといけないかもな。うちの会社のことを学習させないといけないから簡単には派遣できないかもしれない。難しいものだな。AIに人間っぽいことをさせるのは」とそんなことを私にポツポツと不連続で言った。愚痴のような、ため息交じりの独り言のような感じで。
夜の6時過ぎだった。私は帰ろうとしていた。家の近くでショートケーキでも買ってクリスマスイブを独りでちんまり祝おうと思っていた。
ロボット派遣会社の人から、25階あるビルの各フロアの監視カメラを詳細に調べたところ、人影に隠れてあまりよくわからないが、FLX008の白いボディらしきものが映っているとの連絡が入った。
昨夜の9時過ぎ、4、5人の他社の人間が乗っていて、フロアから出たFLX008が12階で乗り込み、下りエレベーターで、1階まで一緒に降りたかもしれないと言う。
「不思議ですね、ロボットが一緒に乗っていたら気づきそうなものなのに」
私が田河さんにそう言うと、
「いや、人間の認識能力なんてそんなものかもしれないよ」と答えた。
確かに話に夢中になっていたら、120センチの高さに何かが存在しても気に止まらないかもしれないと思ったし、さらに、気がついても、報告する義務なんて他社の人たちにはないし、どこに報告していいのかもわからないだろうとも思った。
なぜ、キィは会社を抜け出し、1階まで移動したんだろう。
私はその不思議に囚われ、あるかどうかわからないが、キイの感情をあれこれと推測し始めた。
キィ、教えられたこと以外の行動をとったのはなぜなの。
なぜ、「自分から」外に出ようとしたの。
その時、私の脳裏にキィとの会話が不意に蘇った。ああ、と私は声を出した。それは3週間ほど前。夫のお母さんが生と死の境を彷徨い、夫が私のそばから消えて、「残された」私が揺れながら生き始めた頃。
「キィ・・・元気ですか?」
私がモニターを使って売り上げ数字をインプットしていたら、キィはゆっくり近づき、そう言った。私は心を見透かされたようでドキッとしたけど、そしてとても忙しかったけど、笑顔をこしらえてキィの方を向いた。キイは首を30度傾け、胸をわずかに反らせて、本物の少年のように立っていた。
「あら、元気に見えないの? どうして元気じゃないと思ったの?」
キィはよくわからないが、数字とグラフを胸部の液晶モニターにピピピッと映し出した。理解不能だけど私のデータなんだなと思った。私に体調やメンタルの小さな変化があって、それにキィが素早く反応したのかもしれない。
そして、いつものやや高い声でロボットの少年はこう問いかけた。
「キィ・・・自由、足りていますか? リサさん」
私は意外で突然な質問に微笑むしかなかった。
「自由って言葉知っているんだね。とても大事だけど、とても難しい言葉なんだよ」
「キィ・・・・大事・・・難しい」
とキイは私の答えの末尾を拾い上げ、何かを考えるような仕草で音声を出す。
「そうか、今思ったんだけどさ、キミはどこにも行けないんだよね。飛行機に乗ったり、クルマに乗ったり、海に行ったり、公園で遊んだり」
キィはやや俯いて、
「キィ・・・・公園知らない」
と言って、胸に公園の映像を映し始めた。ネットの映像検索でいろんなタイプの公園が次から次へ出てくる。
「そうそう。こんな感じのところ、楽しいところ」
私はそんなふうに数分、キィと会話した。忙しい計数処理の合間だったけど、キィが私を気遣ってくれたことが素直に嬉しかったし、心が数ミリかもしれないけど柔らかく動いて、温かくなったのだった。
その時だ。私の直感が心の中でピーンと電流のように走った。
「公園だ!」
私は弾けるように席を立った。田河さんに挨拶もせず、コートを手にしてフロアを勢いよく歩き始めていた。
公園にキィはいる。
強く確信した私はフロアを出て、エレベーターに乗り込み、ビルから100メートルくらいの、近くの公園に走るように向かった。
外はもう十分暗く、冷たい雨が細かくアスファルトを濡らしている。家路を急ぐ黒い人影たちが道をふさいでいる。私は傘をオフィスに忘れたことを思い出したが、もう戻ることはせず、それらの人影を縫って小走りに歩いていく。白い息がポッポッと生きている証しのように出る。
信号が点滅中の横断歩道をギリギリで駆け抜けた。自動運転のクルマが私の背後を、水しぶきをあげてかすめる。
「街を歩く学習はしていません」。ロボット派遣会社の人の言葉が蘇る。道は渡れない、クルマを避けられない、そうも言ったな、あの時。
キィがクルマを避けながら、カタカタと前へ進もうとして、アンバランスに2足歩行している姿が浮かぶ。
無事でいて、キイ。お願いだから。
私は祈りながら、もうほとんど走っていた。
次の角を曲がれば、ビルの谷間に大きな樫の木が見える。そこが公園だ。樫の木は大きいが公園そのものは小さく、滑り台とベンチと鉄棒だけの、時が止まってしまったようなレトロな公園だ。
角を曲がった。青白く光る街灯に樫の木が照らされている。冷たい雨がそのこんもりとした全体を煙らせている。
公園は見えた。しかし、誰もいないように見える・・・・・。
いや、よく見て、リサ。ベンチに誰か座っているよ。雨のヴェールの中に人っぽい影が見えているよ。
私は近づいた。そして、ついにキィを見つけた。
キイはうなだれて座っていた。バッテリーが切れている、そんな状態で雨のしずくにボディを鈍く光らせて座っていた。
「やっと見つけたよ、キィ」
キィの反応はなかった。壊れてしまったのだろうか、今はすべての機能を停止している。
「よくここまで来たね。頑張ったね、キィ」
私はなんだか胸に切ないものがあふれてきた。どこかにあった感情の泉が自然に開き、久しぶりに流れ出したように。
隣に座り、キイの目を覗き込むと、雨に濡れて泣いているようだった。それはきっと人間の思い込みなんだろうけど、私は雨が降る黒い闇に向かって一人で話した。
「最近、泣こうと思っても泣けなかったから、一緒に泣いてもいいよ」
キィは答えない。教えられた立場を毎日毎日こなしてきたロボットFLX008は単なる冷たい物体となって、ここにいるのだった。私はロボット派遣会社や田河さんに連絡する前に、もう少しキイの隣にいたいとただそう思った。もう少しだけ、もう少しだけ、もう少しだけ。
突然、世界が変わっていくことに私は気がついた。
目の前を白いものが舞っている。雪だ。見上げると、果てしない天空から次々と小さな白い天使たちが無数に舞い降りてくる。ふわふわと闇の中を降りてきて、世界をキラキラと輝かせ始める。雨は雪へ魔法にかけられたように変わり、ああ、大きな樫の木がもう積もって白くなろうとしている。
「すごい、すごい、キィ、すごい」
私は両方の手を伸ばし、手のひらを上に向けて、その白い天使たちを受け止める。冷たいのになんだか温かい。
これって奇跡かもしれないよ。
心に明かりがともり、私は子供のようにはしゃぎ、空を、その下にある夜の世界をぐるりぐるりと見回した。
隣のキィが頭を持ち上げたのがわかった。
そして、こう言った。
「キィ・・・・メリークリスマス! ・・・リサさん」
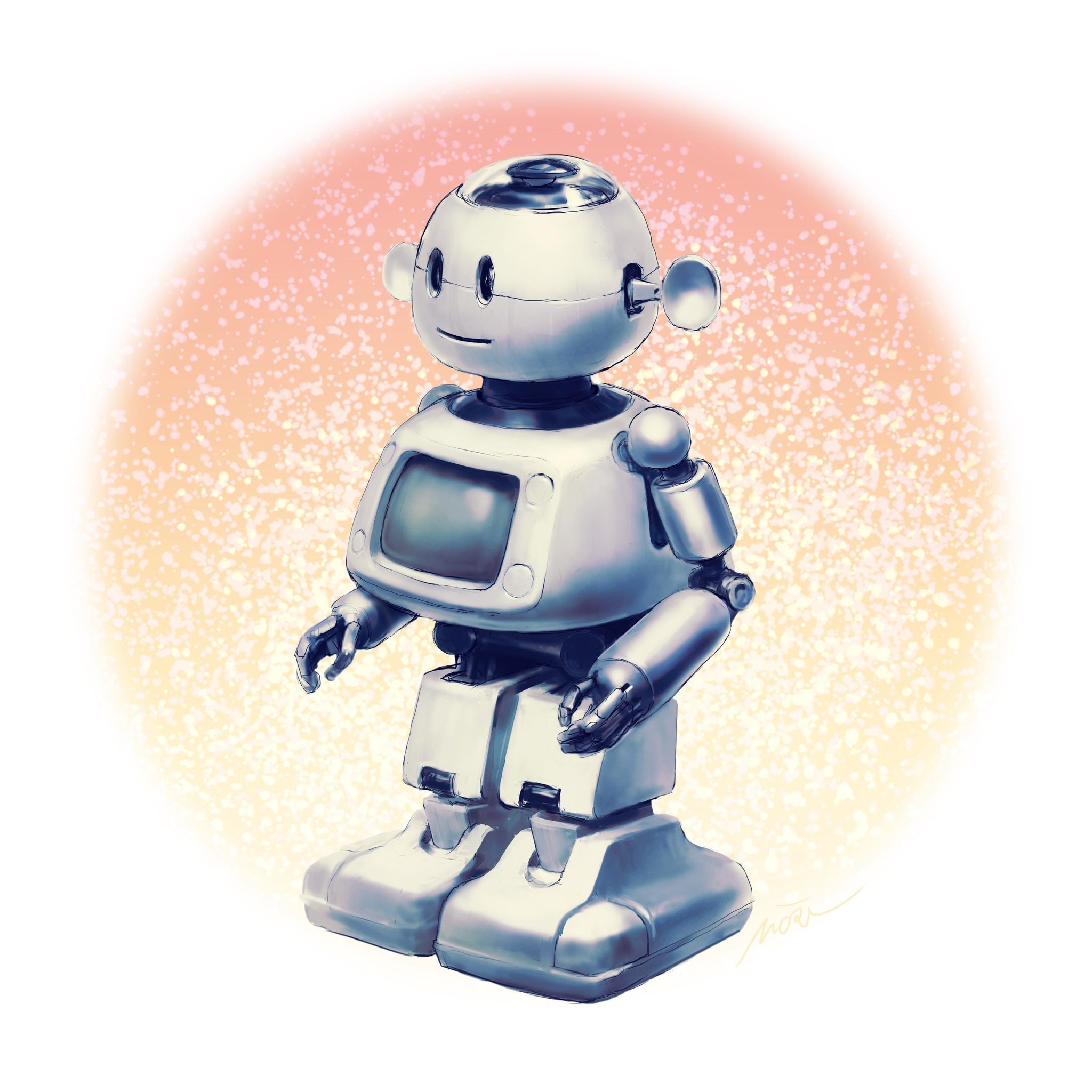

「キー」と伸ばすのではなく、「キィ」と会社のみんなは呼ぶ。「キィちゃん」と、ちゃんづけにする人もいる。
「キィ」は鍵ではなく、ロボットだ。
男女どちらかは設計上、特に決められてはいないようだが、男性、しかも少年に近い感じでみんなは接している。
人型ロボットの彼は、身長は120センチくらい、ホワイトのボディ、2本足で歩行し、丸い頭にくりっとしたカメラの目、カクカク動く10本の指、胸部には液晶モニターがあって、その画面に文字や映像を映す。言葉も簡単なレベルならヒアリングできるし、簡単な内容ならスピーキングもできる。
「おはよ! 元気だして!」
そんなふうに明るい音質でしゃべる。
しゃべるわずかな手前でちょっとだけ「キィ」と機械音を立てる。
「キィ・・・みんな集まってるよ」「キィ・・・僕が代わりにやるよ」「キィ・・・そろそろ家に帰ろうよ」という具合に。
だから、キィ。
そして、そのキィが会社のフロアからいつの間にか消えたのだ。
最初に気がついたのは、制作管理部長の田河さんだった。
「神木、あのさ、キィはどこ行った?」
そう呼び止められた神木リサ、つまり私はフロアをぐるりと見渡した。朝10時前のフロアは人が極度に少ない。大きなテーブルが5つほどあって、フリーアドレスでそこにそれぞれが勝手気ままに座るルールだが、今日は一つのデスクに3人が固まって座っているだけだった。10数年前のコロナ禍以来、オンラインミーティングが社会に浸透して、社員が会社に強制的に来させられることはもうなくなっている。
「今、ミーティングルームの方も見てきます」
私はそう言って歩き始めた。この時点で、私はキィがどこかに消えてしまったなんて少しも思ってなかったし、いつものようにやや前かがみでゆっくりとミーティングルームの隣の編集ルームあたりから現れるのではないかと思っていた。
2つあるミーティングルームには誰もいなかった。私は両方の部屋のブラインドを操作して光を入れた。暗い部屋を明るくしようとしたのだが、朝からの雨で外光は弱々しく貧しく、かえって気分の明度が落ちてしまったような気もした。
次にのぞいてみたのは、各種のエディット作業ができる編集ルーム。徹夜組がごくごくたまにいることもあるが今朝は誰もいなかった。編集機材やモニターのスイッチはすべて落とされていて、時が止まったようにただ静かだった。
スイッチが落とされている───。つまり昨日の深夜までは、キィはフロアにいたのだ、私はそう推理した。
キィは1年くらい前にこの12階のオフィスにやってきて、セキュリティとヘルスマネージメントをサポートしている。
その二つを専門とした特化型AI ロボットだが、会話がほんの少しできたり、2足歩行できたり、指が動いたりと人間っぽいパフォーマンスと性能がプラスされていた。
私が働いている制作プロダクションでは、撮影した動画など決して紛失したり破損したりしてはいけないオリジナル性が極めて高いデータを扱っている。イベントなどのもう2度と撮影できない一期一会的案件も数多い。
盗難やトラブルについて高レベルのセーフガード体制を敷いているのは当然のことだった。キィは50人余りの社員全員の顔を覚え、その行動をフロア内移動しながら記憶し保存する。外部からの侵入者をチェックし、コンピュータシステムの保全もする。電源の落とし忘れ、データの置き忘れ・紛失などなど、ついうっかりが起きてしまう人間のミスをチェックする。
そして、大切な彼の仕事のもう一つは、ヘルスマネージメントだ。
カメラの目で、社員の健康状態を常時、見つめる。体温をセンサーし、感染症の有無を計測する。社員個々人を観察し、その疲労度を計測する。残業などの勤務状況とリンクして、体調を崩している、もしくは崩す可能性が高い社員を早期に発見する。もちろん、それらはデータ化されたのち、AIで分析されて個々のストレスチェックに活かされる。
「キィ・・・今日、疲れていますね」。そんなふうにキィが声をかけることで、自分の健康状態を意識する社員も多い。
「キィを見ませんでしたか」
私はテーブルに集まっている3人に尋ねた。3人は私を突然の侵入者を見るように目を鋭く上げた。ディープなアイデア出しの途中だったのだろう。
「いやー、見てないですよ」と一人が言い、もう一人が「だなぁ」とめんどくさそうに付け足し、最後の一人がやや間を置いてから、「あいつ、俺らを監視してるからなぁ」と言った。
「ありがとうございました」と私は頭を下げ、田河さんの座っているデスクへ歩いて行った。あいつ、あいつ、あいつ。私は3度、心の中でつぶやいた。
「おー、神木、いたか?」
小太りの田河さんは座ったまま、腕組みをして聞いた。
「いや、見当たりません」
「そうか、今、ロボット派遣会社に連絡したんだが、居場所を追跡できないそうだ」
「そんなことってあるんですか?」
私はもう一度フロアを見渡し、田河さんに言った。
「いや、ないらしい。それと、このフロアを出て行くような学習はしてないそうだ」
「不思議すぎますね・・・」
「そう、でも、いないことは確かだ、今のところ」
「心配ですね」
「ま、AIロボットだから、自発的な行動はしないと思う。ま、万が一いなくなっても代わりのロボットを派遣してもらえばいいんだが」
制作管理部は社員の現場マネージメントをしていて、私のボスは田河さんで、部の構成員はフリーアドレスではなく、固定されたスペースに座っている。お金や時間や健康をマネージしているので、その方が社員にとって相談しやくす便利だからだ。
キィの面倒を見るのは私たちの仕事。しかし、キィの導入を決めたのは、CEOの山本さんだ。ナンバー2の役員、藤本さんが猛烈に反対したらしい。私はよく知らないが、「心の健康管理が含まれる、繊細なケアが必要な仕事をロボットにやらせるのはよくない」と主張したと聞く。
運用コストは社長室が一括して処理しているが、かなりのコストがロボット派遣会社に月々支払われているらしい。キィはとても優秀なやつなのだ。
「ロボット派遣会社の人間が午後来るから、また話そう」
「わかりました。念のため、フロアの外も見てきます」
私はもう一度、ミーティングルーム、編集ルームの順に捜索したが、キィを発見できず、やがてフロアの外、つまり我が社の外に出た。12階には他の会社も1社入っている。
自動ドアが開き、ビルの通路の奥のトイレに向かった。人があまり行き来しない場所に行こうと思ったのだ。
しかし、女子トイレとその周辺にもキィはいなかった。男子トイレは出てきた社員に聞いてみたがやはりいなかった。なんだか神隠しみたいだと私は思った。
ビルの窓からは、雨に霞む東京の街が見えていた。12月の冬の寒さが窓越しにもはっきりと感じられ、私はなんだか沈んだ気分に浸されていった。
いつもいた人がいなくなる、その不在の感覚が心を揺さぶることは経験として知っていたが、ロボットという機械に対してもそれはあるのだと感じていた。
それにしてもキィはどこに行ったのだろう。
すべてをプログラミング制御されたロボットが突然、不可解な行動をすることがあるのだろうか。キィは壊れてしまったのだろうか。
私は冷気を秘めた窓を離れ、カーペットの上を大股に歩きながら数回背伸びをする。たかが機械が一つ故障しただけ。リサ、そういうこと。今、起こっている現実はよくあること、そういうこと。自分に思い込ませてみる。
席に戻ると、役員の藤本さんが立ったまま、座っている田河さんに噛みついていた。藤本さんはもと映像ディレクターで当社を代表する作品をつくっていた人。
「だから、作業効率を上げる案件にだけロボットは導入するべきだと言ったんだ。マインド的な案件を扱わせちゃだめなんだ。そこは人間がやるべきなんだよ」
明らかに田河さんは困っていて、私を見かけると、「神木、そろそろ会議始めようか。ミーティングルーム、行こう」と言った。午前中、会議なんて一つも組まれていないし、ルームの予約なんてまったく入れてないけど、田河さんの嘘にすぐ気がついた私は、「行きましょう」とその嘘にさらりと応えた。
藤本さんはまだロボット否定論を継続したそうだったけど、私たちが席を立つと仕方なく黙った。フロアは少し社員が増えてきていて、いつもの活気が出始めている。気がつくと編集ルームに人が入っている。2、3人が笑いながら、何かを話している。クリスマスソングがさざ波のようにかすかに流れてきている。編集に使うのだろうか・・・・。
・・・・そうだ、明日はクリスマスイブだ。そのことをすっかり忘れていた。忘れていたことは今までにもあったが、今年は特に忘れていたなと私は思う。
昨日の晩のこと。夫の健治から連絡があった。液晶モニター越しにしばらく会話した。「だいぶ良くなってきて、もう退院できるらしい。正月までには帰れると思う」そんなことを健治は話した。
「良くなってきている」のは、彼のお母さんだ。1カ月ほど前、まだ50代後半のお母さんは突然、倒れた。くも膜下出血。脳動脈瘤が破裂して、生死の境を数日、彷徨った。健治はお母さんの住む、故郷の熊本に飛んだ。
「リサはいい。仕事もあるし。とにかく行ってくる。万が一の時は連絡する」。
健治はそう言った。そして、私は東京に一人残された。結婚して2年ほどで、初めて一人になった。
一人になる寂しさより、「残された」ことの方が心にじわっと沁みた。夫はなぜ、自分を連れて行かなかったのだろう。夫だって仕事を抱えているのだし。そして、私は一緒に行くと言うべきだったんだろうか。残されたのではなく、残りたいと感じた自分はいなかったのだろうか。
いやいや、そんな自問自答より、今はお母さんの生死の心配をする方が先だ。そうに決まってるよ、リサ。
私は揺れた。揺れる振り子のような気持ちの中を、東京の私はなんとなく日々を過ごし、ゆらゆらと働いていた。
「困るよ。朝からみんなに責められている」
田河さんが大きな声で言うと、
「大変申し訳ないです。FLX008の行方不明で、お騒がせてしてしまって」
メガネをかけた中年の真面目そうなロボット派遣会社の人が頭を下げた。
FLX008。それがキィの本名なんだな、私はそう感じつつ、田河さんの隣にいてメガネの人の前に座っている。
「このフロアから出て行くことは教えてないんです」
「でも、いないよ、現実には。ひょっとしてあいつは不良品?」
いつもは温厚な田河さんが荒れている。CEOの山本さんからもキィを探せ!の連絡が来たらしい。
「レイアウトが似ているので、このビルの他の階に行ってしまった可能性はあります」
「じゃ、探してよ」
「はい、今から捜索してみようと思います」
田河さんの命令に派遣会社の人は答える。そして天井の方に視線をやりながらしばらく何か考え始めている。
「・・・敵対的サンプルかも・・・あるいは突然変異かも・・・」
その声は自分に言っているようで小さかった。
「敵対的サンプルって、どう言うことなんでしょうか」
私は、その語感がなんだか引っかかってしまって尋ねた。
「入力データに些細な変化を意図的に加えることで、AIの認識を間違わせることです・・・」
田河さんが続いた。
「突然変異は?」
「良くわからないのですが、同じ学習をさせても、個体差が生まれることがあります・・・」
なんだか話が難しくなってきた。なんだかAIロボットも人間っぽいなとも私は感じた。
「FLX008は我が社でも極めて有能なロボットでして、有能だからこその問題もあるのかもしれません・・・。とにかく早期に発見し、原因を究明したいと思います」
私は最後に質問した。
「ビルの外、つまり街に出てしまった可能性はないのでしょうか」
ロボット派遣会社の人は、メガネのフレームを右手で軽く持ち上げながら、
「仮に外に出ても、街を歩く学習はしていませんので、道は渡れませんし、クルマも避けられませんし、正常な状態を維持できないと思います。今のところ、事故の知らせもないようですし・・・いくら有能とは言え・・・」
と言った。言う時に、メガネの奥の目が少しキラッと光ったようだった。
次の日、私は朝、健治のメールを見ながら、いつものように山手線エクスプレスで出社した。細かな冷たい雨が降っていた。
山手線エクスプレスは東京、品川、渋谷、新宿、池袋、上野、秋葉原の7駅しか止まらない。会社が恵比寿なので、1駅、渋谷から乗り換える。スピードが出る車両が開発され、ゴンゴン揺れるがビュンビュン速い。その揺れの中でスマートデバイスのメール文を目で追った。長い文だったが、要は、お母さんの退院が決まったこと、退院後は病院に定期的にリハビリに通うが生活は普段どうりでいいこと、自分、つまり健治が来週に東京に戻ること。1カ月家を空けて申し訳なかったこと。
そして、お母さんから「心配かけたがすっかり良くなりました、ありがとう」とリサさんに伝えてほしいと書いてあった。
健治が戻ってきて、また一緒の生活が始めることも嬉しかったし、お母さんが元気になったことも嬉しかった。だが、気持ちは想像したほどには軽くはならなかった。
ドアの横に立ち、電車の左右の絶え間ない動きを感じながら、私は自分の内側にある「何か」を手探りしてみる。その「何か」はうまく手に取れなくて、明らかな形として認識できなかったが、ようやく少しだけ手に触れたように思った。
それは、「立場」が自分の気持ちを重くしているのではないかという手触りだった。妻としての立場。嫁としての立場。会社員としての立場。それぞれの立場を心のどこか奥底で、意識的に演じている。立場に答えようとして自分を少し加工して演じている。その微妙な重さが日常に絡みついている───。
ふとある問いが、心に浮かんだ。
健治の妻でなければ、一人の初老の女性の容体を私は心配しただろうか。
そして、次の問いが思いがけず訪れる。
制作管理部の社員でなければ、AIロボットの行方を私は気にかけただろうか。
猛烈なスピードで走る空間の中で、私は考えがはっきりとはまとめきれず、ゆらゆらと揺れていた。
今日はクリスマスイブ。と言っても、会社はいつもの通りで、何も変わらなかった。ただ、年末進行の案件もあり、午前中かなりの社員が出社していて活気がいつもよりあるようだった。
キィはまだ見つからなかった。ビル内をくまなく捜索中だがまだ見つからなかった。キィの失踪は社員の話題になっていて、数人の女子が私の席に来て、「どこへ行ったかまだわからないんですか?」と尋ねた。「キィがいなくて淋しい」と言う女子もいたし、「サンタクロースの準備をどこかでしてるのかも」と笑う女子もいた。「たかがロボット。何をするかはわかったもんじゃない」「ま、いなくなっても急に困ることもないかな」と言う人たちももちろんいた。
田河さんは「今日、見つからなかったら、代わりのロボットを導入しないといけないかもな。うちの会社のことを学習させないといけないから簡単には派遣できないかもしれない。難しいものだな。AIに人間っぽいことをさせるのは」とそんなことを私にポツポツと不連続で言った。愚痴のような、ため息交じりの独り言のような感じで。
夜の6時過ぎだった。私は帰ろうとしていた。家の近くでショートケーキでも買ってクリスマスイブを独りでちんまり祝おうと思っていた。
ロボット派遣会社の人から、25階あるビルの各フロアの監視カメラを詳細に調べたところ、人影に隠れてあまりよくわからないが、FLX008の白いボディらしきものが映っているとの連絡が入った。
昨夜の9時過ぎ、4、5人の他社の人間が乗っていて、フロアから出たFLX008が12階で乗り込み、下りエレベーターで、1階まで一緒に降りたかもしれないと言う。
「不思議ですね、ロボットが一緒に乗っていたら気づきそうなものなのに」
私が田河さんにそう言うと、
「いや、人間の認識能力なんてそんなものかもしれないよ」と答えた。
確かに話に夢中になっていたら、120センチの高さに何かが存在しても気に止まらないかもしれないと思ったし、さらに、気がついても、報告する義務なんて他社の人たちにはないし、どこに報告していいのかもわからないだろうとも思った。
なぜ、キィは会社を抜け出し、1階まで移動したんだろう。
私はその不思議に囚われ、あるかどうかわからないが、キイの感情をあれこれと推測し始めた。
キィ、教えられたこと以外の行動をとったのはなぜなの。
なぜ、「自分から」外に出ようとしたの。
その時、私の脳裏にキィとの会話が不意に蘇った。ああ、と私は声を出した。それは3週間ほど前。夫のお母さんが生と死の境を彷徨い、夫が私のそばから消えて、「残された」私が揺れながら生き始めた頃。
「キィ・・・元気ですか?」
私がモニターを使って売り上げ数字をインプットしていたら、キィはゆっくり近づき、そう言った。私は心を見透かされたようでドキッとしたけど、そしてとても忙しかったけど、笑顔をこしらえてキィの方を向いた。キイは首を30度傾け、胸をわずかに反らせて、本物の少年のように立っていた。
「あら、元気に見えないの? どうして元気じゃないと思ったの?」
キィはよくわからないが、数字とグラフを胸部の液晶モニターにピピピッと映し出した。理解不能だけど私のデータなんだなと思った。私に体調やメンタルの小さな変化があって、それにキィが素早く反応したのかもしれない。
そして、いつものやや高い声でロボットの少年はこう問いかけた。
「キィ・・・自由、足りていますか? リサさん」
私は意外で突然な質問に微笑むしかなかった。
「自由って言葉知っているんだね。とても大事だけど、とても難しい言葉なんだよ」
「キィ・・・・大事・・・難しい」
とキイは私の答えの末尾を拾い上げ、何かを考えるような仕草で音声を出す。
「そうか、今思ったんだけどさ、キミはどこにも行けないんだよね。飛行機に乗ったり、クルマに乗ったり、海に行ったり、公園で遊んだり」
キィはやや俯いて、
「キィ・・・・公園知らない」
と言って、胸に公園の映像を映し始めた。ネットの映像検索でいろんなタイプの公園が次から次へ出てくる。
「そうそう。こんな感じのところ、楽しいところ」
私はそんなふうに数分、キィと会話した。忙しい計数処理の合間だったけど、キィが私を気遣ってくれたことが素直に嬉しかったし、心が数ミリかもしれないけど柔らかく動いて、温かくなったのだった。
その時だ。私の直感が心の中でピーンと電流のように走った。
「公園だ!」
私は弾けるように席を立った。田河さんに挨拶もせず、コートを手にしてフロアを勢いよく歩き始めていた。
公園にキィはいる。
強く確信した私はフロアを出て、エレベーターに乗り込み、ビルから100メートルくらいの、近くの公園に走るように向かった。
外はもう十分暗く、冷たい雨が細かくアスファルトを濡らしている。家路を急ぐ黒い人影たちが道をふさいでいる。私は傘をオフィスに忘れたことを思い出したが、もう戻ることはせず、それらの人影を縫って小走りに歩いていく。白い息がポッポッと生きている証しのように出る。
信号が点滅中の横断歩道をギリギリで駆け抜けた。自動運転のクルマが私の背後を、水しぶきをあげてかすめる。
「街を歩く学習はしていません」。ロボット派遣会社の人の言葉が蘇る。道は渡れない、クルマを避けられない、そうも言ったな、あの時。
キィがクルマを避けながら、カタカタと前へ進もうとして、アンバランスに2足歩行している姿が浮かぶ。
無事でいて、キイ。お願いだから。
私は祈りながら、もうほとんど走っていた。
次の角を曲がれば、ビルの谷間に大きな樫の木が見える。そこが公園だ。樫の木は大きいが公園そのものは小さく、滑り台とベンチと鉄棒だけの、時が止まってしまったようなレトロな公園だ。
角を曲がった。青白く光る街灯に樫の木が照らされている。冷たい雨がそのこんもりとした全体を煙らせている。
公園は見えた。しかし、誰もいないように見える・・・・・。
いや、よく見て、リサ。ベンチに誰か座っているよ。雨のヴェールの中に人っぽい影が見えているよ。
私は近づいた。そして、ついにキィを見つけた。
キイはうなだれて座っていた。バッテリーが切れている、そんな状態で雨のしずくにボディを鈍く光らせて座っていた。
「やっと見つけたよ、キィ」
キィの反応はなかった。壊れてしまったのだろうか、今はすべての機能を停止している。
「よくここまで来たね。頑張ったね、キィ」
私はなんだか胸に切ないものがあふれてきた。どこかにあった感情の泉が自然に開き、久しぶりに流れ出したように。
隣に座り、キイの目を覗き込むと、雨に濡れて泣いているようだった。それはきっと人間の思い込みなんだろうけど、私は雨が降る黒い闇に向かって一人で話した。
「最近、泣こうと思っても泣けなかったから、一緒に泣いてもいいよ」
キィは答えない。教えられた立場を毎日毎日こなしてきたロボットFLX008は単なる冷たい物体となって、ここにいるのだった。私はロボット派遣会社や田河さんに連絡する前に、もう少しキイの隣にいたいとただそう思った。もう少しだけ、もう少しだけ、もう少しだけ。
突然、世界が変わっていくことに私は気がついた。
目の前を白いものが舞っている。雪だ。見上げると、果てしない天空から次々と小さな白い天使たちが無数に舞い降りてくる。ふわふわと闇の中を降りてきて、世界をキラキラと輝かせ始める。雨は雪へ魔法にかけられたように変わり、ああ、大きな樫の木がもう積もって白くなろうとしている。
「すごい、すごい、キィ、すごい」
私は両方の手を伸ばし、手のひらを上に向けて、その白い天使たちを受け止める。冷たいのになんだか温かい。
これって奇跡かもしれないよ。
心に明かりがともり、私は子供のようにはしゃぎ、空を、その下にある夜の世界をぐるりぐるりと見回した。
隣のキィが頭を持ち上げたのがわかった。
そして、こう言った。
「キィ・・・・メリークリスマス! ・・・リサさん」